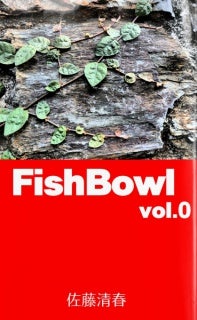「な? そうだよな? 俺たちは大親友だろ? それだってのに、お前って奴はよ。――っていうか、どうでもいいけどお前たち歩くのむちゃくちゃ速くねえか? こりゃ、競歩の練習とかじゃないよな?」
「いいから名乗れよ」と僕は言った。
「は?」
「お前はまだ名前を言ってない」
「ああ、そうだったっけ?」
![]()
突然歩みをとめて小林は内ポケットから名刺入れを取り出した。篠崎カミラも慌ててバッグを開けた。手帳を出し、そこに挟んであったのをつまみ取った。
「いや、申し訳ございません。私、営業二課の小林と申します。以後、お見知りおきいただけると幸いです」
「あっ、あの、わ、私は、そ、そ、総務の、し、し、篠崎カミラと、も、申します」
自分たちが働く会社を目の前にして、どうして名刺交換なんてするんだよ――と僕が思ったのも当然のことだろう。他の者たちもそういう目で彼らを見ていた。
「いやぁ、あの子、面白いな」
十二階で降りると小林はそう言った。篠崎カミラはエレベーターのドアが閉まる間際まで何度も頭を下げていたのだ。
「からかうにはだろ?」
「ま、そうだけど、面白いことに変わりない。それに、えらく美人さんになったじゃねえか。厚化粧して背筋伸ばしてるだけって言ってたけど、なかなかのもんだぞ。着てるもんだってお前がいかにも好きそうなのだったしな」
僕たちは連れだってトイレに行き、並んで用を足した。自ら『大親友』と名乗るだけあって、僕がどんな服を好むのかも知ってるわけだ。まあ、かといって小林が指摘した好みのタイプが全面的に正しいことにはならないけど。
「ああやって、だんだんお前好みになってくってわけだな」
腰を軽く振ってから小林はチャックを閉めた。手をしっかりと洗い、ハンカチで丁寧に水気を取った。意外と神経質な部分を持ちあわせているのだ。
「な、マジでヤッちまったんじゃねえだろうな? あの変わり様はちょっと異常だぜ。大きなきっかけがなかったら、ああはならないはずだ」
きっかけ? と僕は思った。あまり聞きたくない言葉だ。僕も手を洗った。そうなると目の前に鏡があらわれることになる。なるべく見ないようにしていたけど僕は嫌な気分になった。どうしたって左肩に目がいってしまうのだ。
「何度も言ってるけど俺はヤッてない」
「ほんとか? ありゃ、――うーん、そうだな、三十手前まで処女だった女が突然男の味を知ったってくらいの変わり様だ。どうにもこうにもその男に好きでいてもらいたくって、なり振り構わず昔の自分を捨てたって感じだぜ」
僕は首を曲げて小林を見つめた。思いついたことを言ってるようにしかみえないけど、その一部はあたってる。篠崎カミラは三十手前にして処女なわけだから。
「なんなんだよ、その顔は。えらく深刻ぶった顔してんぞ。――で、さっきカミラちゃんが言ってた『深いわけ』ってのはなんだ?」
トイレから出ると僕たちは廊下の端に向かった。そこには自動販売機がある。缶コーヒーを買って、僕たちはその場で飲んだ。小さな窓からは強い陽射しが洩れこんでいた。きっと今日も暑くなるのだろう――そう思いながら僕は外を眺めた。足許にはモップが突っこまれた青いポリバケツがあった。
「教えろよ。どんな『深いわけ』があるってんだ?」
「なにもないよ。あの女がおおげさに言ってるだけだ。さっきしゃべってそれはわかったろ? 言葉遣いが変なんだよ。あれもそういうのの一部だ」
「ほんとか? マジでほんと?」
掃除のおばちゃんが腰を屈めて近づいてきた。僕は身体を反らすようにした。小林はモップの入ったバケツを渡してあげた。たとえ何歳であろうと女には優しい奴なのだ。
「マジでほんとだよ」
ちょっと頬を染めたおばちゃんが階段室に入っていくのを見届けてから僕はそうこたえた。だけど、小林は疑わしそうな表情を浮かべていた。

現代小説ランキング エッセイ・随筆ランキング 人気ブログランキングへ
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》