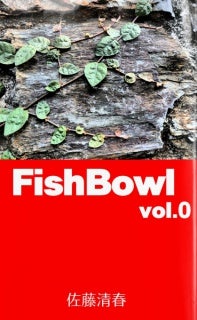その翌日、僕はさらにうんざりすることになった。駅前で篠崎カミラが待ちかまえていたのだ。彼女は姿勢良く立っていて、眼鏡もかけておらず、髪は高いところでまとめていた。僕の姿を確認すると姿勢を崩さぬよう慎重に近づいてきた。とってつけたような笑顔を浮かべてもいた。まるで広告の写真みたいな固まった表情だった。
僕はぷいっと横を向き、足早に立ち去った。機嫌が悪かったのだ。それに、気分も最悪だった。堀端で経験したことは部屋に戻りひとりきりになると深刻な怖れを感じさせた。髪を洗うときも可能な限り薄目を開けながらシャンプーを使ったほどだった。テレビの音量だって普段より大きくしたし、ビールもいつもより二缶多く飲んだ。それでも落ち着かなかったので料理用のワインにまで手をつけたのだ。べろんべろんになった上で、もちろん明かりはつけたまま寝た。そんなこんなで僕の気分は最悪だった。吐き気まではしないけど、二日酔いの一歩手前くらいにはなっていた。こんなのは何年ぶりかのことだった。苛つく女だけじゃなく誰であっても避けたいくらいだ。しかし、篠崎カミラは追いかけてきた。
「あっ、あっ、あの、」
「なに?」
「こ、こ、これで、い、い、いいでしょうか? そ、その、き、昨日、さ、佐々木さんに、お、お、教えて、い、いただいた、とっ、通りに、し、し、してきました」
僕は首の辺りを掻いた。嫌味が通じない人間っているんだな――と考えていた。深刻な怖れが馬鹿らしくなってもきた。歩きながら僕は彼女の顔を見た。化粧もばっちりしている。ただ、ばっちりし過ぎてる。アイメイクがきついし、チークのつけどころがいまいちだ。だいいち服装に合ってない。
「化粧が濃いよ。顔だけ派手になってる」
「そ、そうでしたか。じっ、じ、実は、は、母に、て、て、手伝って、も、もらったので」
だからか――と僕は思った。年齢にも合ってないのだ。
「そういう雑誌あるでしょ。メイクの仕方が載ってるの。なんとか系メイクとか書いてあるヤツだよ。それを見て勉強したら?」
僕たちは猛然たる勢いで会社に向かっていた。逃げ切りたいと思ってる僕のペースがそうさせていたのだ。しかし、背が高いだけあって篠崎カミラも同じ歩幅で進める。
「わ、私は、な、な、なに系なんでしょう?」
「知らないよ、そんなの」
知るわけもない。というか、考えたくもない。僕たちは同じ勢いのまま社内に入っていった。エレベーター前には人が溜まっていた。まいったな――と僕は思った。こんな女と同伴出社みたいに思われるのは嫌だ。僕はゆっくり気づかれぬように篠崎カミラから離れていった。ただ、向こうも静かに動いて横にぴったりとくっついてきた。
「え?」と声がした。「えぇ! 篠崎さん?」
群がる人を掻き分けるようにして出てきた女の子は僕たちの前で首をかなり仰角にさせた。
「びっくり! すごい! かわいい!」
篠崎カミラはうつむきそうになったけれど、ちらっと僕を見てから胸を張った。
「そ、そ、そんなことは」
か細くそう言うと、篠崎カミラは喉の調整をするかのような間をあけた。そして、比較的大きな声でこう言った。
「さ、さ、佐々木さんに、おっ、お、教えて、い、いただいたんです」
「へえ。ふうん」
女の子は僕たちを交互に見あげた。どちらかというとこっちの子の方が僕のタイプだ。だから、変な誤解はしないで欲しい――そう僕は願った。しかし、過剰な反応をするわけにはいかない。こういう場合、印象に残るような行動は控えておくべきなのだ。女の子は意味深そうな目つきをさせていた。僕は可能な限りの無表情で押し通すことにした。しばらくそうしていると、女の子は「それじゃ、お邪魔なようだから」といった感じに背中をみせた。
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》