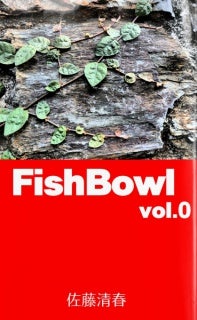まあ、そんな感じにゆっくりではあるけれど確実に僕の生活はかつてのペースを取り戻しつつあった。六月二十七日(鷺沢萌子に出会う前日だ)までとほぼ変わらないルーチンを組めるようになっていた。変わったことといえば自炊をしなくなったこと(できないというのがより正しい表現だけど)、小物の整理に一時間使うようになったことくらいだった。ただ、それだっていつかは収まるはずだった。もうすこしで僕は安逸な日々を取り戻せるはずだったのだ。しかし、運命は僕を落ち着かせてくれなかった。
![]()
七月最後の火曜日のことだった。会社を出ようとしていると走り寄ってくる影が目に入ってきた。ロビーは吹き抜けになっていて、そこここに大きな鉢植えが置いてある。たぶんその後ろに隠れていたのだろう、僕は自動ドアがひらく直前までそれに気づけなかった。そして、気づいたときには激しくうんざりした。背の高さでそれが誰かわかったからだ。
「あっ、あっ、あの、」
篠崎カミラは白いブラウスにこれといって特徴のない黒スカート、細いフレームの銀縁眼鏡といったいつもの格好で僕の前に立ちふさがった。胸に紺と白のクラッチバッグを押しあてるようにしていて、腕はそのためにクロスしていた。
「なに?」とだけ僕は言った。そのまま彼女の横を通り、外に出た。
「あっ、あの、」と呼びかけながら篠崎カミラは追いかけてきた。僕は歩くのが速い。営業職を何年かつづけてると嫌でもそうなってしまうものだ。ただ、篠崎カミラはすぐに追いついた。
「ちょ、ちょ、ちょっとだけ、お、お、お話させて、く、ください。こ、こ、これは、じゅ、重要なことなんです。さ、さ、佐々木さん、あ、あ、あなたにとって、と、と、とても、じゅ、重要なことなんです」
僕は立ちどまった。篠崎カミラは惰性で二、三歩先へ行ったけれど、振り向いて僕を見た。頬には髪がかかり、首は前へ伸びていた。猫背になってるのだ。
「宗教とかでしょ?」
溜息まじりに僕はそう言った。
「そういうの必要ないんだ。自分のことは自分で決められる。なにかにすがりたいとか思わないんだよ。だから、君の言う『重要なこと』ってのにも興味がない」
すぐ横を人が通り過ぎていった。僕は冷静に自分のおかれている状況を考えてみた。えらく背の高い男女が歩道の真ん中に突っ立っているわけだ。それで、まわりの人たちは迂回するように歩いてる。僕は脇に寄った。篠崎カミラも隣に立った。
「しゅ、宗教の、か、か、勧誘なんかじゃ、な、ないんです」
「じゃあ、なに?」
「あっ、あっ、あの、こ、こ、これは、ひっ、ひ、非常に、び、微妙な、も、問題でして、だ、だから、み、み、道端で、いっ、言うような、こ、ことでは、な、なく。で、で、ですから、」
僕は首をぐるりとまわした。ワンセンテンスの文章を言うのにどれだけ時間をかけてるんだよ――と思っていた。しかも、まだ前段しか言えてないじゃないか。
「悪いけど、そんなに暇じゃないんだ。用事があるならすっと言ってくれないか?」
そのように僕は言った。そう、これから帰ってキッチンボウルに向かわなければならないのだ。
「すっ、すみません!」
篠崎カミラは風が巻き起こるほどの勢いで頭を下げた。長い髪はすべて下方への線となり、見えるのはつむじだけになった。
「で、なに? 宗教じゃないならなんなの?」
同じくらいの勢いで頭を上げると篠崎カミラは考えているような顔つきになった。どう切りだしたら僕がきちんと聴くか考えていたのだろう。唾を飲むような表情をしたあとで彼女はこう言ってきた。
「あっ、あっ、あの、ご、ご、合コンに、い、い、行かれる、つ、つもりですか?」
「はあ?」
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》