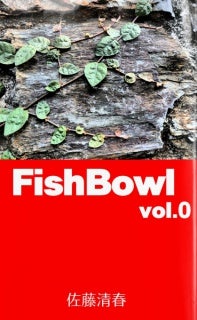「なんか、あの子(ポメラニアンのことだ)ずっとあなたを見てるわね」
それは雨の降る夜中にビールを買いに行ったときのことだった。飼い主を待っていたのだろう、そのポメラニアンは明るい店内の方を見ていた。しかし、僕たちが近づいていくと顔をあげた。彼女の言ったように僕だけを見ているようだった。
![]()
「なんで? 私の方はまったく見ようとしない。見えないのかな?」
鷺沢萌子は腰をかがめ、ポメラニアンに近寄っていった。しかし、邪魔な遮蔽物があらわれたとばかりにポメラニアンは首を伸ばして僕を見つづけた。それでも近づくと激しく吠えはじめた。歯を剥き、毛を逆立て、興奮のためかくるくると回転もしていた。
「なによ、この子、私のことが嫌いなの?」
彼女が諦めて離れるとポメラニアンは吠えるのをやめた。首を伸ばし、さっきまでの興奮を忘れたかのように僕をじっと見た。
――と、まあ、それだけのことではあるけれど、だいたいいつもこのように僕は犬に見つめられることになった。いや、そういうのはよくあることで僕にしか起こらないことではないのだろう。なぜか犬に見つめられると感じている人は多いのかもしれない。しかし、気にはなる。
街灯が突然消えるなんてのを何度も経験してる身にとっては、このこと――犬に見つめられるというのも、なんらかの因果関係の内に含まれているのではないかと考えてしまうものだ。たとえば電磁波が僕から放出されていて、それは電球にも影響をあたえ、犬もそれを気にしてしまうとか。まあ、電磁波に詳しくない僕がそう考えるのに根拠はまったくない。ただ、どのようなことであれ自分の身のまわりに起こる現象に説明をあたえたいと思うのは人間の性のようなものなのだ。そして、僕はその性向が人よりも強いのかもしれない。
部屋はまだ荒れ放題になっていた。僕には片づけをする気力も残ってなかったのだ。持ち出された物たち――鍋や炊飯器や電子レンジ、それにコーヒーメーカーもだ――を新たに買いに行きたいと思っていたけれど、それも億劫だった。あるいは、心的な外傷のせいで動けなかったのかもしれない。騙されたショックが大きすぎて、その瞬間から立ちどまったままになっていたのだ。僕は仕事に打ちこんでいた。小林が言っていたように「鬼気迫る」勢いで仕事に励んだ。残業だって毎日していた。気がつくと部署内に残ってるのは僕だけということもあった。
その日もひとりで残っていた。疲れ果てた僕は背筋を思いっきり伸ばしてから立ちあがり、帰り支度をした。嫌だと思っていても帰らないわけにはいかないのだ。まあ、いずれは立ちなおることになるだろう。あんな女のことは忘れ去り、部屋も元通りにし、それまでのペースを取り戻すのだ――なんてことを考えながらエレベーターを待っていた。
ドアがひらくと、この前の女の子がいた。僕の左肩すこし上を見つめていた子だ。乗っていたのは彼女ひとりだけだった。操作パネルの前に身を縮めるようにしていて、頬にかかる髪が顔を隠していた。ただ、僕を見て身体を強張らせたのはわかった。
「お疲れさまです」
僕はそう言っておいた。彼女の怯え様(たぶんそうなんだろう)を訝しみはしたけれど気にしないようにした。
「お、お、お疲れさまです」と彼女も言った。全体的に震えてるような声だった。それに、語尾までたどりつく前に消え去ってしまうほどの小ささだった。僕は操作パネルを覗きこんだ。《1》になっていた。それを確認したかっただけなのだけど、彼女は身体をさらに強張らせた。髪は長く素直で、それが顔を半分以上ほど見えなくしていた。細いフレームの銀縁眼鏡をかけていて、化粧をしているかはわからなかった。まあ、していたとしても薄くだけなのだろう。服装はこの前と一緒か、変わったところがあっても気づけない程度だった。紺色の小振りなバッグを腕にかけているのだけが違うくらいで、あとは白か黒に覆いつくされていた。背はおそろしく高く、きっと一七五センチはあるに違いなかった。線も細く、スカートから伸びた脚は僕の腕ほどしかなかった。
無音に近い状態でエレベーターは動きつづけた。《10》に行き、《9》に進み、《8》へと降りた。そのあいだ誰も乗りこんでこなかった。《6》の表示がオレンジ色に変わったとき、彼女は突然声をあげた。操作パネルの方を向いたままでだった。
「あっ、あっ、あの、」
「はい?」と僕は言った。それでも彼女はこっちを見ようとしなかった。
「い、いえ、」と彼女。「す、す、すみません。な、なんでもないんです」
《4》の表示がつき、《3》になった。僕はゆっくりと首をまわした。緊張が伝染したような気分だった。首筋は嫌な音をたてた。
「あっ、あの、」と彼女はまた言った。
「はい?」と僕。そのときエレベーターは地上に着いた。僕たちは降りてから向かいあった。ただ、彼女はうつむいていた。
「なにかご用でも?」
僕はそう訊いてみた。小林の言ったこと――「熱い視線」が頭をよぎった。しかし、この子の視線は左肩すこし上方に向けられていたんだと思いなおした。
《佐藤清春渾身の超大作『FishBowl』です。
どうぞ(いえ、どうか)お読みください》