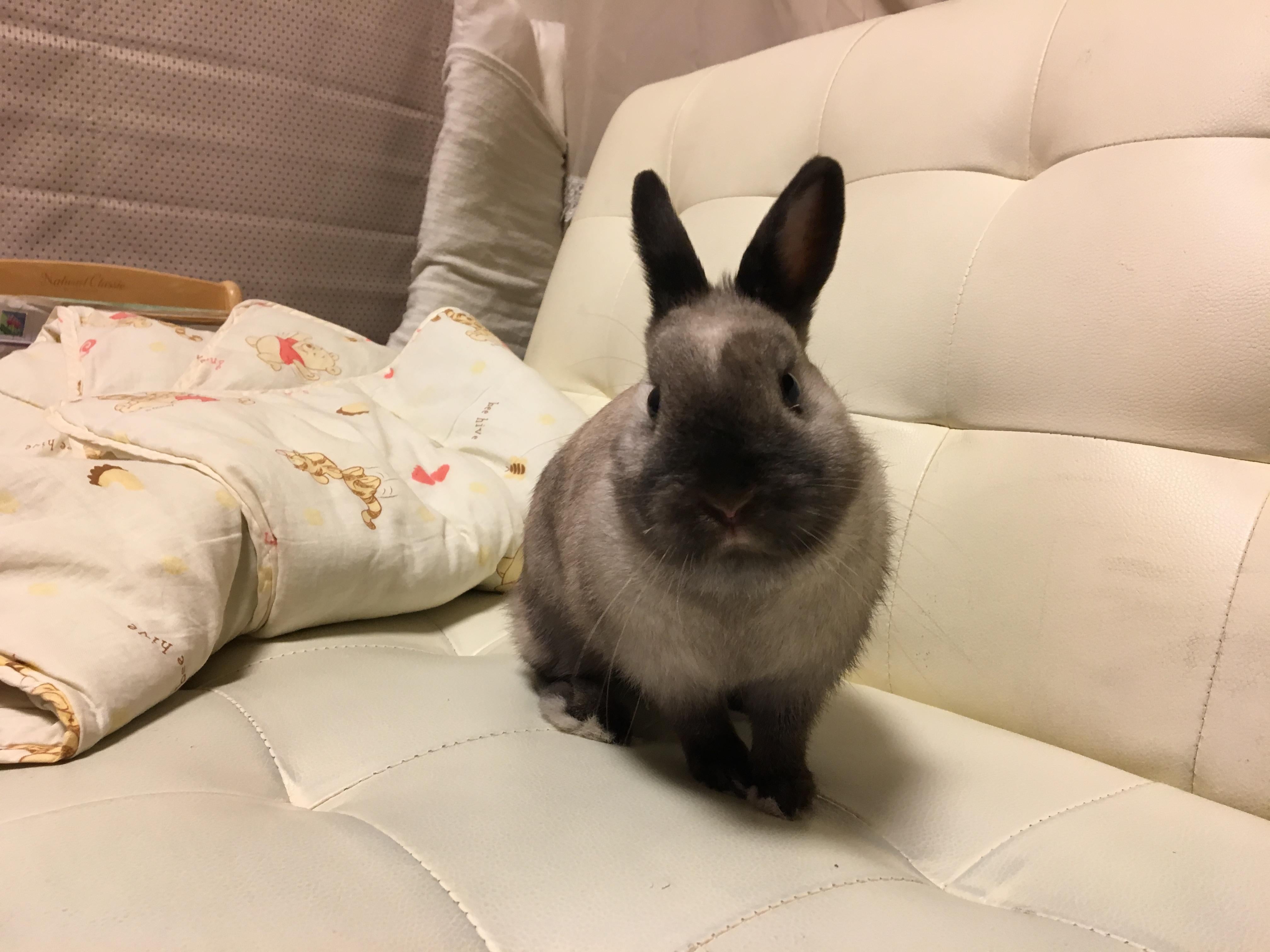ヨハネの福音書1章
1節 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。
2節 この言は、初めに神と共にあった。
3節 万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。
4節 言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。
5節 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
6節 神から遣わされた一人の人がいた。その名はヨハネ(洗礼ヨハネの方)である。
7節 彼は証しをするために来た。光について証しをするため、また、すべての人が彼によって信じるようになるためである。
8節 彼は光ではなく、光について証しをするために来た。
9節 その光は、まことの光で、世に来てすべての人を照らすのである。
10節 言は世にあった。世は言によって成ったが、世は言を認めなかった。
11節 言は、自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
12節 しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
13節 この人々は、血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。
14節 言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
15節 ヨハネは、この方について証しをし、声を張り上げて言った。「『わたしの後から来られる方は、わたしより優れている。わたしよりも先におられたからである』とわたしが言ったのは、この方のことである。」
16節 わたしたちは皆、この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上に、更に恵みを受けた。
17節 律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。
18節 いまだかつて、神を見た者はいない。父のふところにいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
1~2節は創世記1章1節よりさかのぼって書かれている箇所です。
「言は神と共にあった」と書かれています。
つまり、言と神は別の存在であることが分かります。
しかしながら続く文節で「言は神であった」と書かれています。
言と神は同じ存在であることが分かります。
それでは「言」とは何なのでしょうか?
3節以降の内容から「言」はイエスキリストを示唆していることがお分かりいただけると
思います。
よって、「言」=「神」、「言」=「イエスキリスト」であるならば、「イエスキリスト」=「神」であることが言えますね。
しかし、先ほども書かせていただきましたがイエスキリストは神ではありますが異なる存在でもあるのです。
この概念を説明するには三位一体論によらなければ説明することはできません。
それではなぜ、イエスのことをヨハネは「言」と書き表したのでしょうか。
新約聖書の原語で「言」はギリシャ語で「ロゴス」と書かれています。
我々日本人が「ロゴス」と聞くとギリシャ哲学で使われる「ロゴス」を連想しますがではヨハネも
そういう意味合いで使ったのでしょうか?
しかしヨハネはギリシャ哲学者ではなく、元々はユダヤ人漁師です。
ではヨハネは「ロゴス」をどのような意味合いで使ったのでしょうか?
ヨハネはユダヤ人なのでヘブル語の「ダバール」という言葉をギリシャ語に訳したものが「ロゴス」になったと考えるのが適当だと思います。
それではユダヤ人にとって「ダバール」という言葉は何を意味しているのでしょうか?
旧約聖書では「ダバール」が次の個所で使われています。
創世記15:1、詩篇33:4~6、イザヤ書9:8、55:10~11、エゼキエル書1:3
いずれも、擬人法で用いられています。
一例としてイザヤ書55:10~11を見てみましょう。
「雨や雪が天から降ってもとに戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種蒔く者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、わたしの口から出るわたしのことばも、むなしく、わたしのところに帰っては来ない。必ず、わたしの望む事を成し遂げ、わたしの言い送った事を成功させる」
ここでも、「ことば(ダバール)」はイエス様のことを現していることが示唆されています。
加えて赤字の部分を見れば終わりのとおり、イエス様は為すべきことをなされるお方だということが分かります。やり残したことなどないのです。
ヨハネの云う「ロゴス」は旧約聖書で使われている「ダバール」を指していると考えてよいと思います。
つまり、「言」はイエスであり、ヨハネ1章1~18節はイエスキリストについて述べているわけですね。
それではなぜ、ヨハネはこのような書き出しから始めたのでしょうか?
それはこの冒頭部分がヨハネが一番強調したい箇所であったからと私は考えます。
イエスをユダヤ人たちが十字架に架けた理由は神を冒涜した理由によるものです。
ヨハネ5:18
「このためユダヤ人たちは、ますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである」
ヨハネ19:7
「ユダヤ人たちは彼に答えた。『私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば、死に当たります』」
イエス様はご自身のことを神の子と呼んだことが神への冒涜とされたわけです。
参考までに
しかし、当時のユダヤ教のラビたちには「メムラ」信仰というものがありました。
メシアを待ち望んでいたユダヤ人のラビたちは、メシアは神の「言(ダバール)」として旧約聖書にあらわされているということで、アラム語で「言」という意味を持つ「メムラ」という概念を作り出します。
アラム語は当時のユダヤ人社会でも使われていた言語です。
聖書にもアラム語は使用されている言語です。
「メムラ」に関するユダヤ教ラビたちの認識は次のようなものでした。
(1)メムラは、神とは別の存在であるが、神と同じお方でもある。
(2)メムラは、天地創造に参加されたお方である。
(3)メムラは、救いの代理人(agent)、仲介者である。
(4)メムラは、神の栄光の表れ(シャカイナグローリー)である。
(5)メムラは、契約の仲介者である。
(6)メムラは、啓示の仲介者である。
そして
(1)についてはヨハネ1章1節で説明がなされています。
1節 初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。
(2)についてはヨハネ1章3節で説明がなされています。
3節 万物は言によって成った。成ったもので、言によらずに成ったものは何一つなかった。
(3)についてはヨハネ1章12節で説明がなされています。
12節 しかし、言は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
(4)についてはヨハネ1章14節で説明がなされています。
14節 言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。
(5)についてはヨハネ1章17節で説明がなされています。
17節 律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。
(6)についてはヨハネ1章18節で説明がなされています。
18節 いまだかつて、神を見た者はいない。父のふところにいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
つまり、ユダヤ人が十字架に架けたイエスキリストこそが待ち望んでいたメシア(メムラ)だとヨハネは訴えたかったのだと思います。
このヨハネの福音書の冒頭部分は「三位一体」の概念が無いと理解できないですし、またヨハネもその概念を持っていたと思います。
しかし、このように書くと「三位一体」はアウグスティヌスが初めて唱えた概念であってそれまでにはなかったのだと主張する人がいますが私はそれは違うのではないかと考えております。
なぜなら、初代教会のキリスト教徒たちが唱和している使徒信条に既に「三位一体」の概念が伺えるからです。
その内容は次のようなものです。
わたしは、天地の造り主(つくりぬし)、全能の父なる神を信じます。
わたしは、そのひとり子、わたしたちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって
やどり、処女(おとめ)マリアから 生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、
十字架につけられ、死んで葬られ、陰府(よみ)にくだり、三日目に死者のうちから復活し、
天に昇って、全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、生きている者と
死んでいる者とを審(さば)かれます。
わたしは、聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の赦し、からだの復活、
永遠(えいえん)のいのちを信じます。
アーメン
赤字部分が父なる神を、緑字の部分が子なる神イエス・キリストを、青字部分が聖霊なる神を
表しています。
イエス・キリストが十字架に架かられたのが西暦30年と言われていますが、多くの学者が
西暦31~32年頃には既に使徒信条はクリスチャンの共通認識として広まっていたと考えて
います。
つまり、「三位一体」の概念はアウグスティヌスが初めて唱えたものではなく、再発見したというものであると私は考えます。
最初はあったのに途中で無くなった、そのような概念は他にもキリスト教にはあります。
例えば千年王国がそうです。
初代教会にはその概念はありましたが途中で無くなりまた復活しました。
そしてこの「三位一体」の概念が無いと聖書を理解することはできません。そしてその概念があることは明らかなのでキリスト教の共通認識となり、カトリックもプロテスタントも正教会も聖公会もほぼすべてのキリスト教団は三位一体説を支持するのです。
私もまだ若葉マークを付けているクリスチャンなので推測でしかないのですがイエスキリストが神であり人であることを否定する教えを異端だとキリスト者が認定するのはⅠヨハネ4章1~3節に由来するものではないかと考えています。
「愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか、吟味しなさい。神からの霊は、このようにして分かります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです。イエスを告白しない霊はみな、神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなたがたはそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。」(Ⅰヨハネ4:1~3)
この「人となって来られたイエス・キリストを告白する霊はみな、神からのものです。イエスを告白しない霊はみな、神からのものではありません。それは反キリストの霊です。」という箇所が神からのものか反キリストの霊かを識別する判断基準だとヨハネは言っているわけです。
この聖書箇所が書かれた背景には当時教会の中に吹き荒れていたグノーシス主義という考えの影響があります。グノーシス主義の特徴は霊肉二元論です。
この世界は物質と霊によって成り立っており物質は悪であるが、霊は善であるという考えです。ですから、このグノーシスの考えによると、神の子であるキリストが人となって来られるはずがないというのです。神は霊であって善であるのに対して、肉体は物質であって悪だからキリストが人となるわけがない、それは人の目でそのように見えただけであって、まるで人の姿をとって生まれ、人として生き、人として死に、人として復活したかのように見えにすぎないというのです。
こういうのを何というかというと「仮現論」と言います。仮に現れたかのように見えるという意味です。それは本当ではなくただの幻影にすぎないが、そのように見えたというものです。これがキリスト教会の中に蔓延していました。
つまり、簡単に言えばイエスは神ではあるが人間であることをグノーシス主義は否定しておりそのグノーシスの考えは反キリストの霊からきているものだとヨハネは言っているわけですね。
また、ヨハネの福音書の冒頭部分からもからも分かる通り「人となって来られた」と言う箇所の前には「神が」という主語があることがお分かりだと思います。
つまり、イエスが神であることを否定することも反キリストの霊から来ているものだとⅠヨハネの聖書箇所は言っているのではないかと私は思うのです。
使徒の働き17章10,11節には、ベレヤの人たちの信仰について紹介されています。
ベレヤの人達はパウロが語った福音を聖書のとおりかどうか熱心に確認しました。
その結果多くの者がイエスキリストを信じる者となりましたが彼らは盲目的に信じたわけではないのです。
ちなみに、クリスチャンになる前の状態の人を求道者と言いますが求道者が聖書に書かれてある内容に疑問や矛盾に感じる点について質問するとクリスチャンの人は好意的に受け止め、歓迎してくれます。
ですが統一教会はそうではなかったと記憶しています。
疑問点や矛盾点を問うた時にうまく答えられずに怒り出す人たちが多くいました。
家庭連合やサンクチュアリの方々に言いたいことは、カルトだと言われるのが悔しいのであればあなた方もベレヤの人達のように熱心に聖書を調べるべきです。
上から目線にのように思われご不快かもしれませんが、一刻も早くあなた方の目が覚めますようお祈りいたします。