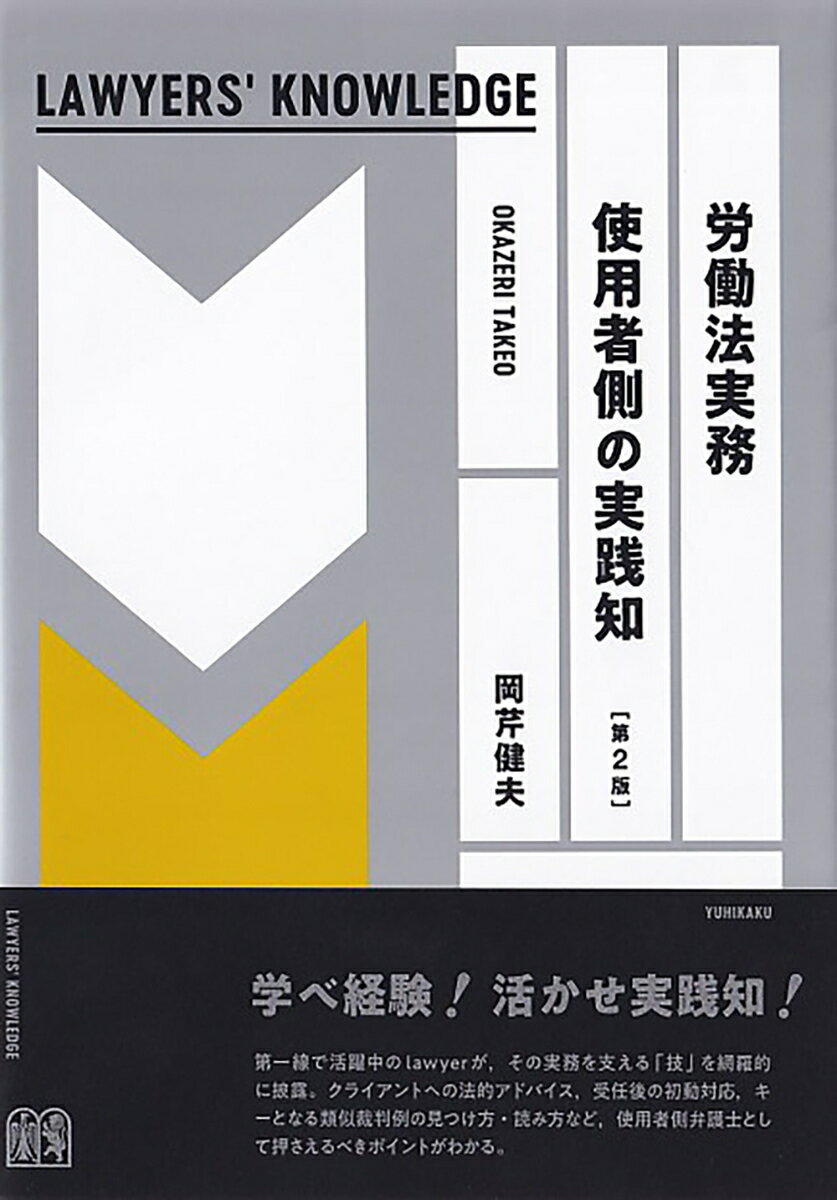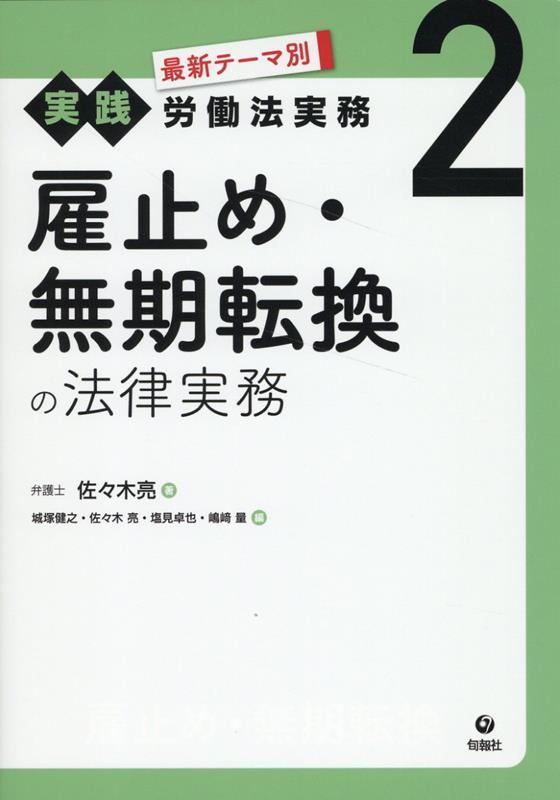日雇い労働者の減少には、いくつかの要因が影響しています。
1. 法規制の強化:
- 日雇い派遣の原則禁止: リーマンショック後の「派遣切り」問題を受け、日雇い派遣が原則として禁止されました。これにより、日雇い労働の機会が大幅に減少しました。
- 労働基準法の厳格化: 最低賃金制度の強化や労働時間の規制が進み、労働者の権利が保護されるようになったため、企業は日雇い労働者を雇用しにくくなりました。
2. 経済状況の変化:
- バブル経済崩壊後の雇用環境の変化: バブル崩壊後、企業はコスト削減を重視し、正社員よりも非正規雇用を増やす傾向が強まりました。しかし、非正規雇用の中でも長期雇用が求められるようになり、日雇い労働の需要は相対的に減少しました。
- 産業構造の変化: 製造業からサービス業への移行が進み、安定した労働力が求められるようになったため、日雇い労働の需要が減少しました。
3. 社会意識の変化:
- 雇用の安定を求める意識の高まり: 労働者はより安定した雇用を望むようになり、日雇い労働を避ける傾向が強まりました。
- 労働者の権利意識の高まり: 労働者は労働条件の改善や社会保障を求めるようになり、不安定な雇用形態である日雇い労働を避けるようになりました。
4. その他の要因:
- 高齢化: 高齢者は体力的・精神的な負担が大きい日雇い労働を避ける傾向があります。
- 外国人労働者の増加: 特定の産業では、外国人労働者が日雇い労働の代替として雇用されるケースが増加しています。
日雇い労働の減少がもたらす影響には以下のようなものがあります:
- 雇用の安定化: 日雇い労働者の減少は、雇用の安定化に寄与すると考えられます。
- 労働者の生活の安定化: 収入が安定することで、労働者の生活も安定すると見込まれます。
- 社会保障制度への影響: 日雇い労働者は社会保障制度への加入率が低いため、その減少は社会保障制度の安定化に繋がると考えられます。
一方で、以下のような課題も存在します:
- 非正規雇用の問題: 日雇い労働が減少しても、非正規雇用全体の割合は依然として高く、労働条件の改善が求められています。
- 高齢者の雇用: 高齢者の雇用機会の創出が重要な課題となっています。
- 外国人労働者の受け入れ: 外国人労働者の受け入れについては、社会全体での合意形成が必要です。
日雇い労働の減少は、労働者にとって良い面と悪い面がある複雑な問題です。