私が大学で学生に教えている「国際関係論」は、科学的思考法と微妙な関係にあります。「国際関係論」は一般的に社会科学に分類されます。しかし、そのことを授業で学生に話しても、多くの学生はピンときません。なぜでしょうか?その根本的理由は、どうやら「科学」という言葉にありそうです。おそらく学生たちが、「科学」から連想するのは、「難しい数式」、「フラスコなどを使った理科の実験」、「白衣を着た気難しそうな学者」なのでしょう。だから、それがなぜ「国際関係論」と結びつくのか、見当もつかない。
(一部の人文学は除き)文系であれ理系であれ、「科学」が大学教育の礎であることは、何十年も前から指摘されていました。社会学者の高根正昭氏はロングセラーとなった良書『創造の方法学』講談社、1979年で、以下のように鋭く指摘していました。
「理論と方法とが、すべての学科の中心を構成しているという学問に仕組みが、私にはいわば空気のように当然のことになってしまった。…科学的思考法、科学的研究法の根本原理を学ぶことこそが、今日の大学教育の根本機能に他ならないのではないか」(同書、186-187ページ)。
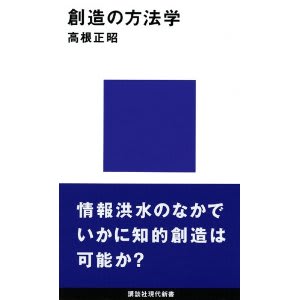
それから約半世紀もの時間が過ぎました。高根氏の指摘したように、理論と方法を学ぶことは、はたして、日本の大学で空気のように当然になったのでしょうか?手元に、これに関する調査データを持ち合わせていないので、確かなことは言えませんが、私が知る限り、そうでもないようです。
科学について素晴らしい啓もう書を書いている谷岡一郎氏(大阪商業大学)は、科学的な社会調査の方法を分かりやすく説いた著書『データはウソをつく』筑摩書房、2007年で、日本における「科学的思考」の欠如をこう憂慮しています。
「してみると、日本という国は、学問に向いていない人が大半のような気がしてきました。…罪のない慣習やアソビにすら真剣に悩む人が多い。ましてやかなり(私から見て明らかに)アヤシゲな…言動を信じる人も少なくありません。…もう一度、科学とは何か、事実とは何かを見つめなおす時間が必要なのだと思います」(同書、161、164ページ)。

私は日本人を学問に向かない「民族」と理解することに無理があると思う一方で、谷岡氏の最後の一言は、高根氏の指摘に重なります。「科学」は大切だということです。今日では、大学進学率が50%を越えました。大学がマス化・大衆化したからこそ、基礎的な「科学的思考法」をキチンと教え、それを学生が学ぶことは、ますます重要ではないでしょうか。
進化生物学者のスティーヴン・グールド氏は、「科学はつねに社会の影響を受けている」と喝破しました(スティーヴン・ジェイ・グールド『ダーウィン以来』早川書房、1995年、359ページ)。この言葉は意味深長です。そして、私は、ついこう考えてしまいます。文系≠科学という誤った日本独特の社会通念が、社会科学としての「国際関係論」に影響しているのだろうか、と。そして、この通念が広く日本の高等教育の文化として定着して、再生産されていく…。そうだとすれば、誠に残念なことだと思います。
