ウクライナ戦争の勃発にともない、いわゆる「国際政治学者」の活動が多くの人たちの目に触れるようになりました。この「国際政治学者」というのは、海外とりわけ北米では、「国際関係学者(International Relations Scholar: IR Scholar)」と呼ばれるのが一般的です。そしてウクライナ戦争がメディアで連日のように報道されたことは、多くの一般の人たちを「国際政治学」に関心を向けさせたのではないでしょうか。これに刺激を受けて、時事評論としての「国際政治学」ではなく、学問としての「国際関係論(国際政治学)」を知りたいと思った人もいることでしょう。それでは、そうした人は、一体、何に頼ったらよいでしょうか。一つの答えは、世界的に高く評価されている良質の基本書を読むことです。
シンプルで美しい国際政治理論
ケネス・ウォルツ著『国際政治の理論 (Theory of International Politics)』(河野勝・岡垣知子訳、勁草書房、2010年〔原著1979年〕)は、国際関係研究における「金字塔」です。国際関係論の動向に関する定期的調査TRIP(Teaching, Research, and International Policy)によれば、過去20年において、この分野に最も大きな影響を与えた研究を行った学者として、ウォルツは第2位にランクされています。また、北米の主要な大学院における国際関係論の授業では、『国際政治の理論』が必読文献のトップです(Colgan, Jeff D. “Where Is International Relations Going? Evidence from Graduate Training.” International Studies Quarterly 60, no. 3 (2016): 486–98.)。これらのことは、ウォルツがいかに重要な「国際関係学者」であったかを物語っています。本書は国際関係のパターンをシンプルな理論で説明するもであり、一般書のように読みやすくはありません。しかし、上記の理由により読む価値は十分にあります。
他方、ネオリアリズムと呼ばれるウォルツの理論は、さまざまな研究者から、その限界や予測に対する反証が提示されています。では、われわれは彼の国際政治の理論をどう評価すべきでしょうか。
『国際政治の理論』の訳者である岡垣知子氏(獨協大学)は、「訳者あとがき」で次のように述べています。
「ウォルツは、理論的な敷居を突破した者のみが知っている美しい世界と科学的研究の醍醐味を示すことによって、国際政治学に新しい学問的知見を開いた」(同訳書、282ページ)。

この「美しさ」とか「醍醐味」といった価値観で科学の理論を評価することには、多くの社会科学者がためらいを感じることでしょう。そのような主観的な物差しではなく、客観的なデータによる実証や反証こそが、科学における理論を評価する基準であると。そして、国際関係研究では、ウォルツの理論は、その予測が観察に合致しないので、「棄却」「否定」されたという見解も示されています。ウォルツ自身が、二極システムの持続性を予測していたにもかかわらず、冷戦があっけなく終了したではないか。ネオリアリズムは、もはや過去の理論だと。
科学における「美しさ」の重要性
では、そもそも社会科学であれ自然科学であれ、「科学」は実証的証拠により、理路整然と理論が選択されてきたのでしょうか。実は、そうでもないようです。科学史において大反響を呼んだ話題の書物、スティーヴン・ワインバーグ『科学の発見』(赤根洋子訳、文藝春秋、2016年)によれば、科学の中の科学たる物理学において、「理論の美しさ」は、とても重要な要因であると指摘されています。
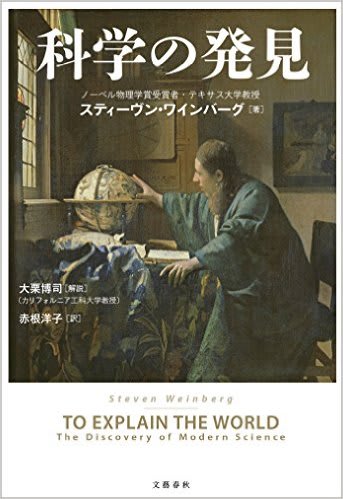
やや長くなりますが、『科学の発見』から引用します。
「コペルニクスの理論は、実証的証拠の裏付けを持たない理論が美的基準によって選択され得ることを示した古典的な例である。…コペルニクスの主張は単に、『プトレマイオス説の奇妙な点の多くが地球の自転と公転によって一挙に説明できるし、惑星の並び順とそれぞれの軌道の大きさに関して、プトレマイオス説よりもコペルニクス説のほうが遥かに明快である』ということに過ぎなかった。…物理学の歴史に繰り返し現れるもう一つのテーマ―観察結果にかなりよく合うシンプルで美しい理論は往々にして、観察結果にさらによく合う複雑で醜い理論よりも真実に近い―の実例である」(同書、202-203ページ)。
ここまで読んだ方は、「コペルニクス説」を強引に引照してウォルツ理論を擁護するのは、「贔屓の引き倒し」だと思われたかもしれません。確かに、そうかもしれません。しかしながら、アナーキー(無政府状態)とパワー分布で、戦争と平和、国家のバランシングや模倣、同盟など、数多くの事象を説明するネオリアリズムは、そう簡単に否定できる理論ではありません。もちろん、ウォルツの理論に対する批判は、国際関係論の発展にとって健全なことでしょう。ですが、ネオリアリズムを全面否定する前に、再度、物理学史の以下の教訓に耳を傾けても、無駄ではないでしょう。
「後世まで残る科学理論や科学手法は…喜びを提供するものである…ニュートンの理論のような、数多くの観察結果を見事に説明する理論を考えもなしに否定してはならない、という教訓である。その理論がうまく機能する理由を考案者自身も正しく理解していない場合もあり得るし、科学理論はいずれ、さらにうまく機能する理論の近似理論だったと判明するものだが、それらは決して単なる誤りではない」(同書、318ページ)。
実際、人文・社会科学のみならず自然科学の多くの研究者は、価値が高い理論をその美しさと関連づけているのです。概して、よい理論とはエレガントで美しいということのようです。このことをまとめたのが、ジョン・ブロックマン『知のトップランナー149人の美しいセオリー』(長谷川眞理子訳、青土社、2014年)です。ここでは、それぞれの学問分野をけん引する科学者たちが、自分の専門分野における「美しい理論」を紹介しています。『利己的な遺伝子』のリチャード・ドーキンス、『あなたの知らない脳』のデヴィッド・イーグルマン、『暴力の人類史』のスティーブン・ピンカー、『実践行動経済学』のリチャード・セイラー、『ブラック・スワン』のナシーム・ニコラス・タレブ、『銃・病原菌・鉄』のジャレド・ダイアモンドなど、錚々たる学者が、読者を魅了するショートエッセイを寄稿しています。
国際政治の単純な法則と複雑な現象
わが国では、残念ながら、国際政治における数多くの観察結果を見事に説明するウォルツの理論は、「何か現実のもののようには思えな(い)」という否定的な評価を受けてしまいました(日本国際政治学会編『学としての国際政治』有斐閣、2009年、12頁)。これは科学理論そのものに対する誤解あるいは理解不足と言わざるを得ません。なぜならば、理論の「視野が広がるとともに、その説明なるものが多くの場合もっともらしさを失い、直観から遠ざかっていく…説明が直観から遠ざかっていくのはやりきれない(が)その反対を期待する理由はない…存在するものを理解するために想像の羽を伸ばす」ことになるからです(リチャード・ファインマン『物理法則はいかにして発見されたか』江沢洋訳。岩波書店、2001年、193-194頁)。要するに、ウォルツは直観ではなく論理により、国際政治の諸事象に認められるパターンを明らかにしたのです。
言い換えれば、理論とは現実世界の描写ではなく、世界を動かしている「法則」を条件つきで説明するものなのです。ですから、多くの出来事を動かす基本的なメカニズムを説明できる理論が「現実のもののように見えない」のは当然です。そもそも国際政治における法則は、物理の世界と同じように、われわれの直観に反して単純なのです。これは国際政治の複雑さを否定しません。どういうことでしょうか。われわれは現象の単純さと複雑さをどのように整理すればよいのでしょうか。優れた物理学者のファインマンに教えてもらいましょう。
「(重力の法則のように)法則は単純明快に言い表され…それは単純でありまして、それゆえに美しいのです…重力の作用(は)現象として複雑ですけれども、基礎のパターンと申しますか、全体の底にある系統は単純なのであります」(前掲書、46頁)。
国際政治も基本的には同じです。国際システムの「ユニット(単位)」としての国家は、アナーキーの目に見えない影響により「生き残る」ことを強いられます。すなわち、どの国家も生き残りを賭けて強くなろうとします。これが国際政治の基本「法則」でありパターンです。しかしながら、世界で200カ国近いユニット同士が相互に影響している「現象」は複雑であり、国家行動の計算が格段に難しくなるのです。また、理論が予測に失敗したからといって、その効用が否定されるわけでもありません。理論は過去を説明できるだけでも十分に価値があります。くわえて、世界の事象が確率的に起こるのであれば、ファインマンが喝破するように、特定の理論が「予言できないのは、細部にわたる知識が不足しているためはありません」(前掲書、224頁)。このことはネオリアリズムにもあてはまります。
「美しさ」と「醍醐味(喜び)」は、どうしても科学的理論と無縁ではないように思えるのですが、いかがでしょうか。そしてウォルツが打ち出したネオリアリズムは、エレガントで美しく、科学研究の醍醐味が凝縮された国際政治の理論の代表であるならば、賛否はあるものの、それを謙虚に学ぶことが学術的に健全な姿勢でしょう。
