日本の「防衛政策」を長年にわたり支えてきた概念が「基盤的防衛力構想」です。これは1976年の「防衛計画の大綱」策定時にセットとして政府が示した日本の国家安全保障の土台となる「戦略」コンセプトでした。その後、この戦略構想は、実に34年もの間、すなわち2010年「動的防衛力」構想が誕生するまで、日本の安全保障戦略の柱だったのです。その間、世界は目まぐるしく変化しました。米ソのデタントとその崩壊、新冷戦、冷戦の終結、アメリカ一極システムの出現、9.11テロとアメリカのリベラル覇権追求、北朝鮮の核開発、中国の台頭などは、日本を取り巻く安全保障環境を激変させたといってよいでしょう。それでも基盤的防衛力構想は生き延びました。
国際システムの変化と日本の防衛政策のパズル
リアリストが主張するように、国家は国際システムの変化に適応しようとします。そして、それに失敗した国家は代償を払うことになります(ケネス・ウォルツ、河野勝、岡垣知子訳『国際政治の理論』勁草書房、2010年〔原著1979年〕)。こうしたリアリズムの理論が正しければ、国際システムの構造的変容すなわちパワー配分の変化は、日本という「ユニット」の行動に影響を与えるはずです。いうまでもなく、アナーキー(無政府状態)下における国家の最大の政策的優先課題は「生き残ること(survival)」すなわち安全保障です。したがって、国家は「合理的アクター」であるならば、その安全保障の極大化する行動をとるべき(はず)です。ところが、日本は外部環境が大きく変わったにもかかわらず、変化前と変化後も同じような安全保障戦略をとり続けていたのです。本来ならば、国際システムの変化は、日本に最適な生き残り戦略を強います。にもかかわらず、日本は外的要因の変化に関係なく、「基盤的防衛力構想」という同じ戦略をとり続けて、しかも、その安全保障を全うしてきました。これはリアリズムの国際関係理論にとっては、大きな「ナゾ」に違いありません。
なぜ「基盤的防衛力構想」は、国内外の環境の変化に耐えて、存続したのでしょうか。そのナゾに挑んだ研究書が、千々和泰明『安全保障と防衛力の戦後史1971-2010―「基盤的防衛力構想」の時代』(千倉書房、2021年)です。日本の防衛政策を探究するうえで、われわれを悩ませるのは、おびただしい「ジャーゴン(難解な専門用語)」が、政府や防衛当局者によって多用されていることです。たとえば、わたしが大学の「国際関係論」の授業で、学生に「基盤的防衛力構想」といったところで、聞いている学生は、よほどの安全保障通でなければ、何のことかさっぱり分からないでしょう。こうした「バズワード」に満ちた日本の防衛政策を分かりやすく、しかも関連情報を過不足なく使いながら解説すると共に、上記の「基盤的防衛力構想」の継続のナゾを解き明かそうとするのが同書です。
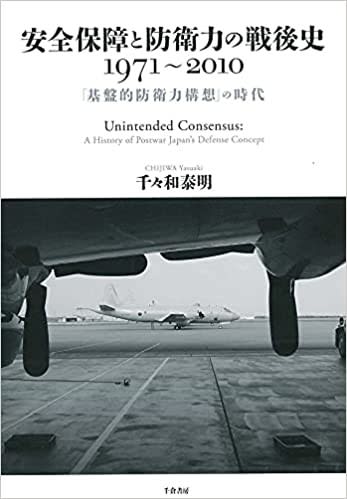
日本の防衛政策の特徴—あいまいな概念の多用—
「基盤的防衛力構想」が冷戦前後で持続した理由について、千々和氏は、国内政治の要因から説明しています。すなわち、その原因は「同構想をめぐる『多義的解釈』であり、それによって基盤的防衛力構想は戦後日本の安全保障政策に関する『意図せざる合意』を形成」できたということです(同書、12ページ)。これを簡潔にいえば、「基盤的防衛力構想」はさまざまな解釈ができる戦略概念だったので、日本の防衛に携わるアクター(政治家、防衛当局者、陸海空自衛隊、有識者など)は、自分たちが都合のよいように、これを利用できたということでしょう。
しかしながら、こうした「基盤的防衛力構想」の耐久性は、2010年頃、臨界点に達して崩壊しました。この変化の原因について、かれは「防衛力の在り方をめぐる国内的な分裂状態そのものが消滅したこと」を挙げています(同書、262ページ)。すなわち、このころから日本の防衛政策において、脅威対抗論と防衛力運用重視でコンセンサスが形成されたので、基盤的防衛力構想は用済みとなったのです。その結果、次々と難解な防衛用語が編み出されてきました。それらが「多機能弾力的防衛力(厳密にいえば、これは『基盤的防衛力構想』を一部踏襲)」「動的防衛力」「統合機動防衛力」「多次元統合防衛力」です。
これらを日本の事情に疎い海外の戦略家や安全保障専門家に解説なしに示したら、どのような反応になるでしょうか。おそらく誰も正確に内容を理解できないでしょうし、そこから演繹される手段である戦力構成や運用も導けないでしょう。それくらい、これらの「ジャーゴン」は、標準的な戦略や安全保障の中心概念から「外れている」ということです。よい戦略は概してシンプルです。
科学的裏づけなき防衛政策の形成
わたしには、本書ならびに類書や関連文献を読む限り、日本の防衛政策は、まったくといってよいほど、「科学的な検証」なくして存続されたり改訂されたりしてきた事実が驚きです。誤解を恐れずに率直にいえば、日本の防衛政策は、政策立案者たちの「直観」や「信条」、「パーセプション」、「(つじつま合わせに近い)バーゲニング」によって構築されてきたのです。それを例証するものとしては、たとえば、「二二大綱」の策定に大きな役割を果たした「防衛懇談会」のあるメンバーによれば、この会合において基盤的防衛力構想は「時代遅れの印象」で語られていたことです(同書、237ページ、強調は引用者)。
もちろん、このことは日本の防衛政策の立案において、軍事情勢に関するオペレーションズ・リサーチやシミュレーションが完全に欠如していたというのではありません。そうではなく、関連する歴史証拠によれば、「基盤的防衛力構想」による防衛政策が、ほとんど実証科学にてらされることなく継続されると同時に、反証されることなく廃棄されたのです。要するに、これは日本の防衛政策の立案と制定、変更、実施における「科学」の欠如にほかなりません。
基盤的防衛力という「幻想」
もし基盤的防衛力が日本の平和を維持してきたのであれば、前者が後者を生み出した因果関係を立証しなければ、こうした主張が正しいことは分かりません(逆も同じです)。そういうと「起こらなかったことの立証は、悪魔の証明であり不可能だ」との批判もあるでしょう。確かに、こうした反論には一理あります。しかしながら、政治学や国際関係論は、そこで「思考停止」していません。上記の因果仮説は検証可能です。
ここでは話を単純にするために、ソ連ファクターだけに論点を絞ります。冷戦期において、日本の安全保障に対する最大の脅威はソ連でした。ソ連が日本に軍事侵攻しなかったから、日本の平和は保たれたのです。そうだとすれば、日本の平和維持には2つの因果経路が推論されます。1つは、ソ連が日本の防衛力により抑止されたということです。もう1つは、ソ連がそもそも日本を侵略しようとしていなかったということです。どちらの仮説がより妥当であるかは、旧ソ連の対日政策決定の史料が、ある程度は教えてくれるはずです。ソ連は、日本の防衛力による拒否のコストが利得を上回ると判断して侵略を自制していた証拠があれば、前者の仮説が正しい可能性は高くなります。このことは基盤的防衛力の政策としての有効性を裏づけるでしょう。他方、ソ連の日本に対する威嚇はブラフに過ぎなかったのであれば、基盤的防衛力は機能していなかった可能性が高まります。
このように、日本の安全保障の因果メカニズムは、科学的に検証可能なのです。はたして、このことを研究した書物や論文あるいは調査は存在するのでしょうか。アメリカでは、政治学者や歴史学者を中心に、冷戦期におけるアメリカの対ソ戦略の有効性に関する実証研究が盛んに行われています。たとえば、ソ連のベルリン侵攻は、西ベルリンおよび西ドイツに展開していた米軍の「トリップワイヤー戦力」が抑止していたと信じられていましたが、実際は、ソ連がベルリン侵攻を企図していなかったことが研究者によって明らかにされています。すなわち、ベルリンをめぐるトリップワイヤー(仕掛け線)による抑止は、虚構だったのです。また、レーガン政権のソ連に対する「大戦略」が、同国の譲歩と穏健化を促したことも、長年の研究の蓄積から分かってきました。ひるがえって、日本の対ソ「戦略」は、はたして日本の安全保障にどのくらい寄与していたのでしょうか。こうした実証なくして、われわれはどうやって基盤的防衛力構想にもとづく日本の防衛政策が正しかったかどうかを知ることができるのでしょうか。
検証されない日本の防衛政策
同じことは、2010年の「二二大綱」以後の日本の防衛政策にもいえるでしょう。「動的防衛力」「統合機動防衛力」「多次元統合防衛力」は、どのようにして日本の安全保障に貢献しているのでしょうか。もちろん、時間が現在に近づけば、歴史証拠による検証は困難になります。しかしながら、原因と結果の因果関係を見定める方法は、史料による過程追跡法だけではありません。
第1に、「反実仮想」は、結果の必要条件を検証する優れた仮想実験方法です。冷戦期において、長い間、激しく対立していた米ソが戦火を交えなかったのはナゾでした。この「長い平和」は、ジョン・ルイス・ギャディス氏(イェール大学)が「反実仮想法」を使って、一定の説得的な分析を行っています。すなわち、冷戦前であれば戦争になっても不思議ではない対立が起こったにもかかわらず、平和が保たれたのは、冷戦前の大国間政治にはなく冷戦期の米ソ関係に存在した要因が引き起こしている可能性が疑われるということです。それが国際システムの二極構造であり核兵器でした(John Lewis Gaddis, The Long Peace, Oxford University Press, 1989)。第2に、理論も政策評価や立案の力強い味方です。戦争と平和については、戦略研究の豊富な蓄積があります。たとえば、通常戦力による抑止は、敵対国の戦闘への期待が「消耗戦」であれば、成立しやすいことが分かっています(John Mearsheimer, Conventional Deterrence, Cornell University Press, 1983) 。この理論が正しければ、日本が通常抑止を維持したければ、潜在的敵国に疲弊を強いるような戦略とそれに沿った戦力を構成・運用をする防衛政策をとって、それをアピールすることが理にかなっています。
日米同盟と安全保障―責任転嫁を続ける日本—
おそらく、日本の安全保障に最も貢献したのは日米同盟でしょう。なぜならば、国際システム(新冷戦や冷戦の終結など)、国内政治(55年体制の崩壊など)、個人(政治指導者の交代など)の全レベルで大きな変化があるにもかかわらず、日米同盟(米軍の日本占領期も含む)と日本の「平和」は変化していないからです。少なくとも、冷戦終結とソ連崩壊の過程でアメリカが果たした役割を考慮すれば、つまり、アメリカがソ連を衰退させて崩壊へと働きかけて、その強大な脅威を消滅させたとすれば、日米同盟から日本は大きな安全保障上の恩恵を受けていたことになります。その意味では、「吉田ドクトリン」は、日本の大戦略として「成功」だったといえます。基盤的防衛力も冷戦前後で変化していないとの反論もあるでしょうが、日米同盟に比べれば、その継続期間がかなり短いので、因果の重みは相対的に軽くなると判断できます。
なお、「五一大綱」の策定においては、日米同盟があるにもかかわらず、日米間で公式の協議が行われませんでした。ある当事者は「米国側の立場に立てば、勝手に大綱を作って、(日本を)支援してくれということになる」と指摘しています(同書、106-107ページ)。同盟とは、そのパートナー国が相互に安全保障のために協力する制度であることにかんがみれば、一方の同盟国が相手国と調整もせず独断で防衛政策を構築しておきながら、有事の際に軍事的支援が行われるはずだと期待することは、戦略の常識からすれば考えられないのではないでしょうか。
新冷戦期においても「五一大綱」を「放置」したことに対して、ある実務者は「無責任だった」と述懐しています(同書、157ページ)。リーマンショック以降、自己主張を強める中国の台頭により変化している東アジアの安全保障環境において、日米同盟が果たす役割はますます大きくなっています。ある研究では、中国の攻撃的行動はアメリカに抑制されることが実証されています(Andrew Chubb, "PRC Assertiveness in the South China Sea," International Security, Vol. 45, No. 3, Winter 2020/2021)。そうであれば、2008年以後の日本の安全保障は、引き続きアメリカとの同盟に支えられているといえます。要するに、日米同盟が、国際システムからの「制裁」から日本を救っていた可能性が高いということです。別の言い方をすれば、日米同盟は日本の防衛政策の「許容原因」だったのかもしれません。
防衛政策への科学的アプローチの必要性
これはまったくの私見ですが、日本における安全保障研究や戦略研究における「科学」の遅れが、政策にもあらわれていると推察されます。安全保障や戦略が、科学であると同時にアートでもあることは、わたしも同意します。しかしながら、率直に申し上げれば、日本の防衛政策の立案者たちは、「主観」に比重を置きすぎていたように思います。日本の生存を左右する防衛政策が、関係者の「印象」で決まっていたとするならば、これは衝撃ではないでしょうか。社会科学がどのように防衛政策の形成にかかわるのかについては、議論の余地があるのでしょうが、アメリカでは「戦略の科学」が学者を交えて追究され、その安全保障政策に一定の役割を果たしてきました。学術的な国家安全保障政策研究の「黄金期」(1945-1961年)において、アメリカが直面する戦略的課題への解決に社会科学者は貢献してきたのです(ただし、アメリカにおいて、社会科学者の研究が、どの程度、実際の国家安全保障政策に影響を与えたのかは、議論の余地があります)。
政治学者のバーナード・ブローディ氏は、核兵器の用途は抑止に限られることをいち早く指摘しました。かれは米空軍参謀本部のアドバイザーとして仕えるとともに、かれの「抑止理論」は、大統領をはじめ政府高官に「核革命」のインパクトを理解するための「メンタル・マップ」を提供したのです。後にシカゴ大学の政治学教授となるアルバート・ウォルステッター氏は、ソ連の第1撃に対する戦略空軍司令部の脆弱性を分析した「基地使用研究(basing study)」を主管したり、核攻撃からのICBMの脆弱性を硬化サイロによって減少させることを提言したりしました(Michael Desch, The Cult of Irrelevance: The Waning influence of Social Science on National Security, Princeton University Press, 2019, pp. 145-175)。ひるがえって、日本でも、社会科学者が「防衛問題懇談会」などを通して、安全保障政策の立案にかかわるようになりました。その一方で、アメリカでは今も昔も戦略家とよばれる多くの社会科学者が大学やシンクタンクに籍を置いて活動しているのに対して、我が国では、どのくらいのアカデミアの戦略家が存在するのでしょうか。日本の防衛政策に「戦略の科学」が求められるゆえんは、ここにあるとわたしは思います。