ウクライナ危機は、ロシアの侵略により、本格的な戦争へと悪化してしまいました。ロシアによるウクライナ侵略が懸念されていた当時、日本のメディアでは、ロシアやヨーロッパの「地域研究の専門家」や「軍事アナリスト」、「ジャーナリスト」、「外交実務経験者」たちが、この危機をさまざまな方面から解説していました。この記事では、アメリカの代表的な国際関係理論家によるウクライナ危機の分析を紹介したいと思います。
ここで取り上げるのは、このブログで何度も紹介してきたスティーヴン・ウォルト氏(ハーバード大学)が、フォーリン・ポリシー誌に寄せたエッセーです。わたしがウォルト氏の記事に言及するのは、かれがリアリストだからだということもありますが、国際関係論という学問の政策への関連性のみならず戦略の実践を意識しながら、ウクライナ危機を紐解いているからです。ここでは、かれのブログ記事「ウクライナにおける戦争へと歩む夢遊病者の西側」(2022年2月23日)を部分的に引用しながら、その分析を解説してみます。
見過ごされるバーゲニングの非対称性—軽視されたロシアの決意—
ウクライナ危機に関しては、これに深く関与してきた大国であるアメリカと「ドンバス戦争」の事実上の当事国であるロシアの間に、能力や利益、決意(resolve)に大きなギャップが存在していました。にもかかわらず、危機の行方を左右するこれらの要因は、アメリカの対外政策には反映されてきませんでした。なぜアメリカは「非論理的」といわれても仕方がない対ロシア政策を実行してきたのでしょうか。この点に関するウォルト氏の「困惑」は、以下の通りです。長くなりますが、重要な指摘なので引用します。
「わたしはアメリカとNATOおよび同盟がとってきた外交的立場から伝達された決意のレベルのギャップに当惑している。アメリカのバイデン大統領は、アメリカがウクライナのために戦う米軍を派遣しないことを明確にしてきたし、ヨーロッパのいかなる主要国もそのようなこと(部隊の派遣)を提案していない。どちらかといえば、アメリカは米軍人を撤退させ、外交官を退避させることにより、逆のメッセージを送ってきたのだ。何人かの気の短い人を除いて、アメリカの対外政策の主流派は、誰もウクライナのために実際の戦争を行おうと思っていない。これは実際には(ウクライナが西側の)本当の死活的利益ではないと暗黙に了解されているということだ。
これとは対照的に、ロシアはその中核的目的すなわちウクライナのNATO加盟を今だけでなく将来のいかなる時点でも実現させないために、武力行使も辞さないことを明言してきた。それは以前の2014年における意思表示が例証していた…2014年の時と同じように、ドンバス地方へのロシア軍の現在の進撃は、西側の視点からすれば、不法であり、非道徳であり、弁解の余地がない。しかし、にもかかわらず、それは起こったのだ。もしロシアがたとえより大規模な侵攻を始めようとしていないにせよ、この危機は既にウクライナに甚大な経済的損害を与えてきた。
ここで何が私を当惑させているのか。決意すなわちロシアが死活的利益(つまり戦うに値する利益)とみなすものが、西側にとって死活的とはいえない(つまり戦うに値しない)だけでなく、直接に関係する軍事力において著しい不均衡が存在する…ウクライナはロシアのすぐ隣にいるので、その航空戦力や陸上戦力からの攻撃に脆弱である。
だが、能力と決意の双方における、この大きなギャップにもかかわらず、アメリカ(そしてNATO全体)は、交渉において、双方で隔たりのある中心的問題にまったく譲歩の姿勢を見せてこなかった。ここで問題というのは、ウクライナの将来の地政学的連携のことである。わたしが見逃していなければ、NATOは今でもウクライナが加盟条件を満たせば同盟に入る権利があると主張している。ウクライナが早い段階で加盟できるとは誰も信じていないのに、西側は一つの点(ウクライナの加盟の非現実性、引用者)を繰り返し訴えればモスクワの懸念が和らぐと期待して、この抽象的な原則への立場を変えようとしなかった。
わたしが以前から主張してきたように、ウクライナとジョージアが最終的に同盟に加入するであろうとする2008年の宣言を取り消すのに、NATOが躊躇したことは、脅されてもモスクワには妥協しない気持ちだったと部分的に理解できる。しかし、この核心的問題に関して、ロシアが幾分か望むものを同国に与えることなくして、どうやって西側の指導者がこの危機を解決できると考えていたのか、わたしには理解できないのだ…あなたの敵が現地で軍事的優勢を保持しており、あなたより結果をもっと気にしている場合、紛争を解決するには、あなたの方がある程度の調整を行う必要がある。このことは正しいとか間違っているとかの問題ではない。これは相手を動かす力(leverage)の問題なのである」。
ウクライナ危機において、能力や決意で優るロシアはアメリカとNATO諸国に対してバーゲニングで有利な立場にあります。ですので、リアリズムのロジックからすれば、ロシアは妥協しないだろうと予測できます。にもかかわらず、なぜ弱い立場のアメリカやNATOが強い立場のロシアから譲歩を引き出せると考えていたのかが、ウォルト氏にはナゾなのでしょう。これは理論的なパズルであるだけでなく、直観にも反することでしょう。こうしたアメリカの矛盾をはらんだウクライナ危機への対応の源泉は、政策エリートが陥りやすい以下の思考の「歪み」、すなわち「見たいものは見て、見たくないものは見ない」ということなのかもしれません。
「誤用」される歴史の教訓—ミュンヘンのアナロジー—
国際危機や紛争において多用されるのが、「ミュンヘンの教訓」です。ウクライナ危機も例外ではなく、「ミュンヘンの教訓」がいつのまにか分析に援用されているようです。
「あなたはタカ派の決まり文句にでくわすだろう…プーチンだけが問題の根源だと語られ、アドルフ・ヒトラー、ヨシフ・スターリン、サダム・フセイン、フィデル・カストロ、バシャール・アル=アサド、イランのすべての政治エリート、習近平といった独裁者と並んで巧妙に悪者扱いされる…西側はこの危機を核武装国家間の利益の複雑な衝突としてではなく、善と悪との道義的争いとして見てしまうのだ。いつものように、社会では、何が問題なのかは、ウクライナの地政学的連携ではなく、人類史の全体的な方向性として語られる。そして、タイミングよく、使い古されたミュンヘンのアナロジーが登場する。あたかもプーチンは大虐殺狂であって、本当の目的は、ヒトラーが試みたようにヨーロッパ全てを征服することだとみなされるのだ…この傾向はとくに危険である。というのも、いったん紛争がこのような硬直した一本調子の術語に収まると、妥協は破門宣告になってしまい、唯一の受け入れられる結果は一方の側による全面降伏になる。この環境では、外交は余興以上のものではなくなってしまう。西側の政策上の反応は、見慣れた同じようなものである。すなわち、決意の平凡な声明、同盟国を安心させるための部隊の象徴的展開、経済制裁の発動であり、戦争のリスクを緩和する可能性のある妥協を考慮する余地はなくなっていく」。
イギリスのベン・ウォレス国防相(当時)は、ロシアに対する外交努力には「ミュンヘンのにおいがする」と発言しています。「ミュンヘン宥和の再来はごめんだ」との意図を示唆する発言でしょう。ただし、この歴史の教訓は全ての危機や紛争にあてはまるわけではありません。また、国家間の対立をミュンヘンのアナロジーで理解してしまうと、それが善と悪との戦いに再解釈されてしまい、政治的妥協の可能性をほぼ消滅させてしまいます。これは悪とみなされた敵を徹底的に倒す行動を正当化しかねないので、ウクライナ危機をめぐる核武装大国である米ロ間の恐ろしい核戦争のリスクを高めてしまう悲劇に現実味を与えてしまいます。要するに、ミュンヘンのアナロジーのメンタル・マップを持った国家の指導者は、プーチンという「悪」に対するいかなる妥協も許されないと考えてしまうことにより、危機や紛争への柔軟な外交的アプローチの幅をどんどん狭めてしまうのです。
興味深いことに、当時、アメリカの対外政策のタカ派は、それほど対ロ強硬路線を主張しませんでした。共和党上院議員のテッド・クルーズ氏は、バイデン大統領がウクライナにアメリカ軍を派兵すること、プーチンとの武力戦争を始めることを望んでいないとしています。その他のタカ派と見られる共和党のマルコ・ルビオ氏も、世界の2つの最大の核大国間の戦争は誰にとってもよくないことだと発言しています。驚くことに、アメリカの世論調査(2022年2月)によれば、72%が、アメリカはロシアとウクライナの紛争において小さな役割を果たすか、全く何もすべきではないと回答したのです(Barbara Plett Usher, "Ukraine Conflict: Why Biden Won't Send Troops to Ukraine," BBC, 25 February 2022)。
にもかかわらず、バイデン政権はロシアに対して妥協を拒む強い姿勢でのぞみました。バイデン大統領はインテリジェンスからロシアの侵攻が迫っているとの報告を受けた際、「これは狂気の沙汰だ…何よりも第一にそれを防ぐのだ…しかし、このことを防ぐわれわれの能力には限界がある」と発言したにもかかわらず、「とにかくやれ。試してどうなるかを見よう」という投機的で論理的でない方針をとってしいました(Bob Woodward, War, Simon&Shuster, 2024, pp. 68-69)。かれには、ウクライナ危機の肯定的結果に期待する自信過剰バイアスがあったようです。
無視される戦略の基本原則—学習されない失敗—
「残念ながら、もしアメリカの目的がモスクワを屈服させることであり、ウクライナをいつかNATOに加盟させられると暗黙的あるいは明示的に認めることであるならば、それは失望になりそうだ。過去に繰り返されたことが、ここでもあらわれている。アメリカの対外政策のエリートは、アメリカのパワーの限界を認識したり、現実的な目標を設定したりすることができないことを繰り返し証明してきた。
1990年代初め、アメリカの指導者は自分自身にこう言い聞かせた。①地球規模のリベラル秩序は創出できるだろう、②中国を責任ある利害関係者に引き込めるだろう(そして最終的には西欧の政治的価値を信奉させられるだろう)、③イラク、アフガニスタンそしていくつかの他のまゆつばものの国家を安定した自由民主主義国へと迅速に転換できるだろう、④世界から悪を取り除けるだろう、⑤北朝鮮とイランに核開発計画の放棄を強要できるだろう、⑥ロシアからの敵対的な反動あるいはモスクワと北京をより緊密な関係にすることに直面せずに、NATOを思うがままに拡大できるだろう、と。数十兆ドルが、ほとんど成果を挙げることなく、これらの(そしてその他の)目的のために使われてきたのだ。
これらのみすぼらしい失敗にもかかわらず、現在の危機は、アメリカが世界中の政治的取り決めを規定する権利や責任、そして(すべての中で最も重要な)能力を持っていると思い込む反射的傾向が存在することを明らかにしている…(しかし)アメリカは単極時代の絶頂期でさえ、そのような能力を持っていなかったし、今日では、そのような能力がないのは確かだ…アメリカは今でも世界最強国であるが、同国ができることには限界があり、成功は明確な優先順位を設定することと達成可能な目標を追求することを必要としている…アメリカのNATO同盟国はこの危機を自分自身でどうにかする準備ができていないために、アメリカはまたもやヨーロッパの危機に対する第一の対応者の役割を担ってきた。もしアメリカとNATOが戦争に至ることなくこの危機を本当に何とか乗り越えるとすれば、それはヨーロッが自分自身の安全保障問題を扱えないという考えを強化すると共に、アンクル・サムが必要な時には今でも助けに駆け付けてくれるだろうから、試みる必要もないということになるのだろう。ヨーロッパ諸国の防衛能力を強化する努力は勢いが衰えるだろう。アメリカの同盟国はロシアからのガス栓を結局放棄することになるだろう。ウクライナとジョージアはNATOの扉をたたき続けるだろう。そしてアメリカは裕福な民主主義国を防衛するコミットメントを継続し続けることになろう…この結果の最大の受益者は、いったい誰なのだろうか」。
ここでウォルト氏が主張したいのは、以下の諸点ではないでしょうか。
第1に、ウクライナ紛争に対する関係各国の現在の行動は、誰の利益にもならないということです。アメリカが武力による強制外交や本格的な軍事介入を控えており、ヨーロッパ諸国が力でロシアに対抗することに及び腰である事実は、ウクライナ紛争で同国とNATO諸国がいかなる妥協も拒み続ける意味を喪失させているのです。
第2に、アメリカがロシアとウクライナをめぐり直接対決することの戦略的優先順位は低いので、この紛争への対応は現地のヨーロッパ同盟国に任せるべきということでしょう。国家が戦略を構築する際に従うべき根本原則は、その目標を手段と一致させることです。目標が高すぎると、それに見合う手段は入手しにくいので戦略は失敗しがちです。手段が限られている場合、戦略を成功させるためには、目標を手段に見合うまで下げることも必要になります。かつて、永井陽之助氏は、「戦略の本質とはなにか、と訊かれたら、私は躊躇なく、『自己のもつ手段の限界に見あった次元に、政策目標の水準をさげる政治的英知である』と答えたい」と喝破しました(『現代と戦略』中央公論新社、2016年〔原著1985年〕、328ページ)。日米のリアリストに共通する戦略的思考です。
おそらくウォルト氏は、アメリカが世界中の出来事を仕切る能力を持っていないのみならずこの紛争が同国の死活的利益を脅かすものでない以上、ウクライナ紛争への対応の責任はヨーロッパ諸国に負ってもらう「オフショア・バランシング」戦略をとるべきだといいたいのでしょう。
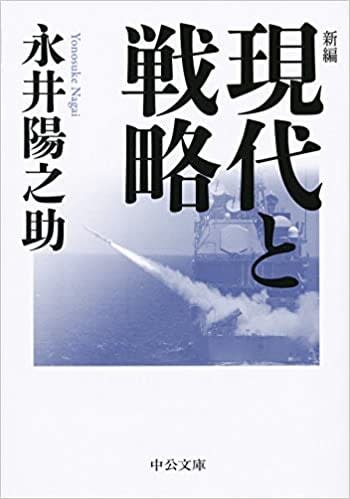
ウォルト氏はウクライナ危機の解決方法を明示してはいませんが、かれが主張したいことは以上のように明らかです。もちろん、ウォルト氏の提言が正しいかどうかは、将来の「歴史」が決めることです。われわれがかれの分析から学べることは、リアリズムや戦略の原理が示唆するウクライナ危機への1つの診断と処方ということだと思います。ウクライナ危機が戦争へとエスカレートするプロセスを理解するには、ウォルト氏とかつて同僚だったジョン・ミアシャイマー氏(シカゴ大学)の6年前のレクチャー「なぜウクライナは西側の過ちなのか」が参考になります。出来事を事後に説明する学者が多い中、かれはリアリズムの理論から、今日のウクライナ紛争を条件つきで予測していました。ミアシャイマー氏の『ニューヨークタイムズ』紙に寄稿した論評「ウクライナを武装させてはならない」も慧眼でした(この記事は日本語に訳されています)。
読者の皆さまには、これらの講演や論評は、ロシアのウクライナ侵攻が始まる何年も前のものであり、この対立を戦争に発展させないための分析・政策提言だったことに注意してください。
ミアシャイマー氏は、ロシアのウクライナ侵略が始まった後の3月1日に、『ニューヨーカー』のインタヴューを受けています。その一部を以下に紹介します(この対談記事も日本語に訳されています)。
ミアシャイマー氏「理想の世界において、ウクライナ人は自分たちの政治システムや自身の対外政策を自由に選べるだろうから、これは素晴らしいことだろう。しかし、現実の世界において、これは実現可能ではない。ウクライナ人はロシア人が自分たちに望んでいることに深く注意しなければならない。かれらがロシア人を根本的な方法で遠ざけるならば、甚大なリスクを冒すことになる。もしロシアは、ウクライナがアメリカやその西洋の同盟国と連携するために、ロシアに対して実存的な脅威を与えていると考えるならば、このことはウクライナにとって、とんでもない損害を生み出すことになる。もちろん、このことは今まさに起こっている。だから、わたしはこう主張する。ウクライナにとって戦略的に賢明な戦略は、西側とりわけアメリカとの緊密な関係を断ち切り、ロシアに便宜を払うよう試みることだ、と。もしウクライナをNATOに含めようとする東方拡大の決定がなかったら、クリミアやドンバスはウクライナの一部であっただろうし、ウクライナにおける戦争もなかっただろう」。
聞き手:そのアドバイスは今では少し非現実的に見えます…ウクライナのためにロシアを何らかの形で宥和するというのですか。
ミアシャイマー氏「わたしは、ウクライナがロシアとの何らかの暫定協定を上手く見いだせる大きな可能性は存在すると思っている。この理由は、ロシア人がウクライナを占領することやウクライナ政治を乗っ取ることは大きなトラブルを招くことになると、今や気付き始めていることだ」。
このようなミアシャイマー氏の「ウクライナ戦争」への見立てには、反対意見もあります。アンドレイ・スシェンツォフ氏(MGIMO大学)とウィリアム・ウォールフォース氏(ダートマス大学)は、ミアシャイマー氏が、アメリカは収奪的な(predatory)行為者としてNATOを拡大させ、安全保障を追求するロシアを追い詰めたとの暗黙の前提に立っているが、これは理論的に矛盾していると次のように指摘しています。
ミアシャイマー氏が依拠する攻撃的リアリズムは、アメリカであれロシアであれ大国を安全保障の収奪的追求者とみなしているのだから、もしアメリカが抑制的な戦略をとった場合、ロシアはヨーロッパ広域で自国優位の安全保障アーキテクチャを構築できたであろう。そして「アメリカが本国に帰ったところで、(ロシアの)利益がどこかに行ってしまうことはない。このことが意味するのは、もしアメリカが本当に本国に帰ってしまい、その後になって強い国益を認識して戻ってこようとしても、そこにはアメリカのパワーを受け入れようとしないロシア主導のヨーロッパ安全保障構造があると知ることだろう…アメリカが収奪的な安全保障の目標を得て、ロシアが得られなかったのは、アメリカがパワーを持ち、ロシアが持っていなかったからなのだ」。
要するに、かれらにいわせれば、ヨーロッパにおける米ロ関係の悪化は、西側のせいではなく、現状打破の衝動にかられた米ロ両国の戦略的な競争の結果と見る方が適切だということです(Andrey Sushentsov and William C. Wohlforth, "The Tragedy of US-Russian Relations: NATO Centrarity and the Revisionists' Spiral," International Politics, Vol. 57, No. 3, 2020, pp. 427-450)。
繰り返されるドミノの誤謬
我が国では、ウクライナ危機でロシアに妥協することは、アジアにおける中国の現状打破行動を大胆に促してしまうのではないかと一部で懸念されています。岸田総理の「ウクライナは明日の東アジアかもしれない」のだから、ロシアの侵略には毅然と対応するという姿勢は、多くの日本国民に受入れられたようです。イギリスのジョンソン首相も、当時、ロシアがウクライナに侵攻すれば、影響は台湾に及ぶと警戒していました。『アトランティック』誌は、「次は台湾か―ウクライナへのロシアの侵攻は中国がこの島の支配権を握る恐ろしい可能性をより現実的なものにしている―」("Is Taiwan Next? Russia’s invasion of Ukraine makes the frightening possibility of China seizing control of the island more real," by Michael Schuman, The Atlantic, February 24, 2022)と題する記事を発表しました。
確かに、こうした主張には頷けるところもなくはありません。また、国家は威嚇や対決の本気度を相手国の過去の行動から判断するとの研究結果もあります。その一方で、有力な国際関係研究は、国家の指導者が抑止の威嚇を過去の行動から判断するのでなく、バランス・オブ・パワーにもとづいて、その信ぴょう性を評価することを明らかにしています。これが正しいとするならば、東アジアにおける中国の攻撃的行動は、ウクライナ情勢に関係なく、現状維持国に有利なバランス・オブ・パワーが保たれれば、原則として抑止されると期待できます。また、台頭する野心的国家の現状打破行動に周辺国が恐れをなしてバンドワゴンすること(脅威を与える国家の側に加わること)は稀であり、国家は脅威に対抗するバランシング行動をとる傾向にあることも、国際関係研究で分かっています(これはウォルト氏が自著『同盟の起源』ミネルヴァ書房、2021年〔原著1987年〕やその他の論文で実証しています)。したがって、抑止の信ぴょう性を保つためだけの理由で行う戦争は、あまりにも危険です。
周辺国が脅威の源泉にバンドワゴンすることを防ぐための軍事介入を擁護する「ドミノ理論」は、政策を導く知的ツールとしての信頼性に欠けるのです。為政者はこの安易な使用を慎むべきでしょう。