戦争研究は、多様なテーマから成り立っています。戦争の原因を究明する研究、紛争の性質と戦争勃発の関係に関する研究、戦争の継続性や列度などを明らかにする研究、政治体制と戦争の関係についての研究など、さまざまです。これらのトピックについては、現在では、かなりの研究の蓄積があります。他方、これまで比較的に看過されてきたのが、戦争終結についての研究です。この分野で先駆的な業績を残したフレッド・イクレ氏がいうように、「全ての戦争は終わらなくてはならない」(Every War Must End, Revised ed., Columbia University Press, 2005〔初版は1971年〕)。にもかかわらず、どのように戦争が終わるのかについて、研究者たちは、あまり注目してきませんでした。戦争原因の研究を網羅したテキストは何冊もありますが、戦争終結の研究を系統的に概説するテキストは、私が知る限り、ありません。このことは、われわれが戦争終結メカニズムの究明より、戦争生起の探求に多くのエネルギーを注いできたことを示唆しています。
戦争が収束する因果プロセスを明らかにすることは、とても重要です。なぜならば、上記のイクレ氏の研究が示すように、始めてしまった戦争を終わらせるのは、たいへんな作業だからです。国家の指導者はしばしば戦争の出口戦略を十分に吟味せずに、武力行使に踏み切ることがあります。不幸にして起こってしまった戦争に終止符を打って平和を回復することは、多くの人たちの望みです。人々が求める戦争終了のしくみを分析する研究は、それ自体に価値があるだけでなく、戦争を終わらせるための政策立案にも貢献できるでしょう。そこで、このブログでは、戦争の終結の理論的、経験的な文献を紹介したいと思います。ダン・ライター氏(エモリー大学)が執筆した『いかに戦争は終わるのか』(Dan Reiter, How Wars End, Princeton University Press, 2009)です。
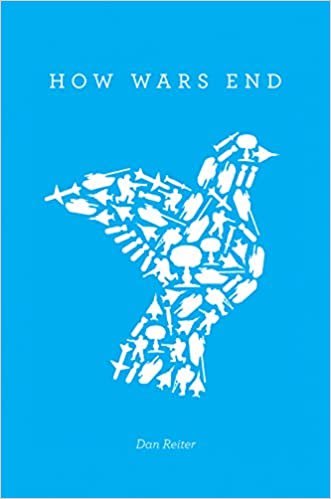
本書でかれは、戦争のバーゲニング理論を応用して、戦争の終結プロセスを理論化しています。すなわち、「情報」と「コミットメント問題」が、戦争の終わり方に、どのような影響を及ぼしているのかを明らかしているのです。不完全情報下では、交戦国間のバランス・オブ・パワーは、明確には分かりません。こうした情報の不確実性は、交戦国のパワーの配分に応じた取引を妨げる結果、戦争の終結を難しくします。また、戦争終結の「公約(コミットメント)」を定められたとしても、それが必ず守られるとは限りません。一方の交戦国が公約に違反して相手国を再び攻撃した場合、攻められた方は大きな被害を受けます。こうした「コミットメント問題」も、交戦国が戦闘を終わらせることを妨げるのです。戦争において、国家はしばしば相手国に無条件の降伏を求めたり(たとえば、太平洋戦争)、体制転換を追求したりします(たとえば、アメリカのイラク戦争)。こうした国家の行動は、コミットメント問題を克服する究極の手段になります。なぜならば、相手国を完全に打ちのめしてしまえば、また、自国に従順な体制をつくってしまえば、そうした国家は公約を破る力を喪失してしまったり、公約を破ろうとしたりしないので、コミットメント問題は解消するからです。要するに、戦争終結は、情報とコミットメントがカギを握っているということです。
ライター氏は『いかに戦争は終わるのか』において、戦争終結の5つの主要命題を提起しています。第1の命題は、「コミットメントの信ぴょう性は疑われるが、究極的な勝利の望みがあると、ネガティヴな情報(discouraging information)があっても、戦争終結にまつわる要求はより高くなる」です。交戦国は敵国が戦争終結の公約を守らないかもしれないと考える場合、戦況が芳しくなくでも、受け入れられるコストで最終的な勝利を収められると期待すれば、妥協したがらないということです。この仮説は、アメリカの南北戦争において、1862年夏に北部のアメリカ合衆国が妥協しなかった事例、1863年末に南部のアメリカ連合国が交渉しないと決定した事例、1864年夏に北部が交渉しないと決めた事例、1865年初めに南部が妥協を拒んだ事例、1940年5月にイギリスがヒトラーと交渉しない決定をした事例、1942年初めにアメリカが枢軸国に無条件降伏を求めることを公約した事例、1950年8-9月において朝鮮戦争でアメリカが北朝鮮の占領を目指すと決定した事例が例証しています。どの事例においても、交戦国は苦戦していましたが、最終的な戦勝に望みを託して、敵国と妥協しませんでした(上記書、212-213ページ)。
第2の命題は、「コミットメントの信ぴょう性は疑われるが、究極的な勝利の望みがほとんどない場合、ネガティヴな情報を受けて、戦争終結にまつわる要求はより低くなる」です。戦争を継続するコストは、勝利を期待できない国家に重くのしかかるので、たとえ戦後の平和が不安定だとしても、妥協を求めやすいということです。1940年の「冬戦争」と1944年の「継続戦争」で、フィンランドがソ連との戦争を終わらせるために譲歩したのが、この事例です。フィンランドは、ソ連が同国を併合するのではないかと懸念しており、また同国の中立宣言を無視して複数の都市を空爆してきたソ連を信用していませんでした。しかし、フィンランドはソ連に勝利できるとは考えておらず、カレリア州と南部沿岸の軍港をソ連に譲らざるを得ませんでした。1941年夏にモスクワ陥落寸前まで追い詰められたソ連が、ナチス・ドイツに譲歩をもちかけようとしたのも、この事例に含まれます。1945年8月の日本の降伏もそうです。日本はアメリカに一撃を与えられる望みを失った時点で、ほぼ無条件に近い降伏を受け入れたのです(上記書、213-214ページ)。
第3の命題は、「コミットメントの信ぴょう性は疑われるが、戦争の継続には、とてつもなく高いコストをともなう場合、ネガティヴな情報は戦争終結にまつわる要求をより低くする」です。朝鮮戦争において、1951年初め頃、アメリカは参戦した中国に苦戦を強いられて、北朝鮮の征服を放棄しました。中国との戦争のコストの高さが、アメリカに朝鮮半島の統一をあきらめさせたのです。この命題は、太平洋戦争における日本の降伏にもあてはまります。「広島・長崎への原子爆弾の投下は、米兵を犠牲にするリスクなくして、1発の爆弾で何万人もの死傷を強いるアメリカの能力を示威した。日本文明が消滅する将来像は、東京の指導層にとって、耐えるにはあまりに重すぎた」(上記書、215ページ)のです(なお、このブログ記事では、原爆投下とソ連参戦のどちらが日本の降伏を促したかという「歴史論争」にはふれません)。
第4の命題は、「ポジティヴな情報(encouraging information)は、戦争終結の要求を吊り上げる」です。1940年と1944年において、ソ連はフィンランドとの戦争でにおいて、軍事的な優勢を確保した結果、フィンランドに高い要求をつきつけました。ただし、ソ連は1940年にはイギリスとフランスの介入を警戒して、また、1944年にはナチス・ドイツへの攻撃に集中するために、フィンランドとの戦争を迅速に終わらせました。第5の命題は、「自然にまつわる財がコミットメント問題に影響する場合がある」です。「冬戦争」と「継続戦争」において、ソ連はフィンランドの領土の一部を獲得することにより、レニングラードの防衛態勢を強化できました。第一次世界大戦において、ドイツがベルギーの支配にこだわったのは、将来にイギリスやフランスから攻撃される可能性を低めるためでした。1864年夏に、戦況が芳しくなかったにもかかわらず、北部のアメリカ合衆国が「奴隷解放」を後退させなかったのは、そうしてしまうと黒人による北部軍の支持は損なわれ、同軍の軍事力の低下を導きかねないからでした。このように重要な領土の確保や軍事的アセットといった財は、コミットメント問題にかかわるのです(上記書、216-2017ページ)。
ライター氏の戦争終結研究で印象的なのは、情報の不確実性やコミットメント問題を克服するために、国家は敵国に対して「絶対勝利」をしばしば追求してきたことです。「戦争を遂行する上で、国家は相手国を抹殺すること、あるいは少なくとも相手国に選択の余地を与えなくすることにより、容赦のなく公約不履行の問題を解決できる」(上記書、223ページ)ということです。太平洋戦争における連合国の日本に対する「無条件降伏」の要求は、このコミットメント問題の文脈で理解できます。それでは、こうした残忍な戦争の終わらせ方は、政策として追求すべき選択なのでしょうか。ライター氏は、そうではないといいます。かれによれば、対外政策として絶対戦争を追求することには、2つの大きな問題があります。1つは、絶対戦争には非常に高いコストがかかることです。アメリカのイラクの体制転換を試みた戦争は、高い代償をともないました。もう1つは、こうした戦争の利得は誇張されていることです。たとえば、大量破壊兵器による攻撃を抑止することは、成功の見込みが高い選択肢です。アメリカはソ連や中国の核武装化を阻止する軍事オプションを検討しましたが、そうせずに抑止戦略をとり、核兵器の脅威から自国を守ってきたのです。かれの結論はこうです。「コミットメント問題を克服するための戦争は万能薬ではなかったし、これからもそうであろう…外交や抑止といった他の対外政策のツールの方が、よりコストが低く、より効果的なものになり得る」(上記書、230ページ)。
『どのように戦争は終わるのか』は、政治学のバーゲニング理論を用いて、戦争終結のメカニズムを解明する、画期的な研究成果だと思います。戦争は、当事国間の勝敗が明らかになっても、なかなか終わらずに、「無益で」甚大なコストを生み出すことがあります。なぜ勝敗が決した戦争が、ずるずると続いてしまうのか。こうしたパズルは「コミットメント問題」の観点から、上手く解くことができるでしょう。なお、同書の内容については、H-Diplo/ISSF Roundtable が「書評フォーラム」を実施しています。Political Psychology誌も、書評を掲載しています。興味のある方は、参考になさってみてはいかがでしょうか。
わたしは、ライター氏が提示した命題にある「究極的な勝敗の期待」の原因は何になるのかについて、疑問がわきました。アナーキー(無政府状態)は不確実性を極端に高めます。国際政治において国家の意思を知ることは、不可能とはいわないまでも著しく困難です。政策立案者が、究極的には勝利できると期待するか、それとも敗北は必至と諦念するかは、何によって決まるのでしょうか。たとえば、1940年5月時点で、イギリスのチャーチル首相は、ヒトラーと交渉するかどうか悩んだ末、徹底抗戦を決意しました。ここで興味深い「反実仮想」を提起してみましょう。もしイギリスの首相がハリファックス卿であったとしても、イギリスはドイツへの徹底抗戦を貫いたのかということです。おそらく、イギリスはドイツとの早期講和に動いたのではないでしょうか。そうだとするならば、指導者個人が戦争の終結を左右することになります。しかしながら、われわれは他国の指導者が、本心で何を考えているかを知ることはできません。ライター氏の主要な命題は、トートロジーに陥る可能性があります。
そもそも、合理的選択理論やゲーム理論で中核概念として用いられる「効用や主観的蓋然性は可視的には直接観察ができない」(Bruce Bueno de Mesquita, "War and Rationality," in Manus I. Midlarshy, ed., Handbook of War Studies Ⅲ, The University of Michigan Press, 2009, p. 27)ものです。そこで、効用や期待、選好がどのように形成されるのかを明らかにすることが求められます。「政治心理学」は、こうした作業にとって必要不可欠です。上記のチャーチル首相の決断は、かれの「感情」抜きには語れないでしょう。ただし、チャーチルは、正しい判断を間違った理由により行ったといわれています(Robert Jervis, How Statemen Think: The Psychology of International Politics, Princeton University Press, 2017, pp. 156-157)。チャーチル首相の決断は、偶然の正しさだったのでしょうか。これは一般化できない「特異なケース」なのでしょうか。こうした複雑な事例は、記述することはできますが、理論的に説明するのは、とても難しいでしょう。いずれにせよ、政策決定者の勝利への期待(主観的蓋然性)を左右する心理的な属性や物質的な条件を特定することは、戦争終結研究に残された、今後の課題だと思います。