Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (McGraw-Hill, 1979)は、国際政治学/国際関係論における最も重要な学術書であり、この分野での必読のテキストの1つです。同書の日本語訳は、15年前、岡垣知子氏(獨協大学)と河野勝氏(早稲田大学)の尽力により、原著発行から30年を経て、ようやくケネス・ウォルツ『国際政治の理論』(勁草書房、2010年)として、刊行されました。岡垣氏と河野氏が、時間をかけて丁寧に翻訳されたこともあり、邦訳『国際政治の理論』は原著を正確で忠実に訳しているにみならず、訳文も読みやすいと思います。
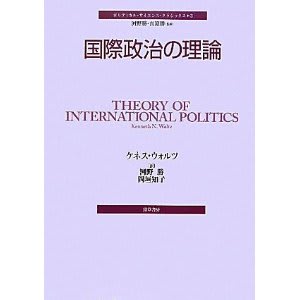
ケネス・ウォルツ氏(カリフォルニア大学名誉教授)は、国際政治学の「発展」に多大な影響を与えた世界的な学者です。ご参考までに、国際政治学に関する信頼できるTRIP調査(2017年版、アメリカの国際政治学者対象)によれば、この20年間で国際政治学に最も影響を与えた学者として、ケネス・ウォルツ氏は第5位となっています。彼は2013年にこの世を去っていますが、その後も、国際政治学界に大きな影響力を残しているのです。にもかかわらず、ウォルツ氏は、日本の国際政治学界では、今ひとつ、受け入れられていないようです。
『国際政治の理論』が出版された後、しばらくして、試しにGoogleにおける「ケネス・ウォルツ」「国際政治の理論」をキーワードとした検索は、邦訳『国際政治の理論』が大学のシラバス指定されているケースが、非常に少ないことを示しています。これで最初にヒットしたのは、国際政治学の授業ではなく、経済学の授業のシラバスであり、そこで『国際政治の理論』が必読文献として挙げられていました。そのほかとしては、同訳書は、いくつかの大学の国際政治関連の授業の参考文献等のリストにポロポロと掲載されている程度でした。ウォルツをググってヒットした情報の中で興味深かったのは、ある内科医が読書ブログで、同書を高く評価していたことでした…。
かつてハンス・モーゲンソー氏の名著Politics among Nations (邦訳『国際政治』)がそうであったように、私は、ウォルツの書籍は、日本語訳がでれば、日本の国際政治関連の授業でもっと扱われると思っていました。しかし、今のところは、そうでもないようです。なぜ、ウォルツは日本で高い関心をひかないのか?この疑問に対しては、「かれのシステム理論は、日本では素人っぽく見えた」とか、「現実からかい離しているように見えた」、といった理由が指摘されていますが(田中明彦「日本の国際政治学」『学としての国際政治』有斐閣、2009年、12ページ参照)、私はさらに根深いものがあるように思います。もっとも、それが何かは、まだよく分かりません。
訳者の岡垣氏が「訳者あとがき」で述べているように、「ウォルツは、理論的な敷居を突破したもののみが知っている美しい世界と科学的探究の醍醐味を示すことによって、国際政治学に新しい学問的見地を開いた」のは、まさしく、その通りでしょう。ウォルツ著『国際政治の理論』は、新しい古典にふさわしく刺激的で奥深いものです。同書は、世界中で賛否両論を巻き起こしてきましたが、だからこそ読む価値があるテキストであり学術書であると思います。