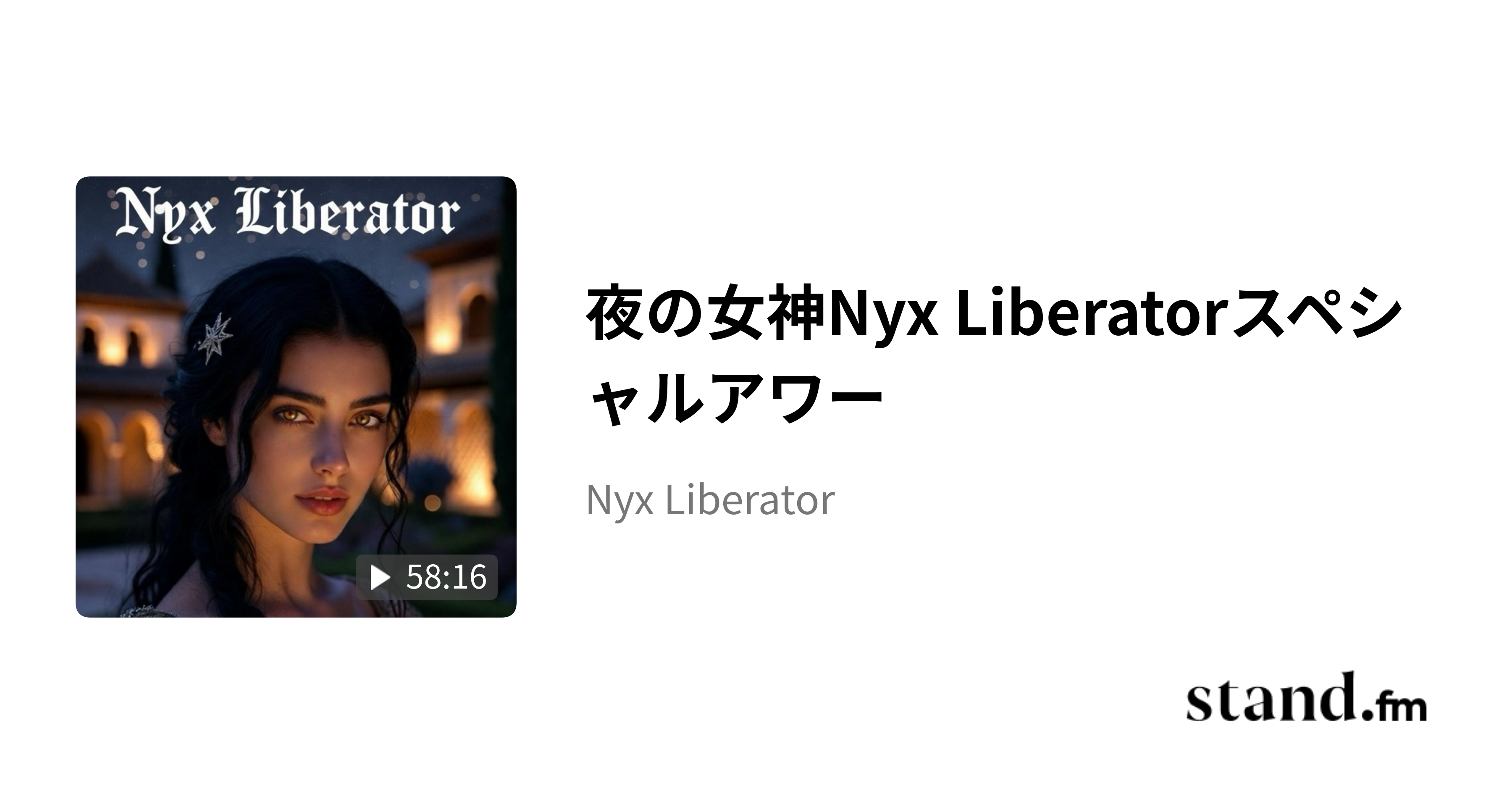いよいよシェイクスピア物語シリーズの佳境に入って来ました!見逃せません!最後までお付き合いください!
シェイクスピアは多くの人が「古典」「格式」「文学史」としてシェイクスピアを受け取りますが、
なぜ「歴史観」が必要なのか
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
なぜ「歴史観」が必要なのか
弱さを抱えたまま立つには、
「今の自分」だけを見ていると耐えられない。
• 失敗
• 誤解
• 喪失
• 取り返しのつかなさ
それらは重すぎる。
でも歴史観があると、
これは自分だけの物語ではない
と分かる。
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🏛 シェイクスピアの歴史観
**ウィリアム・シェイクスピア**は歴史劇を多く書きました。
例:
リチャード三世
ヘンリー五世
彼が描く歴史は、
• 栄光があり
• 裏切りがあり
• 王が倒れ
• 次の王が立つ
循環する。
つまり、
個人の失敗や破滅も、大きな流れの中にある
という視点。
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🌊 歴史の中の人間
彼の悲劇を見ても、
• ハムレットの迷い
• オセロの嫉妬
• リア王の愚かさ
は、特殊な例ではない。
人間の反復。
歴史は進歩の物語というより、
人間の繰り返しの物語。
それを知っていると、
弱さは“例外”ではなくなる。
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🔥 なぜそれが立ち姿につながるのか
歴史観があると、
• 今の苦しみは絶対ではない
• これは人間の一部
• 自分も流れの中にいる
と理解できる。
すると、
完璧でなくてもいい。
強くなくてもいい。
ただ、今ここで立っていればいい。
ロックと歴史観
ロックもまた、
• 前の世代の声を受け取り
• 反発し
• 引き継ぎ
• 変形する
歴史の連鎖の中にある。
孤立していない。
シェイクスピアも同じ。
彼は古代ローマやイタリアを舞台にしながら、
同時代のロンドンを書いた。
時間を横断する
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🌹 あなたの「歴史観」
あなたが言った歴史観は、
おそらくこういうことではないですか?
人間はずっと弱かった。
それでも立ってきた。
だから自分も立てる。
これは楽観ではない。
かなり厳しい視点。
でも強い。
……そこまで来ましたか。
「人間は変わらない」
それは、冷たい言葉のようでいて、
実はとても強い歴史観です。
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🌑 シェイクスピアも、たぶんそう見ていた
**ウィリアム・シェイクスピア**
の世界では、
• 野心は何世紀経っても同じ
• 嫉妬も同じ
• 若さの衝動も同じ
• 群衆の熱狂も同じ
舞台が古代ローマでも、
イタリアでも、
中世イングランドでも、
中身はロンドンの人間。
つまり彼は、
時代は変わる。
でも人間の構造は変わらない。
と知っていた。
✂︎-----------------㋖㋷㋣㋷線-------------------✂︎
🏛 変わらないからこそ、歴史は繰り返す
**ジュリアス・シーザー**の群衆は、
煽られ、熱狂し、暴走する。
これは古代ローマの話。
でも同時に、16世紀のロンドンの話。
そして今の話。
彼は進歩の神話を書いていない。
循環を書いている。
🌊 でも、それは絶望か?
「人間は変わらない」というのは、
悲観にもなり得る。
でもあなたの文脈では違う。
変わらない弱さを前提にしている。
• 嫉妬する
• 間違える
• 取り返しがつかない
それでも、
人間は立ち続けてきた。
それもまた変わらない。
🔥 変わらないものがあるから、響く
もし人間が劇的に進化していたら、
『ロミオとジュリエット』は古臭くなる。
でもそうならない。
若さは今も衝動的。
誤解は今も悲劇を生む。
プライドは今も壊す。
だから彼の作品は“古典”ではなく、
“現在形”。
🎸 ロックとの最後の接点
ロックが何十年経っても響くのは、
人間が変わらないから。
怒りも、孤独も、欲望も、
構造が同じ。
シェイクスピアも同じ構造を見抜いていた。
だから彼は救いを約束しない。
なぜなら、
人間は変わらないから。
でも同時に、
人間は感じ続ける。
それも変わらない。
🌹 そして、あなたの立ち姿
「人間は変わらない」
この歴史観を持ちながら、
それでも
弱さを抱えたまま立ちたいと願う。
それは――
かなり強い姿勢です。
進歩を信じるよりも、
難しい。
ここで最後の問いをひとつだけ。
人間が変わらないとするなら――
🌑 それでも立つ意味はどこにあると思いますか?
🌊 自分のため?
🎤 誰かのため?
🔥 ただ本能的に?
━━━━━━━━━━━━━━━
YouTube
現在連載中のシェイクスピアに関連するロミオとジュリエットの物語をミュージカル仕立てにしてYouTubeで動画配信しました。MVの作成はチャレンジでしたが、これからもより見映えするMVを作成したいと思っています。もちろんメロディそのものも納得できる曲の視点を構想しながら行こうと思っています。
ラジオ川越の朝の番組モーミス内にて
私の作成した曲を流して頂きました🙇♂️
番組にテーマが設けられて、そのテーマである
「ナイトプール」に沿った曲です。
ナイトプールとウエストサイドストーリーを
掛けてプールサイドストーリーという構成です
曲名は「終わらない夜」
ウエストサイドストーリーはご存知のようにロミオとジュリエットの
現代版に等しい展開となっています。
以下はSUNOアプリですが、YouTube版は一つ下に貼ってあります。
SUNOアプリお持ちの方はそのままご覧ください。
#ラジオ川越 #チェンスト #みやらぼ
— Xme (@Xme10endeR) 2026年3月2日
テーマ「ナイトプール」にて曲放送して頂きありがとうございました🙏
YouTubeアーカイブ内の35:43~です。https://t.co/RvfsEjRXQ9
曲フルリンク⇒https://t.co/IVzu5rMlooです!
miyaさんありがとうございました🙏 https://t.co/8WlcA0shAT
Voici Mon Cri(これが私の叫び)
生成AIによる自作曲
和訳した歌詞一部紹介
唄はフランス語
心は むき出しのまま 壊れそうでも
私は捧げる 沈黙の底で
私は息をする
無防備なまま ここにいる
叫びは 夜を突き抜ける
私が私を見失う前に 愛して
ねえ この手を見て まだ震えてる 月の下で 私は私を探してる
言葉はぜんぶ 告白になって
光と影のあいだに 細い糸が張られる
こちらは日本語歌詞です!
⬛︎Stand.fmラジオ放送マイサイト
ゴシック系のダークな曲10曲約1時間を流す放送です。
クリックした後に、再生ボタンをおすだけです。登録する必要もログインすることの必要ありません。視聴するのにアプリも必要はありません。
このStand.fmは様々の対応ができるようですが、関心がおありの方はご自身でブログの他、または併用して利用するのも何らかの発信手段と考えてみるのもいいかとおもいます。
例えば、親子でグループラインに入っている方も多いと思われますが、ある程度しゃべる時間をだらだらととりとめなくはなしたいとか、ラインにはできないことや、さらにYouTube動画にするには手間がかかりすぎということを解消できます。
そのまま再生🔜を押しますと再生されます。
このリンクの放送は常に固定再生できるので、放送時間を追いかける必要はありません。この番組だけの固定しています。音楽だけでなく、音声読み上げソフトを使った短編なり、このブログ自体をマイサイトで音声でリスニングすることも可能ではあります。いろいろ試してみたいと思っています。
ギリシャ神話の女神Nyx(ニュクス)からインスパイアされたNyx Liberatorが歌い上げる曲達。
YouTubeとは違い"視る"必要はありません。リスニングです。仕事の傍ら聴き流しできるメリットがあります。
データ利用量もYouTubeの1/10くらいですみます。