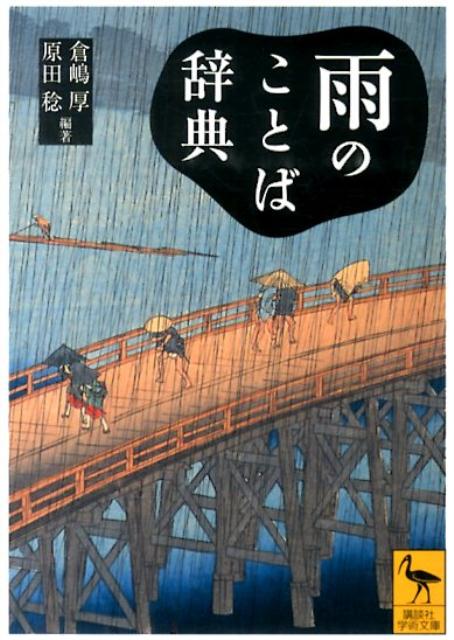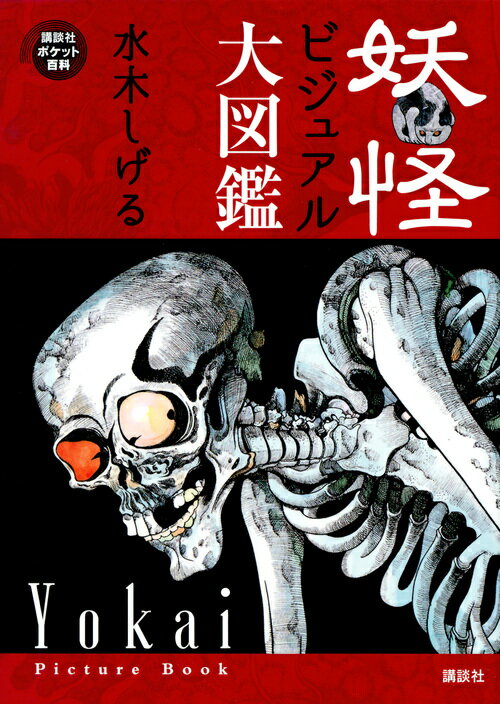ようやくの梅雨入り・・・(憂鬱)
ようやくの梅雨入り・・・(憂鬱)
2024(令和6)年梅雨入り
沖縄・・・・・・・・5月21日 平年より11日遅く、昨年より3日遅い
奄美・・・・・・・・5月21日 平年より9日遅く、昨年より3日遅い
九州南部・・・・6月8日 平年より9日遅く、昨年より9日遅い
九州北部・・・・6月17日 平年より13日遅く、昨年より13日遅い
関東・甲信・・・6月21日 平年より14日遅く、昨年より13日遅い
近畿・・・・・・・・6月21日 平年より15日遅く、昨年より23日遅い
東海・・・・・・・・6月21日 平年より15日遅く、昨年より23日遅い
四国・・・・・・・・6月22日 平年より4日遅く、昨年より11日遅い
中国・・・・・・・・6月22日 平年より16日遅く、昨年より24日遅い
北陸・・・・・・・・6月22日 平年より11日遅く、昨年より13日遅い
東北南部・・・・6月23日 平年より11日遅く、昨年より14日遅い
東北北部・・・・6月23日 平年より8日遅く、昨年より14日遅い
なぜ、雨の日を“良い天気”といわないのか?
よく考えるとそうですよね~(反省)![]()
そこで、今回はその疑問や「雨」にまつわる雑学の数々を考察していきたいと思います![]() m(_ _)m
m(_ _)m
挿絵画像:Facebook 「ジブリ」より(おっしゃる通り!m(_ _)m)
そもそも “天気(の意味)” とは?
1. ある地点の ある時刻における 大気の総合的な状態(=気象状態)※意外と難しい
具体的には、気温、湿度、風向き、視程、降水、雲量、気圧などの要素を指すそうな
2. 晴天。※これだ![]()
天気 = 晴天 の概念が
“良い天気” = “晴天な日”
“悪い天気” = “晴天でない(雨もしくは曇りな)日”
という考え方になる
雨の種類が400種以上!?
![]() には、雨の種類を言いあらわす言葉が400種以上あるそうな
には、雨の種類を言いあらわす言葉が400種以上あるそうな![]()
日本語には雨を表現する言葉(呼び方)がたくさんあり、一説には400種以上あるそうな※さすが、四季があり、一年中雨が降る国、NIPPON![]()
それゆえに日本人は、昔よりその雨を疎み、時には感謝しながら、共生してきましたが、
その中で、悪いイメージの雨の表現や、逆に良いイメージの表現を解説![]()
ダークサイドな雨の表現
【天気予報でよく聞く言葉】
・大雨(おおあめ)
大量に降る雨。大雨注意報の基準を超える雨
・強雨(きょうう)
大量に降る強い雨
・豪雨(ごうう)
大量に降る激しい雨
・ゲリラ豪雨(げりらごうう)
限られた場所に短時間集中的に降る、急激な強い雨
・ゲリラ雷雨(げりららいう)
雷を伴ったゲリラ豪雨
・集中豪雨(しゅうちゅうごうう)
限られた場所に集中的に降る激しい雨。警報基準を超えるような局地的な大雨
・スコール
短時間に猛烈に降る雨。熱帯地方で雨を伴ってくる突発的な強風に依る
・線状降水帯(せんじょうこうすいたい)
次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし組織化した積乱雲群によって、数時間にわたり、ほぼ同じ場所を通過、または停滞することで作り出される線状に伸びた、長さ50~300 km程度、幅20~ 50 km程度の強い降水をともなう雨域
【日本古来の言葉】
・鉄砲雨(てっぽうあめ)
大粒の、鉄砲のような強烈な雨
・篠突く雨(しのつくあめ)
細い竹や篠で突くような、激しく降る雨
・飛雨(ひう)
風が混じった激しい雨
・夕立(ゆうだち)
夏の夕方に降る、短時間で降る雷を伴った雨※「スコール」の和名ともいわれる代表的な表現
・神立(かんだち)
神様が何かを伝えようとしている「雷」を指すことから、夕立や雷雨を意味する※“神ってる” “神対応” という良い言葉もありますが、元々“神”は、畏怖の念を抱くものなんですね
・電雨(でんう)
夏に稲妻とともに降る俄雨
・鬼雨(きう)
鬼の仕業ともいえるような、急で激しい雨※「ゲリラ豪雨」の和名ともいえる表現。現代でもよく、“鬼かわいい” “鬼速い” とかいいますよね(笑)
・肘笠雨(ひじかさあめ)
急に降り出す雨。笠をかぶる暇もなく、肘で頭を覆う様子が由来
・長雨(ながあめ)
数日以降降り続く、まとまった雨
・陰雨(いんう)
しとしとと降り続く陰気な雨。「淫雨」とも書く
・地雨(じあめ)
強さが一定の長く降り続く雨
・連雨(れんう)/霖雨(りんう)
連日降り続く雨
・積雨(せきう)
積もっていくように、長く降り続く雨
・宿雨(しゅくう)
前夜から降り続く雨
・漫ろ雨(そぞろあめ)
それほど強くはないが、降り続く雨
・怪雨(かいう)
色がついていたり、異物を含む雨。つむじ風に巻き上げられた魚やカエル、木の実、火山灰などが降ったという観測もある
・時雨(しぐれ)
あまり強くないが、降ったりやんだりする雨。傘を差す間もなくすぐに晴れるような通り雨
・村時雨(むらしぐれ)
ひとしきり強く降り、すぐに通り過ぎる雨※ある意味“村時雨”も「ゲリラ豪雨」ですよね!
・片時雨(かたしぐれ)
ひとところに降る村時雨※まさに「ゲリラ豪雨(局地的大雨)」!
・横時雨(よこしぐれ)
横殴りに降る村時雨
・氷雨(ひさめ)
霙(みぞれ)や雪に変わる前の、非常に冷たい雨※ホント、冷たくて寒い雨も嫌ですね~![]()
・凍雨(とうう)
凍るような冷たい雨
・黒雨(こくう)
空を真っ暗にするような大雨
以上が、雨を悪いイメージにさせる表現
昨今、地球温暖化による異常気象の代名詞といっても過言でもない「ゲリラ豪雨」や「線状降水帯」と似た表現が古来日本にもあるのが、とても興味深い![]()
次に、良いイメージとして・・・
ライトサイドな雨の表現
・翠雨(すいう)
青葉に降り注ぐ恵みの雨
・喜雨(きう)
日照り続きの後に降る喜びの雨。「雨喜び(あまよろこび)」ともいう
・慈雨(じう)
干ばつを救い、草木を潤す恵みの雨。「喜雨」と同義
・甘雨(かんう)
草木を潤す、しとしととした雨。「慈雨」と同義
・穀雨(こくう/瑞雨(ずいう)
穀物の成長を促す雨
・緑雨(りょくう/青雨(せいう)
青々とした新緑の草木に降る雨
・紅雨(こうう)
春に咲いた花々に降り注ぐ雨
・白雨(はくう)
夏、明るい空から降る、俄雨※暑い夏の日の俄雨は “一服の清涼剤” になりますよね!
・洗車雨(せんしゃう)
陰暦7月6日、七夕の前日に降る雨。彦星が織姫に会う際に使用される牛車を洗う水と云われている※私も自家用車が汚れてる際に雨で洗車しますね(笑)
・血雨(けつう)
土壌由来の成分を含んだ、赤い色の雨
・作り雨(つくりあめ)
打ち水のこと※別名でこういう表現があるのですね
・樹雨(きさめ)
濃霧の森林を歩いている時に葉から滴り落ちてくる雨※心地よさそうですね
・雪解雨(ゆきげあめ)
冬に積もった雪を解かすようにふる雨※雪国の方には “恵みの雨” では?
・催花雨(さいかう)
花の育成を促す雨。「養花雨(ようかう)」「育花雨(いくかう)」とも呼ばれる
・麦雨(ばくう)
麦が熟する頃(梅雨の時期)に降る雨
以上が、雨を良いイメージにさせる表現
さすが、 “農耕民族” らしい “用水” としての役割が大半ですね
なぜ、「梅雨」に「梅」の漢字がはいるのか?
次に「梅雨」についてのお話
なぜ「梅雨」というのか?
諸説あるそうで、一般的なものとして下記の二つが挙げられるそうな
1.中国ルーツ説
![]() の揚子江周辺では、梅の実が熟す頃が雨期にあたり、そのことから「梅」の字を使うようになったとされる
の揚子江周辺では、梅の実が熟す頃が雨期にあたり、そのことから「梅」の字を使うようになったとされる
2.当て字説
雨によって黴(かび)が生えやすくなることがあげられ、そこから「黴雨(ばいう)」という言葉が生まれたというもの。ただし、語感が良くないので、「黴(ばい)」の字ではなく、「梅(ばい)」という字になったそうな
以上、二つの説で共通することは、「梅雨」は、当初 「ばいう」 と呼んでいたということ
なぜ、「梅雨」は「つゆ」と読むのか?
諸説あるそうで、一般的なものとして下記の二つが挙げられます
1.露(つゆ)けし語源説
雨が多い時期であることから、「露にぬれて湿っぽい 」という意味を持つ
「露けし」 からとったとされる
2.潰(つい)ゆ語源説
梅が熟して潰れる時期であることや、長雨により食べ物や衣服が傷んでしまう時期であることから、「潰ゆ(ついゆ)」 からとったとされる
「梅雨」にも色んなものがある
・入梅(にゅうばい)
梅雨に入ること。由来は梅の実が熟す頃に降る雨から
・栗花落(ついり)
梅雨に入ること。由来は栗の花が散る頃に降る雨から。「堕栗花」とも書く
・五月雨(さみだれ)
旧暦五月に降る長雨。梅雨のこと
・走り梅雨(はしりつゆ)
五月中旬から下旬にかけて降り続く、梅雨入り前の雨
・暴れ梅雨(あばれつゆ)
梅雨の時期の終盤に降る、強烈な雨
・送り梅雨(おくりつゆ)
梅雨明けを知らせる、雷を伴った雨
・返り梅雨(かえりつゆ)
梅雨明け後に、再び雨が降り続くこと。「戻り梅雨」「残り梅雨」とも呼ばれる
・旱梅雨(ひでりつゆ)
雨があまり降らない梅雨。「空梅雨(からつゆ)」「枯れ梅雨(かれつゆ)」とも呼ばれる
・男梅雨(おとこつゆ)
雨が降るときは激しく降り、雨が止むときはすっきり晴れる梅雨
・女梅雨(おんなあめ)
しとしととした、雨脚の弱い梅雨
※「男梅雨」「女梅雨」は、現代ではNG表現ですよね
「雨」にも “におい” がある
1.雨の降り始めのにおい・・・ペトリコール(石のエッセンス)
雨が降り始める際に、アスファルトから漂ってくる “におい”
これは、カビや排ガスなどを含むほこりが水と混ざり、アスファルトの熱によって、においの成分が気体となったものだそうです
この “におい” のことを 「ペトリコール(Petrichor)」。ギリシャ語で、「石のエッセンス」と呼ばれ
①雨粒が地面や植物の葉などに落ちた際に、微小な粒子を含んだエアロゾル(気泡)が放出
②植物由来の油が付着したエアロゾルが乾燥した粘土質の土壌や岩石に当たった際に、それらがもつ成分がエアロゾルの中に取り込まれる
③これらが、空気中に巻き上げられ、雨の降り始めの独特のにおいが生じる
そうな![]()
また、雨がまだ降っていないところでも、不思議と雨を感じさせるにおいがするのは、雨が降っているところで、においを取り込んだエアロゾルが、風などによって運ばれてきたことが一因と考えられるそうな
2.雨上がりのにおい・・・ゲオスミン(大地のにおい)
雨上がりの際に、地面から漂ってくる “におい”
これは、土中のバクテリアなどにより作り出された有機化合物で、カビ臭いにおいで、雨水によって拡散するそうな
この “におい” のことを「ゲオスミン(Geosmin)」。ギリシャ語で、「大地のにおい」と呼ばれます
「ペトリコール」や「ゲオスミン」の他にも、雨を感じさせるにおいの成分として、オゾンもあるそうな
それにしても、さすがギリシャ![]() 紀元前よりアスファルトを使い、石畳等の舗装道路を作っただけありますよね
紀元前よりアスファルトを使い、石畳等の舗装道路を作っただけありますよね![]()
「雨」にまつわる妖怪
日本の伝統文化でもある “妖怪”
この中にも「雨」にまつわるものがいて、そのことが「雨」に対して悪いイメージを与えたのでは・・・?
・雨降り小僧/豆腐小僧/雨の小坊主
![]() では雨の神を「雨師(うし)」と呼ばれ、それに仕える子供が「雨降り小僧」だといわれる。
では雨の神を「雨師(うし)」と呼ばれ、それに仕える子供が「雨降り小僧」だといわれる。
![]() では和傘を頭に被り、提灯を持った姿で描かれ、時に通り雨を降らせ、 人が困る様子を見て喜ぶいたずら好きの妖怪。似た妖怪に「豆腐小僧」 「雨の小坊主」がいる※ちなみに「豆腐小僧」が持っている豆腐をすすめられて食べてしまうと、体中にかびが生えるそうな(誰が食べるかっ
では和傘を頭に被り、提灯を持った姿で描かれ、時に通り雨を降らせ、 人が困る様子を見て喜ぶいたずら好きの妖怪。似た妖怪に「豆腐小僧」 「雨の小坊主」がいる※ちなみに「豆腐小僧」が持っている豆腐をすすめられて食べてしまうと、体中にかびが生えるそうな(誰が食べるかっ![]() )
)![]()
・すねこすり
犬のような姿をし、雨の降る夜に現れ、夜道を歩いていると、足の間をこすりながら通り抜けたり、歩いている人の足をひっぱって転ばせるという妖怪※メッチャ迷惑な妖怪や![]()
![]()
・雨女
ルーツが諸説あり
①産んだばかりの子供を雨の日に神隠しに遭って失った女性が「雨女」となり、泣いている子供のもとに大きな袋を担いで現れ、さらっていくもの
②雨の日に訪れる神が堕落して妖怪化したもの
などがある
基本雨女は、「雨を呼ぶ迷惑な妖怪」とされるが、干ばつが続いたときに雨を降らせてくれる「雨を呼び人を助ける妖怪」という神聖な「雨神(龍神)」の一種とされることもあるそうな※その昔、自称「雨女」の会社の同僚が慰安旅行で、本当に天気を覆して大雨を降らし、時の上司に「雨が降らない砂漠の国の王子の嫁になれ❗」と今なら立派なモラハラになることを言われてたの思い出しました(ある意味、神ってるよな~)
ちなみに、私も 迷惑な 「雨男」 です![]()
最後に、これから始まる「梅雨」の時期が楽しく過ごせるよう
「雨」にまつわる歌やその他アイテムを!
「雨」にまつわる歌
「雨の日」の髪の広がりやうねり、本当に嫌ですね
「雨の日」の過ごし方の本