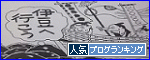伊豆高原情報ひろば発信元荻企画さんが”伊東・伊豆高原
案内図を持って来てくださいました。
その中に”伊東の民話”も少し盛り込まれていて、着実に
”伊東の民話”を広めようという動きが出て来たのではないかと
感じます(^_^)
神社には何ヵ所か行きましたが、ここは別の世界にすっぽりと
入ってしまう・・そんな感じです。
観光客の方がたくさん参拝する神社ではないかも知れま
せんが、とても魅力的・・という表現は不適切かも知れませんが、
何度行ってもまた訪れてみたくなります。
八幡宮来宮神社
広い階段が本殿まで続いています。
本殿の横には、大木があります。
八幡宮来宮神社の本殿には、向かって右に八幡宮、左に来宮が
祭られています。
社殿は、本殿・幣殿・拝殿の三棟によって構成され、本格的な堂宮建築の
手法で統一されています。
平成9・10年の大修理とそれに伴う諸調査により現存の社殿は、
本殿が寛政7(1795)年、拝殿が文政7(1824)年の建築であり、
伊豆各地の優秀な大工職がかかわっていることが判明しました。
本殿は二間社流造、拝殿は入母屋造で、両者をつなぐ幣殿は両
下造です。多くの神社建築が一間または三間の柱間となるのに対
して、この本殿は二間となっている点で非常に類例の少ない形態
であることが注目されます。
伊豆石製の強固な基礎に支えられ、社殿を飾る精妙な彫刻群の
存在とともに江戸後期を代表する神社建築として重要です。
平成11年3月15日指定 伊東市教育委員会
図説伊東の歴史より
照葉樹林の社叢が広がる。昭和9年に国指定天然記念物。
この社叢は、日本列島の暖かい地域の海岸線から遠いところ
に成立する照葉樹林の典型的な状態を示しています。
林をつくる高木としては、ウラジロガシ・アラカシ・スダジイ・タブノキ・
イチイガシなどがみられます。
また、高木にからみつくツル植物として、カギカズラ・フウトウカズラ・
テイカカズラなどがみられます。
林床には、リュウビンタイ・ハナミョウガ・モロコシソウ・オオヌスビトハギ・
ハイホラゴケなどがみられます。
これらの植物の中で、植物分布上注目すべき種類は、カギカズラ・
リュウビンタイ・モロコシソウなどです。
なかでも、大型のシダ植物であるリュウビンタイは、この社叢が日本列島
における北限自生地です。
この社叢は、ヒトの活動の影響をうけていない、自然の状態が保たれて
いる樹林として貴重なものです。
昭和9年8月9日 指定 伊東市教育委員会
リュウビンタイを発見しましたヽ(゜▽、゜)ノ
江戸後期にこの神社を現在の姿に整えた”肥田晴安”という方が
いました。
国学や医学を学び、曽我物語のパンフレット(版画)なども
旅人のために用意したと図説伊東の歴史に書かれています。
この神社との関わりももっと知りたいと思います。
初詣におススメ!!
●八幡宮来宮神社 伊東市八幡野
元旦0時~ もちつき大会 甘酒・お菓子(先着順)
応援お願いしますo(^-^)o