千葉県庁
毒物劇物取扱者試験のポイント
① まずは過去問を
ご存知のように、毒劇の試験は都道府県単位で行われています。
そして自治体によって出題内容がマチマチです。
真偽のほどはわかりませんが、ネット上の口コミでは、京都府がいちばん簡単だという情報があります。
ぼくは東京、埼玉、千葉で受験し、山梨県の過去問にも挑戦していましたが、勉強方法としては、受験しようと思う自治体に的を絞る方が格段に効率的だと思います。
すべての自治体ではないのですが、ホームページで過去問をダウンロードできる場合があります。
過去問は書籍でも購入できますが、高価ですし、複数の自治体で受験するのでなければ、大半のページが受験しない自治体の過去問になりますからちょっと勿体ない気がします。
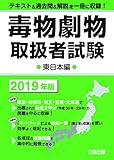 | 毒物劇物取扱者試験 2019年版 東日本編 2,800円 Amazon |
 | 毒物劇物取扱者試験 平成30年版 6,300円 Amazon |
 | 毒物劇物試験問題集〈東京都版〉過去問 平成31年度版―解答・解説付 6,200円 Amazon |
まずは入手可能な過去問をひと通りやってみましょう。自治体ごとに問題の作られ方に特徴があることがわかると思います。
→法令は穴埋めのみで簡単だけど、基礎化学に必ず計算問題があってハイレベル
→設問自体は高度だけど毎年同じ物質からの出題なので暗記で対応可能
などなど
特に、自治体ごとの過去問をこなすことで、出題される物質がある程度絞れてくるのではないかと思います。
毒劇物試験の参考書の多くは自治体ごとのそうした傾向には対応していないので、いわゆる「一般的」なことが記載されているだけです。
過去問で傾向を掴み、的を絞った上で必要な部分だけ毒劇物試験の参考書を活用するのがよいと思います。
② 基礎化学は中高の参考書を
基礎化学に関しては、毒劇物試験の参考書よりも、中学や高校の参考書の方が格段に分かりやすいと思います。
過去問で出題傾向を掴み、そこを重点的におさえていけば良いと思います。
 | 【改訂版】宇宙一わかりやすい高校化学(理論化学) 1,598円 Amazon |
中学生や高校生向けに作られた化学の解説動画もいくつかあるので検索してみると良いと思います。
③ 効率の良い暗記を
すべての物質について覚えるのはハッキリ言ってムリだと思います。
出題されそうな物質がある程度絞れたら、物質ごとに性状、貯蔵方法、廃棄方法、応急措置、毒性を表にまとめて暗記するのが効果的です。
例)黄リン
ロウ状固体、自然発火性→水中保存、燃焼法、土砂又は水で覆う、触れると火傷
また、「この言葉が出たらコレ」という風に、キーワードで覚えるのもオススメです。
例)貯蔵方法で「ライニング」→弗化水素
 | 毒物劇物取扱者合格教本 Amazon |
個人的には、過去問はすべてダウンロードしたものをプリントアウトして使い、使った参考書は2冊だけでした。
準備期間は約2ヶ月。
勉強時間は週に3時間くらい。
カフェなどで1回40分を週に3〜4回。
カフェ代は結構かかったかもしれません。
元素周期表は半分くらいは暗記した方が良いでしょう。「見て書いて」を繰り返していれば、意外と覚えてしまいます。
【来年受験される方】
ぼくの場合は千葉県ですけど、実際に何をどう暗記したのか、メッセージを頂ければ具体的にお伝えします。

