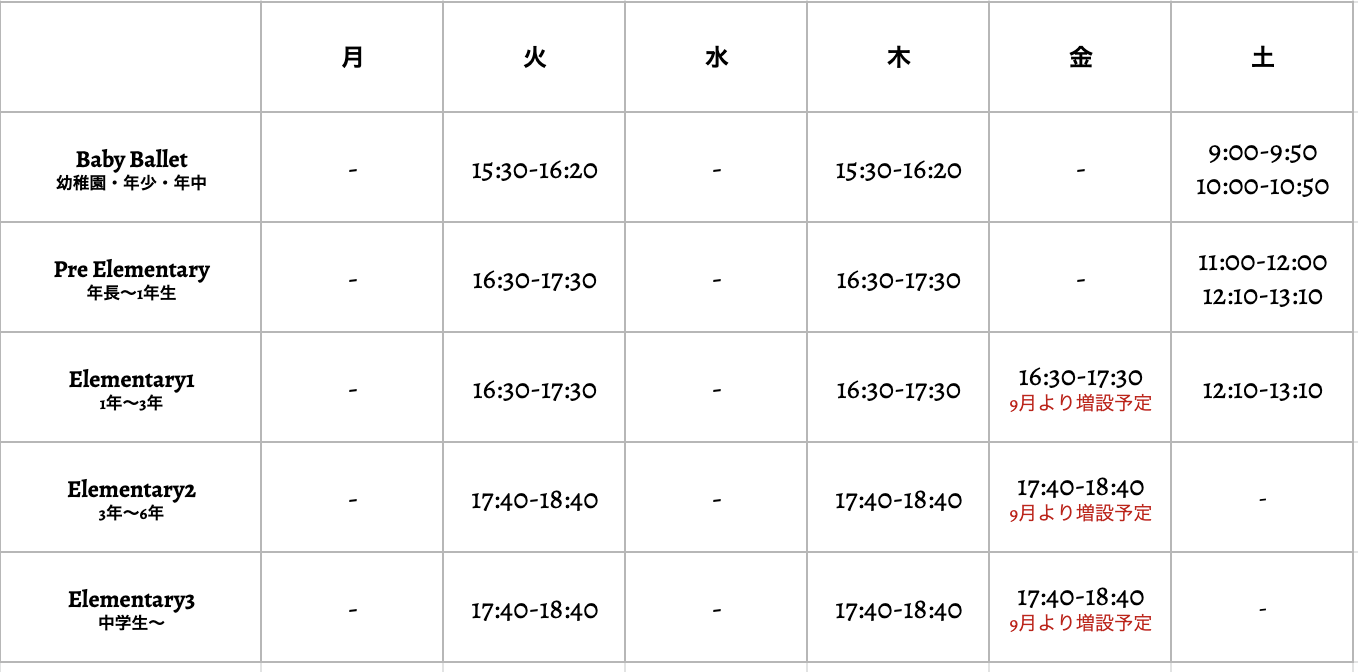こんにちは、池上校講師の木村美那子です。
幼稚園や保育園、そして小学校での生活にも慣れ、各自のペースが出来て来ていると思います。
お友だちと遊ぶ機会も増え、様々な刺激に触れるようになった子どもたちにとっては、毎日が学びのチャンス、成長のチャンスです。
一方で刺激を受ける機会が増えるということは、ポジティヴな面だけでなく、刺激によるダメージや、影響も大きく受けるという少々ネガティヴな面もあります。
特に子どもたちの思考や心には、大人ほどの自覚的な防衛線は張られていませんから、より丁寧な配慮や段取りが必要になります。
コミュニケーション能力の向上に必要な要素として、共感と共有があげられます。
赤ちゃんのうちは、泣くことでしか自分の状態を伝えることが出来なかったものが、段々と自分の快・不快を表現出来るようになり、そして自分が今どんな気持ちでいるかを整理し、また他者がどのような気持ちになるかを想像することが出来るようになっていきます。
この成長段階にあって大切なのが、共感と共有というキーワードです。
子どもたちはこの世界に生まれてわずか数年ですから、そもそもの経験値が少ない上に、語彙の学習以前の聞く力や見る力の向上も必要な状態です。
そのような状態で、子どもたちが自分の力だけで、自分の気持ちを冷静に整頓し、相手に伝えることは時によっては難しい場合もあります。
例えばお友だちとかけっこをしていて、お互いにぶつかってしまった時に、大声で泣いてしまうことは良くあることです。
もちろん事前に「(走らないで)歩こうね!」と声がけをすることや、「お友だちとぶつからないように注意しようね!」という注意喚起も大切ですが、子どもの「いま、ここ」へのフォーカスは大人が考えているよりも限定的なので、「ほーら、言ったでしょ!」は有効でないばかりか、子どもたちにすれば「(いま)怒られた…」という経験に結び付きがちなので、注意が必要です。
そのような時に「泣かないの!」という心身の反応を無理やり押し止めるような声がけや「大丈夫だよ」という安易に意味の無い声がけをするよりは、現実的な「ぶつかっちゃったね」、「いたかったね」、「びっくりしたね」など、子どもたちの複数突発的に起きた事象や刺激、感情に寄り添い、代弁することで本人も思考を整理することが出来るようになっていきます。
もちろんいつまでも大人が代弁していては、自分の頭で考えるようにならなくなってしまうので、段階的に「いま、どうしたかな?」、「どんな気持ちかな?」と問いかけをしていくことで、子どもたちの思考回路を形成していく段取りも大切です。
そこで本題の「その言葉、正しく伝わっていますか?」となります。
大人で言うところの正しさが、子どもたちに「いま、ここ」で必要な正しさとイコールではないことは、子どもの発達、発育、成長の段階を考えれば、思いが及ぶところですが、子どもたちにとって理解しやすい音であるか、イメージしやすいものであるか、共感性があるかどうか、また子どもたち本人の体験を共有した声がけであるかどうか…等、考えるべきところは多くあります。
レッスンで言えば、子どもたちがお家や幼稚園、保育園、学校でどのように呼ばれているか、から始まり、オノマトペはもちろんのこと、名詞、動詞、形容詞、副詞の難易度や正確性、複雑性はすべて考慮して段階的に向上していくべき、重要なポイントです。
「大きくなってから困らないように」と正しさを優先して、共感性の低い声がけばかりをすることがないように、大人の側がしっかりと考えて声がけをするよう心がけていきたいものです。(木村)