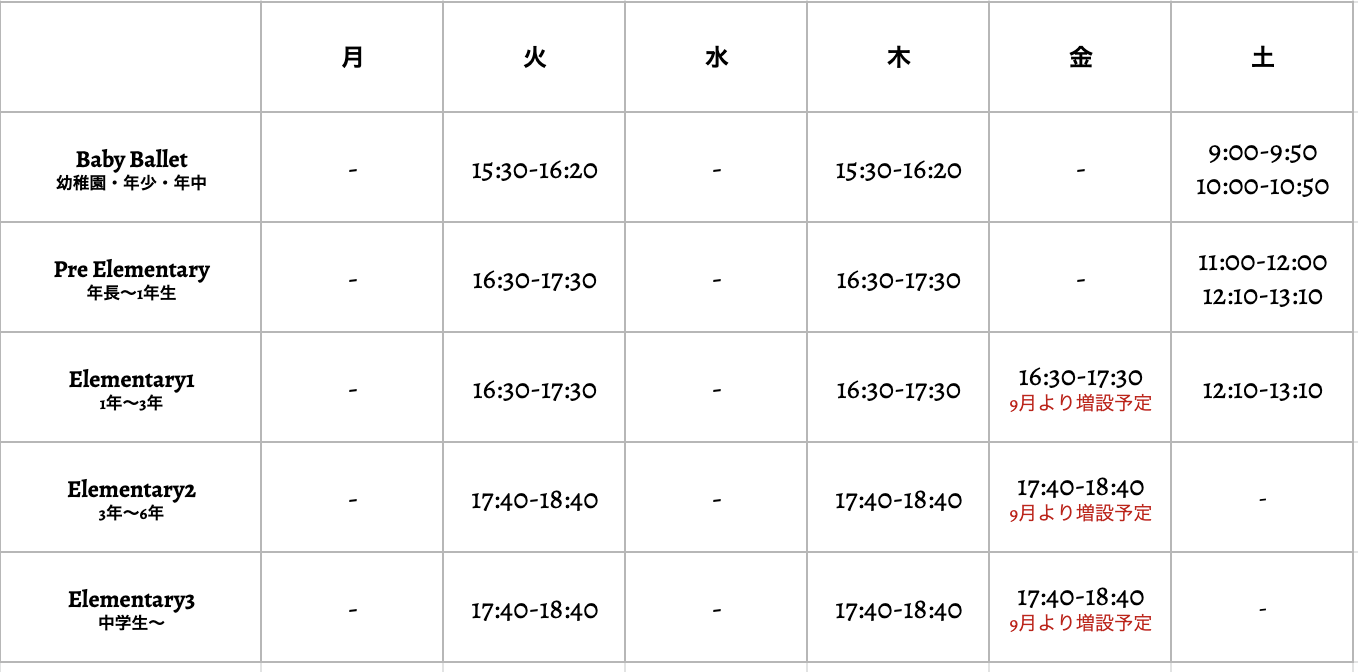こんにちは、池上校講師の木村美那子です。
みなさんは「まなぶ(学・ぶ)」という言葉の語源が「まねぶ(真似・ぶ)」であるという説があるのをご存じですか?
ものを学ぶことの第一歩として、お見本の真似をすることの大切さを今回はお伝えしてまいります。
お見本の見せ方については、先の投稿でもお話しましたが、まずは何の説明も加えずに通常の2倍から3倍の時間をかけた速度で実施し、その後に言葉の説明を付け加えたり、上手に行うためのポイントを伝えたり、その動きを一緒に繰り返し練習したりします。
大人が何かを学ぶ時は、同時に説明を加えることもありますが、これは大人の情報処理能力に合わせて行っていることであり、また少々ネガティブな表現をすれば「大人になるまでに不足している身体操作性や運動性(動きのセンス)を補うため」でもあります。
しかし子どもの場合は、まだ固定化されていない(可能性の大きな)身体操作性の余白がありますし、情報処理の段取りや、1回に処理出来る情報量が限られていることを考えて、手渡す情報を限定したり、純粋に身体を動かすことから馴染ませていくようにしています。
近年、学習や習熟を早めようという狙いもあってか、真似っこではなく、マニュアル的に正しさだけを優先する身体操作のみを実施している幼児教育が多くなっているように感じています。
たとえば、向かい合って立ってある動きをする時に、シンプルに相手の動きを(または先生のお見本を)真似っこするのではなく、右左や上下の正解について「頭で」考えてから動こうとするお子さんや、時にそれらを考えすぎて身動きのとれなくなっているお子さんを見かけます。
左右の感覚などを身に付けることについては、早い方が良いのかも知れませんが、右左の感覚が実際に子どもたちの「知識」として定着するのは、小学1年生以降のことであるという説もありますし、マニュアル的な正しさにとらわれて、身動きがとれなくなることは、レッスンにおいては本末転倒ですから、まずは真似っこをするところから、楽しくのびのびと身体を動かし、バレエを学んでいってほしいと思います。(木村)