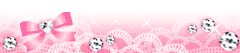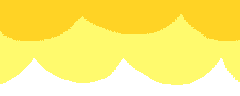「マナブ。小学校のときに同じクラスだった丸山君て憶えてる?
あの子、先日病院で亡くなったそうよ。
今日がお通夜なんだけど、あなたも一緒に来なさいね」
中学校から帰って来た学は突然の母の言葉が理解できなかった。
<丸山が死んだ? 丸山って何カ月か前に駅前で偶然会って話したじゃん>
今まで想像もしたことが無い同級生の死という事実は、学の頭の中を素通りしてなかなかとらえることができなかった。
実際、学は丸山とそれほど仲の良い友達という関係では無かった。
直ぐに思い出せる想い出と言えば小学校6年のときのドッチボールの試合のときのことくらいである。
「丸山って結構ドッチ上手いじゃん。普段あまりやらないから下手なのかと思っていた」
毎週放課後にある自由参加のクラス対抗ドッチボールの帰りに学は丸山と一緒の帰り道でそう話しかけた。
「そんなことないよ。でも勝ててよかったね」
「また来週も一緒にやろうよ」
学は普段あまり遊ばない丸山だったが、ドッチボールでは気が合ったのでなんとなく親近感が湧いていたのだ。
「うん。でも今日は特別なんだ。普段は塾があって放課後は直ぐに帰らないと間に合わないからね。
今日は運よく塾の先生が休みなのが分かっていたから、母さんがたまには友達と遊んできて良いって言ってくれたから」
「そうなんだ。毎日塾で勉強なんて大変だな。だから丸山は頭良いんだな」
「いや、塾の勉強は受験用で学校の勉強とは違うんだ」
「丸山って中学受験するの?」
「うん、親がその気で4年の頃から勉強させられているんだ」
丸山はそれが普通のことのように答えた。
「僕は中学は公立だから勉強は必要ないけど、やっぱり受験は大変なんだろうな」
「まぁ、あと少しだし入るまでだから。親の期待もあるし頑張ってみるさ」
自分でもまんざらではないような口調で丸山は独り言のように言った。
以上が学が憶えている丸山との小学校での思い出である。
葬儀は近くの公民館で行われていた。
行ってみると同級生がそれぞれの親につれられ散見された。
学区が違うために小学校以来久しぶりに見る顔もあり、学はなんだか同窓会のような気持ちになっていたが、
さすがに周りが神妙な雰囲気のため声をかけることができず、互いに小さく手を挙げて挨拶する程度ですれ違うのであった。
祭壇では大きく引き伸ばされた丸山の写真が笑っていた。
<あれはきっと小学校の頃の写真だな>
学は母親をマネて焼香をしながらそう思った。
焼香が終わると簡単な食事が用意されていると案内されたが、学達同級生は皆外でたむろい、母親達は挨拶だけということで会場へと別れた。
こういう場で会う同級生は、普段街で会うのとは違い各々がちょっと大人びて見え、会話も必然的に小学校時代を懐かしむ話題ばかりが交わされた。
「丸山君、実は自殺だったらしいよ」
家に帰ると母はちょっと気まずそうに学に教えた。
お通夜の席で丸山と仲の良かったママ友がそっと教えてくれたそうだ。
「状況はよくわからないけど、お母さんが発見して直ぐに救急車で病院に運んだけど間に合わなかったんだって」
学はそれを聞くと何も言わずに自分の部屋へ向かった。
部屋に入った学は力なくベッドに座り、ほんの数カ月前に駅前で丸山と会ったときのことを思い出した。
「木村君?」
「あれ?丸山じゃん。久しぶりだね」
「木村が本屋にいるなんて、珍しくない?」
「別に。今日は漫画の発売日だからちょっと立ち読みにね」
そうい言うと学は照れ笑いした。
「丸山は相変わらず参考書でも探しているの」
「僕は塾までまだ時間があるから時間つぶしだよ」
そう言うと丸山は腕時計をちらっと見ながら
「そうだ。まだ時間あるからちょっとマックにでも行かない?」
と学を誘った。
夕方の駅前のマックは学生が沢山いたが、窓際のスタンド席にはまだ少し空きがあった。
二人はコーラを買って並んで座ったが、あまりに久しぶりで共通の話題が直ぐには見つからず、手持ちぶたさに各々のコーラを飲んだ。
「ほんと久しぶりだな。卒業以来だよね?」
学はまたコーラを一口飲んでから、話題を切り出した。
「丸山は何処の中学に行ったんだっけ?」
「宿宿だよ」
「何それ?」
「新宿教育学園新宿中学」
「えっ、そんなの聞いたことないけど、やっぱり新宿にあるの?」
「まぁね」
丸山はちょっと笑って言った。
「やっぱり偏差値高いんだろうな…」
学はどんな学校か解らないけど中学受験していた丸山のことだからきっと有名進学校だと思った。
「木村。進学校ってなんで沢山の東大合格者を出すか知ってる?」
丸山は学の質問には答えず、逆に学にクイズのように質問した。
「やっぱり良い先生がいて、勉強も凄いからなんじゃない?」
「ブー。生徒がみんな頭良いからです」
丸山は笑いながらそう答えた。
「何だよそれ」
学は当りまえじゃんと思い笑った。
「いや、そういう意味じゃなくて。
受験に合格して入ってくる奴らって本当に頭良いんだ。
とにかく毎日最低でも5時間以上は勉強してるんじゃないかな。
もちろん学校以外でだよ。
あいつら本当に勉強が大好きなんだよ」
丸山は更に続けた。
「逆に、学校ではあまり勉強しないんだ。
学校の授業だって、確かに進みは早いけどみんな塾で先に習っているから全然追いついていけるんだ。
だからみんな学校は塾の復習くらいに思っているんじゃないかな。
学校も通常のカリキュラムを進めて、早く受験用の授業に移したいからその日に終わりきらない部分はみんな宿題にして終りだよ」
「へぇ、そうなんだ。大変そうだな。でも丸山だってその中の一人なんだから凄いじゃん」
「違うよ。僕は受験のために毎日5時間くらい勉強したけど、あいつらは、勉強するために毎日5時間勉強しているんだ。
僕は受験という目標のために5時間勉強したけど、あいつらは勉強が生活の一部なんだよ。
僕は毎日の授業について行くために勉強するけど、あいつらはその必要がないから学校は息抜きの場なんだよ」
丸山は呆れたようにそう言った。
「でも丸山だって頭良いじゃん。テストだっていつも満点だったし」
「範囲が決まっている学校のテスト勉強なんて楽なもんだよ。ほとんど暗記すれば良いだけなんだもの」
「その暗記が大変なんじゃん。僕なんていくら憶えようとしても一晩経てばみんな忘れちゃうもの」
学は笑いながらそう答えた。
「それは暗記の仕方が悪いからさ。
たとえば元素の周期表を憶えようとするだろ。
だいたい最初の4段くらいが範囲だから、1番目から順番にクラスの人に割り振るんだ。
木村だってクラスの人の名前くらい直ぐに憶えるだろ?
それと同じで、クラスメイトの名前が元素記号だと思えば良いんだよ。
一番前の左が水素。その次がヘリウム。
顔を思い出しながら『あいつはリチウム君』てな具合にね」
顔を思い出しながら『あいつはリチウム君』てな具合にね」
丸山は小学校時代に暗記のためにクラスメイトに付けた名前を思い出しクスッと笑った。
「良いこと教わった。今度からそれ使わせてもらうわ」
学は関心しながらそう言った。
「ところでさぁ、木村ってマクロとミクロって習った?」
丸山は突然学にそう質問した。
「良くわからないけど、多分習っていないと思うよ。それって何?」
「マクロは全体的なことでミクロはその一部って言う感じかな。
たとえば宇宙全体がマクロならミクロは地球のこととか。
でも地球をマクロとすれば、そこに住む人はミクロっていうことになるんだ。
だから宇宙的マクロにみると僕達ミクロな存在は、ゴミみたいなものなんだよ」
丸山は更に続けた。
「たとえば、足元の蟻を踏み潰しても僕らの生活には何も影響無いだろ。
マクロな地球から見ればミクロな蟻なんてなんてこと無いんだよ。
たとえそれで生態系が崩れたとしても、マクロな宇宙から見ればミクロな地球の生態系なんて何ら関係ないんだよ」
学は丸山が何を言いたいのか皆目わからなかったが、なんだか教養的な話なので黙ってうなづいて聞いていた。
「何を言いたいかというと、僕らの受験勉強なんてさ…
宇宙から見ればなんてことないことなんだよ。
学校だってさ、行っても行かなくても地球の営みにはなんら影響ないよ。
そう思うと勉強なんてくだらないことだと思わないか?」
「なんだかよく解らないけど、確かに宇宙から見れば僕らはちっぽけな蟻んこに見えるんだろうね」
学は丸山が何か悩みがあるのかと思い調子を合わせてそう答えるのが精いっぱいだった。
「もうこんな時間だ」
丸山は時計を見た。
「なんか変な話して悪かったな。でも久しぶりにともだちと話せて嬉しかった」
丸山は笑顔で言った。
そしてこれから塾だからと、いっしょに店を出て別れた。
これが最後に丸山と会ったときの会話である。
今思えばあの時から丸山は悩みがあって苦しんでいたのかも知れない。
「あのときにもっと悩みを聞いてあげればよかった。きっと僕に同意を求めていたんじゃないかな。
だったら、マクロな宇宙から見れば学校の悩みなんかくだらないことだと、もっと励ましてあげればよかった」
学は自分に何かできたかも知れないかと思うと悔しかった。
そして取り返しがつかない今、後悔することしかできないのが悲しかった。
普段は忘れていた丸山の存在は、もうこの世に居ないという事実により学の心に重くのしかかっていた。
『なんだよ、死んじゃったら悩みは無くなるかも知れないけど、この先の人生も無くなっちゃうじゃん。
これから大人になって恋人とかにももう出逢えないじゃん。
結婚して自分の子供と遊ぶこともできないじゃん』
学はやりきれない気持ちでいっぱいだった。
それは丸山の若過ぎる死を嘆くとともに丸山だけが既に大人になっていたような、
自分がまだ成長してないような取り残された気持が混ざった複雑な気持ちだった。
けっして丸山が大人だとは思いたくは無いが、もう追いつくことができない事実が悔しかったのかも知れない。
『丸山。もし魂になって僕のことを見ているなら、今の気持ちを教えてくれないか?
死んで苦しみから解放されたの?
悔いは無いの?
死を選んだ気持ちってどうだったの?』
学は繰り返し心の中で丸山に問いかけてみた。
でも、いくら考えても本人の本当の気持ちを知り得ることはなかった。
たとえ遺書があったとしても全て正直に書かれているとは限らないし、気持ちはいつでも変化するものだ。
そこに至る考えは解ったとしても、それを実行したとき頭は空白であったかも知れない。
もしかしたら、息絶える時にはその行為を後悔したかも知れない。
結局のところ人の死って本当にそれでおしまいで、
本人の時間はそこで止ったままに残された者の心の中だけに存在し、
残された者はその想い出だけを心で育てるしかできない。
もしそれすら忘れさられてしまえば、本人がこの世に存在したこと自体が自分には無かったも同然になるだろう。
だからずっと心のどこかに持っていてあげて、何かのときに思い出してはこの世にひき出してあげるのがせめてもの供養なのかも知れない。
「今の僕にはそれしか思いつかないよ…」
《おしまい》
なんだかうまく終われなかった(´□`;)