| スマトラ島沖地震 | |
|---|---|
  震源の位置(USGS) |
|
 ジャカルタ バンダ・アチェ |
|
| 本震 | |
| 発生日 | 2004年12月26日 |
| 発生時刻 | 7:58:53(現地時間) 0:58:53(UTC) |
| 震央 | 北緯3度18分57.6秒 東経95度51分14.4秒(  地図) 地図) |
| 震源の深さ | 30km |
| 規模 | モーメントマグニチュード(Mw)注19.3 |
| 最大震度 | 改正メルカリ震度IX:バンダ・アチェ |
| 津波 | 平均10m、スマトラ島北部で最大34mの津波 |
| 地震の種類 | 海溝型地震(逆断層(衝上断層)型) |
| 余震 | |
| 回数 | Mw6.0以上: 45回 Mw1.0以上: 4,700回以上 |
| 最大 余震 |
2004年12月26日11:21(現地時間)、Mw7.1 |
| 被害 | |
| 死傷者数 | 死者 22万人注2 負傷者 13万人注2 |
| 被害総額 | 9億7,700万ドル(必要とされる緊急支援額)注3 |
| 被害地域 | スマトラ島を中心とするインドネシア、およびマレーシア、タイ、ミャンマー、インド、スリランカ、モルディブ、ソマリアなど |
| 注1: ノースウェスタン大学の調査による。USGSは9.1としている。 注2: 2005年6月現在、ロイターおよびWHOによる。 注3: 国連による。 出典:特に注記がない場合はUSGSによる。 |
|
| プロジェクト:地球科学、プロジェクト:災害 | |
| テンプレートを表示 | |
2004年スマトラ島沖地震(スマトラとうおきじしん)は、2004年12月26日、インドネシア西部時間07時58分53秒(UTC00時58分)にインドネシア西部、スマトラ島北西沖のインド洋で発生したマグニチュード9.1[1]の地震である。単に「スマトラ島沖地震」といった場合、この地震を指すことが多い。
目次
解説
この2004年スマトラ地震におけるマグニチュード9.1は、1900年以降でチリ地震に次いで2番目に大きい規模である。これはモーメントマグニチュード (Mw) であり、ハイチ地震 (Mw7.0) の約1,400倍、2003年十勝沖地震 (Mw8.0) の約40倍、東北地方太平洋沖地震 (Mw9.0) の約1.4倍に相当するエネルギーである。
また、アメリカ地質調査所 (USGS) の暫定発表で当初マグニチュード8.1と発表されていたが、次にマグニチュード8.5、さらにマグニチュード8.9と発表された後、9.0に修正された。さらにその後、アメリカ・ノースウェスタン大学などの研究グループにより、9.3に再修正された。
2012年現在、USGSではマグニチュード9.1としている[1]。最終的には米ノースウエスタン大学と同程度の値になる可能性もある。これは、震源地でプレートが3回に渡って南から順にずれ、そのずれの継続時間が6 - 7分にわたったためと見られている。
震源域は研究機関によって異なり、およそ1,000km - 1,600kmと長さをもつ。地震後のGPSや実地調査では、スマトラ島北西沖にあるニアス島からインド領のアンダマン諸島北端までの広範囲で隆起・沈降・水平移動といった地面のずれ(変位)が観測されている。国土地理院の分析によれば、震源域はミャンマー領ココ諸島(英語版)とアンダマン諸島北端の間付近から、ニアス島の北西に位置するシムルー島(英語版)北部までの約1320kmとされている。
平均を取って約1,300kmだとしても、日本列島沿岸の海溝に当てはめれば銚子沖から得撫島南方沖あたり、あるいは銚子沖から奄美大島東方沖あたりにまで及ぶ規模である。M9.3の本震だけを見ても,ずれた断層(プレートの境界面)は南北に約400km、東西に約150kmにわたる範囲に及び、ずれた距離(変位)は最大約20mという巨大な規模のものであった。
大津波が発生し、インドネシアのみならず、インド洋沿岸のインド、スリランカ、タイ王国、マレーシア、モルディブ、マダガスカル、ソマリアなど東南アジア全域に加え、東アフリカ等でも被害が発生した。本地震ののち、チリで津波デマによるパニックが起こり1人が死亡したほか、世界各地で新たな地震発生後に津波を警戒して住民が早期に避難した事などから、この地震が世界中に知れ渡り、人々の心に強く残ったことを示している。
この地震以降、スマトラ島周辺では大きな地震が多発している(詳細は「スマトラ島沖地震」参照)。
各機関の解析によるマグニチュード
地球シミュレータによる計算結果よりMw=9.1[3]、埋込式体積ひずみ観測結果よりMw=9.1~9.2[4]、深部ボアホールひずみ観測結果よりMw=9.2、地球の自由振動の観測結果よりMw=9.1 - 9.3の値が算出されている。
地震の発生間隔
過去数千年で複数回の、大規模な津波の発生の痕跡が発見されている。
地層の発掘調査による
2008年、日本の産業技術総合研究所とアメリカの地質調査所、豪州地質調査所、ワシントン大学、タイのチュラロンコン大学などにより組織された共同調査隊は、タイ王国南部のインド洋沿岸で地質調査を行い、過去約2500年間の地層中から4層の津波による地層を発見した。この調査結果から、2004年と同様の大津波は数百年に1回発生していて、それぞれ550 - 700年前頃、2200 - 2400年前頃と推定されている。。
歴史文学による
900年に、インド南部のベンガル湾に面したタミル・ナードゥ州にインド洋からの大津波が襲来し、修道院・寺院にいる数百人の人々が犠牲になったという記録が、同州の図書館に残っている。また、インドのジャーナリストであるKalki Krishnamurthyの小説「Ponniyin Selvan(犠牲の頂点)」にも同様の記述がある[6][7]。
考古学的な調査による
インドの研究者は、インドの東海岸に位置する7 - 12世紀の考古学遺跡から発見された津波堆積物が900年頃に大津波があったことを示していて、2004年と同規模の超巨大地震は周期性があると推測している[8]。同調査によれば、インド東岸に被害をもたらしたインド洋からの大津波は、過去2000年間で900年頃と2004年のものが判明している。
前兆的変化
統計数理研究所の解析によれば、スマトラ・アンダマン地域での1973年以降の地震を調査したところ、2000年7月(M9.1 の約4年半前)から同地域の地震活動が活発化していた。しかし、日本の東北地方太平洋沖地震の例では地震前に静穏化傾向が示されており、何故『活発化』で有ったのかは不明である。
地震の概要
スマトラ島の西方約160km、深さ10kmで発生した地震はマグニチュード9.3の巨大なもので、1960年に発生したチリ地震のマグニチュード9.5に次ぐ超巨大地震であった。震源はスンダ海溝に位置し、インド・オーストラリアプレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことによる海溝型地震の多発地帯の中にあった。これにより、ビルマ・マイクロプレートの歪みが一気に開放された。
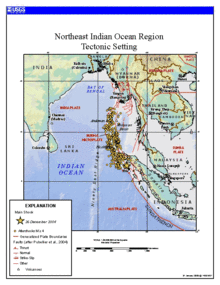
スマトラ島沖地震の本震(☆)と余震(○)の震源の分布、M4.0以上、USGSによる
この地震の破壊開始点は震源域の南端にあたる北緯3.298度、東経95.779度付近で、海洋研究開発機構らの解析にれば、大きく分けて3段階で進行したことが分かった[10]。第一段階は、南側のスマトラ島沖(スマトラセグメント)が断層長さ420km * 幅240km(平均5 - 20mのずれ量)、次いで中央部の(ニコバルセグメント)が断層長さ320km * 幅170km(同5m)、さらに北側(アンダマンセグメント)が断層長さ570km * 幅160km(同2m以下)ずれた。全体として長さ1,200 - 1,300kmの震源域であり余震域にほぼ一致する。
断層のずれは逆断層型で、断層面が平行に近い衝上断層と見られている。地震発生時、沈み込むインド・オーストラリアプレートに対して、上にあるユーラシアプレートの海溝に近い西側の帯域が隆起、海溝から少し離れた東側の帯域が沈降したことによって、震源域より西側のスリランカやアフリカなどでは初めに押し波、東側のタイなどでは初めに引き波が押し寄せたと考えられている。
この隆起や沈降は、現地調査やGPS観測によるもので、地震の際に大きく変動を起こした上、震源域より北の地域でも数ヶ月間に渡り地殻の変動が続き、橋本学・京都大学大学院教授によるとモーメントマグニチュードの換算でMw8.8 - Mw9.0と見積もられるという (PDF)
(余効変動)。アンダマン諸島北西のノースリーフで約1.3mの隆起、南東のポートブレアで約0.95mの沈降を観測するなどし、海岸線が移動して、隆起した地域ではサンゴが死滅するなどした。
- 安藤雅孝・名古屋大学環境学研究科附属地震火山・防災研究センター長によると、ビルマプレートに対するインドプレートの沈み込み速度が年間2センチ程度で今回のすべり量が30mであることから、同様のM9クラスの超巨大地震の歪蓄積にはおよそ1000年前後必要だと報告している(日本応用地質学会 平成17年度研究発表会)。
地震動(地震の揺れ)は震源の南端では3分ほど、インドネシアのバンダ・アチェなど少し離れたところでは6 - 7分続いた。バンダ・アチェの揺れは、気象庁震度階級では震度5強から6弱程度の強い揺れで、しかもその揺れが6 - 7分も続いたことで、住民に強い恐怖感を与えた。
遠いところではバングラデシュ、インド、スリランカ、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、タイ、モルディブまで伝わったほか、日本では防災科学技術研究所の広帯域地震観測網(F-net)で表面波(レイリー波の鉛直成分)のうち周期200~330秒の超長周期地震動として観測された。北海道大学によると秒速約4km、14400km/h(空気中のマッハ11前後に相当)で地球を少なくとも5周(約3時間で地球を一周)しており、13周した可能性もあるとみられている。
- 長さ1,200 - 1,300kmに及ぶ震源域で余震が発生しており、本震発生後24時間以内にマグニチュード5以上の余震が26回、(ベンガル湾東端のアンダマン諸島付近で13回(最大6.3)、ニコバル諸島付近で5回(最大7.3)、スマトラ島北部西方沖で6回(最大6.2)、スマトラ島北部で2回(最大6.0))発生した他、2005年1月17日までにMs6.0以上の余震が16回に達するなど、規模が大きい余震の回数が非常に多かった。
- 12月28日、アメリカ合衆国地質調査所は、この地震によってプレートが最大で約30mもずれ、ニコバル諸島等が地図の書き換えが必要なほど移動した、という観測結果を発表した。1月4日には訂正し、地表面が1 - 2m以内で移動したに留まるという試算結果を発表した。
以下の表は、アメリカ合衆国地質調査所 (USGS) が観測した本震と以後の余震の一部である(資料元:USGS)。
| マグニチュード | 日時 (年/月/日) |
協定世界時 (時:分:秒) |
北緯 (度) |
東経 (度) |
震源の深さ (km) |
震源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1(または9.3) | 2004/12/26 | 00:58:53 | 3.316 | 95.854 | 30.0 | スマトラ島北部西岸海上 |
| 5.9 | 2004/12/26 | 01:48:47 | 5.393 | 94.423 | 10.0 | インドネシア、スマトラ島北部 |
| 5.8 | 2004/12/26 | 02:15:58 | 12.375 | 92.509 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 6.0 | 2004/12/26 | 02:22:02 | 8.838 | 92.532 | 10.0 | インド、ニコバル諸島 |
| 5.8 | 2004/12/26 | 02:34:50 | 4.104 | 94.184 | 10.0 | スマトラ島北部西岸海上 |
| 5.8 | 2004/12/26 | 02:36:06 | 12.139 | 93.011 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 6.0 | 2004/12/26 | 02:51:59 | 12.511 | 92.592 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 5.9 | 2004/12/26 | 02:59:12 | 3.177 | 94.259 | 10.0 | スマトラ島北部西岸海上 |
| 6.1 | 2004/12/26 | 03:08:42 | 13.808 | 92.974 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 7.1 | 2004/12/26 | 04:21:29 | 6.885 | 92.938 | 39.7 | インド、ニコバル諸島 |
| 5.7 | 2004/12/26 | 06:21:58 | 10.623 | 92.323 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 5.7 | 2004/12/26 | 07:07:10 | 10.336 | 93.756 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 5.8 | 2004/12/26 | 07:38:25 | 13.119 | 93.051 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 6.6 | 2004/12/26 | 09:19:59 | 8.874 | 92.368 | 6.4 | インド、ニコバル諸島 |
| 5.5 | 2004/12/26 | 10:18:13 | 8.950 | 93.730 | 10.0 | インド、ニコバル諸島 |
| 6.2 | 2004/12/26 | 10:19:30 | 13.455 | 92.791 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
| 6.3 | 2004/12/26 | 11:05:01 | 13.542 | 92.877 | 10.0 | インド、アンダマン諸島 |
津波
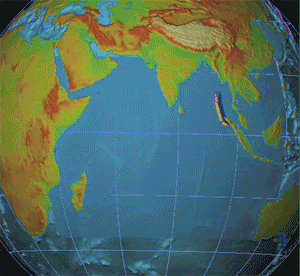
【イメージ】大津波のアニメーション(赤が海面の隆起、青が海面の沈降を表す)

タイの海岸に押し寄せる津波

津波襲来前の大規模な引き波、タイ・プーケットにて

モルディブの首都マレの海岸に押し寄せる津波
平均で高さ10mに達する津波が数回、インド洋沿岸に押し寄せた(地形によっては34mに達した場所もあった)。アンダマン・ニコバル諸島近海からスマトラ島北西部近海にかけてのおよそ1,500kmの帯状の地域(上のアニメーション参照)の、およそ海底4,000mの場所で津波が発生、津波発生時には2~3mほど海底が持ち上がり、ジェット機並みのスピード(約700km/h)で津波が押し寄せたと見られる。前述の速さで波が押し寄せたスリランカ、インド、モルディブ、アフリカ諸国などに対して、震源の東側となったタイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマーなどでは、比較的遅いスピードで津波が押し寄せた。特に、タイのプーケットに津波が到達したのは、地震発生から2時間30分後だった。これは、津波が通過したアンダマン海が、広い大陸棚が広がる浅い海で、津波が進むスピードが遅かったためである。
津波はアフリカ大陸東岸のソマリア、ケニア、タンザニアにも到達し、ソマリアで100人以上の死者が発生。ケニアのモンバサでは避難命令が出された。また南極大陸の昭和基地でも半日後に73cmの津波を観測した。また、アメリカ合衆国の西海岸、南アメリカ大陸でも数十cmの津波を記録した。