バイタルサイン(脈拍)
[心臓]
興奮-収縮連関(EC連関)とは・・・
心臓の興奮は1分間に約60回の頻度で周期的に生じている。この興奮は電気的なもので、まず右心房にある洞房結節から始まり、0.1秒間に心房全体に広がり、心室の機械的な収縮を引きおこします。
この洞房結節がペース・メーカーになって、心臓全体の収縮の頻度を決めています。そしてこの機能は、洞結節自身の活動の現われなのですが、同時に刺激的に作用する副交感神経の影響を受けて、そのペースが速くなったり遅くなったりします。
心房を興奮させ房室結節に到達した電気的興奮は、この部位で約0.1秒の遅れを生じ、次にヒス束、左右両脚を通じて心
室のプルキンエ線維を0.1秒以内で興奮させ、同様のEC関連によって心室筋を収縮させます。房室結節の伝導も交感神経や副交感神経によって影響されます。
心室筋の収縮によって左心室内圧は高まりますが、それにつれて僧帽弁が閉じると、左心室内は閉鎖された1つの部屋となります。そのままの状態で収縮がつづくので、心室内圧はさらに高くなっていきますが、この時、左心室の容積は変わらないので、等容積性の収縮と呼びます。左心室内圧が大動脈内圧を越えて高まると、初めて大動脈弁が開いて血液が全身に送り出されるのです。
[脈拍]
動脈内の圧の変化は、このような心臓の周期的な収縮によって血液の駆出で生じ、これが心臓側から動脈の末梢側へと伝達され、体の表面近くを走る動脈で拍動として脈拍として触れる。
ピーキング現象
心臓に近い部位から、末梢にいくにしたがって、最大収縮気圧は高まり、終末拡張気圧は低くなり、両者の脈差が大きくなる。
ダンピング現象
脈波をみて、末梢へいくほど丸みを帯びる。
脈波
脈波は脈の拍動としてとらえられる。
動脈内の血圧の変動として表される時には圧脈波。
血管外から血管の径、あるいは容積の変化としてとらえられる時には経脈波・容積脈波。
指先で触れる感覚は主に経脈波・容積脈波。
脈の所見
脈拍は心臓、血管、血液、神経系、内分泌、代謝などの状態を表す重要な徴候。
脈数とリズム
脈の一般的な所見では、数と調律に注目します。
脈の数は心臓の活動状態を端的に表すもので、交感神経緊張が亢進しているときは速く、副交感神経の緊張が強いときには遅くなります。
脈の性状
脈の性状で、脈波のパターン、脈波の立ち上がりの速さ・大きさ、消退の速さ、血管壁の硬さ、蛇行の有無、動脈壁の硬化状態がわかる。
頸動脈・・・
脈拍の性状が心臓の機能をよく表現し、重要な情報をあたえる。拍動パターンは急峻に立ち上がり、速やかに消退していきますが、この形状は年齢や種々の病態によって変化します。
脈波・・・
脈波の立ち上がりの速さは、左心室の収縮性、収縮の強さと速さを表すので、左心室の機能が亢進しているときには速く、きびきびした脈になる。反対に、収縮性が低下するか、左心室の出口に当たる大動脈弁口に狭窄などがあって血液が出にくい状態にあると、立ち上がりは緩やかになり遅脈となる。
脈の大きさ・・・
脈の容積とよばれ、左心室から駆出される血液量・1回拍出量を表す。1回に拍出される血液量が多ければ大きく、少なければ小さく触れることになる。
速脈・跳躍脈・・・
脈波は立ち上がりから、大きさを増して頂点(ピーク)に達した後、漸次減少していきますが、大動脈の閉鎖不全があって駆出された血液が左心室内に逆流するときには、この脈波の消退が急速に起こり、脈波は全体的に大きく速く立ち上がり、素早く減少していくこと。
分裂脈・・・
脈波の頂上にくぼみが出来て分裂したもの。これは、大動脈弁に軽度の狭窄を伴った逆流や大動脈弁下狭窄などでみられます。
[不整脈]
調律の異常は、脈拍数とリズムの異常パターンとしてとらえられる。脈拍数は分時60以下、60-100、100-150、150以上の4つの範疇に区別され、リズムのパターンは、規則的な整脈と不規則な不整脈に区別されます。また不整脈は、周期的に現れる規則性不整脈と全く規則性のない不規則性不整脈に区別されます。
期外収縮
脈拍数と心室拍数は正常では一致しますが、病的状態では一致しないことがある。期外収縮*の場合にはそれが、上室性であれ、心室性であれ、周期以外の早期に興奮が起こるときには、心室の血液充満が十分に行われないため、駆出される血液量が少なくなり、従って末梢まで脈として伝えられないので、触診上は脈が1つ欠落したように感知される。この欠落の後には通常の周期により、長い休止期が続くので、心室充満は通常よりも多くなり、左心室は強く、速く収縮して脈は大きく強く触れてきます。
*期外収縮―期測的な脈の間に割り込むように別の脈が入り込み、リズムを乱すこと。
頻脈
心室拍数が分時100以上の場合を頻脈と呼び、これには興奮生成やその伝達の機序に異常を生じて心室拍数が増す場合と、心拍出量を高める代償機序として心室拍数が増す場合が区別されます。心臓に病的な機能障害が発生して、1回拍出量が低下する場合には、これを補うために心拍数が増して、心拍出量を保とうとする。
心室拍数の増加・・・
これは、代償機序として必要だが、それが分時120を越えるときには不利益を生じる。まず、拡張期の短縮は心室の血液充満時間を短くして、1回拍出量をさらに減少させ、心拍出量はむしろ下降傾向となって冠血流量を減らし、冠循環は主として拡張期に生じる。このため、拡張期の短縮はそれ自体冠循環を減少させる。心拍数の増加は心筋の酸素消費量を高める。
徐脈
心室拍数が分時60以下を徐脈とする。スポーツマンなどでは、安静時心拍数が40以下ということがあるため、徐脈がすべて異常とはいえない。徐脈になると、拡張期がより延長して心室の血液充満度が増す。
また、徐脈は心筋の酸素需要を減らすので、それによって循環動態の破綻がこなければ、徐脈はある程度心筋にとって有利といえる。
[運動と脈拍]
最大心拍数とは・・・
運動によって心拍数が増し、血圧は上昇するが、その反応の大きさは運動の方法や強さ、年齢によって異なります。年齢が増すとともに、運動による心拍数の増加は少なくなり、最大に酸素を消費して行われる最大運動レベルでの心拍数、最大心拍数は年齢に比例して低下する。
最大心拍数=220-年齢
最大心拍数の意義・・・
これは、性差はなく、年齢と逆比例する。狭心症や心筋梗塞などの冠動脈性心疾患では、運動負荷試験によって症状や症候がでてきますから、その時点でテストを中止するため、最大心拍数は低くなる。
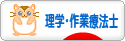
にほんブログ村


[心臓]
興奮-収縮連関(EC連関)とは・・・
心臓の興奮は1分間に約60回の頻度で周期的に生じている。この興奮は電気的なもので、まず右心房にある洞房結節から始まり、0.1秒間に心房全体に広がり、心室の機械的な収縮を引きおこします。
この洞房結節がペース・メーカーになって、心臓全体の収縮の頻度を決めています。そしてこの機能は、洞結節自身の活動の現われなのですが、同時に刺激的に作用する副交感神経の影響を受けて、そのペースが速くなったり遅くなったりします。
心房を興奮させ房室結節に到達した電気的興奮は、この部位で約0.1秒の遅れを生じ、次にヒス束、左右両脚を通じて心
室のプルキンエ線維を0.1秒以内で興奮させ、同様のEC関連によって心室筋を収縮させます。房室結節の伝導も交感神経や副交感神経によって影響されます。
心室筋の収縮によって左心室内圧は高まりますが、それにつれて僧帽弁が閉じると、左心室内は閉鎖された1つの部屋となります。そのままの状態で収縮がつづくので、心室内圧はさらに高くなっていきますが、この時、左心室の容積は変わらないので、等容積性の収縮と呼びます。左心室内圧が大動脈内圧を越えて高まると、初めて大動脈弁が開いて血液が全身に送り出されるのです。
[脈拍]
動脈内の圧の変化は、このような心臓の周期的な収縮によって血液の駆出で生じ、これが心臓側から動脈の末梢側へと伝達され、体の表面近くを走る動脈で拍動として脈拍として触れる。
ピーキング現象
心臓に近い部位から、末梢にいくにしたがって、最大収縮気圧は高まり、終末拡張気圧は低くなり、両者の脈差が大きくなる。
ダンピング現象
脈波をみて、末梢へいくほど丸みを帯びる。
脈波
脈波は脈の拍動としてとらえられる。
動脈内の血圧の変動として表される時には圧脈波。
血管外から血管の径、あるいは容積の変化としてとらえられる時には経脈波・容積脈波。
指先で触れる感覚は主に経脈波・容積脈波。
脈の所見
脈拍は心臓、血管、血液、神経系、内分泌、代謝などの状態を表す重要な徴候。
脈数とリズム
脈の一般的な所見では、数と調律に注目します。
脈の数は心臓の活動状態を端的に表すもので、交感神経緊張が亢進しているときは速く、副交感神経の緊張が強いときには遅くなります。
脈の性状
脈の性状で、脈波のパターン、脈波の立ち上がりの速さ・大きさ、消退の速さ、血管壁の硬さ、蛇行の有無、動脈壁の硬化状態がわかる。
頸動脈・・・
脈拍の性状が心臓の機能をよく表現し、重要な情報をあたえる。拍動パターンは急峻に立ち上がり、速やかに消退していきますが、この形状は年齢や種々の病態によって変化します。
脈波・・・
脈波の立ち上がりの速さは、左心室の収縮性、収縮の強さと速さを表すので、左心室の機能が亢進しているときには速く、きびきびした脈になる。反対に、収縮性が低下するか、左心室の出口に当たる大動脈弁口に狭窄などがあって血液が出にくい状態にあると、立ち上がりは緩やかになり遅脈となる。
脈の大きさ・・・
脈の容積とよばれ、左心室から駆出される血液量・1回拍出量を表す。1回に拍出される血液量が多ければ大きく、少なければ小さく触れることになる。
速脈・跳躍脈・・・
脈波は立ち上がりから、大きさを増して頂点(ピーク)に達した後、漸次減少していきますが、大動脈の閉鎖不全があって駆出された血液が左心室内に逆流するときには、この脈波の消退が急速に起こり、脈波は全体的に大きく速く立ち上がり、素早く減少していくこと。
分裂脈・・・
脈波の頂上にくぼみが出来て分裂したもの。これは、大動脈弁に軽度の狭窄を伴った逆流や大動脈弁下狭窄などでみられます。
[不整脈]
調律の異常は、脈拍数とリズムの異常パターンとしてとらえられる。脈拍数は分時60以下、60-100、100-150、150以上の4つの範疇に区別され、リズムのパターンは、規則的な整脈と不規則な不整脈に区別されます。また不整脈は、周期的に現れる規則性不整脈と全く規則性のない不規則性不整脈に区別されます。
期外収縮
脈拍数と心室拍数は正常では一致しますが、病的状態では一致しないことがある。期外収縮*の場合にはそれが、上室性であれ、心室性であれ、周期以外の早期に興奮が起こるときには、心室の血液充満が十分に行われないため、駆出される血液量が少なくなり、従って末梢まで脈として伝えられないので、触診上は脈が1つ欠落したように感知される。この欠落の後には通常の周期により、長い休止期が続くので、心室充満は通常よりも多くなり、左心室は強く、速く収縮して脈は大きく強く触れてきます。
*期外収縮―期測的な脈の間に割り込むように別の脈が入り込み、リズムを乱すこと。
頻脈
心室拍数が分時100以上の場合を頻脈と呼び、これには興奮生成やその伝達の機序に異常を生じて心室拍数が増す場合と、心拍出量を高める代償機序として心室拍数が増す場合が区別されます。心臓に病的な機能障害が発生して、1回拍出量が低下する場合には、これを補うために心拍数が増して、心拍出量を保とうとする。
心室拍数の増加・・・
これは、代償機序として必要だが、それが分時120を越えるときには不利益を生じる。まず、拡張期の短縮は心室の血液充満時間を短くして、1回拍出量をさらに減少させ、心拍出量はむしろ下降傾向となって冠血流量を減らし、冠循環は主として拡張期に生じる。このため、拡張期の短縮はそれ自体冠循環を減少させる。心拍数の増加は心筋の酸素消費量を高める。
徐脈
心室拍数が分時60以下を徐脈とする。スポーツマンなどでは、安静時心拍数が40以下ということがあるため、徐脈がすべて異常とはいえない。徐脈になると、拡張期がより延長して心室の血液充満度が増す。
また、徐脈は心筋の酸素需要を減らすので、それによって循環動態の破綻がこなければ、徐脈はある程度心筋にとって有利といえる。
[運動と脈拍]
最大心拍数とは・・・
運動によって心拍数が増し、血圧は上昇するが、その反応の大きさは運動の方法や強さ、年齢によって異なります。年齢が増すとともに、運動による心拍数の増加は少なくなり、最大に酸素を消費して行われる最大運動レベルでの心拍数、最大心拍数は年齢に比例して低下する。
最大心拍数=220-年齢
最大心拍数の意義・・・
これは、性差はなく、年齢と逆比例する。狭心症や心筋梗塞などの冠動脈性心疾患では、運動負荷試験によって症状や症候がでてきますから、その時点でテストを中止するため、最大心拍数は低くなる。
にほんブログ村

