骨癒合
[骨折の修復]
①炎症期
骨折の起こった直後から骨軟骨形成(仮骨形成)が
生じるまでの期間。骨折部の血管は損傷され血腫が形
成され、骨折端では血流が遮断されるために、骨折部
の細胞が死ぬ。
また、骨形成細胞の増殖が骨髄内・骨膜周囲の軟部
組織からも毛細血管の増殖が起こる。
②修復期
骨折部位を取り囲んで、新しく形成された修復組織
に骨形成および軟骨形成が生じる。
骨形成は主として、骨折部からやや離れた骨膜下に
みられ、膜性骨化が起こる。
③再造形期
形成された仮骨が層板骨に置換される程度である。
海綿骨化した仮骨は再造形によって、皮質骨と骨髄
腔が形成され、仮骨量の減少とともに構造も正常化す
る。この再造形を完了するのに数年間を要する。
*骨癒合とサイトカイン
骨折の修復は、骨折部の細胞の増殖と、骨芽細胞または軟骨細胞への分化によって局所的に骨新生が生じて再生
修復される。この過程での細胞の機能を制御する生理活性因子が存在するとされる。炎症期の未分化細胞の増殖
にPDGF(血小板由来成長因子)が関与し、骨に含まれるIGF(インスリン様成長因子)は、骨芽細胞の前駆細
胞の増殖や軟骨細胞による軟骨基質の合成の促進に関与しているとされる。また、骨形成蛋白(BMP)は炎症期
に骨折部近傍の細胞で、その生産が一時的に亢進し、未分化細胞を骨芽細胞や軟骨細胞への分化を誘導すること
によって、仮骨形成を促進する方向に作用しているとされている。
*仮骨(callus)
骨折治癒過程で形成される仮骨は、形成される部位により係留仮骨・橋渡し仮骨・結合仮骨・髄腔仮骨がある。
係留仮骨は、骨折部から離れた部位で、骨膜から始まる膜性骨化で形成されるもので、骨折部をはさんだ係留仮骨が連結したものが橋渡し仮骨である。
結合仮骨は、骨折間隔の血腫に形成された軟骨からの内軟骨性骨化の部分である。
骨折治癒過程で形成される骨量は、骨折部の安定とも関連する。一般に、骨折部が不安定でわずかなひずみが生じている力学的環境では仮骨量は多く、力学的に安定している場合には、形成される仮骨量は少ない。特に外科的処置によって骨折部を正確に整復しプレートなどで骨折端同士を強固に圧迫して固定した場合には、仮骨形成は殆どみられず、ハバース管での生理的な再造形(骨改変)過程によって骨折部が治癒することがある。このように外仮骨の形成がなく治癒する場合は、骨癒合に要する期間は必ずしも短くなくプレートの抜去時に、再骨折を起こすことがあり、このような治癒は骨折治癒法としての利点は必ずしもないと考えるべきである。
[骨折の治癒過程]
1)一次性骨折治癒
仮骨を形成せずに骨折部が治癒する治癒形式で、両骨折端が正しく解剖学的に整復され転位がなく強固に固定
されたときにのみ生じる。
2)二次性骨折治癒
仮骨を形成して癒合する治癒形式。骨折部に生じた血腫内に肉芽が形成され、やがて仮骨によって再骨折端が連結されたあと、局所の力学的要請に応じた強度を有する骨として再造形されていく。骨折端に多少でも血腫が介在する隙間がある場合には、常にこの過程を経て骨折が癒合する。
[骨癒合の条件]
骨折部の接合、骨折部の固定、十分な血流適度な圧迫重樹が必要。癒合を左右する因子は、骨折の状況・型・部位・年齢などに影響される。また、骨内血行の乏しい部位の骨折では血腫と軟性骨化が、不十分で治癒が遅延する。骨折部位は不動でなければならないが、肋骨と鎖骨は多少動いてもよい。
また、骨癒合は引張応力がなく垂直方向に働く適切な圧縮力が必要であり、その反面骨折に働く剪断力・屈曲力・捻転力は骨癒合を障害する。骨癒合の判断は、動揺の有無・腫脹の有無・レントゲン像による仮骨形成の状態・限局性の圧痛(骨に分布する骨髄神経や骨膜神経が、骨折の臍に損傷されるか、骨折部位に存在している神経が損傷されたためと考えられる。)
骨折に影響する因子
①全身的因子:◍年齢 ◍栄養状態
◍代謝性疾患 ◍骨代謝に影響する薬剤の使用 など
②局所的因子:◍皮下骨折か開放骨折か ◍感染の有無
◍骨折部位 ◍皮質骨か海綿骨か
◍骨破壊・欠損の有無 ◍転位の程度と整復位の良否
◍神経・血管損傷の有無 ◍骨折間隙における軟部組織の介在
◍固定性の良否 など
[癒合日数]
Gurltによる各骨の平均癒合日数
中手骨→2週
肋骨→3週
鎖骨→4週
前腕骨→5週
上腕骨骨幹部→6週
脛骨・上腕骨頸部→7週
両下腿骨→8週
大腿骨骨骨幹部→8週
大腿骨頸部→12週
[骨折癒合の異常経過]
1)変形癒合
解剖学的なアライメントと異なった異常な形態で癒合が完成した状態。整復位不良のまま固定が行われた場合や、整復位が保持できなかった場合などに角状変形(内反、外反、あるいは屈曲)、回旋、短縮変形などが起こることがある。
2)遷延治癒
骨折癒合に予測される期間を過ぎても骨癒合がみられないものをいう。しかし、治癒過程が緩慢ではあるが、少しはつづいているものである。したがって、骨癒合を妨げている因子があればこれを解決することによって再び骨癒合が進行する。不十分な固定が原因であることがもっとも多い。
3)偽関節
骨折部の治癒過程が止まって、過剰可動性を示す場合である。骨折端は丸みを帯びたり萎縮したり、骨髄腔は骨性
に閉鎖される。骨折間隙は繊維性の瘢痕組織で充満され、過剰可動性を認める。不十分な固定や感染、骨欠損などの
原因が多い。治療としては、硬化あるいは萎縮した骨折端を切除し、骨髄腔を開通させ、十分量の自家骨を移植するとと
もに、安定した固定を施す。強固な内固定を用いることもある。
*一般的に遷延治癒と偽関節は、受傷後の期間とX線写真によって判定されるが、両者を鑑別することは容易ではないことから、同一の分類として扱われることが多い。
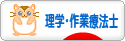
にほんブログ村


[骨折の修復]
①炎症期
骨折の起こった直後から骨軟骨形成(仮骨形成)が
生じるまでの期間。骨折部の血管は損傷され血腫が形
成され、骨折端では血流が遮断されるために、骨折部
の細胞が死ぬ。
また、骨形成細胞の増殖が骨髄内・骨膜周囲の軟部
組織からも毛細血管の増殖が起こる。
②修復期
骨折部位を取り囲んで、新しく形成された修復組織
に骨形成および軟骨形成が生じる。
骨形成は主として、骨折部からやや離れた骨膜下に
みられ、膜性骨化が起こる。
③再造形期
形成された仮骨が層板骨に置換される程度である。
海綿骨化した仮骨は再造形によって、皮質骨と骨髄
腔が形成され、仮骨量の減少とともに構造も正常化す
る。この再造形を完了するのに数年間を要する。
*骨癒合とサイトカイン
骨折の修復は、骨折部の細胞の増殖と、骨芽細胞または軟骨細胞への分化によって局所的に骨新生が生じて再生
修復される。この過程での細胞の機能を制御する生理活性因子が存在するとされる。炎症期の未分化細胞の増殖
にPDGF(血小板由来成長因子)が関与し、骨に含まれるIGF(インスリン様成長因子)は、骨芽細胞の前駆細
胞の増殖や軟骨細胞による軟骨基質の合成の促進に関与しているとされる。また、骨形成蛋白(BMP)は炎症期
に骨折部近傍の細胞で、その生産が一時的に亢進し、未分化細胞を骨芽細胞や軟骨細胞への分化を誘導すること
によって、仮骨形成を促進する方向に作用しているとされている。
*仮骨(callus)
骨折治癒過程で形成される仮骨は、形成される部位により係留仮骨・橋渡し仮骨・結合仮骨・髄腔仮骨がある。
係留仮骨は、骨折部から離れた部位で、骨膜から始まる膜性骨化で形成されるもので、骨折部をはさんだ係留仮骨が連結したものが橋渡し仮骨である。
結合仮骨は、骨折間隔の血腫に形成された軟骨からの内軟骨性骨化の部分である。
骨折治癒過程で形成される骨量は、骨折部の安定とも関連する。一般に、骨折部が不安定でわずかなひずみが生じている力学的環境では仮骨量は多く、力学的に安定している場合には、形成される仮骨量は少ない。特に外科的処置によって骨折部を正確に整復しプレートなどで骨折端同士を強固に圧迫して固定した場合には、仮骨形成は殆どみられず、ハバース管での生理的な再造形(骨改変)過程によって骨折部が治癒することがある。このように外仮骨の形成がなく治癒する場合は、骨癒合に要する期間は必ずしも短くなくプレートの抜去時に、再骨折を起こすことがあり、このような治癒は骨折治癒法としての利点は必ずしもないと考えるべきである。
[骨折の治癒過程]
1)一次性骨折治癒
仮骨を形成せずに骨折部が治癒する治癒形式で、両骨折端が正しく解剖学的に整復され転位がなく強固に固定
されたときにのみ生じる。
2)二次性骨折治癒
仮骨を形成して癒合する治癒形式。骨折部に生じた血腫内に肉芽が形成され、やがて仮骨によって再骨折端が連結されたあと、局所の力学的要請に応じた強度を有する骨として再造形されていく。骨折端に多少でも血腫が介在する隙間がある場合には、常にこの過程を経て骨折が癒合する。
[骨癒合の条件]
骨折部の接合、骨折部の固定、十分な血流適度な圧迫重樹が必要。癒合を左右する因子は、骨折の状況・型・部位・年齢などに影響される。また、骨内血行の乏しい部位の骨折では血腫と軟性骨化が、不十分で治癒が遅延する。骨折部位は不動でなければならないが、肋骨と鎖骨は多少動いてもよい。
また、骨癒合は引張応力がなく垂直方向に働く適切な圧縮力が必要であり、その反面骨折に働く剪断力・屈曲力・捻転力は骨癒合を障害する。骨癒合の判断は、動揺の有無・腫脹の有無・レントゲン像による仮骨形成の状態・限局性の圧痛(骨に分布する骨髄神経や骨膜神経が、骨折の臍に損傷されるか、骨折部位に存在している神経が損傷されたためと考えられる。)
骨折に影響する因子
①全身的因子:◍年齢 ◍栄養状態
◍代謝性疾患 ◍骨代謝に影響する薬剤の使用 など
②局所的因子:◍皮下骨折か開放骨折か ◍感染の有無
◍骨折部位 ◍皮質骨か海綿骨か
◍骨破壊・欠損の有無 ◍転位の程度と整復位の良否
◍神経・血管損傷の有無 ◍骨折間隙における軟部組織の介在
◍固定性の良否 など
[癒合日数]
Gurltによる各骨の平均癒合日数
中手骨→2週
肋骨→3週
鎖骨→4週
前腕骨→5週
上腕骨骨幹部→6週
脛骨・上腕骨頸部→7週
両下腿骨→8週
大腿骨骨骨幹部→8週
大腿骨頸部→12週
[骨折癒合の異常経過]
1)変形癒合
解剖学的なアライメントと異なった異常な形態で癒合が完成した状態。整復位不良のまま固定が行われた場合や、整復位が保持できなかった場合などに角状変形(内反、外反、あるいは屈曲)、回旋、短縮変形などが起こることがある。
2)遷延治癒
骨折癒合に予測される期間を過ぎても骨癒合がみられないものをいう。しかし、治癒過程が緩慢ではあるが、少しはつづいているものである。したがって、骨癒合を妨げている因子があればこれを解決することによって再び骨癒合が進行する。不十分な固定が原因であることがもっとも多い。
3)偽関節
骨折部の治癒過程が止まって、過剰可動性を示す場合である。骨折端は丸みを帯びたり萎縮したり、骨髄腔は骨性
に閉鎖される。骨折間隙は繊維性の瘢痕組織で充満され、過剰可動性を認める。不十分な固定や感染、骨欠損などの
原因が多い。治療としては、硬化あるいは萎縮した骨折端を切除し、骨髄腔を開通させ、十分量の自家骨を移植するとと
もに、安定した固定を施す。強固な内固定を用いることもある。
*一般的に遷延治癒と偽関節は、受傷後の期間とX線写真によって判定されるが、両者を鑑別することは容易ではないことから、同一の分類として扱われることが多い。
にほんブログ村

