Yahooの防災速報の地域設定に都内の某区を設定したままの私。昨日は目を覚ますと、東京震度5弱という文字が目に飛び込んできた。あわててスマホで詳細を確認。都内在住の友達のSNSを見てもそれなりに揺れたようだ。
また、3.11の津波を思い出してしまうほどの茨城県の洪水。なんだか....。千葉在住時の時のことが蘇ってきた。福岡に転居して1年半。自然災害を身近に感じる機会が千葉在住時ほど多くなく気が緩んでいる。日本に住んでいる限り自然災害とは隣り合わせ。気を引き締めないと!と思う反面、自然災害に対するストレスが少ないことを幸せに思う。
東日本大震災1ヶ月後あたりに関西に帰省避難した都内の友達が、「帰省したら心身が軽くなった....。ここまでストレスが溜まっていたんだ....」と話していたが、自覚していないストレスは結構ある。私も震災から2か月後あたりに親族の結婚式で初めて関東を離れ関西に行ったが、関西でホッとするものを凄く感じた。この体験を鑑みても、自然災害に対するストレスが少ない現在は幸せだ。
さて、先日、たまたま川島なお美さん関連記事内で彼女の写真を目にした。見た瞬間、正直、ドキッとした。それは....。ここでも何度か触れている昨年秋、つまり一年ほど前に大腸がんのため旅立った親しい友人(高校の同級生)の姿と重なってしまったからだ。旅立って1年という節目でもあるので、最近、彼女のことを想うことが増えたが、そのためだけではない。フワッとした華やかな衣装と腕を覆う長い手袋、そしてスカーフを身にまとった川島さんだが、顎や肩のあたりの細さが、旅立った高校の同級生と重なってしまったからだ。高校の同級生もスタイルが良くお洒落でいつも美しかったが、旅立つ1年ほど前から、ちらっと見える腕・肩のあたりがとても細くてドキッとし心が締め付けられた。その時のことを思い出してしまった。
話は変わり、先日、NHKで認知症に関する番組を目にした。高齢化社会。人々が認知症に対する理解を深め、地域で助け合い支え合うことが重要!という内容だった。その中で、希望がもてる具体的な症例が紹介された。「30分ウォーキングなどの適度な運動」「社会参加・社会との接点の維持」「できるだけ今までの生活スタイルを維持」が認知症の進行を遅らせる大きなポイントだと指摘されていた。
私は認知症義母の介護を5年ほどしたことがあるが、この3点はその通り!社会との接点が増えたり、自分の役目が与えられ必要とされている実感が持てたり、運動をしたりすると、義母の認知機能が驚くほど改善したことがあった(初期の頃)。ただ、難しいのは、それがなくなると、また認知症が進んでしまうこと。なので、本人及び家族などの周辺の方々の双方の努力が必要になる。また、社会や地域の寛容性も必要だ。初期の認知症であれば、経験的にもちょっとした見守り程度で十分なことも多い。分かっていても実行するのは難しいのだが。
認知症に限ったことではない。病との向き合い方は人それぞれだし、疾病の種類や重症度によっても異なるが、「できるだけ社会参加を続ける・できるだけ今まで通りの生活スタイルを維持する」はとっても重要なことだと私は自身の闘病を通じて感じている。「やっぱり、エネルギーは人とのふれあいから最も得られる。闘病者やサバイバーにとって社会参加や人との交流は薬などの医学的治療からは得られない何かがある」と私は感じている。
つんくさんも音楽活動を再開した。川島さんも新たな挑戦をしているとか。私ももっと貪欲に日々を楽しみたいな。ちょっと違うか...。
「よー分からん内容だね。でもOKよ」
「読んでよかった」と思われたら
↓クリックをお願いします!
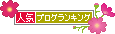
人気ブログランキングへ
また、3.11の津波を思い出してしまうほどの茨城県の洪水。なんだか....。千葉在住時の時のことが蘇ってきた。福岡に転居して1年半。自然災害を身近に感じる機会が千葉在住時ほど多くなく気が緩んでいる。日本に住んでいる限り自然災害とは隣り合わせ。気を引き締めないと!と思う反面、自然災害に対するストレスが少ないことを幸せに思う。
東日本大震災1ヶ月後あたりに関西に帰省避難した都内の友達が、「帰省したら心身が軽くなった....。ここまでストレスが溜まっていたんだ....」と話していたが、自覚していないストレスは結構ある。私も震災から2か月後あたりに親族の結婚式で初めて関東を離れ関西に行ったが、関西でホッとするものを凄く感じた。この体験を鑑みても、自然災害に対するストレスが少ない現在は幸せだ。
さて、先日、たまたま川島なお美さん関連記事内で彼女の写真を目にした。見た瞬間、正直、ドキッとした。それは....。ここでも何度か触れている昨年秋、つまり一年ほど前に大腸がんのため旅立った親しい友人(高校の同級生)の姿と重なってしまったからだ。旅立って1年という節目でもあるので、最近、彼女のことを想うことが増えたが、そのためだけではない。フワッとした華やかな衣装と腕を覆う長い手袋、そしてスカーフを身にまとった川島さんだが、顎や肩のあたりの細さが、旅立った高校の同級生と重なってしまったからだ。高校の同級生もスタイルが良くお洒落でいつも美しかったが、旅立つ1年ほど前から、ちらっと見える腕・肩のあたりがとても細くてドキッとし心が締め付けられた。その時のことを思い出してしまった。
話は変わり、先日、NHKで認知症に関する番組を目にした。高齢化社会。人々が認知症に対する理解を深め、地域で助け合い支え合うことが重要!という内容だった。その中で、希望がもてる具体的な症例が紹介された。「30分ウォーキングなどの適度な運動」「社会参加・社会との接点の維持」「できるだけ今までの生活スタイルを維持」が認知症の進行を遅らせる大きなポイントだと指摘されていた。
私は認知症義母の介護を5年ほどしたことがあるが、この3点はその通り!社会との接点が増えたり、自分の役目が与えられ必要とされている実感が持てたり、運動をしたりすると、義母の認知機能が驚くほど改善したことがあった(初期の頃)。ただ、難しいのは、それがなくなると、また認知症が進んでしまうこと。なので、本人及び家族などの周辺の方々の双方の努力が必要になる。また、社会や地域の寛容性も必要だ。初期の認知症であれば、経験的にもちょっとした見守り程度で十分なことも多い。分かっていても実行するのは難しいのだが。
認知症に限ったことではない。病との向き合い方は人それぞれだし、疾病の種類や重症度によっても異なるが、「できるだけ社会参加を続ける・できるだけ今まで通りの生活スタイルを維持する」はとっても重要なことだと私は自身の闘病を通じて感じている。「やっぱり、エネルギーは人とのふれあいから最も得られる。闘病者やサバイバーにとって社会参加や人との交流は薬などの医学的治療からは得られない何かがある」と私は感じている。
つんくさんも音楽活動を再開した。川島さんも新たな挑戦をしているとか。私ももっと貪欲に日々を楽しみたいな。ちょっと違うか...。
「よー分からん内容だね。でもOKよ」
「読んでよかった」と思われたら
↓クリックをお願いします!
人気ブログランキングへ