やることは山ほどありつつ、
随分いろいろ落ち着いてきたこの1週間。
新しい学期が始まる直前ということで
新しい出会いもちらちらあったり。
この週末は大変天気が良く
夏っぽい雰囲気もこれでいよいよ最後かという雰囲気。
コペンハーゲンにいた某氏から届いた
デンマーク料理のデンマーク語のレシピに首を傾げたり、
バーデンで開かれてた某映画祭に参加したり、
湖畔でのバーベキューに参加したり、
ネットレンタルで映画を観たり、
そんな週末。
という訳で、今回みた映画は“Hable con ella (トーク・トゥ・ハー)”。
10年ほど前のスペインの映画です。
ヨーロッパの映画って
ヨーロッパに住んでいながらあんまり観てこなかったんです。
アメリカの映画の様な
分かりやすいストーリーテリングと演出に慣れ過ぎると、
「あれっ」とちょっとした違和感を感じてしまうようなところがあって、
なんとなく積極的には観てこなかったのかと。
その「あれっ」て違和感って
古臭い演出とか、洗練されていない編集とか、
そんなせいだと思い込んでいたのも事実。
でも、最近は
何でもかんでも簡単に割り切って
分かりやすく簡単に伝えてしまうもの(映画に限らずね)に
なんとなくうんざり気味な気持ちでいて。
エンターテイニングであるのももちろん大事やし、
分かりやすい表現のパワーって本当に強いし、
それを否定する気は全くなく、
というよりむしろそういうのも大変好きなんやけど。
そんなタイミングで観たこの映画。
ハリウッド的な要素とは対極の表現で、
やっぱり商業主義の観点からは
垢抜けない部分があるのは事実。
でも、
「いや、そのカット要らんのちゃうの」って
一瞬突っ込みを入れたくなるかと思いきや
(以前は実際そう突っ込んでいた)、
その表現の持つ懐の深さというか
そこから派生するねっとりと心に絡みつく密度感が
映画をとても芳醇にしていてね。
なんていうんでしょう、
ヨーロッパのダサさとかっこよさの紙一重のところが
かっこよさに転んだというか、
別に映画自体が「かっこいい」訳では全然ないけど、
心をぐぐっと引きつけるパワーに溢れてて
鑑賞後大きくため息をつかされたのでした。
経済第一に考えたら絶対にしないであろう休みの取り方とか、
良く言って臨機応変な
悪く言うと行き当たりばったりな問題解決の方法とか、
自分の言いたいことは言わなきゃしょうがないとか、
プロフェッションの定義とか、
しばらくの期間こちらに住んできてるからこそ
生々しく見える感じるポジティブ、ネガティブ両方の色々があって、
「ヨーロッパ的」って言うのが
最近自分の中のもやもやでして、
だからこそびびっと響いたのかと思うのです。
あー、全然言葉にならないや。
でも言葉にならないレベルでモヤモヤしてたなにかに
光を当ててくれたこの映画に感謝。
随分いろいろ落ち着いてきたこの1週間。
新しい学期が始まる直前ということで
新しい出会いもちらちらあったり。
この週末は大変天気が良く
夏っぽい雰囲気もこれでいよいよ最後かという雰囲気。
コペンハーゲンにいた某氏から届いた
デンマーク料理のデンマーク語のレシピに首を傾げたり、
バーデンで開かれてた某映画祭に参加したり、
湖畔でのバーベキューに参加したり、
ネットレンタルで映画を観たり、
そんな週末。
という訳で、今回みた映画は“Hable con ella (トーク・トゥ・ハー)”。
10年ほど前のスペインの映画です。
ヨーロッパの映画って
ヨーロッパに住んでいながらあんまり観てこなかったんです。
アメリカの映画の様な
分かりやすいストーリーテリングと演出に慣れ過ぎると、
「あれっ」とちょっとした違和感を感じてしまうようなところがあって、
なんとなく積極的には観てこなかったのかと。
その「あれっ」て違和感って
古臭い演出とか、洗練されていない編集とか、
そんなせいだと思い込んでいたのも事実。
でも、最近は
何でもかんでも簡単に割り切って
分かりやすく簡単に伝えてしまうもの(映画に限らずね)に
なんとなくうんざり気味な気持ちでいて。
エンターテイニングであるのももちろん大事やし、
分かりやすい表現のパワーって本当に強いし、
それを否定する気は全くなく、
というよりむしろそういうのも大変好きなんやけど。
そんなタイミングで観たこの映画。
ハリウッド的な要素とは対極の表現で、
やっぱり商業主義の観点からは
垢抜けない部分があるのは事実。
でも、
「いや、そのカット要らんのちゃうの」って
一瞬突っ込みを入れたくなるかと思いきや
(以前は実際そう突っ込んでいた)、
その表現の持つ懐の深さというか
そこから派生するねっとりと心に絡みつく密度感が
映画をとても芳醇にしていてね。
なんていうんでしょう、
ヨーロッパのダサさとかっこよさの紙一重のところが
かっこよさに転んだというか、
別に映画自体が「かっこいい」訳では全然ないけど、
心をぐぐっと引きつけるパワーに溢れてて
鑑賞後大きくため息をつかされたのでした。
経済第一に考えたら絶対にしないであろう休みの取り方とか、
良く言って臨機応変な
悪く言うと行き当たりばったりな問題解決の方法とか、
自分の言いたいことは言わなきゃしょうがないとか、
プロフェッションの定義とか、
しばらくの期間こちらに住んできてるからこそ
生々しく見える感じるポジティブ、ネガティブ両方の色々があって、
「ヨーロッパ的」って言うのが
最近自分の中のもやもやでして、
だからこそびびっと響いたのかと思うのです。
あー、全然言葉にならないや。
でも言葉にならないレベルでモヤモヤしてたなにかに
光を当ててくれたこの映画に感謝。
- トーク・トゥ・ハー スタンダード・エディション [DVD]/日活
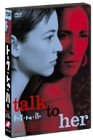
- ¥3,990
- Amazon.co.jp