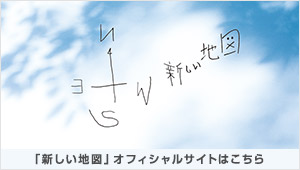小沢問題の観方については先日いくつか紹介したが、この2日間、良識あると見られている評論家等は同じような視点を持って発言してきている。オウム事件で有名になった江川紹子氏は、『私は、小沢氏の人となりを直接知らないし、格別支持・支援する立場でもないので、彼を擁護したいとは思わない。彼の権限のふるい方にも違和感を感じてきたが、』とそのブログに書いてあるが、全く同感である。
某新聞の社会部長は本日の朝刊で「ちゃんと取材してきた」と泣き言のように書いているが、記者の取材力の衰えとデスククラスの思い込みは、かなり激しいものがある。あらかじめ結論ありきで、若手記者に取材させ、違う事実を書いてきたら、それは違うと勝手に書き直すデスクの話も何度か聞いた事。さらに、ロッキード事件捜査とは逆の意味で『東京地検特捜部といえば、エリート検事の集団。数々の難事件を解決してきた東京地検特捜部が自信を持って捜査を行っているのだから、まず間違いはない』」という"東京地検特捜部幻想"を今こそ払拭しなければならない。
◆東京地検特捜部の判断は常に正しい、のか=2010年01月19日 江川紹子氏
「検察の正義」が常に「社会の正義」とは限らず、検察の判断が常に正しいとも限らない。私たちはこのところ、いくつもの冤罪事件を通して、検察の判断の誤りを見て来た。かつては冤罪と言えば、警察の無理な取り調べが最大の原因とされてきたし、最近明らかになった冤罪の数々でも、警察の捜査の問題は大きい。問題なのは警察ばかりではない。昨年12月に最高裁で再審開始決定が確定した布川事件では、別件逮捕された2人が警察の強引な取り調べでやむなく「自白」したが、拘置所に移送された後、検察官に対して否認した。すると、なんと検察は2人を警察の留置場に送り返し、再び「自白」に追い込んだのだ。そのうえ、裁判や再審請求の課程でも、検察側は2人に有利な証拠を隠し、真実の発見を遅らせた。
しかし、刑事責任を問う一連の報道の仕方には、「メディアの過去の教訓や反省はどこにいったのだろうか」と嘆かわしく思わざるをえない。報道機関の役割の一つは権力を監視することなので、政権与党の最大実力者の小沢氏の言動を厳しくチェックすることは当然といえる。だが、検察も権力機関だ。その検察のやることについては無批判に受け入れるだけでいいのだろうか。検察の「説明責任」を追求していくのは、もっぱら新聞社を初めとする記者クラブの役割のはずだ。その役割を、新聞社はきちんと果たしているだろうか。マスコミが検察の監視役ではなく、露払いや煽り役を果たしてしまった前例は少なくない。先に挙げた長銀事件もそうだろう。多額の税金を投入しなければならなくなった責任を誰もとらないというのは釈然としないという国民感情を背景に、誰かを「犯人」にしなければ気が済まない雰囲気が醸成された。それにメディアは大きな役割を果たしている。◆
珍しく政治問題に関わっているが、小沢一郎氏の公設第一秘書、大久保隆規容疑者(48)は2003~04年、下請け業者の「水谷建設」から盛んに向島接待を報じた新聞各紙が報じている。向島の利用についてはバブル期から盛んに出ており、新橋や赤坂の料亭が再開発で客足が遠のき、格下だった向島が、都心から離れていて人目を避けられる点で利用されるようになったという。官僚もタクシー代が好きなように使えた時代だから、さほど遠くはないのである。実際に利用していたと言う話はマスコミ人を含めて、何人かから聞いている。
向嶋墨堤組合のホームページによると、現在は料亭15軒、芸者105人ほどだそうである。向島は、昔の遊郭にあたる花街、花柳界があるところで、「見番通り」を中心に料亭街があり、芸者は「一本さん」と呼ばれ、三味線や踊りなどを単独でも披露する。年齢は、20~70歳までおり、中心は35歳ほど。ほかに、「半玉さん」までいかない臨時お手伝い「かもめさん」もいる。数年前に、実際におかみさんの話を聞いたことがあるが、今は気軽に利用してくださいと言っていた。
さて、その様子は、領家高子の「向島」「墨堤」「言問」の3部作を読めば、分かりやすい。
●向島 (単行本)
花街という、一見古くて新しい世界に生きる女性の、成熟と憂愁が、気品ある文体とともに生々しく伝わってくる。――渡辺淳一 愛と哀しみの秀作!向島生まれの著者が涼しやかに描く現代の芸者25歳の全く新しい肖像。
●墨堤 (単行本)
花街向島、水の女!現代の芸者芳恵は26歳、パトリ〔鐘の音の響く範囲の地〕向島の愛と哀しみを清澄な文体で描く秀作。こんな小説をもう1冊読みたい。本書を読了し最初に思うのはこれである。が『墨堤』ほどの作品はそうはありはしない。自らの拠って立つ所を求めて彷徨する人に、歓喜と諦観のない混ぜとなった堤の風は、何と心地よくその心の襞までをも浄化してくれることか。そして読者は至福の時を求めてこう決断するだろう。本書をはじめからもう一度読み返そうと。再読三読に耐える力作の登場といえよう。――(縄田一男)
●言問 (単行本)
久々に出現した恋愛小説の秀作。満々と水をたたえた隅田川を見つめる芸者芳恵と二人の男。人をつき動かす愛の連なり、愛の哀しみ。
帯には「硬質な文体」とあるが、やわらかで、しかしピンと背筋の伸びたしなやかさ、強さ、を感じる美しい文章である。舞台は向島。華やかな花街・・・切ない初恋のような同級生である高級官僚との出会いそして、自立した旦那に囲われ、生きる道を見いだして行く、生きる活きる姿が伝わってくる。
本屋で探し出した珠玉の作家であるが、もう一人、菅浩江という女性作家も愛読しているが、最近あまり本を出していない。ところで、領家高子の中では、「美容院ベビーフェイス物語 (単行本)」というのあるが、これも隅田川が流れる墨堤にほど近い店を舞台にした小説である。下町にある椅子はたった二つ、順番待ちの人には座席の高めのシンプルなラブチェア、美容師は35歳の千夏ひとり。その名は美容院『ベビーフェイス』。
千夏の恋人は「入道」と呼ばれる製薬会社主席研究員にしてロックンローラー。微妙に揺れ動く三十代の男女の愛の機微を静かな文章で描いている。飼って10年になるオス猫のヒョウ太、そしてにぎやかな下町の客たち、囲む人々が織り成す、ひだまりのような物語である。心温まる人間模様、美しく深みのある抒情性、青空のような透明感が拡がっている。心が触れ合う、行き交う小説が今一番面白い。地球の中心で愛を叫んでも、何も帰って来ないのだ。