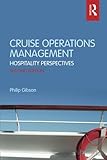今月末、イタリア視察を控えている身ですが、イタリアの個人旅行と同等に愛しているのが地中海クルーズ。
これまでの人生で3回地中海クルーズを経験しています。
そして、実は、幻の1回も存在しています。
搭乗予定であったコスタ・コンコルディア号が、我々の搭乗1週間前に座礁事故を起こし、クルーズ旅行を急遽キャンセルせざるを得なくなり、イタリアの個人旅行へと切り替えたからです(ウィキペディア:コスタ・コンコルディアの座礁事故)。
自他共に認めるクルーズ馬鹿ですが、一時期、クルーズ誘致の業務に携わっていた際には、専門書でクルーズ産業やオペレーション・マネジメントを真剣に学んでいました。
鹿児島でも過去最高のクルーズ寄港回数を記録し、奄美や屋久島など世界的ブランドが確立しつつある島嶼クルーズの期待も高まりつつありますが、他方で、「クルーズ観光客は宿泊が伴わない」とか「買い物ばかりで地元経済への波及効果が小さい」とかネガティブなことばかりが言われています。
ただ、それらの議論を聞いていると、目先のことばかりにとらわれている浅薄な議論で、クルーズ産業の裾野の広さや、マザー・ポート(母港)化による物流・雇用などを勘案すれば、「クルーズ産業」をどのように、育成し、発展させていくかを考え、現在は、その過渡期であることを十分認識すべきです。
クルーズ産業のポテンシャルを、なぜ、このように確信しているかと言えば、4年前の西地中海クルーズで、スペインのマラガを訪問した際に、度肝を抜かれるような規模のクルーズ施設を見たからです。
マラガは60万人弱の人口で、人口規模で言えば、鹿児島市と同じくらい。
しかし、御覧のように、10万トンを超えるクルーズ船が同時に2隻寄港しています。
当時のクルーズでは、マラガのようなヨーロッパ大陸の都市だけでなく、自然遺産と文化遺産が併存する複合遺産であるイビザ島や年間2000万人を超す観光客が訪れるパルマ・デ・マヨルカ島など、地中海に浮かぶ島嶼部にも寄港しました。
今、振り返ってみると、今年7月に世界自然遺産登録が予定されている奄美や、日本初の世界自然遺産である屋久島と、既に年間150回を優に超える寄港回数を誇る鹿児島との間を結ぶクルーズ観光を考える、絶好の経験をしていたといえます。
そして、訪問した都市では、相当数の観光客がオプションツアーを選ぶことなく、タクシーに乗ったり、徒歩で街中を散策したり、するなど各々の活動を楽しんでおり、かく言う私も、食事や買い物先で、クルーズ観光客のグループと多々遭遇して、かなりの消費がされている現場を目の当たりにしました。
観光の成熟度が上がっていけば、このような風景が、鹿児島や奄美、屋久島などでも見られるようになるんだろうなという確信があります。
なぜなら、現在、LCCで鹿児島を訪れている外国人観光客は、自分で自由に観光や買い物、食事を楽しんでおり、情報技術の進歩が、その動きを一層加速させることは間違いないからです。
私が、地中海クルーズをこよなく愛する理由は、寄港地での観光の楽しみもありますが、船内での自由な時間を楽しめることもあります。
船内には各種施設が設置されていますが、プールで泳いだり、ジャクジーで他国からの乗客と会話をしたり、あるいは、デッキチェアに寝転がって読書をしたり、贅沢な時間の過ごし方を満喫できます。
また、1週間から10日間、同じ船内で過ごすスタッフや乗客と仲良くなり、夕食時には、一緒にダンスをしたり等の交流を味わうこともできます。
このように、滞在期間中に、思いっきり現実逃避をして、地中海から昇る朝日を見ると、「人生には楽しいことや美しいものがまだまだたくさんある」ことを再確認できて、以後、リピーター化しています。
今月末のイタリア視察が終わった後は、1年後に、また、クルーズ旅行に行く計画を立てようと思います。