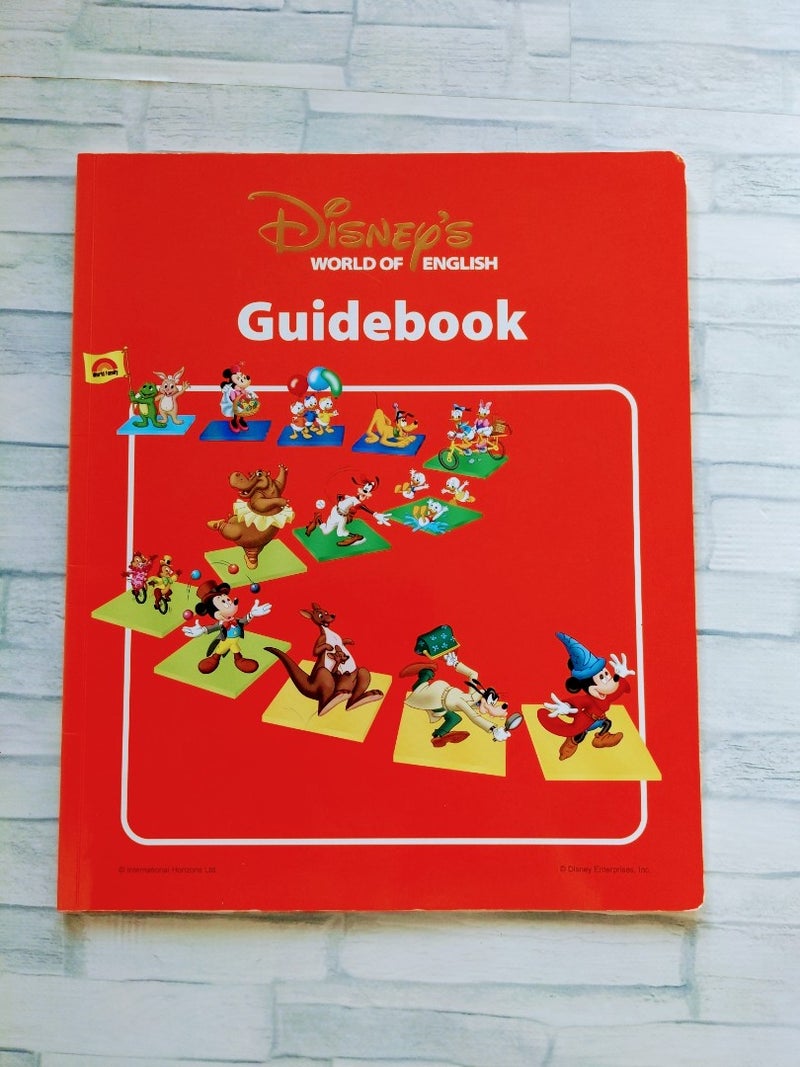2021年の8月に出版された本ですが、長女も小学校にあがりお勉強モードになっていたので、気になり図書館で借りてきました。
頭が良くなる方法のノウハウ本などは沢山あると思いますが脳医学の観点、特にこどもに重要だなと思ったところをまとめたいと思います。
大人の認知症予防にも触れています。
脳を成長させる要素
①熱中体験
②知的好奇心 (脳の成長の原動力、能動的に取り組む)
③自己肯定感 (努力次第で自分が成長していけると思う気持ち)
④しなやかマインドセット(失敗してもまた頑張ろうとする気持ち)
⑤生活習慣 (睡眠、食事、運動)
熱中体験とは?
興味を持ったものをとことんやるということ。
それが知的好奇心をはぐくみ脳の成長の原動力となる
本来の目標に無関係に思えても熱中していれば脳はちゃんと成長する。
東大生の共通点として子供のころに並外れた熱中体験をもっているということも挙げられています。
子どもが熱中するものを見つけるには、
幅広い知識・情報にふれ、リアル体験を増やす。
親が熱中している姿を見せることもいいそうです。
親がスマホやテレビばかりに熱中している姿を見せる、、
なんてことにならないようにしなくてはと私も反省しました。
すきなものをやるのがいい理由
好きなものは覚えやすく興味のないことは全然覚えられない
誰しもがそんな経験があるがそれはなぜなのでしょう??
それは
脳には海馬のすぐそばにあり、密接に関係している好き嫌いを判断する「偏桃体」という領域があります。
海馬は記憶に関係しているので
自分が好きだと感じている物事については苦も無く覚えられる。
勉強は苦手だけど、サッカー選手の名前ならいくらでも覚えられるとかですね。
大人の趣味
大人で趣味をするときはわざわざ辛い思いをする必要はない
好きなことをがんがんやればいい
とあります。
趣味の一例として特に楽器演奏は脳に刺激が入り、コミュニケケーションの機会も増え、創造性も増える。
私もこどもの習い事にかこつけて電子ピアノを購入して時々弾いていますが、
正直
子供の頃習い事としてやっていた時より100倍楽しくて夢中になっています。
練習曲をひたすらやるより、
自分の好きな曲を自分の好きな時に弾けるって本当に楽しいです。
■関連記事
寝る子は「海馬」が育つ
脳の奥にある「記憶の倉庫番」と言われる部分「海馬」の体積が5-6時間しか寝ない子より、8-9時間寝る子の方が大きい
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811911013541?via%3Dihub
書籍にのっていた著書の参考文献が見つからなかったので、類似の参考文献をのせてあります
・脳の神経細胞は減っていく一方、海馬では年齢を重ねても脳をちゃんと使って負荷をかけることで神経細胞が新しく作られる
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867416314040
・ストレスは海馬を委縮させる→認知症にもなりやすくなる
 理想的な睡眠時間
理想的な睡眠時間
【6-13歳】 9-11時間
【14歳-17歳】 8-10時間
【大人】 7時間前後
ぐっすり眠るためには脳にとても良いことが自然と取り込まれることになります。
 寝る前にブルーライトをあびない
寝る前にブルーライトをあびない
ということは親子でテレビやスマホから遠ざかり、家族間のコミュニケーションが増える。
コミュニケーション力は脳の様々な領域(感情の認知、言語、共感性、社会性)を使う。
 日の光をあびて昼間運動をする
日の光をあびて昼間運動をする
酸素を取り入れる有酸素運動をすることで、脳内の血流が増え、脳内細胞の成長を促すホルモンが出る
(週2回以上の運動は認知症リスクを40%下げるとも言われています)
大人にとっても睡眠は超重要
・歳をとるとアミロイドBというたんぱく質がたまって認知症になりやすくなる。睡眠中は細胞同士の間隔が緩くなるため細胞間液で有害な老廃物を洗い出しやすくするといわれています。
・人体の細胞の染色体にあるテロメアがストレスや寝不足で短くなる。テロメアは人体を構成する細胞の細胞分裂の分裂回数を数えるカウンターのようなもの。
日本の子供は自己肯定感が低い?
らしいです。
なんででしょうね?
 自己肯定感(学力を伸ばすための要素として本書では記載されています)
自己肯定感(学力を伸ばすための要素として本書では記載されています)
記憶と感情に関係している、自分は何かを変えられる、自分にOKを出してあげられる。小さいときからの記憶が自己イメージをつくる。
自己肯定感を高めるために親は、結果よりも努力をほめて、長所も短所も個性として受け入れる、子供自身に物事を決めてもらう。
他の人と比べない、失敗したときにダメ出ししない、こどもに理想を描かない、他人のよいところをみつけるといいとあります。
本書には言及されてなかったのですが、
日本の子供の自己肯定感が低い理由を調べてみたところ
日本の文化に適応するための自己呈示の方略や単なる測定方法による問題である可能性が 高いとあります。
日本人は謙虚さを美徳と考える文化はやはりありますよね。
本書と同時に読んでいた本があります。
いわゆる中学受験の話で、親の期待が知らず知らずのうちに子供を追い詰めていくという話です。
「ちょっとやってみて大変だったらやめればいいし」と始めたのに、お金や労力に比例してどんどんやめられなくなる
気持ちが増えていく。(コンドル効果)そして、子供は親を喜ばすためだけについに、、、
本中で印象的だったフレーズがあります。
・あの時親がすごかったといえばすごかった、頑張ったといえば頑張った
・もう〇〇が〇〇でいてくれること以外は求めない
絶望的な中で、こどもの心に残っていたものはやはり好きなことであり、それを原動力に親のための勉強ではなく自分のための勉強をしていく。
かなり考えさせられる内容だったので良かったら読んでみてください。
■アマゾン
■楽天
将来の夢を持つことの有効性
勉強を続けていくときに、長期目標の果たす役割は大きく、良い成績をとるために段階的なステップを重ねることを
意識していた学生は、単に良い成績をとることだけを意識した学生より成績の向上が見られたという研究があるそうです。
親が時折、将来の夢は何?何になりたいなど聞くことで、脳内の特定のネットワークを使うことになり、将来の自分と今の自分を対比することが出来るようになるとあります。
東大生の共通点 「東大脳の育て方」より(瀧先生監修)
・東大生は並外れた熱中体験を持っている
・親子で一緒にいろんなことを体験している
・親子仲が良く、コミュニケーションが多い
・勉強しなさいと言われたことがない
リビングルームで勉強している
・家族で規則正しい生活をしている
・勉強自体が好き、ただし効率を追求している
東大生が親からかけられていた言葉(プレジデントFamily 2016秋号より)
・何でも好きなことをやっていいよ
・勉強は好きな時にしなさい
・自分の人生なんだから自分で決めていい。サポートするから
・勉強はやればやるほど伸びる。それが楽しんだ
・負けたら自分のせい、勝ったら人のおかげ
・何があっても味方だ
・面白いね、よくそんなこと気が付くね
・あなたは努力しているから、きっと誰かが認めてくれる
まとめ
本書でも学力を伸ばす方法は色々記載されていますが、大事なことは
脳の成長と脳への良い刺激
つまり
十分な睡眠と熱中体験
親ができることは子供の好きなことに目を向けて、余計なことは言わずに、こどもが求めてきたものに返すということかなと思いました。
あくまで私の見解なので、他の要素等気になる方は本書をご覧になってみてください^^ 大人の脳にとっていいことなども沢山書いてあります。
■Amazon
■楽天
脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて下さい [ 瀧 靖之 ]
本日は以上となります。
最後までお読みくださりありがとうございました!
よく読まれている記事
カテゴリ
- 幼児英語 ( 7 )
- 育児グッズ ( 6 )
- 暮らし ( 2 )
- メルカリ ( 2 )
- 習い事 ( 1 )
- 子供のもの ( 2 )
- コロナ ( 2 )
- DWE(ディズニー英語システム) ( 17 )
- こどもちゃれんじイングリッシュ ( 8 )
- 育児の悩み解消 ( 17 )
- 幼児教育 ( 8 )
- その他 ( 3 )