的感受性を育てる意識が強ければ、より良い社会作りにも寄与して「教育に携
わる」者の教え子の成長が「自分の喜び」となれば、次の世界へと続きもしよ
うが、以下のような「職業教育者」では、そんな淡い期待も霧散してしまう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「さいたさいたセシウムがさいた」。埼玉県教職員組合(埼教組)が事務局を
している講演が、こんなタイトルをつけていたことが分かった。
これに対し、批判が相次ぎ、組合がタイトルを削除する事態になっている。
物議を醸したのは、さいたま市内で2012年3月10日に行われる予定のイベン
ト「国際女性デー埼玉集会」のチラシだ。

■「不快な思いをさせてしまった」
集会は、埼教組が実行委事務局をしており、その中では、日本の詩人が講
演を行うことになっている。
副題は、「3・11後の安心をどうつくり出すか」。埼教組は、全日本教職員組合
(全教)の傘下にあり、日教組埼玉とは違う組織だ。
ところが、埼教組のサイトでこのチラシを掲げたところ、ネット上で、「これはひ
どい」「どういうセンスなんだよ」などとタイトルを疑問視する声が相次いだ。
東海テレビが11年8月に「怪しいお米セシウムさん」と誤って番組で流し、謝罪
した経緯もあったからだ。
自民党の片山さつき参院議員は、ツイッター上で埼教組に抗議して下さいと
呼びかけられ、サイトの告知で確認したとして、12年3月3日のツイートで怒り
を露わにした。日教組埼玉のことだと誤解していたようだが、「こういう言葉平
気で公に使うセンスで授業やられちゃかなわん!」とぶちまけている。
埼教組の執行委員長は、取材に対し、こうした批判を受けて、チラシから「さ
いたさいたセシウムがさいた」のタイトルを削除し、修正チラシを再配布して
いることを明らかにした。
「こちらにも、『タイトルが被災者の気持ちを逆なでする表現だ』とご意見がい
くつかあり、不快な思いをさせてしまったと考えました。詩人の方も、話し合っ
た結果、了承していただいたと聞いています」
■「講演者の詩人がタイトル考えた」
タイトルについては、埼教組の執行委員長は、「もともと詩人の方が付けたと
聞いています」と明かした。
ネット上では、日本の童謡「チューリップ」を元に詩の表現として考えたのかと
いった声や、「さいた」という表現に「さいたま」をかけた言葉遊びではないか
といった指摘が出ている。この点については、「原発への何らかの思いがあ
って付けたのだと思いますが、詳しいことは本人でないと分からず、承知して
いません」とした。
埼玉県では、三郷市などが「放射線ホットスポット」になると識者らから指摘さ
れているが、そのこととタイトルが関係するのかについても分からないという。
講演をする予定の詩人は、メディアやネット上で、政府の原発事故対応ぶり
を繰り返し批判している。
集会では、反原発の考え方を打ち出しているが、執行委員長は、「詩人の方
がどのような立ち位置かは承知していませんが、集会の趣旨には賛同して
いただきました」と言っている。
東京都内在住の詩人に取材しようとしたが、外出中だったため話は聞けなかった。
▽J-CASTニュース
http://www.j-cast.com/2012/03/07124705.html?p=all
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「言葉狩り」というこれまで日本の姑息過ぎるマスコミや「公務員労働者」の
手段が、一般に広まれば、それが「ブーメラン」となって「公務員労働者」も
それの代償を支払う格好となる。
まぁ、一般常識の欠落している「教育労働者」には、人の痛みへの理解が足り
ないのか、ほんの少し思考を巡らせれば分かりそうな事案も、批判を受けて
そしてそ弁明が「講演者云々」とかで、自分達の責任回避する「不恰好ぶり」
わ見せているのだから、教えて貰う「生徒」の親にすれば、「思慮深さ欠落者」
が「聖職たる教育者」とは到底思えないだろう。
大体にして「教育労働者」だから「組合」とかの論理が歪み過ぎている。
そこから派生する「偏った思考法」に幼子が晒されるのは溜まったものではない。
それでなくとも以下のように「指摘される」教職公務員では尚更である。
「参議院決算委員会」
すべてにおいて「金の問題」でもないだろうに・・・。
たとえば「教える」という語句を持ってすれば、すべてにおいて人間は教わっ
て成長して行くものだし、それが先人から後継され後輩へと受け継がれ、そし
て「教える者も、教えながら学習する」側面を持っているものである。
スポーツの世界でも、これは共通で「教え込む」のに侵食を忘れるとかいう人
が、教え子の成長とか輝かしい成績に我の事のように喜ぶのは、やはり教育の
醍醐味を味わえる。結果的に戦績が振るわぬ者でも、何かしらの人間的成長を
見出せれば、それについての小さな喜びはあるものであろう。
だからこそ「教える怖さ」も同時に味わうことになるものだが、それを単に労
働と捉えれば、そんな機会は自分から放棄していることになる。
「教えて覚えられない」のは知っちゃことでない「トコロテン」で次々生徒は
やってくるのだから「ベルトコンベア」のそれと大差ないでは、いささか人間
的情緒欠落ではないだろうか・・・。
で、その昔の「聖職の者達」の過ちを扱った映画というものがあった。
それが「聖職の碑」という新田次郎原作の作品である。

「聖職の碑」七十八年公開作 (映画動画はなく、音楽ものです)
山岳小説といっていい新田次郎の実際の「遭難」事故のものであるが、それが
軍隊でもなく、高等小学校の生徒と教育者の山岳遭難の物語り・・・。
そこに理想主義と保守的教育者とかの対立と、それを束ねる校長の度量とかが
キャラクターを際立たせて、鍛錬と思える山岳行に生徒とともに向かわせる。
これは「八甲田山」と同じくの展開が見られる山岳遭難の原因とともに、如何
に自然災害に立ち向かったかの記録の再現とも取れる。
まず学校内での教職員同士の対立とそれを取り持つ校長の立場とかが描かれ、
そして結果的に無謀な山岳行についての「落ち度」の告発的映像となり、そし
てその後の参加した者の周囲からの目を通しての「教職者の愚かさ」も同時に
そして遭難記念の碑を建立しようとする者の懸命な行動とかを通して、教育に
携わる者たちの「覚悟」と「責任」のありかについての柔らかい指摘、そして
自然の美しさと反する自然の猛威の凄まじさ・・・。
八甲田山の決断の「錯誤」と相通じる万全への「不覚」、教訓としての「遭難」
と哀悼の「碑」建立には、二度と同じ過ちを犯してならない警句も・・・。
校長を演じるのは鶴田浩二で、責任ある行動力を見せつけ、そして理想主義の
ひ弱な「口だけ番長」役を三浦友和、頑迷なほどの保守的教員に地井武男とキ
ャラ的にもキャストは合っているし、ちょんのま出る碑の建立決定者としての
丹波哲郎の後半ちょっと出て、強い印象を与える美味しい役とかにはにやりと
してしまう。
にしても「認識不足」があちらこちらにあったとしても、幼子を自然から守る
行動には、今の教育労働者とは雲泥の違いがありそうで、さて戦前の云々とか
批判もあまり当てにならない教訓ではないだろうか・・・。
聖職の碑 [DVD]/鶴田浩二,岩下志麻,三浦友和
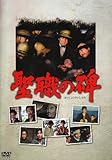
¥4,800
Amazon.co.jp
といったところで、またのお越しを・・・。