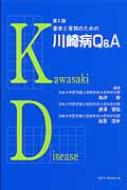■川崎病
1967年に川崎富作博士が、手足の指先から皮膚がむける症状を伴う小児の「急性熱性皮膚粘膜りんぱ腺症候群」として発表された症候群が、新しい病気であることが判明。
博士の名前をとって川崎病という病名になりました。
この病気は世界各地で報告されていて、とくに日本人、日系アメリカ人、韓国人などアジア系の人々が多く、開発途上国ではまれである。
原因はまだはっきりしていませんが、ウイルスや細菌に感染したのをきっかけにそれを防ごうとする免疫反応がおこり、
全身の中小の血管に炎症が生じるのではないかと言われています。
血液の中には白血球という体を守る働きをする細胞があります。細菌などが侵入すると、それが刺激になって白血球が増え、血管の壁(血管壁)に集まってきます。この状態が血管炎で、炎症が強すぎると白血球から出る酵素によって血管壁は傷んでしまいます。もともとは細菌などの侵入に対応して体を守るための反応なのに、反応が大きすぎる場合、自分自身の組織が破壊されてしまうことになるのです。
乳幼児の0.3%が発症する![]()
■川崎病の症状
特徴的な症状から診断。
次の6つの主な症状のうち、5つ以上がみられた場合と、4つの症状しかなくても冠動脈瘤がみられた場合は川崎病(定型の川崎病)と診断します。
症状はそろわないものの、他の病気ではないと判断された場合は「非定型の川崎病」とされる。
主な症状
- 5日以上続く発熱(38度以上)
- 発疹
- 両方の目が赤くなる(両側眼球結膜充血)
- 唇が赤くなる、苺舌がみられる。
- 初期に手足がはれたり、手のひらや足底が赤くなる。
熱が下がってから、手足の指先から皮膚がむける膜様落屑(まくようらくせつ)がある - 片側の首のリンパ節がはれる
アスピリンという薬を内服する治療法。
血管の炎症を抑える効果と血液を固まりにくくすることにより血栓を予防する効果があります。症状の軽い患者様にはこの治療法のみが行われることもあります。
免疫グロブリン療法
免疫グロブリン製剤を静脈内に点滴し、全身の炎症を抑えて冠動脈瘤ができるのを防ぎます。
最も効果的な治療法で、アスピリン療法単独よりも冠動脈瘤ができる頻度を少なくします。
現在、日本では約90%以上の患者さんに免疫グロブリン療法が行われています
ワーファリン(ワルファリン)を使用する事もある