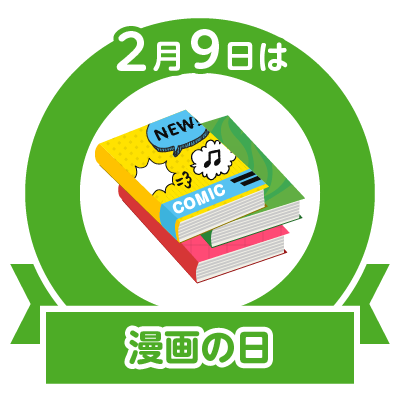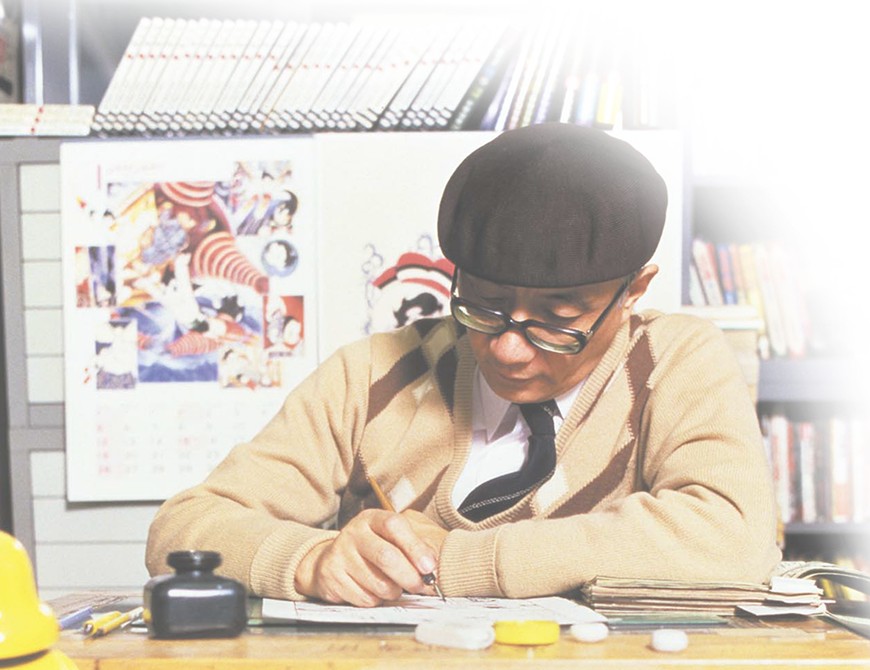最終回まで読み切った漫画ある?
▼本日限定!ブログスタンプ
この日は、漫画家・アニメーション作家の手塚治虫(てづか おさむ)の1989年(平成元年)の忌日。そのため、この日は「治虫忌」とも呼ばれる。
関連する記念日として、7月17日も「漫画の日」となっている。また、国民の祝日「文化の日」と手塚治虫の誕生日に由来して11月3日は「まんがの日」、日本初の少年向け週刊誌『週刊少年マガジン』『週刊少年サンデー』が発刊された日に由来して3月17日は「漫画週刊誌の日」となっている。
●「手塚治虫」について手塚治虫は、1928年(昭和3年)11月3日に現在の大阪府豊中市に生まれる。本名は治。明治天皇の誕生日「明治節」に生まれたことから「明治」にちなんで「治」と名付けられた。また、少年の頃から昆虫をこよなく愛し、自身のペンネームに「虫」という字を当てた。
大阪帝国大学附属医学専門部在学中の1946年(昭和21年)1月1日に『少国民新聞』連載の4コマ漫画『マアチャンの日記帳』で漫画家としてデビュー。翌1947年(昭和22年)、酒井七馬原案の描き下ろし単行本『新宝島』がベストセラーとなり、大阪に赤本ブームを引き起こす。
1950年(昭和25年)より漫画雑誌に登場、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボンの騎士』といったヒット作を次々と手がけた。60歳で死去。そのほかの代表作に『火の鳥』『ブッダ』『ブラック・ジャック』『三つ目がとおる』『アドルフに告ぐ』などがある。
デビューから死去まで第一線で作品を発表し続け、存命中から「マンガの神様」と評された。また、藤子不二雄(藤子・F・不二雄、藤子不二雄A)、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、横山光輝、水野英子、矢代まさこ、萩尾望都などをはじめ数多くの人間が手塚に影響を受け、接触し漫画家を志した。】といことです。Ωヾ(゚ェ゚*)ヘェヘェヘェ
あ、そうなんだ手塚治虫さんの亡くなった日から設定されているんですね。(σ゚∀゚)σナットク‼神様が亡くなって随分経ちますが神様が生みだした作品は永遠ですねο(*´˘`*)ο📚
で、もちろん漫画っ子だったかなさん最終回まで読み切った漫画はたくさんあります(`・∀・´)エッヘン!!逆に楽しみに読んでいたのに悲しいことに作者がなくなって未完のままで完了して最終回まで読めなくなった作品もあります。特にイタズラなkiss」は突然なことに本当に驚き悲しかったです![]()
![]() 今でも入江ベイビーが見たかったと思うとすごく残念に思います
今でも入江ベイビーが見たかったと思うとすごく残念に思います![]()
そんなこんなで・・・ホイ![]() 本日の気になったニュースはこちらです!
本日の気になったニュースはこちらです!
■「異常だ」フィギュア中国代表の“帰化選手”イ・ジュウは再び号泣…国内の大バッシングに海外メディアもあきれ顔【北京五輪】
※イメージです
![]() オリンピックって特別な大会なだけに失敗すると批判や非難がすごい。選手追い込んでどうするんだと不愉快になる。国の代表で舞台に立って頑張った結果だから 励まして次に繋げてあげればいいと思う。よくわからないが、きっと代表が決まるまでにきっと国内でゴタゴタしていたんだと思う。でも選んだのは大人たちなので、本人はベストを尽くしたかったはず。ただし選ぶ過程で、そういう父親の存在への忖度があったかなかったかは闇の中。もちろん本人の責任ではない。選手個人ではなく、帰化させた国や選考委員会そういった権力に文句を言えばいい。他国の有力選手でメダルを取ろうとした国の姿勢が1番悪いと思う。彼女も親の影響だの言われて凄いプレッシャーの中での失敗とかメンタルやられたのかもしれない。特に中国ってこの手の重圧は日本の比じゃないと思う。ただ日本もこれは言えない。おそらくほとんどが出場できなかった選手のファンだと思うがアイスダンスの小松原組への誹謗中傷は酷い。メダル獲得後もまだ誹謗中傷人もいる。選手たち頑張って団体初メダルをとったのに素直に喜べないのかと不思議でならない。北京オリンピック始まってから規定違反とか失格とか非難とかよく問題になっている。頑張ってる選手が気の毒でならない。中国は国家の重圧がすごいから、失敗したら辛いと思う。成績主義、メダル主義、国家の闘いという、五輪憲章から外れた外野ルールのせいで一生懸命やった選手が苦しむ。日本もマスコミがメダル主義の傾向が強いからこれも控えるべきだと思う。熱しやすいナショナリズムは、良い方向を向いている時には、国の発展の起爆剤になり得えるのだろうが、一歩間違えば、自国中心主義、戦争の後押し位の役にしか立たないと思う。あと19歳の女子フィギュアスケーターで思い出したのが、その年頃の安藤美姫さんが失敗すると必要以上に叩かれていた。太り過ぎだとか酷い言われようもあったと記憶している。日本のテレビ番組で今回の件を取り上げていましたが、近年女子プロレスラーが亡くなった件など、日本のマスコミに批判が可能なものかと、疑問に感じる。中国国内でも当然問題視はされていると思うので、むしろそちらを取材して日本との対比が知りたい。
オリンピックって特別な大会なだけに失敗すると批判や非難がすごい。選手追い込んでどうするんだと不愉快になる。国の代表で舞台に立って頑張った結果だから 励まして次に繋げてあげればいいと思う。よくわからないが、きっと代表が決まるまでにきっと国内でゴタゴタしていたんだと思う。でも選んだのは大人たちなので、本人はベストを尽くしたかったはず。ただし選ぶ過程で、そういう父親の存在への忖度があったかなかったかは闇の中。もちろん本人の責任ではない。選手個人ではなく、帰化させた国や選考委員会そういった権力に文句を言えばいい。他国の有力選手でメダルを取ろうとした国の姿勢が1番悪いと思う。彼女も親の影響だの言われて凄いプレッシャーの中での失敗とかメンタルやられたのかもしれない。特に中国ってこの手の重圧は日本の比じゃないと思う。ただ日本もこれは言えない。おそらくほとんどが出場できなかった選手のファンだと思うがアイスダンスの小松原組への誹謗中傷は酷い。メダル獲得後もまだ誹謗中傷人もいる。選手たち頑張って団体初メダルをとったのに素直に喜べないのかと不思議でならない。北京オリンピック始まってから規定違反とか失格とか非難とかよく問題になっている。頑張ってる選手が気の毒でならない。中国は国家の重圧がすごいから、失敗したら辛いと思う。成績主義、メダル主義、国家の闘いという、五輪憲章から外れた外野ルールのせいで一生懸命やった選手が苦しむ。日本もマスコミがメダル主義の傾向が強いからこれも控えるべきだと思う。熱しやすいナショナリズムは、良い方向を向いている時には、国の発展の起爆剤になり得えるのだろうが、一歩間違えば、自国中心主義、戦争の後押し位の役にしか立たないと思う。あと19歳の女子フィギュアスケーターで思い出したのが、その年頃の安藤美姫さんが失敗すると必要以上に叩かれていた。太り過ぎだとか酷い言われようもあったと記憶している。日本のテレビ番組で今回の件を取り上げていましたが、近年女子プロレスラーが亡くなった件など、日本のマスコミに批判が可能なものかと、疑問に感じる。中国国内でも当然問題視はされていると思うので、むしろそちらを取材して日本との対比が知りたい。