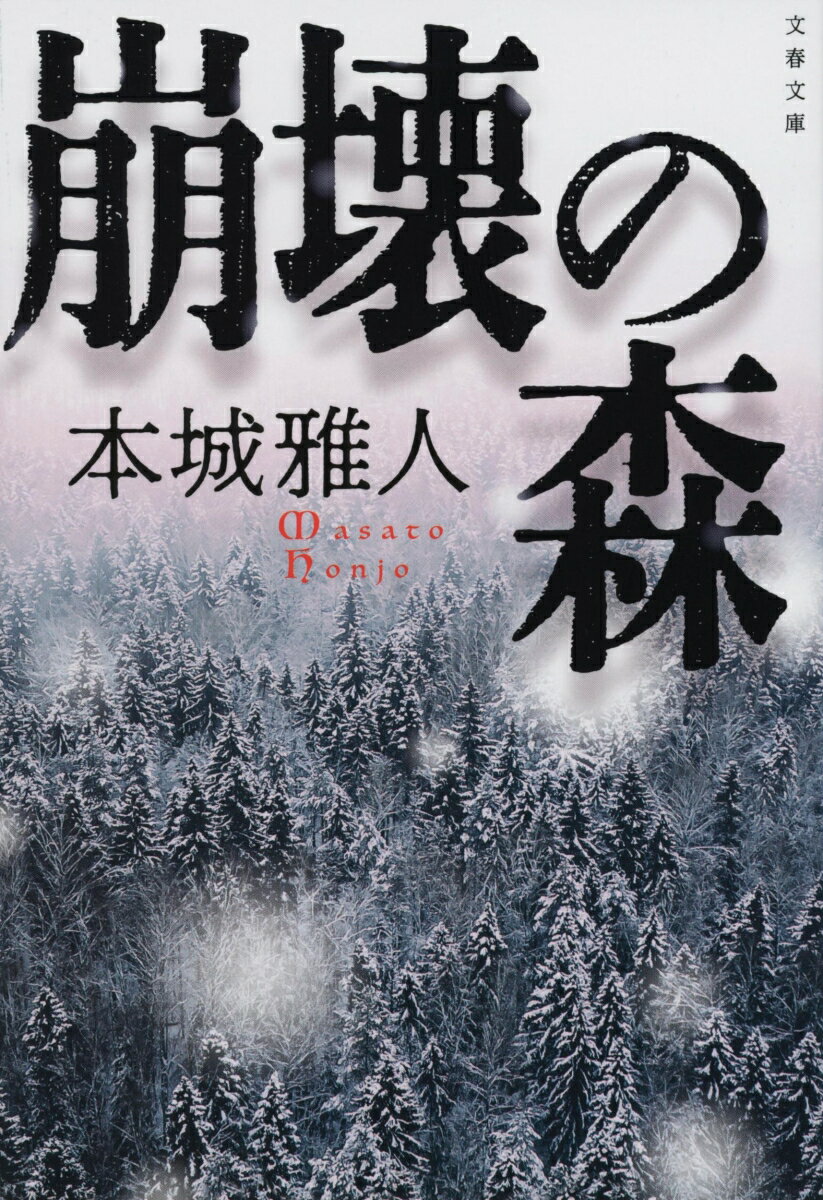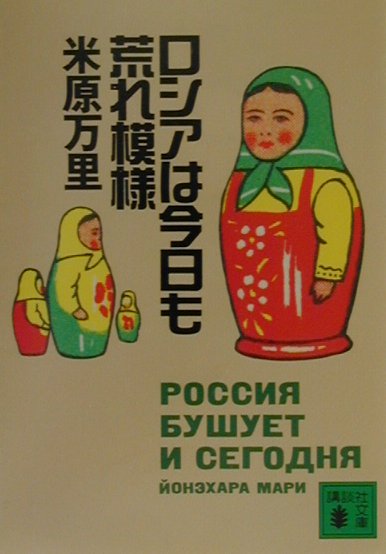ペレストロイカからソ連崩壊という激動の時期に、モスクワ特派員として駐在した新聞記者が主人公。
エリツィンの登場、ゴルバチョフの失墜、ソ連の崩壊と、事象としては知っていましたが、そのなかで新聞記者がなにを思ってどう働き、生活していたのか、具体的に見えておもしろい。
記者さんは体力勝負ですね。
世界的スクープをものにする主人公もそうだし、いかにもスパイ、いかにも共産党員、いかにもソ連人という、いかにも小説、という印象を受けたかと思えば、細かい描写が妙にリアルに感じたりして、不思議な感覚がありました。
そしたら、これは実話を基にしていたのでした。
主人公は、当時実際に大スクープをものにした産経新聞記者がモデルで、情報通の大使館職員は佐藤優がモデル。さらに、著者自身が元新聞記者。なるほど~、細部が生々しいわけです。
エンタメ的おもしろさはありましたが、ソ連崩壊を背景にした本ならば、正直なところこれまで読んだノンフィクションの方がスリリングでおもしろかった。同時代人として当時の社会情勢を知ってる人でなければ、小説の方が読みやすいのかもしれません。
特に同時通訳者としてゴルバチョフやエリツィンらと間近に接した米原万里さんは、観察眼も文章力も最高。
『ロシアは今日も荒れ模様』米原万里著
一般市民、と言えるかはわからないけど、庶民の暮らしや精神世界、人間関係などは、こちらの随筆。著者は記者ではないのだけど、まさにソ連崩壊前後にモスクワに滞在し、メディアで通訳として働いたこともある。
『モスクワ狂詩曲 ロシアの人びとへのまなざし 1986-1992』安達紀子著
「シベリア送り」の意味、社会の背景にある恐怖を理解するなら、この体験記。
『明るい夜 暗い昼 女性たちのソ連強制収容所』