ゆう@子育てパパ
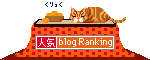
人気ブログランキングへ
レールの間隔が異なる新幹線と在来線を、走りながら車輪をスライドさせて直通運転するフリーゲージトレイン(軌間可変電車、FGT)が今年、九州で実用化に向けた最終試験に入る。地上装置の核となる技術「軌間変換装置」を担当するのは高岡市福岡町に主力工場を持つ、鉄道分岐器メーカー鉄道機器(本社・東京都中央区、吉田晃社長)だ。近く福岡町の工場で部品をつくり、熊本県の試験線へ運び込んで走行試験に備える。
鉄道機器は1914年、吉田社長の祖父で高岡市中田出身の要三さんが分岐器や鉄道用信号メーカーとして東京で創業。45年に工場疎開で、出身地に近い高岡市福岡町下蓑へ主力工場を移した。94年から始まったFGTの研究には、鉄道建設・運輸施設整備支援機構やJR各社、車両メーカーなどとともに参加。地上装置の開発に協力してきた。
装置は4本のレールからなる。軌間変換区間に列車が入ると、まず外側の支持レール2本で、車体の重みを車軸の両端に設けた軸箱と呼ぶ装置を通じて引き受け、車輪を浮かせる。その間に、内側の案内レール2本で車輪の間隔をスライドさせる仕組み。車体側には車輪のロックを解除、固定する装置や軸箱がある。
新幹線のレール間隔である標準軌(1435ミリ)から、さらに広い軌道へ変換する技術はスペインなど海外にある。ただ、標準軌から在来線のような狭軌(1067ミリ)への例はない。長崎新幹線での導入を目指すJR九州の唐池恒二社長は「狭軌への変換は日本でしかできない技術。地上設備も大事な部分で、線路の専門家の技を生かしてほしい」と鉄道機器に期待する。
FGTは2021年度の長崎新幹線に続き、25年度末の北陸新幹線の金沢-敦賀開業時にも導入が予定されている。政府は新年度予算案に21億円余りを計上し、九州新幹線と鹿児島本線で実用化に向けた3年間の最終試験に入る。北陸新幹線の場合、この技術が完成していないと富山-関西間は敦賀駅での乗り換えを余儀なくされることになる。
鉄道車両の制御などが専門の永瀬和彦金沢工業大客員教授は「開発経過で地上側の装置に大きな問題点はない」と説明。ただし「スペインの装置は時速15~20キロで走り抜けられるが、日本は5~10キロ程度。さらにレベルアップが必要だ」と指摘している。
国交省によると、FGTの技術は新幹線と在来線の直通だけでなく、レール間隔が異なる私鉄や地下鉄へも応用できる。吉田社長は「鉄道移動が乗り換えなしでできる素晴らしい技術。実用化されるように努力したい」と意気込んでいる。 (社会部部長デスク・西嶋伸一)
北日本新聞社