ゆう@子育てパパ
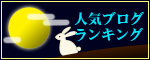
人気ブログランキングへ
日光東照宮(栃木県日光市)の国宝・陽明門の約40年ぶりとなる大修理で、伝統的製法による金沢箔(はく)17万枚が使われることになった。安価な外国産金箔も出回る中、修復を担う公益財団法人日光社寺文化財保存会が「良質な国産箔が必要だ」として石川県箔商工業協同組合に依頼した。同組合は、今回の大量受注を金沢箔の知名度向上の好機と捉え、箔打ち職人の後継者確保・育成にもつなげたい考えだ。
東照宮では2007年度から「平成の大修理」事業が実施されている。陽明門の修理は今年度から2018年度まで続き、飾り金具の補修に10・9センチ四方の箔が使われる。
金沢金箔伝統技術保存会によると、通常の社寺の修理で使われる金箔は多くて2、3万枚で、西本願寺(京都市)は本堂の天井などに10万枚以上、金閣寺(同)は外壁に約20万枚が用いられている。陽明門の17万枚は「一度に使う量としてはかなり多い」という。
日光社寺文化財保存会によると、一般的に飾り金具の補修では金箔を3重程度に重ねて貼るが、今回は激しい風雨や紫外線に耐えられるよう最大で7重とするため、大量の金箔が必要になる。
東照宮の「平成の大修理」は総事業費約26億円のうち、55%が国の補助で半分近くを東照宮側が負担する。
現在、国内市場には国産の半値近い中国産などの金箔が出回っている。文化庁は国宝修復に際し、外国産の使用も認めているが、日光社寺文化財保存会は「日本の伝統的な製法による金箔がほしい」とし、国産の99%を生産する金沢の金箔を使うことにした。金沢金箔伝統技術保存会の松村謙一会長は「金沢に伝統技術が残っている証であり、職人として誇らしい」と語る。
陽明門の修復に用いられる金箔は、雁皮(がんぴ)紙(し)に金を挟んで打ち延ばす「縁付(えんづけ)」という伝統技法で作られる。現在、この技を継承する職人は県内に23人で、30年前の4分の1に減っている。今年4月に縁付による箔製造が金沢市の選定保存技術となり、製法の保全に向けた活動が進められている。
県箔商工業協同組合は「東照宮の大修理は多くのメディアに取り上げられており、金沢箔の知名度が上がれば、需要の拡大も期待できる」とし、今後も東照宮の仕事を継続的に請け負って職人の技術継承の機会としても活用したいとしている。
陽明門 世界遺産「日光の社寺」の一つ、日光東照宮の門で、国宝に指定されている。東照宮は徳川家康を祭っており、陽明門は1636(寛永13)年、3代将軍・徳川家光が東照宮を建て替えた際に完成した。500以上の彫刻が施され、いつまでも見飽きないことから「日暮の門」とも呼ばれる。
北國新聞社