是非、行って下さいね。 (#^.^#)
ゆう@子育てパパ
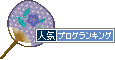
人気ブログランキングへ
この記事がアップされているころには、一部をのぞき全国各地で参院選の投票が始まっている。インターネットを使った選挙運動が初めて解禁された今回の参院選は、投票率の行方も注目の一つとなっている。若者はよくネットを使う。だからネット選挙解禁で政党や候補者に加え、有権者も特定候補の応援などを発信することができ、関心が高まって、低迷する若い世代を中心に投票率が上がるのではないか、というわけだ。
だが、雲行きは怪しい。今晩には分かることだが、ネット選挙解禁「元年」にもかかわらず、今回の投票率は下がるのではないかとみられている。3年前の前回参院選は全体で57・9%で、抽出調査の世代別調査で20代は最も低い36・1%にとどまった。20代の3人に2人程度は投票に行かなかった計算になる。これよりも下がるとは、にわかに信じがたい。
初めて選挙権を得た約20年前のことを今でも覚えている。やっと日本の政治に参加することができるようになった、と。以来、一度も投票しなかったことはない。投票に行かないことは、裸で外を歩くぐらい恥ずかしいことだとさえ思っている。
「それは政治部の新聞記者だからだ」「忙しいサラリーマンにそんな暇はない」という声があることだろう。しかし、「忙しい」の理由に正当性はあるだろうか。
ネット選挙解禁のための公職選挙法改正案を審議していた4月の衆院政治倫理・公選法特別委員会(倫選特)。参考人で呼ばれたIT業界のカリスマといわれる某氏は「日曜日は私のように子供がいると忙しいんです。ディズニーランドも行かなきゃいけないし、いろいろなところに行かなきゃいけない」と語っていた。
どんなに忙しいのか知らないが、最近は期日前投票も行いやすくなったというのに、カリスマによれば、投票に行くことよりも家族とディズニーランドに行く方が優先すべきことなのだそうだ。こんな人物を参考人として呼んだ国会議員も議員だが、開いた口がふさがらなかった。国政選挙なら数年に1回程度、地方選挙は年に数回あるかないかの投票日に、投票所に足を運ぶことがそんなに大変なことなのだろうか。
最近は経費の問題などもあって、自治体が投票所の数を減らす傾向があるという。しかし、それは人口が少なく、交通の便も悪い地方がほとんどだ。それでも地方の方が都市部よりも投票率は高い。都市部の投票所はたいてい徒歩圏内にある。「面倒くさい」は単なる言い訳にすぎない。
「ネット選挙解禁に加えて、ネットによる投票の実現を」という人もいる。自宅などでも可能なネット投票は便利かもしれないが、逆に言えば、ネットで投票できないと投票所に行かないのだろうか。本末転倒だ。
期日前投票ではなく、投票日当日に投票に行く予定だったが、事故にあって入院したとか、立ち上がれないほどの高熱が出たとか、暴風雨で一歩も外に出られないとか、もっと極端なことを言えば、投票日に亡くなる人も必ずいるわけだから、投票率100%はあり得ない。それにしても有権者のほぼ2人に1人が投票に行かないのは、いったいどういう了見なのか。投票に行くか行かないかが議論になること自体、不思議でならない。
成年後見人が付いたことで選挙権を失った女性は国を相手取って裁判を起こした。最終的に公選法が改正され、今回の参院選から選挙権を「回復」した。そこまでして一票を投じたい人もいる。
日本にも在外投票制度があるが、事前に登録した人しか投票できない。国内なら、そんな手続きは無用だ。お隣の大国も含め、外国では国民の選挙権すらない「共和国」もある。それなのに日本の若者のほぼ3人に2人は自ら投票する権利を放棄している。
国政選挙のいわゆる「一票の格差」について、弁護士らを中心とするグループが全国各地の裁判所に提訴し、最高裁も違憲状態と判断したことで、国会でも格差是正の動きが出た。格差是正もいいが、より深刻なのは、そこまで貴重な一票を投じない人が多いことではないか。
「自分の選挙区には、投票したいと思う候補者がいない」という声もある。そういうケースもあるに違いない。だが、国政選挙では比例代表がある。少なくとも主要政党は候補を出している。それでも選択肢がないという場合は、望ましくないと思うが、白紙で投票するという手段だってある。
6月下旬、東京・本郷の東大で開かれた若者を中心とする投票率向上を目指す団体が集まったシンポジウムがあるというので、のぞいてみた。10代後半から20代の若者が代表を務めるさまざまな団体がネット選挙解禁を契機に若者の投票率を上げるためのアイデアを披露した。
登壇する若者たちは「政治家は何か悪いことをしているイメージがあった」「政治なんて自分に関係ないと思っていた」と語った。ステレオタイプな発言に閉口していると、彼らのアイデアを聞いて、めまいがしてきた。
「投票所の前で写真を撮り、投票に行ったことが証明できれば、お店で割引になる特典がある取り組みをやっています」「投票を証明した人の中から抽選でグッズが当たります」などといった軽薄なアイデアが大半だったからだ。
双方向性が特徴のネットを使い、政治家と有権者が直接やりとりする機会を設けようとの企画もあったが、少数派だった。若くして積極的に何かに取り組む姿勢はすばらしい。ただ、「とりあえず投票に行こう」というだけで、何のために投票するのかということを広く浸透させようとの発想はあまりなかった。
「なぜ政治や選挙への関心がないのか」という話題になると、「しんぶんはかんじがあるからよまない。ぜんぶひらがなだったらいいのに」と発言する団体の代表もいた。会場は笑いに包まれたが、とても笑う気になれず、怒りさえこみ上げてきた。ネット選挙解禁を生かそうという若者の代表的な人たちにして、これだ。
せめてもの救いは、シンポジウムの主催者で、若者の投票率向上に取り組んでいるNPO団体「Youth Create(ユースクリエイト)」の原田謙介代表の言葉だ。原田代表は別の機会で取材したとき、「投票率を上げるには教育が大事だ」と語っていた。その通りだと思う。
「自分が一票を投じたところで何も影響はない」との理由で棄権する人もいるという。本当にそうだろうか。私たちの生活は、あらゆる面で法律のもとに動いている。国のお金の使い方も企業活動も交通規則も。その法律を作るのが国会議員の仕事であり、その国会議員を選ぶのは有権者だ。だから、政治的無関心や投票の棄権はあり得ない。国民として最低限の権利の行使について、まともに教えていない親や学校が多いのだろう。
というわけで、今からでも遅くありません。まだ投票を済ませていない有権者の方は、恥をかかないためにも投票所に行きましょう。私もこれから投票所に行き、22日朝まで会社で結果の行方を見守ります。(酒井充)
- 参院選「63」「70」「101」…3つの数字が焦点
- 開票中に「進撃の巨人見たい」… MX“ゆるすぎる”選挙特番の裏側
- 池上彰さんと考える「面白い選挙報道」 政治家個人に焦点
- 「若者から搾取」「格差是正は…」候補者に不満届ける逆選挙サイト
- 参院選候補 17日間の選挙当選で6年間の身分保障で収入3億円
- CIA元職員が気づかせた