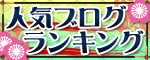
人気ブログランキングへ
先ごろ文化庁が公表した平成23年度「国語に関する世論調査」に「異字同訓の漢字の使い分けについて」という項目がありました。異字同訓(同訓異字とも言う)とは「漢字は異なるが、意味が似ていて、訓での読みが同じになるもの」のことです。例えば「直る、治る」「乗る、載る」「油、脂」などです。
文化庁のアンケートは「5つの異字同訓の漢字の使い分けについて、難しいと感じるか、それとも感じないか」を尋ねたものでした。
以下が5つの異字同訓の漢字です。
・おさめる(収、納、修、治)
・かえる(変、換、替、代)
・かたい(堅、固、硬)
・はかる(図、計、測、量、謀、諮)
・もと(下、元、本、基)
さてアンケートの結果は、「難しい」と回答した人の割合が最も高かったのは「はかる」で、42・4%。最も低かったのは、「かたい」の21・3%でした。
驚いたのは、「はかる」以外の4語は「難しくない」と回答した人の割合が過半数に達し、5割台半ばから6割台後半にまで達していたことです。
もし私がこのアンケートを受けたとすれば、全ての問いに「難しい」と回答したでしょう。実は、私たちが日々参考にする用字用語集「産経ハンドブック」の中で最も多くのページが割かれているのが、この異字同訓をはじめとした漢字の使い分け例なのです。それだけ漢字の使い分けがややこしくて難しいということでしょう。しかも、ハンドブックの使い分け例も絶対ではありません。
過去にこんな質問を受けたことがありました。「『プレゼントをおくる』は『贈る』でいいと思うのですが、『プレゼントを宅配便でおくる』という場合は『送る』か『贈る』、どちらがいいのでしょうか」と。
ハンドブックでは「荷物をおくる」は「送」、「お祝いをおくる」は「贈」と区別しています。このときは答えに窮しつつも、「まあ、この場合はどちらを使ってもいいと思うけど、おくる人の気持ちを考えると『贈』の方がいいのかな」と、なんとも自信のない返答をしましたが…。
今回の文化庁のアンケートに話を戻します。これらの漢字の使い分けがなぜ難しくなるのかを考えてみましょう。例えば、「おさめる(収、納、修、治)」の使い分け方ですが、ハンドブックの定義では、
「収」=収容、収拾、取り込む
「納」=納付、納入、落ち着く
「修」=身につける、正しくする
「治」=乱の対語、鎮める、支配する
となっています。
ただ、「収納(物をしまう、税を受領するなどの意)」、「修治(つくろいなおすの意)」という熟語があります。
他の4つの異字同訓の漢字にも「変換、代替、堅固、計測、計量、測量、元本、基本」など、ほとんど同じ意味をもつ漢字で構成されている熟語があるので、使い分けが困難なケースが生まれてくるのです。
しかし、新聞紙面の中で使い分けがバラバラで整合性がとれてないと困ります。そこで何とか理由を考え使い分けます。それでも判断が付かないときには、仮名を使うという裏ワザがありますが。
でもこれが日本語の「表現」の奥深さなのでしょう。表現といえば「表れる、現れる」の使い分け、これもまたややこしいんですよね。(に)
- テープレコーダー、MP3… 技術進んでも声を聞くのは心地いい
- 個性的な名前「々奈」「々寧」はダメです
- 気象と時に関する用語 気になるその定義とは…
- 気になる「しせんたー」 誤字脱字の部類について考える
- 「再々々々々々々婚」 何度目の結婚?
- 藻からバイオ燃料 日本も産油国?