【カルーゾ】
※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
-----------------------------------------------------------------
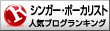
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。
世の中には、カレーが好きな人もいれば、お蕎麦が好きな人がいます。伝統的なフランス料理が大好きな人もいれば、バターをたっぷり使ったソースに胸焼けを起こしてしまう人もいます。
いきなり今日はグルメの話題と思われる方がおられるかも知れませんね。
なぜ、こんなお話からから始めたかというと、「シャンソニエ(シャンソンの店)にいらっしゃるお客様が、何を求めてお店にいらっしゃるのか」とうことを知ることが、まず大切だと思ったからです。
こんな話を、こ業界2年目の私がするのも僭越かも知れませんが、こちらに来て、特に感じることです。
もちろん、演奏の完成度は高めなければならないのだけれど・・・・・。
1年あまりステージに立ちながら感じたことは、単に声のよさを聴きに来ているのではないんだとういことです。
オペラの世界ではまず、声、声、声。
特にイタリアオペラのテノールは、極端な言い方をすれば、「聴かせどころの高音」が決まったかどうかが、その日の評価のすべてだったりします。
もちろん、一流ともなれば、歌のクオリティーだけでなく、演技や顔の表情まで、どこをとっても完璧に近いパフォーマンスをする人もいますが・・・。
でも、まずは最低限楽譜に書かれた音(時には書かれていない高音まで)を、決まった発声法(例 ベルカント唱法)を用いて声にしていけば、ある程度音楽が自然にに出来上がっていく感じ。そして、そこから更に深い感情表現を、発声の技術を使って極めていくもの。
壮大なドラマの中の喜怒哀楽を、声で表現するもの。
表現の仕方も、自己流ではなくて、人間の声の生理的なメカニズムと限界を理解した上に成り立つ「メソッド」がしっかりと確立されているのです。
メソッドは科学です「ここはこういう出し方をすればクリアできる」という体系化されたテクニックに数々。
だから、才能の差はあるにせよ、万人にとって、「これを習得すれば歌い切れる」という再現性があるのです。
専門用語を使わずに説明しますと、人間の声は、低音から中音、そして、高音に上がっていくときに、下から突き上げていくと、割とすぐに天井にぶち当たり、限界があります。
そこで、まず、声を「下の声」から、「上の声」へとチェンジしてく時の、転換点を選んで決めます。
「両方の声で歌うエリアも決めます」(だいたい決まっている)。上の声にする時は、息を細くして流速を増し、口の中を狭くして声の方向を「カクッと」少し曲げて鋭くしていきます。
ホースで放水するとき、ホースの先を指でつまんで狭くして遠くへ飛ばす感じです。
そのときに、聴いている側は、中音域までの声に、更にプラスアルファの心地よい緊張感が生まれます。
発声メソッドが確立されているわけですから、作曲家もそれを意識して曲を書きます。
例えば、苦悩を表現したいとき、わざと苦しい高音を「上の声の出し方で伸ばして、緊張感を作れと言わんばかりに書いてきます。」
そして、「さらに高音」はまた別の出し方、他にもフィギアスケートの「トリプリアクセル」や「トリプリトーループ」などのように、名前が付けられたいたテクニックが沢山有り、それらを駆使して表現します。
そして、オペラファンのお客様も歌手がいかに苦しさに打ち勝って出しているのかを解って聴いているのです。
だから、上手くクリアして、素晴らしい高音を伸ばせば最大級の賞賛をしますし、ミスをすれば、ブーイングも起こります。
【見よ恐ろしい火を】敵に捕らわれた母を救出に行くときのアリア
最後の高音と聴衆の熱狂にご注目
(人の声は人を狂わせる力を持っていますね)
特に、オペラを観にいらっしゃるお客様は、喜怒哀楽を声で表現する、優れた歌手たちの声の共演に酔いしれたいのです。
ところが、私が、シャンソンの舞台に出始めた頃、高音のパワーを見せようと、シャンソニエでも時々歌われる「オー ソーレ ミオ」の途中を、パヴァロッティがよくやったように、トリル(音を一つ上の音と細かく往復させる)を徐々に細かくして膨らませてうたい、最後の高音を長々と伸ばして歌ったことがありました。
上の動画の高音ほどではありませんが、かなりいい感じで歌えました。
聴衆から熱狂的な「Brava!」の声援が飛ぶことを期待して、満面の笑みで誇らしくジェスチャーを決めました。
すると、何やら舞台上で味わったことのない気まずさ!「これは一体何なんだ?」と当時はおもいました。
しかし、後で聞くとお客様も同じように思っていたそうです。
演奏後、「あのアクロバットは何?」を言われました。
ベルカントオペラで普通に使われる技術。あの「トリル」。
そのお客様にとっては、今まで体験したことのない表現だったようです。
マイクを外して歌う歌手も始めでカルチャーショックだったようです。
カレーを食べに来た蕎麦アレルギーのお客様に、お蕎麦を出してしまったようです。
そうですよね!私がケンさんの歌に感動したのも、美輪さんの歌に心を動かされたのも、歌を超えた深い洗練された表現力と、その背後にある大きな愛情や優しさや、厳しさや意志の強さなどを感じたからなんですよね。
大事なことを見落としていました。
お客様が何を求めて、こちらにいらっしるのかを、しっかり考えなければならないと、改めて教えられたステージでした。
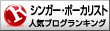
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
追伸
歌手になって、声を安定させるために行った増量も行き過ぎて、10キロオーバー。
お正月のテレビ出演に向けて、10キロダイエットに成功。
一番好んで食べたのが、こちらのお粥専門店のお粥。
先日も美味しく戴いて来ました。
小さい器は、ハーフサンラーメンです。

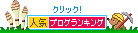
人気ブログランキングへ
※喉頭癌に倒れた伝説のオペラ歌手、カルーソーの晩年をテーマをにしたカンツォーネ!恋人(娘)へ別れと、諦観を歌い上げるルチオ・ダッラの名曲!
-----------------------------------------------------------------
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
みなさま、おはようございます。村上リサです。
世の中には、カレーが好きな人もいれば、お蕎麦が好きな人がいます。伝統的なフランス料理が大好きな人もいれば、バターをたっぷり使ったソースに胸焼けを起こしてしまう人もいます。
いきなり今日はグルメの話題と思われる方がおられるかも知れませんね。
なぜ、こんなお話からから始めたかというと、「シャンソニエ(シャンソンの店)にいらっしゃるお客様が、何を求めてお店にいらっしゃるのか」とうことを知ることが、まず大切だと思ったからです。
こんな話を、こ業界2年目の私がするのも僭越かも知れませんが、こちらに来て、特に感じることです。
もちろん、演奏の完成度は高めなければならないのだけれど・・・・・。
1年あまりステージに立ちながら感じたことは、単に声のよさを聴きに来ているのではないんだとういことです。
オペラの世界ではまず、声、声、声。
特にイタリアオペラのテノールは、極端な言い方をすれば、「聴かせどころの高音」が決まったかどうかが、その日の評価のすべてだったりします。
もちろん、一流ともなれば、歌のクオリティーだけでなく、演技や顔の表情まで、どこをとっても完璧に近いパフォーマンスをする人もいますが・・・。
でも、まずは最低限楽譜に書かれた音(時には書かれていない高音まで)を、決まった発声法(例 ベルカント唱法)を用いて声にしていけば、ある程度音楽が自然にに出来上がっていく感じ。そして、そこから更に深い感情表現を、発声の技術を使って極めていくもの。
壮大なドラマの中の喜怒哀楽を、声で表現するもの。
表現の仕方も、自己流ではなくて、人間の声の生理的なメカニズムと限界を理解した上に成り立つ「メソッド」がしっかりと確立されているのです。
メソッドは科学です「ここはこういう出し方をすればクリアできる」という体系化されたテクニックに数々。
だから、才能の差はあるにせよ、万人にとって、「これを習得すれば歌い切れる」という再現性があるのです。
専門用語を使わずに説明しますと、人間の声は、低音から中音、そして、高音に上がっていくときに、下から突き上げていくと、割とすぐに天井にぶち当たり、限界があります。
そこで、まず、声を「下の声」から、「上の声」へとチェンジしてく時の、転換点を選んで決めます。
「両方の声で歌うエリアも決めます」(だいたい決まっている)。上の声にする時は、息を細くして流速を増し、口の中を狭くして声の方向を「カクッと」少し曲げて鋭くしていきます。
ホースで放水するとき、ホースの先を指でつまんで狭くして遠くへ飛ばす感じです。
そのときに、聴いている側は、中音域までの声に、更にプラスアルファの心地よい緊張感が生まれます。
発声メソッドが確立されているわけですから、作曲家もそれを意識して曲を書きます。
例えば、苦悩を表現したいとき、わざと苦しい高音を「上の声の出し方で伸ばして、緊張感を作れと言わんばかりに書いてきます。」
そして、「さらに高音」はまた別の出し方、他にもフィギアスケートの「トリプリアクセル」や「トリプリトーループ」などのように、名前が付けられたいたテクニックが沢山有り、それらを駆使して表現します。
そして、オペラファンのお客様も歌手がいかに苦しさに打ち勝って出しているのかを解って聴いているのです。
だから、上手くクリアして、素晴らしい高音を伸ばせば最大級の賞賛をしますし、ミスをすれば、ブーイングも起こります。
【見よ恐ろしい火を】敵に捕らわれた母を救出に行くときのアリア
最後の高音と聴衆の熱狂にご注目
(人の声は人を狂わせる力を持っていますね)
特に、オペラを観にいらっしゃるお客様は、喜怒哀楽を声で表現する、優れた歌手たちの声の共演に酔いしれたいのです。
ところが、私が、シャンソンの舞台に出始めた頃、高音のパワーを見せようと、シャンソニエでも時々歌われる「オー ソーレ ミオ」の途中を、パヴァロッティがよくやったように、トリル(音を一つ上の音と細かく往復させる)を徐々に細かくして膨らませてうたい、最後の高音を長々と伸ばして歌ったことがありました。
上の動画の高音ほどではありませんが、かなりいい感じで歌えました。
聴衆から熱狂的な「Brava!」の声援が飛ぶことを期待して、満面の笑みで誇らしくジェスチャーを決めました。
すると、何やら舞台上で味わったことのない気まずさ!「これは一体何なんだ?」と当時はおもいました。
しかし、後で聞くとお客様も同じように思っていたそうです。
演奏後、「あのアクロバットは何?」を言われました。
ベルカントオペラで普通に使われる技術。あの「トリル」。
そのお客様にとっては、今まで体験したことのない表現だったようです。
マイクを外して歌う歌手も始めでカルチャーショックだったようです。
カレーを食べに来た蕎麦アレルギーのお客様に、お蕎麦を出してしまったようです。
そうですよね!私がケンさんの歌に感動したのも、美輪さんの歌に心を動かされたのも、歌を超えた深い洗練された表現力と、その背後にある大きな愛情や優しさや、厳しさや意志の強さなどを感じたからなんですよね。
大事なことを見落としていました。
お客様が何を求めて、こちらにいらっしるのかを、しっかり考えなければならないと、改めて教えられたステージでした。
シンガー・ボーカリスト ブログランキングへ ←こちらを、クリックお願いいたします!!
追伸
歌手になって、声を安定させるために行った増量も行き過ぎて、10キロオーバー。
お正月のテレビ出演に向けて、10キロダイエットに成功。
一番好んで食べたのが、こちらのお粥専門店のお粥。
先日も美味しく戴いて来ました。
小さい器は、ハーフサンラーメンです。

人気ブログランキングへ