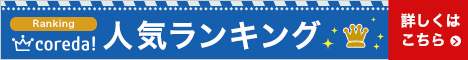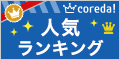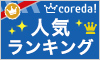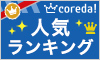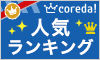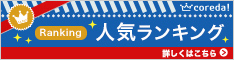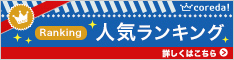成功する人の頭のなかみ 米山 公啓著
神経内科の医者であり、作家の米山さんの本の紹介は2冊目になります。
お医者さんが専門家の目から診た「成功する人の頭のなかみ」の本です。
米山さんによれば、脳は自分で作っていけるもので、成功するような脳に自分の脳を変えていくことができるということで、これはGood Newsでしょう。
今日の英語ブログ でアップル社のスティーブ・ジョブズ会長のスタンフォード大学でのスピーチをご紹介しましたが、彼は"You've got to find what you love!"といって、自分が本当に楽しめることを、もっと極端にいうと「自分が今日死ぬことが分かっていたらやりたいと思うこと」を仕事として見つけよ、と言っています。
米山さんのこの本でも、自分が好きなことをやっているときは、脳が活発に働くというようなことが書かれています。また、自分の脳を「成功脳」にするための日常的に実践できることが書いてありますが、そんなにおおげざな、無理なことをするよりも、積極的なことばを聴き、言い、そうした楽しいノウハウがならべられています。
道徳教育的に「良い人間になるには。。。」「成功するには。。。」と教えられるよりも、「こうしたら脳はよりよく動くようになる」といわれると、「やってみようかな」と思ってしまう。そう思わせる本です。
ひとことでいうと、成功するために自分をどんな環境におくかということを、極めて具体的に教えてくれる楽しいノウハウ本です。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
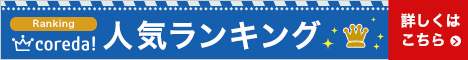
志のみ持参 上甲 晃著

- 上甲 晃
- 志のみ持参―松下政経塾十三年の実践録
著者の上甲晃さんはあの松下政経塾の塾頭をされていた方です。
先日上甲さんの講演を聴いたばかりだったので、講演内容と重なる部分が多く有りましたが、講演で話されたことばは、過去のこんな経験に基づいた発言だったんだなどと思いながら読むと、別の楽しみがありました。
この本の内容は、ひとことでいうと「知識を得ること以上に大切な知恵を得ることの大切さ」を説いているように思います。
ことばという便利なものを獲得したために、とかく私たちは抽象的な議論を好み、そういう議論をしていることが高邁な活動をしているように錯覚しているのではという指摘がこの上甲さんのことばにはあります。それは、彼が薫陶を受けた松下幸之助という人物から学んだものを多く含んでいるようです。
例えば掃除ということを通して、人に言われてではなく、自分が進んでことをなす事の重要性をしきりに説いていらっしゃる部分は、多くの人にとっては「古臭い」と感じることかも知れませんが、多くのことを経験したものほど、その説得力を感じるのではないでしょうか?
人を教えることの大切さと難しさを同時に思わせてくれる本でした。自分の今後のあり方を考えさせられる本でもありました。また、さまざまな出来ごとを人のせいにせず、「自分が変れば良い」と確信を与えられて元気も出ました。
一度、上甲さんの分かりやすい、日常のことばで述べられている貴重な真実に耳を傾けられてはいかがでしょうか?
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
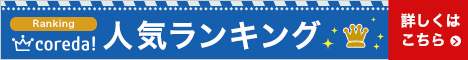
夢に日付を! 渡邊美樹著

- 渡邉 美樹
- 夢に日付を! ~夢実現の手帳術~
手帳関連書ばやりの感があり、私も多く読みました。どの本もよいヒントがありました。
しかし、その中で、私にとってはこの本が一番具体的なヒントになりました。
印象に残ったことはいくつかあり、自分に足りないとことろを反省させられました。
ひとつは志の高さ。これが、やはり夢実現の第一歩、これを忘れないための工夫が必要であること。
もうひとつが「緊急で大切なこと」に振り回されて「緊急じゃないけど大切なこと」(著者によればこれが一番大切なもの)を忘れてしまうこと、それが結果的に大きな夢の実現を妨げること。
渡邊社長に近づくような手帳jを持つことを当面の目標にしたいと思いました。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
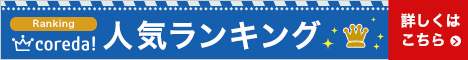
早朝起業 松山真之助
ある本がきっかけで読んだ人の行動が変ったら、その著者にとってはたいへんな喜びでしょう。
この本の著者松山さんは、この本でそういったことを実現されたのではないでしょうか?
自称「夜型」の私が早起き(といっても、勤務先と家が比較的近いので6時に起きることにしたのですが)して、出勤前に一仕事することを始めたのは、この本がきっかけです。
実は、ある方の紹介で、近々松山さんにお会いすることになっており、事前準備として読んだのですが、朝起きすることで、航空会社の要職をこなしながら、メルマガ発行、講演、執筆などの活動もこなす「人生の大回転」(帯紹介文)を果たされた人への興味を高まりました。
一回の人生、濃く生きたいと思っている方(私もその一人ですが)、読む価値のある本だと思います。この手の本で、ありがちな「この方法がベスト。なぜやらないんだ!」的な押し付けトーンがなく、自分に一番合うやり方を見つけるきっかけにするように勧めていらっしゃるのも、読後感の良さの要因だろうと思います。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
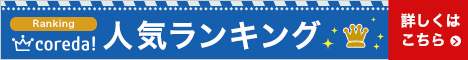
「稼ぐ」脳 米山公啓著 ”医学的”に一番正しい脳の使い方

- 米山 公啓
- 「稼ぐ」脳 "医学的"に一番正しい脳の使い方
著者の米山さんは神経内科を専門とするお医者さんであり、作家という方です。
「稼ぐ」脳というタイトルと目次で思わず買ってしまいました。
最近脳を鍛えることの重要性を説く本が多く出ているようです。ひとつのテーマでたくさんの本が出ると、世の中は「脳とはこうであるべき」という話題になりがちです。
この本を読んでほっとしたのは、脳にはどうも個性があり、それを伸ばす、すなわち、自分の脳(すなわち自分自身)の個性に合った使い方、鍛え方をすれば、自分に合った生き方ができるということではないかと思ったからです。
読んでいて「参考にしたいな」と思う部分と、「あー、これまでやってきたことは間違ってなかったんだ!」と交互に感想がでるような、なかなか楽しい本でした。
私の場合は、目次をさーと見て、辞書的に興味のある章をまず読んでから、全体を読みました。真っ先に読んだのが「オリジナルを発揮する脳」(第9章)、「行き詰まりのない脳」(第3章)「忘れない脳」(第4章)などです。自分の課題にあって脳に関する話題が一杯詰まっていて、読んでいて元気付けられました。
ご参考に、目次をつけておきます。
はじめに
プロローグ 「稼ぐ」脳を正しく理解するための予備知識
第1章 アイデアを出せる脳
第2章 金のためでなく働く脳
第3章 行き詰まりのない脳
第4章 忘れない脳
第5章 人を覚えている脳
第6章 仕事が早い脳
第7章 追い詰められて働く脳
第8章 飽きない脳
第9章 オリジナルを発揮する脳
第10章 時間をゆったり使える脳
第11章 人から好かれる脳
第12章 自分を発見した脳
第13章 楽観的な脳にする
第14章 人生100年を考えた仕事
第15章 脳は変えられる
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
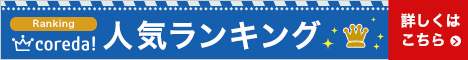
「決断力」 羽生 善治
仕事仲間の一人、若手のホープから投稿を頂きました。最近流行りの「あまぁーーーーい」ニックネームで登場です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1996年、王将位を獲得し、名人、竜王、棋聖、王位、王座、棋王と合わせて「七大タイトル」全てを独占。「将棋会始まって以来の七冠達成」として日本中の話題となった羽生 善治氏の、将棋に対する熱い思いがギッシリ詰まった一冊です。
オールラウンドで幅広い戦法を使いこなし、終盤に繰り出す妙手「羽生マジック」がどのようにして生まれるのか?またタイトル戦登場75回、タイトル獲得合計60期、といった強靭なる精神力は、将棋ファンならずとも、一社会人、またビジネスマンとして大変勉強になります。
その中の一つに、「知識」と「知恵」についての頷かされるコメントがありました。羽生さんは何かを「覚える」、それ自体が勉強になるのではなく、それを理解しマスターし、自家薬籠中のものにする - その過程が最も大事だと言っています。それは他人の将棋を見ているだけではわからないし、自分のものにはできない。自分が実際にやってみると、「ああ、こういうことだったのか」と理解できる。理解できたというのは非常に大きな手応えになる。なによりもうれしい。そして、新しい発見があるとまた次も頑張ろうと、フレッシュな気持ちになれる。羽生さんは、将棋を通じて知識を「知恵」に昇華させるすべを学んだが、その大切さは、すべてに当てはまる思考の原点であると言っています。
私は仕事柄、金融関連の情報提供を主な業務としているのですが、クライアントに“カタイ”資料をお送りする際に、一言、“ヤラカイ”営業トーク(メール文面)を付けることにしています。単なる「知識」の提供ではなく、少しでもクライアントの方々の「知恵」として使って頂けるように・・・
金融業 バニラ(28歳)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
羽生さんのように若くして成功する人もいれば、私のように50近くになって第二の人生を考えるやつもいる。若くして学ぶ姿勢を忘れず、早速この本読んでみようと思います。 cbohiro
あなたの成長が地球環境を変える! 立山裕二著
金曜日に楽天のブログも持っていらっしゃる梶川さんの主催するとどろく塾セミナーに行ってきました。
うれしい方に「想定外」の成果でした。
講師は今日紹介する本の著者であり、「環境コンサルタント」の立山裕二さん。はるばる尼崎からの来演。とにかく立山さんの常に絶やさない笑顔が印象的でした。
一杯印象に残ることばを頂きましたが、一番印象に残ったことばのひとつが「プラス思考がとらわれになることがある」というもの。
よくプラス思考ができているかどうかのテストとして使われる「水が半分入っているコップ」。
確かに「半分しか。。。」と考えるより「まだ半分も。。。」と思う方が前向きの姿勢に見えるが、他人が「私は「もう半分なくなっている」派」宣言をすると、その人に対し、「あなたはマイナス思考の人で、それはなおさなくてはいけない」とその人に言ったり、責めたりするようになる。これは「ポジティブ・シンキング」に思い込み、されにとらわれるということが起こった入る状態だということです。
立山さんによれば、「半分も。。。」という発想と、「半分しか。。。」という両方の発想をそのまま受け入れるのが真のプラス思考だというこです。こう考えると、えらく気持ちが軽くなりました。
確かに「ポジティブ・シンキング」を少しかじると、教科書に書かれている、あるいは講師の言う「ポジティブ・シンキング」がいつもできるとは限らない自分がいるっていうことありませんか。「ポジティブ・シンキング」の勉強をし、ポジティブな人間になろうとしているのに、「なぜ自分はポジティブになれないんだろう」というふうに悩んだり、自分を責めたり。。。
そういう悩みを若干持っていた私自身にとって、立山さんのことばはおおげさにいうと「福音」でした。
今日紹介する本は、こうした立山さんの生き方と、環境問題と私たち個々の生活者の生き方のつながりをやさしく披露した本です。
生き方パートで元気をもらい、環境問題パートでは環境問題も身近に考えるきっかけをもらう、そういう本です。14-5年前に「将来は環境が大きなビジネスになる」といった友人がいて、今になって彼の先見性に驚いているのですが、立山さんは、まさにそういう時代を生きてきた人です。今後もっとお付き合いしたい人です。
皆さんもこの本で、立山さんのお人柄と知恵に触れて下さい。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
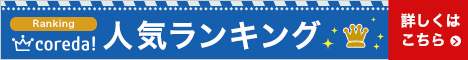
エンジニアが書いた環境エッセイ-現代の恐竜
松村さんは私が最近参加しはじめた勉強会の中心的な人物、人生の大先輩であります。
勉強会第2回目の出席の時に「これ書いたから」と参加者全員にこの本をプレゼントして下さいました。
第一印象は、この恐竜の画がかわいいし、白地に緑色の恐竜がすっきりしていて、いいデザインだなというものでした。やさしい感じがしますね。
中味は、雑誌に連載されていたものをまとめられたものですが、われわれ文系の人間にはない視線で、しかも身近なことに話題を拾って、さまざまな環境問題を取り上げていらっしゃいます。理科系らしいのは、いろいろな問題を例えば「これを石油消費量にすると一日○○リットル」と数値化して示されていることです。
恐竜は、食料を大量に消費する生き物だったため、大きな環境の変化による資源の減少に適応できずに絶滅した、人間はエネルギー消費という観点でみれば「現代の恐竜である」というメッセージなどは、数値化して始めて実感のわくものです。(数値が大きすぎて実感の湧かないひとも多いかもしれません)
その他にも、私たちが具体的に何をすれば環境問題に貢献できるかという視点からのもおもしろく読めました。また、ありがちな、「環境を改善するにはこうあらねばならない、しかるに。。。」といった一本調子の現代批判ではなく、「高速道路で前に車がのろのろ走っていると、本当は同じような速度でコンスタントに走ったほうが良いんだけど、どうしてもアクセルふかして追い越したくなっちゃうよね!」的な人間的な側面もそこここに出てくる、人間味あるれるエッセー集ともなっています。
愛知博で有名になった「Mottainai」(もったいない)のオリジナルはこの本では。。。ずいぶん以前に書かれた原稿に、もの「もったいない」を拡げようというメッセージが既に載っているのには驚きました。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
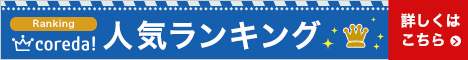
十人十魚 八重洲地下街
月に一回くらいでしょうか、ちょっと寿司をつまみたくなると行くのがここです。
かなり以前に紹介しました八重洲地下街にある「ばくだん」という広島つけ麺のお店の向かいにあります。
やや高級感のある回転寿司ですが、カウンターが比較的広く、お店もきれいなので、カウンターでひとりでふらっと行って生ビールを飲みながら5-6皿の寿司をつまみたいという時にはうれしいお店です。
ネタは新鮮で、季節のものがあります。今日は気仙沼(だったかな?)のさんまがあり、脂がのっておいしかったですよ。ただ、夜遅く行くと、いつまでも回転台にあるのは止めたほうが良いです。必ず板さんに指定して握ってもらうのが正解です。
値段も手頃です。ちょっとつまみたくなったら、お勧めです。店の数箇所にある魚の絵もなかなか好きです。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!
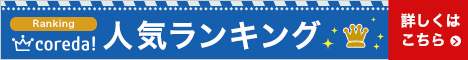
インターネット時代の英語術 鐸木 能光著

-

- 鐸木 能光, SCCライブラリーズ, 茅野 美ど里
- インターネット時代の英語術
まえがきには「★本書を読破しても、あなたは急に英語の達人にはなれません」とありますが、これは謙遜も謙遜、著者は相当な自身を持って、英語習得に関する立派な教科書を書いています。
これまでも、さまざま、英語に関する本を紹介してきましたが、その中でも実践的という意味では、1、2を争う良書です。
題名の「インターネット時代の。。。」に関する記述よりも、第2、3章辺りの著者の学習塾で英語を教えた手法を披露した部分が、極めて参考になります。ここだけ読みだけで、この本の価値は十分あります。
今日から実践したいような簡略化された、それでいてきわめてポイントをついた(「美味しんぼ的表現になったしまいました)習得の原則がまとめられています。いわく「「動詞の使い方」さえ分かれば英語力は今からでも向上する」「大人になって始める「英語の九九」。
おすすめです!!!英語学習者必読
この本について私の英語ブログ にもコメントしました。
この書評がお気に入りましたら、左のバナーをクリックして下さい。ランキング挑戦中!