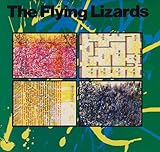ほとんど閉店状態のこのブログは、YMO(というかテクノそのもの)に正直飽きたという、投稿者の身も蓋もない心境によって殺されたといっていい。今だから白状するが――決して嘘をついていたわけではないにしても――当ブログが最も盛んに更新していた時分、私は今では考えられないほど幼い子供だった。私はインターネットの匿名性に身を包んで、精一杯の背伸びをしていた。
YMOを好きと称していたのは、「背伸び」のための作為的方便ではなく、実際本当に好きでたまらなかったからである。誰もが息を呑むような、YMOについての考察、評論をしたいと考えつつも、私の頭脳は天才どころかむしろ馬鹿の部類に入っていた。「これは良い」「これは良くない」という評価を下すだけでも、「本当に良い/良くないのか?」と疑わずにはいられず、いつ他者からの叱責が飛ぶか分からないと、始終自信がない怯える日々だった。もちろん子供特有の無邪気さもあって、ある程度までは平気で拙い文章を書けていたのだが。
年の経過は、あれほど馬鹿だった私の知識・能力を、緩慢ではあるが向上させ、それを私に実感させた。賢くなる度に思うのは、当ブログの馬鹿馬鹿しさであった。このブログは、年を経るごとに更新しにくいものになっていった。仮に素晴らしい記事を書けたとしても、読者は簡単に過去を溯って、私の幼い頃の記事を暴いてしまうだろう。私の見栄は、足手まといな過去を引き連れながらブログを更新することを許さなくなった。
――――
私はこんなブログ一刻も早く削除したいのですが、過去の自分を自分の手で葬るのは惜しい気もするので、諦めの気持ちを強く持って消さずに残しています。
成長とともに私は繊細さが割と抜けてきました。だからといってこのブログを更新する気は起きませんでした。書くことがなかったからです。ところが今は是非書かなければならないことを見つけているのです。
以前私は、「微妙なY.M.O.のベスト盤」という記事を書きました。日付を見ると2013年3月10日とありますので時の流れを感じます。
この記事で言いたいことは簡単で、「このCDはすべてにおいてしょうもない」です。特に私が拘泥したのは、ジャケットのデザインです。当時の私はこう云います。「このデザインは、まるで海賊盤がやるような代物で、作者の何某はCGを使用しておきながら、こんなものしか作れない」
この記事に対する当時の他者からの意見は皆無でした。無視同然に扱われたということです。私はそれを悲観するでもなく、いつしか記事を書いたことすら忘れていたのでした。
ところが私は、この記事に反応する者が現れていることを知ったのです。しかも、反応者とは、他ならぬ作者本人だった! 作者は、私のブログにコメントを直接寄せたのではなく、某SNSで当時を回想する形で、私の記事URLを引用していたのです。日付を見ると去年でした。私がデザインを酷評した2013年から、六年以上かけて本人のもとへ届いたのです。
私はこれが意外でしかたがなかったです。このCDが世に出たのは1993年です。1993年に、こんな訳の分からないデザインをした人が、今も生きている? ヒトラーが実は今も生存していると知ったら、誰だって驚くではありませんか。私にとって、このデザイナーとヒトラーは同じような立ち位置にいたのです。しかし考えてみれば、1993年は明らかに最近のことではないですか。これしきのことで驚いているようでは、YMOの三人を全員殺さなければならなくなるわけで、大変不本意です。1993年という時代にCGに着手しているということは、ある程度新しい感覚を持っていたということでして、つまり当時若者だったと推定するが自然でしょう。当時若かった人が2020年現在も生きている。何も不思議なことはありません。
以下、例の記事を書くまでの経緯を覚えている限りで書きます。
2013年3月、私は叔父の車に乗せられリサイクルショップに行ったのです。そこで見つけたのが、例のベスト盤CDだったのです。このCDの存在は2013年より前から知っていました。Amazonで売られているわけでもない、ジャケットの何とも言えないデザインを有するCDを画像で見て、子供心に異様なものを感じつつ、「本当にこんなものが実在するのか?」と不審でした。その謎のCDが店に売られているのです。二枚がビニールで包まれセット売りになっていました。バラ売りではなかったのです。値段は覚えていませんが千円以上はしたと思います。私は「何となく希少そうだ」という理由で買いました。愚かだと思います。今の私なら決してしないことです。当時YMOのアルバムはすべて所持していたのですから、こんなもの買うのは無駄なのです。
購入した正確な日は不明です。私の予想では、記事を投稿した2013年3月10日が購入日でした。しかしどうも違うようです。なぜそう言えるかというと、私は2013年以降に買ったCD・LPをすべてパソコンのメモ帳に記録しているからです(今はUSBにデータを移している)。メモ帳の3月10日の辺りを見ると、例のCDは記録されていませんでした。
さらに不思議なことに、私の記憶によると、リサイクルショップで買ったCDは、例のYMOの謎ベスト盤と、PSY・Sの『Mint Electric』の計三枚でした。ところが記録によると、私が『Mint Electric』を買ったのは4月6日となっています。私が例の記事を投稿したのは3月10日ですから、4月6日に買ったのでは辻褄が合いません。
2013年の購入履歴の一部
私は昔買ったCDをどこで買ったか、今も大抵覚えています。上の画像で私の記憶を想起してみましょう。
51~52枚目:タワーレコード新宿店
53~54枚目:モレラ(祖父に買ってもらった。こんなの老人に買わせるな)
55枚目:???
57枚目:ブックオフ(叔父に連れられて。一度しか訪れていないので店名失念)
58枚目:ヤフオク
59枚目:ブックオフ、オーキッドパーク店(叔父とともに。)
60~62枚目:バナナレコード四ツ谷店(今は閉店してます)
63枚目:Amazonマーケットプレイス
私の記憶はやはり大抵確かなのです。そうなると尚更、55枚目の『Mint Electric』が謎です。推理するとすれば、
1.メモ帳に誤った日付を記載した
2.YMOのベスト盤を買ったのは2012年以前
3.ブログの投稿日時を改変した
4.例のYMOをCDを、CD以下の何かと認識していた(メモする価値がない)
といったことが挙げられます。1は少しあり得る。2が一番有力。3も否定できないが、こんな記事のために改変する理由がわからない。4には完全同意ですが、これは今の私の心境が多分に込められているので、純粋だった当時の私とは別人です。
謎は迷宮入りになりそうです。仕方がないので、私の眉唾な記憶をお送りしましょう。
CDを購入した私は、叔父の車で祖父母の家に帰った。2013年当時の私は、CDをプリンターでスキャンすることに熱中していた。早速買ったCDもスキャンした。例の記事で掲載した画像は、私がこの手でスキャンしたものだった。
ここで思い出したのですが、スキャンしたデータが今もUSBに残っているのです。私にとって最初に使ったUSBでした。久しぶりにそのUSBを挿すと、果たして様々なアルバム・ジャケットをスキャンしたデータがありました。しかし、例のYMOのCDはおろか、『Mint Electric』もないのです。
謎は深まりますが、とにかくスキャンしました。
ちょうどその頃、当ブログでは、99%偽物のファースト・アルバム(US版)とか紛うことなき海賊盤とか、どうしようもない盤を記事にして取り上げていたのです。その流れにおいて、あのジャケットは恰好の材料だったのです。こんなデザイン、家のパソコンでも作ろうと思えば作れると。
要するに私は、「技術」というものに感謝が足りなかったのです。先人によるテクノロジーとの闘いがあったからこそ、私は「こんなの自分で作れる」と言えるのです。このデザインが作られたのは1993年です。二十年後の私が「自分でも作れる」と言ったところで、それはそうだろとしか言えないのです。
ジャケットをデザインされた方は私の記事を見て、SNSに投稿することになります。その方は私に怒っているわけではなく(内心どうか知らないですが)、優しく当時を回想していました。これが大人というものなのでしょう。私はまた一つ賢くなりました。
作者の何某様。軽率なことを申してしまい大変申し訳ございませんでした。何せ子供がやったことでございますから……。
しかし、このデザインは、やっぱりいかがなものかですよ。
その方の証言によりますと、あるレコード会社(アルファ・レコードではないらしい)が、「YMO」の三文字を乗せよと指定してきたそうです。馬鹿じゃないですか? 幼稚園に依頼して園児達に書かせ方が面白いものがいくつか出てくると思いますよ。作者が悪いのでは決してなくて、会社がお馬鹿さんだったのです。それから当時のCGの技術もおバカです。ついでにアルファもです。三馬鹿が揃ったではありませんか。
大体私は、『BGM』のジャケット・デザインだって変なものだと思いますよ。ファースト・アルバムの日本盤なんかもっと変じゃないですか。ウィンター・ライヴのステージだって、無理に褒めることないです。YMOというのは、つくづく変なデザインをされるために生まれたバンドだったですね。
さよなら