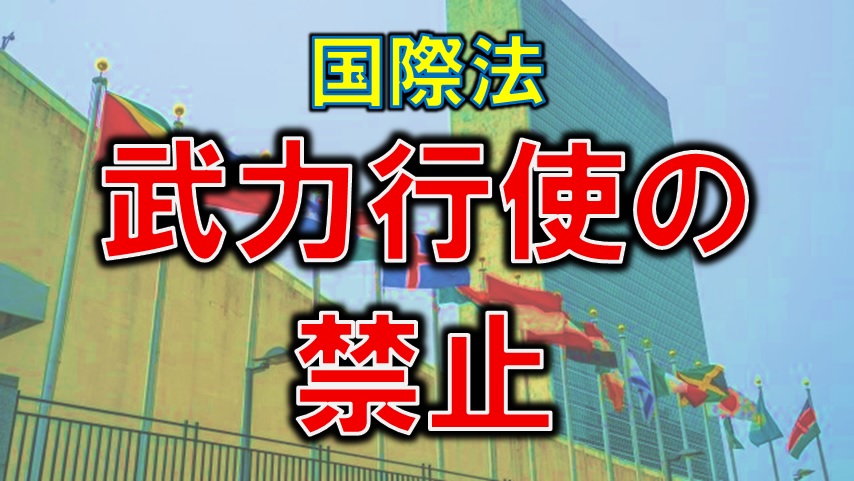国際社会を語る上で、避けて通れないのが「戦争」。
残念ながら、2023年現在も続くウクライナ侵略然り、国際社会に戦争はつきものです。
だからといってドンパチが許容されてる訳ではなく、
国際法はきちんと戦争を規制しようと努力してきました。
今回は国際法における武力紛争の規制をみていきましょう。
武力紛争規制の歴史
武力紛争規制の動きとして、まず始まったのが、「こういう戦争ならやってもいいですよ」と、戦争を正当化する根拠づけです。
17世紀、蘭国のグロチウスは、著書「戦争と平和の法」にて、
防衛、回復、処罰
が戦争の正当原因としました。
逆にいうと、これらの原因があれば戦争していいので、
戦争する権利を認める結果になります。
時は流れ、20世紀初頭辺りから、戦争する権利を手続き的に禁止する動きが始まりました。
例えば、債権回収に兵力の使用を制限した「ボーダー条約」、
紛争解決の為の調停委員会の報告があるまで開戦宣言や敵対行為をしないとする「ブライアン諸条約」を、米国が各国と締結しました。
第1次世界大戦後にできた国際連盟では、
国交断絶に至る虞のある紛争については、国際裁判手続又は理事会審査の結論の後、3ヶ月は戦争禁止とする「戦争モラトリアム制度」を設けました。
1928年には「不戦条約」が締結されました。
この不戦条約によって、初めて戦争が一般的•実体的に禁止されました。
然し、事実上の戦争、詰り開戦宣言を伴わない軍隊の移動が規制の対象外だったり、
違反者に対する制裁がなかったりと、
抜け穴の多い条約だった為、第2次世界大戦を防げませんでした。
第2次世界大戦後、国際連合は、国連憲章2条4項で「武力行使•武力による威嚇」を禁止しました。
事実上の戦争を防ぐ為、’戦争’ ではなく ‘武力’ という名詞を使ったんですね。
これは「武力行使禁止原則」といって、現在では国際慣習法とされています。
2022年の露国は、武力行使禁止原則に違反してる可能性が高いですね。
武力行使禁止原則には、国連憲章上の明確な例外があって、
1.自衛権に基づく武力行使
2.安保理の決定に基づく軍事的措置
であれば武力行使を容認しています。
2022年からのウクライナは、自衛権に基づく武力行使してるといえますね。
逆にいうと、自衛権、又は安保理の決定が、新しい正当原因といえますね。
これが国連憲章の武力行使についてですが、
自衛権以外にも許容される新しい武力行使の類型があるんじゃないか、という考えがあります。
人道的干渉
大規模な人権侵害をやめさせる為、他国が武力で介入します。
安保理の決定がない限りは違法行為とされます。
在外自国民救出活動
自国民の生命に重大な危険が迫り、他に有効な手段がない場合、最小限の実力を行使します。
民族解放戦争
植民地独立付与宣言等の総会決議によって人民自決権に基づく民族解放団体の武力行使が正当化されました。
第3国の武力支援が許されるかは争いがあります。
低強度紛争
準国家団体と国家の間のイデオロギー対立を含む紛争です。
主にテロ組織との戦いです。
米国は、テロとの戦いは一種の警察活動であり、武力行使禁止原則の例外になると主張しています。
軍縮
軍備水準を削減•廃止する措置です。
戦前は主に海軍、戦後は核兵器について、多くの条約や交渉がなされてきました。
核兵器に関する条約について、主なものを列挙します。
中距離核戦力(IMF)全廃条約
中距離核の全廃と、戦略核の弾頭数を1/3まで削減しました。
戦略兵器削減条約(START1)
核弾頭を6000発まで削減しました。
部分的核実験禁止条約
大気圏、宇宙、水中での核実験を禁止します。
地下は禁止されてません。
米、英、ソ連が入りましたが、仏、中国は未加盟です。
包括的核実験禁止条約(CTBT)
地下も含めて核実験を禁止します。
国連総会で採択されました。核保有国、事実上持ってるとされる国を含む44ヶ国の批准で発効します。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!