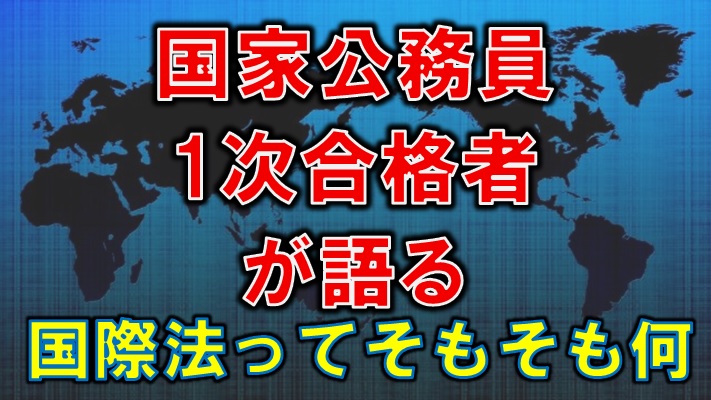うぷ主が公務員試験で勉強してきた内容を語るシリーズ。
突然で申し訳ございませんが、
今回から急に国際法を語ろうかと…
国際法が出題される試験種
各公務員試験に於て、国際法が出題されるのは以下職種です。
- 国家総合職
- 外務省専門職
- 国立国会図書館
国家総合職、所謂キャリア官僚ですが、
院卒者試験の行政区分、大卒程度試験の法律区分で出題されます。
いずれも
1次試験の択一で3問、2次試験の記述で1題が出題されます。
1次試験は選択科目なので、別に選ばなくてもいいですし、
うぷ主が受験した当時は、例えば「国際法3問中1問だけ解いて、後は別科目で解答」みたいな解答も許されました。
今はどうか知りませんが、
分る問題だけ摘食いできるのは有難いですよね。
外務省専門職では、
1次試験で択一、記述の両方やっちゃうんですが、
両方で国際法が必答です。
まあ、そうか!
国立国会図書館は、うぷ主はよく知らないんですが、
2次試験の専門択一及び専門記述で国際法が選択科目になってます。
国家総合職で専門記述の1科目として扱われてるので、それなりの科目ではありますが、
外務専門官を受けない限りは回避可能な科目でもあるので、
微妙な扱いですね。
国際法とは?
そもそも国際法とは何でしょうか?
ざっくりいえば
「国と国との決り事」
です。
名前的に「法律かな!?」と思うかもしれませんが、
法律ではありません。
法律というのは1つの国の中で適用される決りです。
米国に行ったら、日本の銃刀法は通じないでしょ!
なので法律とは別物です。
じゃあ、「法律じゃなかったら何なのか?」と聞かれると、
「独自の法形式」としかいい様がありません…
国際法の構成要素
国際法には幾つかの構成要素があります。
構成要素の事を、専門用語で「法源」といいます。
形式的法源
国際法の代表的な法源です。
条約と国際慣習法です。
条約
国と国との約束を文書にしたものです。
国際法の基本となるルールです。
幾つか種類はあって、
立法条約は、
世界や特定地域の共通規則を決めましょう的な目的で、沢山の国に入って貰いたい条約です。
契約条約は、
国同士の約束を決めた、正に契約の如き条約です。
解放条約は、
新規加盟国にどんどん入って貰いたい条約で、
閉鎖条約は、
2国間、もしくはそれに準ずる位の数の国だけで、ご新規さんを入れない条約です。
アイドルで例えれば、
AKBが解放条約、
タッキー&翼が閉鎖条約
といった風でしょうか。
立法条約と契約条約
解放条約と閉鎖条約
が対比関係にあります。
共通していえるのは、
条約に入ってない国は守らなくていい。
当り前ではありますが、
例えば「核兵器を廃絶しましょう」条約があったとして、
「俺そんな条約は知らん!」と言出す北朝鮮の如き国が、然し法的には問題なしという結論になってしまいます。
それがいいのか?
っていわれたら、なかなか深い問題ですよね。
国際慣習法
慣習国際法ともいいます。
呼び方はどっちでもいいので、
お好みでどうぞ!
名前の通り、慣習がそのまま法になっています。
礼節や道徳がそのまま法扱いになったのかというと、
そうでもありません。
一応、定義がありまして、
「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」
だそうです。
何書いてるかさっぱりですが、
国際慣習法の成立には
- 一般慣行
- 法的確信
の2つが必要とされています。
一般慣行
利害関係国を含む沢山の国が同様の行いを繰返し継続してやってる
のをさします。
最も古い国際慣習法に「公海自由の原則」がありますが、
海に面してない国が主張してもしょうがないでしょ。
続きはこちらで公開しています!!!
その他の記事はこちらから!!!