有望技術ランキング
AI以外も存在感、
脱炭素やエレクトロニクス関連の注目株に焦点
岡部 一詩
日経クロステック
野々村 泰香
AI・データラボ
有望技術ランキング AI以外も存在感、脱炭素やエレクトロニクス関連の注目株に焦点 | 日経クロステック(xTECH)
(当時は)大規模言語モデル(LLM)の性能がいま一つで、すぐ下火になった」――。日本総合研究所の近藤浩史先端技術ラボ次長兼エキスパートが、こう評する技術がある。現在、熱狂的な盛り上がりを見せる「AI(人工知能)エージェント」だ。
ChatGPTがもたらした生成AIブームに乗って、「AutoGPT」や「BabyAGI」といったAIエージェントが盛り上がったのは2023年のこと。ただ、長続きはしなかった。簡単なタスクしか解けなかったからだ。
それからわずか1年強。LLMの飛躍的な性能向上を受け、AIエージェントは生成AIの次なる進化形として、2024年後半には再びブームの中心に舞い戻った。こうした曲折は、技術の世界における目まぐるしさを物語っている。
AIエージェントは世間の注目だけでなく、実際に資金も引き付けている。日経クロステックとスタートアップデータベースを運用するZuvaは、技術セクターごとの成長期待を表す「テクノロジー未来投資指数」を開発。トップ50までをランキングにしたところ、AIエージェント キーワード解説 が1位だった。同指数の基となるスタートアップの資金調達データは2024年12月末時点のものだ。
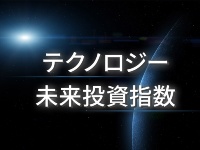
キーワード別解説一覧
テクノロジー未来投資指数
日経クロステックと、スタートアップデータベース(DB)を運用するZuvaは共同で、「テクノロジー未来投資指数」を開発した。Zuvaが保有する155万社を超えるスタートアップの資金調達動向を分析し、技…
トップ10は次の通り。テクノロジー未来投資指数は、「トレンド指数」と「成熟度指数」の2つを組み合わせて算出している。詳しくは前回の記事をご覧いただきたいが、トレンド指数は資金流入の伸びを、成熟度指数は各技術セクターの成長余地を示す。
「テクノロジー未来投資指数」のトップ10
(出所:日経クロステック、Zuva)
[画像のクリックで拡大表示]
将来有望な技術トップ50を独自指数でランキング、潜在力抜群の知られざる領域ずらり
日経クロステックと、スタートアップデータベース(DB)を運用するZuvaは共同で、「テクノロジー未来投資指数」を開発した。Zuvaが保有する155万社を超えるスタートアップの資金調達動向を分析し、技…
AI領域に当たるAIエージェントと「検索拡張生成(RAG)」 キーワード解説 は、資金流入が大きく伸びている一方、成熟に近づいている可能性がある。「スピントロニクス」 キーワード解説 や「デジタル嗅覚分析」 キーワード解説 は逆だ。資金流入の勢いは見劣りするものの、伸びしろは大きい。二酸化炭素(CO2)削減の領域では、「岩石風化促進」 キーワード解説 と「人工光合成」 キーワード解説 が共にトレンド指数と成熟度指数のバランスがいい。
ランクインした技術セクターの中には、知る人ぞ知るものも少なくない。トップ50のうち、注目しておきたい技術を幾つか紹介しよう。
業務の補助から代替へ
AIエージェントのキーワードは自律性だ。従来の生成AIはユーザーによる細かな指示を必要とした。これに対し、自身で計画を立てて実行していくのが典型的なAIエージェントの姿である。日本総研の渡邊大喜先端技術ラボエキスパートシニアリサーチャーは、2028年ごろには「個人がお気に入りのAIエージェントに仕事を頼むのが当たり前になっている可能性がある」との見方を示す。
日本総研によると、現在登場しているAIエージェントに関するサービスは大きく3つに分類できる。1つ目は、特定の業務やタスクに対応する「特化型」だ。情報収集を対象とした米Google(グーグル)や米OpenAI(オープンAI)の「Deep Research」、コーディングを支援する「Devin」などが代表格。米Salesforce(セールスフォース)のサービスで利用できるエージェント機能「Agentforce」も含まれる。
AIエージェントの類型
(出所:日本総合研究所の資料を基に日経クロステック作成)
[画像のクリックで拡大表示]
2つ目は、広範なタスクに対応できる「汎用型」。ブラウザー操作を自律的に実行できるオープンAIの「Operator」の他、中国の「Manus」も当てはまる。中国のITに詳しい匠新(ジャンシン)の齋藤慶太創新加速事業部マネージャー/アナリストは、Manusに関して「DeepSeekに続くダークホースとして大きな話題になっている」と語る。
3つ目は、AIエージェントを開発するためのツールやプラットフォームである。米Microsoft(マイクロソフト)の「Microsoft Copilot Studio」に加え、前述のAgentforceも機能を提供している。
AIエージェントが社会に浸透すると、どの程度のインパクトをもたらすのか。三菱総合研究所の高橋怜士生成AIラボ主席研究員は「生成AIの時代は業務の補助が主な役割だったが、エージェントに一定の権限を渡せば業務を代替できるようになる。普及したときの影響は大きい」と説明する。日本総研の渡邊シニアリサーチャーは「いずれ、ユーザーが最初に接するUI(ユーザーインターフェース)の多くがAIになる」と見通す


