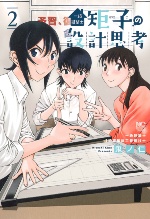完成前から光害の苦情噴出、“蛇腹壁”がもたらした複数の太陽
壁・屋根:光害
文:浅野 祐一 きらびやかな外観を持つガラス壁面のビル。目を引くデザインである半面、近くを通ると壁面に反射する光が目に突き刺さることがある。近年は住宅地でも屋根面に設置した太陽光発電パネルからの反射光が近隣トラブルに発展するケースも出てきている。本コラムでは「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)
のキャラクターを用いたイラストで記事の内容を解説する
[画像のクリックで拡大表示]
日経アーキテクチュアで過去に取材した建築トラブルなどを「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを使って新規に描き下ろしたイラストとともに振り返るコラム「一級建築士矩子と考える危ないデザイン」。今回取り上げるのは光害だ。
ここで扱うのは、夜間の照明などがもたらす光害ではない。建物の壁や屋根がもたらす日射の反射光害だ。ガラスや金属、明色の塗装などがトラブルを招きやすい。太陽の南中高度が高く、朝夕に太陽が北寄りを通り、日照時間が長い夏季は、思わぬ光害が顕在化しやすい傾向にある。
直接、体を傷付けるような事象には至らないものの、道路を通行する車両の運転者の目に強い光を当てれば、運転者の視界が奪われて交通事故などを招きかねない。2013年には警察庁科学警察研究所の研究者が、太陽のまぶしさは交通事故に大きな影響を与えていると結論付けた論文をまとめている。加えて、強い反射光が収れん火災の原因となった事例もこれまでに複数発生している。
ここではまず、日経アーキテクチュア10年2月8日号の特集記事で、筆者が紹介した以下の事例からひもといていく。
便利な反射が問題を招く場合も
「一級建築士矩子の設計思考」(鬼ノ仁/日本文芸社)のキャラクターを基に制作
[画像のクリックで拡大表示]
「太陽が2つ、3つあるようだ」「まぶしいうえに、顔が熱くなる」「パソコンの画面が見にくい」──。福岡市内に立つ天神グラスビルディング(以下、グラスビル)に対して、こうした苦情が沸き上がった。
天神グラスビルディングの南側を見たところ。2008年4月に撮影した。完成後のビルでは空室が目立った。09年11月25日時点で、1階にテナント募集のお知らせを貼り出していた(写真:日経アーキテクチュア)
[画像のクリックで拡大表示]
声を上げたのは、グラスビルの向かいに位置する天神パークビルと伊藤久ビルに入居する複数のテナントだ。建物の完成を控えた2008年初めの出来事だった。
地上9階建ての店舗を含む事務所として、グラスビルは建設された。同ビルに対する苦情の原因は、道路に面する南側に設けたガラスのファサードからの日射の反射にあった。
グラスビルの建て主は、イーストウィング。同建物を建てるために設立された特別目的会社だ。トラブル発生時は、アーバンコーポレイション(08年8月に民事再生手続きの開始を決定するも、その後清算)の子会社がアセットマネジメントを担っていた。基本設計を設計事務所のcdiが、実施設計と施工を東急建設が、それぞれ手掛けた。
名が示す通りガラス製のファサードが、グラスビルの最大の特徴だ。三角すいを上下に並べた蛇腹のような外観を持つ。表面のガラスは、水平面や鉛直面に対して複雑に傾く。cdiが設計を手掛けた東京都渋谷区内のジ・アイスバーグのような建物を求めたクライアント側の考えを踏まえた意匠だった。一様でないガラス配置がもたらす表層の“きらめき”感を狙っていた。
クライアント側が天神グラスビルディングを計画する際に、モデルとして考えたジ・アイスバーグ。東京都渋谷区内に立つ(写真:日経アーキテクチュア
完成前から光害の苦情噴出、“蛇腹壁”がもたらした複数の太陽 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)