誰かを助けた・誰かに助けられたことある?
▼本日限定!ブログスタンプ
令和4年度塩釜地区統一防火標語
『 消したはず 消したつもりが 火のこわさ 』 会社員 西條 淳さん
『 忘れない 「点けた」「使った」 火の始末 』 会社員 寺坂 純さん
過去の塩釜地区統一防火標語
| 昭和54年度 | 消した火を たしかめようね もう一度 |
|---|---|
| 昭和55年度 | あわてるな あせる心も 火事のもと |
| 昭和56年度 | 幸せを みんなでまもろう 火の用心 |
| 昭和57年度 | おでかけは ゆとりをもって 火の始末 |
| 昭和58年度 | 茶の間から 呼びかけあって 火の始末 |
| 昭和59年度 | 火のしまつ パパ見て ママ見て ぼくが見て |
| 昭和60年度 | ちょっとまて 火のもと点検 もう一度 |
| 昭和61年度 | ひろげよう 家族ぐるみの 防火の輪 |
| 昭和62年度 | まち守る 君とあなたの 火の用心 |
| 昭和63年度 | 火事出さぬ 家から町から 明るい笑顔 |
| 平成元年度 | 火の元を しっかり守って 明るいわが家 |
| 平成2年度 | 火の用心 一人で見るより みんなの目 |
| 平成3年度 | なれた火も こまめに点検 あとしまつ |
| 平成4年度 | 家族の目 みんな集めて 火の用心 |
| 平成5年度 | 指差しで 火の元確認 良い家庭 |
| 平成6年度 | 火の始末 一人の目より 家族の目 |
| 平成7年度 | よい町は みんなで協力 火の始末 |
| 平成8年度 | 防火の輪 広げて住みよい 家と街 |
| 平成9年度 | 火の用心 みんなで声かけ 火のしまつ |
| 平成10年度 | みんなの輪 声かけあって 火の用心 |
| 平成11年度 | 火の用心 わが家の防火は 茶の間から |
| 平成12年度 | 消すまでは 責任持ちます わたしの火 |
| 平成13年度 | 子育ての 中に入れよう 火のしつけ |
| 新世紀 心に誓う 火の用心 | |
| 平成14年度 | まかせない 家族みんなで 火の用心 |
| 平成15年度 | いちど消し にど見て さんど火の用心 |
| 平成16年度 | 消したはず 気持ちで消すより 目でかくにん |
| 平成17年度 | 消したかな 急ぐ時ほど もう一度 |
| 平成18年度 | 火の用心 一人一人が 消防士 |
| 平成19年度 | 火の用心 急ぐ時ほど もう一度 |
| 平成20年度 | 火あそびは やっちゃいけない やらせない |
| 平成21年度 | 火のしまつ 家族みんなで 心がけ |
| 平成22年度 | 火災ゼロ! 職場のみんなの マニフェスト |
| 平成23年度 | 住警器 しっかり備えて 安心家族 |
| 平成24年度 | ぼくたちが めざす未来は 火災ゼロ |
| 平成25年度 | 火災ゼロ 絆で守る おらが街 |
| 平成26年度 | しあわせと 未来を守る 防火の輪 |
| 平成27年度 |
火の始末 あなたが消火の 責任者 |
| 平成28年度 |
消しましょう 油断という名の 心の火 |
| 平成29年度 |
伝え行く 防火の心 家庭から |
|
平成30年度 |
怠らない 命のために 日々(火々)確認 |
|
平成31年度 |
火は消した? 私も確認 お手伝い |
|
令和2年度 |
火の元よし! 家族みんなが 消防士 |
|
令和3年度 |
消したかな 家族で確認 ヨシ!よし!良し! |
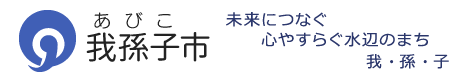
『お出かけは マスク戸締り 火の用心』
| 回数 | 年度 | 標語 |
|---|---|---|
| 第57回 | 2022年度 | お出かけは マスク戸締り 火の用心 |
| 第56回 | 2021年度 | おうち時間 家族で点検 火の始末 |
| 第55回 | 2020年度 | その火事を 防ぐあなたに 金メダル |
| 第54回 | 2019年度 | ひとつずつ いいね!で確認 火の用心 |
| 第53回 | 2018年度 |
忘れてない? サイフにスマホに 火の確認 |
| 第52回 | 2017年度 |
火の用心 ことばを形に 習慣に |
| 第51回 | 2016年度 |
消しましょう その火その時 その場所で |
|
第50回 |
2015年度 |
無防備な 心に火災が かくれんぼ |
| 第49回 | 2014年度 | もういいかい 火を消すまでは まあだだよ |
| 第48回 | 2013年度 | 消すまでは 心の警報 ONのまま |
| 第47回 | 2012年度 | 消すまでは 出ない行かない 離れない |
| 第46回 | 2011年度 | 消したはず 決めつけないで もう一度 |
| 第45回 | 2010年度 | 「消したかな」 あなたを守る 合言葉 |
| 第44回 | 2009年度 | 消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子 |
| 第43回 | 2008年度 | 火のしまつ 君がしなくて 誰がする |
| 第42回 | 2007年度 | 火は見てる あなたが離れる その時を |
| 第41回 | 2006年度 | 消さないで あなたの心の 注意の火 |
| 第40回 | 2005年度 | あなたです 火のあるくらしの 見はり役 |
| 第39回 | 2004年度 | 火は消した? いつも心に きいてみて |
| 第38回 | 2003年度 | その油断 火から炎へ 災いへ |
| 第37回 | 2002年度 | 消す心 置いてください 火のそばに |
| 第36回 | 2001年度 | たしかめて。 火を消してから 次のこと |
| 第35回 | 2000年度 | 火をつけた あなたの責任 最後まで |
| 第34回 | 1999年度 | あぶないよ ひとりぼっちにした その火 |
| 第33回 | 1998年度 | 気をつけて はじめはすべて 小さな火 |
| 第32回 | 1997年度 | つけた火は ちゃんと消すまで あなたの火 |
| 第31回 | 1996年度 | 便利さに 慣れて忘れる 火のこわさ |
| 第30回 | 1995年度 | 災害に 備えて日頃の 火の用心 |
| 第29回 | 1994年度 | 安心の 暮らしの中心 火の用 |
| 第28回 | 1993年度 | 防火の輪 つなげて広げて なくす火事 |
| 第27回 | 1992年度 | 点検を 重ねて築く “火災ゼロ” |
| 第26回 | 1991年度 | 毎日が 火の元警報 発令中 |
| 第25回 | 1990年度 | まず消そう 火への鈍感 無関心 |
| 第24回 | 1989年度 | おとなりに あげる安心 火の始末 |
| 第23回 | 1988年度 | その火 その時 すぐ始末! |
| 第22回 | 1987年度 | 消えたかな! 気になるあの火 もう一度 |
| 第21回 | 1986年度 | 防火の大役 あなたが主役 |
| 第20回 | 1985年度 | 怖いのは 「消したつもり」と「消えたはず」 |
| 第19回 | 1984年度 | “あとで”より “いま”が大切 火の始末 |
| 第18回 | 1983年度 | 点検は防火のはじまりしめくくり |
| 第17回 | 1982年度 | 火の用心 心で用心 目で用心 |
| 第16回 | 1981年度 | 毎日が防火デーです ぼくの家 |
| 第15回 | 1980年度 | あなたです! 火事を出すのも防ぐのも |
| 第14回 | 1979年度 | これくらいと思う油断を火が狙う |
| 第13回 | 1978年度 | それぞれの持場で生かせ火の用心 |
| 第12回 | 1977年度 | 使う火を消すまで離すな目と心 |
| 第11回 | 1976年度 | 火災は人災 防ぐはあなた |
| 第10回 | 1975年度 | 幸せを明日につなぐ火の始末 |
| 第9回 | 1974年度 | 生活の一部にしよう火の点検 |
| 第8回 | 1973年度 | 隣にも声かけあってよい防火 |
| 第7回 | 1972年度 | 慣れた火に 新たな注意 |
| 第6回 | 1971年度 | いま燃えようとしている火がある |
| 第5回 | 1970年度 | あぶない!消し忘れ、切り忘れ |
| 第4回 | 1969年度 | 今捨てたタバコの温度が700度 |
| 第3回 | 1968年度 | あなたは火事の恐ろしさを知らない |
| 第2回 | 1967年度 | さあねようアッそのまえに火の点けん |
| 第1回 | 1966年度 | 火の始末人にたのむな任せるな |
良い句とは?
うまい俳句の定義や基準・特徴

五・七・五のリズム感がある
俳句は【五・七・五】の文字のつらなりが生み出す歯切れの良いリズム感が命です。
柿くへば(5) 鐘が鳴るなり(7)法隆寺(5) by 正岡子規
このリズムによって力強さが生まれ、句の情景がありありと目に浮かんできます。
俳句を作ったら、まずは声に出してリズム感があるかどうかを確認してみましょう。
季語のチョイス
季語とは、多くの人がいかにもその季節らしいと感じるような言葉のことを言います。
例えば、春なら桜やひな祭り、夏なら海水浴やかき氷といった季語があります。
俳句には原則的には季語を1つ入れる必要がありますが、その言葉のチョイスは大切です。
良い俳句にするためには、「季語はこれで良いのか」「別の物に置き換えた方が良いのか」という点を今一度確認しましょう。
季語はあまり聞き馴染みの無い言葉まで含めると膨大な数があります。
そのため、1度「歳時記(さいじき)」という書籍を使って、季語はどのようなものがあるのかというのを勉強することをおすすめします。

リス先生
中には無季語俳句や2つの季語を含んだ作品も存在するけど、まずは季語は1つというのを基本に俳句を作ってみると良いよ!
オリジナリティがある
ご自身が作成した俳句が、過去に発表された俳句に似ていたり、ありきたりな表現を使った場合には良い俳句とは言えません。
例えば、季語1つとっても春の季語で「桜」を使うのはちょっとオリジナリティに欠けるかもしれません。
ありきたりな俳句の例 (季語 運動会)
運動会 全力応援 声からす
オリジナリティのある俳句の例 (季語 爽やか)
爽やかに 早まる鼓動 待つバトン

リス先生
「プレバト!!」でも「ありきたりな表現」や「誰でも思い付く」と先生にズバッと言われて、凡人や才能無しの評価を受けている方をよく見かけるね!
失敗しないためにも押さえておきたい!悪い俳句の特徴

無駄な説明が多い俳句は悪い俳句の特徴です。
無駄な説明が多い俳句の例
コスモスが 風に揺れるよ こころもち(風に揺れるは不要な説明)
俳句は五・七・五の17音しかないため、1文字も無駄にしてはいけません。そのため、まずは「で、ば、が、に、は」といった助詞は使わないようにしましょう。
また、個人的感情や感想の表現も不要です。この句に対してどう思うかは読み手の解釈に任せましょう。
無駄な説明がない俳句の例
コスモスや 医者に行きたい こころもち
また、意味が重複するような言葉もギリギリまで削るのがおすすめです。読み手の想像力で補うことが可能な語は排除しましょう。
そして基本的なことですが、初心者の方は季語は1つ、動詞は1つ、句切れは1つで俳句を作ってみましょう。

リス先生
一応季語が2つだったり、句切れが2箇所だったりするような技法もあるけど、初心者には難易度が高いから、あまりおすすめしないよ!
良い俳句の作り方・コツ・注意点

字面で全てを表現しすぎない
俳句は作者の思いなどを何でも直接的に述べてしまうと、標語のような出来上がりとなってしまいます。
そもそも五・七・五の17音で全てを説明することは不可能なため、読み手がいろいろと想像を膨らませることが出来る作品が良い俳句と言えます。
中間切れを用いてみる
中間切れとは、五・七・五の七音の途中で句切れさせる手法のことを言います。
万緑の 中や/吾子の歯 生え初むる(吾子の歯の前で一旦切れている)
上記の句のように途中で句切れさせることによって、読み手にその単語を鮮烈に印象付けることが出来ます。
主語は必ずしも必要ではない
俳句を作る際、主語は必ずしも入れる必要はありません。
俳句というのは、読み手の解釈に任せて自由に楽しんでもらうという部分も大切です。

リス先生
「誰が」という主語はあっても無くても問題ないよ!
知っておきたい!!おすすめ有名俳句集【5選】

【NO.1】松尾芭蕉
『 古池や 蛙飛び込む 水の音 』
淀んだ水である古池は静まりかえっているけれど、一瞬ポチャンと蛙が飛び込む音がして、その後は再び静寂である様子を描いた作品。
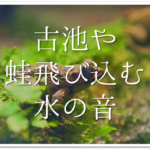
【古池や蛙飛び込む水の音】俳句の季語や意味・魅力(すごさ)・表現技法・作者など徹底解説!!
2019.12.5
日本には多くの有名な俳人がおり、これまでにたくさんの俳句が残されてきました。 そして、現代になっても身近なテーマを中心に数多くの俳句が詠まれています。 今回はそんな数ある名句の中からという松尾芭蕉の句をご紹介します。 野間記念館の裏の胸突坂を神田川の方へ下ったところにある関口芭蕉庵。神田上水...

俳句仙人
蛙が池に飛び込むという単純な情景ではありますが、蛙を季語に用いると、普通の人だと「ケロケロ」という鳴き声に着目すると思います。しかしこの作品は、蛙の動きに着目している点が妙味です。
【NO.2】小林一茶
『 雪とけて 村いっぱいの 子どもかな 』
やっと春になって村の子どもたちが元気よくはしゃいでいる様子を描いた作品。
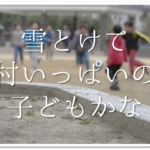
【雪とけて村いっぱいの子どもかな】俳句の季語や意味・作者「小林一茶」など徹底解説!!
2019.12.12
「江戸の三代俳人」として活躍した「小林一茶」。 彼の作る俳句は、子供やかえる・すずめなど小さな生き物を句材にしたものが多く、親しみやすい句風は「一茶調」と呼ばれました。 一茶が生涯で残した数は約2万句にものぼるといわれていますが、その中からという句について紹介したいと思います。 雪とけて村い...

俳句仙人
これは江戸時代に書かれた俳句ですが、当時は冬を越すのに相当な苦労を強いられたのだろうということが、この句からはわかります。それに、「春になって嬉しい!」という子どもたちの表情が容易に想像出来るという点も素晴らしいです。
【NO.3】中村草田男
『 万緑の中や 吾子の歯 生え初むる 』
夏の見渡す限り青々とした草原の中でも、我が子の生え始めた真っ白な乳歯の鮮やかさが際立っている様子を描いた作品。
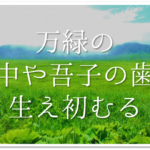
【万緑の中や吾子の歯生え初むる】俳句の季語や意味・表現技法・鑑賞文・作者など徹底解説!!
2019.12.4
五・七・五の十七音で四季の美しさや心情を詠みあげる「俳句」。 中学校や高校の国語の授業でも取り上げられ、なじみのある句も多くあることでしょう。 今回はそんな数ある俳句の中でもという中村草田男の句に注目します。 万緑の 中や吾子の歯 生え初むる(中村草田男) #俳句 pic.twitter.c...

俳句仙人
大胆な中間切れ(七音の途中で句切れをさせる技法)が使われていて、我が子の歯=笑顔は大いなる希望であり、輝きに満ちている様子がまざまざと伝わってきました。
【NO.4】堀内稔典
『 三月の 甘納豆の うふふふふ 』
甘納豆を頬張って思わず「うふふふふ」という笑みがこぼれている日常の風景。
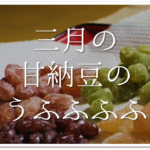
【三月の甘納豆のうふふふふ】俳句の季語や意味・表現技法・鑑賞・作者など徹底解説!!
2020.1.8
俳句は難解で高尚な趣味…と敬遠されがちですが、実はとても身近で、誰もが簡単に始めることのできる文芸です。 俳句は、日常の情景や事柄、人々の感情と連動していますので、身の回りのことは全て俳句に詠むことができるといっても過言ではありません。 今回は、現代俳句の第一人者として有名な坪内稔典の作、...

俳句仙人
「うふふふふ」の部分が強烈に印象に残ります。この句には主語が無いので、笑っているのは子どもなのか、若者なのか、お年寄りなのかなんていう想像を巡らせてみるのも楽しいです。
【NO.5】小林一茶
『 ふるさとや 寄るもさはるも ばらの花 』
故郷へ遥々やってきてみると、家族だけではなく、村人までもが、薔薇の花の棘のように私の心を痛めつけるという意味の作品。

俳句仙人
薔薇の花から棘を連想させ、そこから私の心を痛めつけるというメッセージが込められているというところがまさに達人技です。
以上、上手い俳句の作り方でした!
今回は、うまい俳句を作るためにはどんなところに気を付ければ良いのかという点についてご紹介しました。
俳句はたくさん読んでたくさん作れば、どんどん上達していくのでとても面白いです
