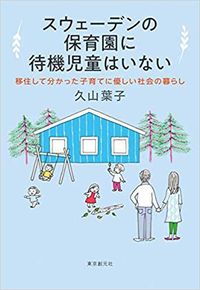なぜ日本は「専業主婦社会」を抜け出せないか
1/22(水) 6:15配信
仕事と家庭の両立を望む女性が増える一方で、専業主婦を希望する、あるいはそうせざるを得ないという人も少なくありません。日本は本当に「共働き社会」になっているのか──。家族のあり方を研究する筒井淳也先生に聞きました。
■週1時間のパート勤務でも共働き
今、夫も妻も働く「共働き世帯」が増えていると言われています。しばしば目にする共働き世帯と専業主婦世帯の推移を表す統計だと、共働き世帯は専業主婦世帯の約2倍にものぼっており、数値だけ見れば、多くの人は「専業主婦は減っているんだな」と思うことでしょう。
しかし、この種の統計には意外な裏があります。それは、夫婦ともに少しでも雇用の収入があれば「共働き」にカウントされてしまうことです。妻がパートで週1時間だけ働いていても、フルタイムで男性と同じように働いていても、同じ「共働き世帯」として計算されているのです。
これを、妻が25~34歳で子どものいる核家族に絞ってみると、夫がフルタイムで働いている世帯のうち、妻もフルタイムで働いているのはたったの17.9%です。これに対して専業主婦世帯はその2倍以上、38.3%です(2018年の労働力調査による)。出産・子育て期の家庭の多くでは、妻が仕事より主婦業に時間をかける、または主婦業に専念する生活を送っているのです。
■日本はまだまだ専業主婦社会
その意味では、日本は決して共働き社会ではなく、まだまだ専業主婦社会だと言えるでしょう。そもそも日本の企業は、主婦業に専念する人が家にいないと働きづらい仕組みになっています。
長時間労働も転勤も珍しくない──そんな状況に対応するためには、夫婦のどちらかが家事育児に専念し、かつ転勤にも対応できる状態でいなければなりません。これが「家庭か仕事か」という苦しい二者択一を生み出しています。
■「一段落してから再就職」が一番人気
ただ、今は多くの企業がこうした仕組みを変えていこうとしています。実際、結婚や出産で退職する女性は減っており、未婚女性を対象とした「理想とするライフコースの調査」(国立社会保障・人口問題研究所「結婚と出産に関する全国調査」)でも、仕事と家庭の「両立コース」(産休・育休後に復帰するライフコース)を希望する人が増えつつあり、32.3%を占めます(図表1)。
しかし最も人気が高いのは、一度退職して子育てが一段落してから再就職する「再就職コース」(34.6%)であり、結婚や出産を機に退職して家庭に入る「専業主婦コース」を選ぶ人(18.2%)も減ってはいません。
一方、理想ではなく「予定」のライフコースはどうでしょうか。こちらは両立コースと再就職コースがそれぞれ28.2%、31.9%となり、専業主婦コースは年々減少し2015年は7.5%にすぎません(図表2)。この中には「本当は専業主婦になりたいが、夫の収入だけでは食べていけないだろう」と、現実的な考えを持つ女性も多数含まれているように思います。
両立を目指す女性が増える一方で、専業主婦志向の女性が減らないのはなぜなのでしょうか。一時は「専業主婦=勝ち組」という風潮もありましたが、それは夫が高収入の場合のみ。サラリーマンの給与が下がり続けている現状では、優雅な主婦ライフを満喫できる人はほんの一握りにすぎません。
■大黒柱の座を降りたい男たち
専業主婦志望の女性も、そうした現実はよくわかっているはずです。結局は日本全体に、男性に“一家の大黒柱”を求める雰囲気が根強く残っているためなのかもしれません。この風潮は、男性の幸福度にも影響している可能性があります。
幸福度の男女格差は、先進国の中で日本が一番大きく、女性が高く男性が低い状態にあります。原因については、私もこれから究明したいと思っていますが、今のところ、稼がなければならないというプレッシャーや、家庭内での孤立感が影響しているのではないかと考えています。
では、男性は妻にどんなライフコースを望んでいるのでしょうか。現在、彼らが望んでいるのは圧倒的に「再就職コース」と「両立コース」で、「専業主婦コース」は激減し2015年は10.1%です(図表3)。ここからは、自分だけで家族を養うのは大変だとわかっていて、大黒柱の座を降りたがっている様子がうかがえます。これも現実的な考え方と言えますが、問題は妻に家事も求めていることです。
男性も、家事をする気がまったくないわけではありません。実際、結婚前や直後には「共働きだから分担しなくては」と思っている人もたくさんいます。しかし、時がたつうちにやらなくなってしまうことがほとんど。この場合、仕事の忙しさを言い訳にすることが多いようです
働く女性は、もっとキレていい
働く女性には、一人で家事育児を背負ってしまう人も少なくありませんが、私には我慢しすぎているように思えます。正直、もっとキレていいとさえ思っています(笑)。出産後の働きにくさや両立の大変さについて、男性はまだ女性ほど理解できていないのです。
前出の調査結果からは、結婚せずに働き続ける「非婚就業コース」を予定ライフコースとして回答する女性が増え、21.6%に達していることもわかっています。自分が専業主婦でいられるほど稼ぎがある男性は少ない、でも共働きは大変だから結婚せずに仕事だけに絞る──。そう考える女性が増えるのは自然な流れかもしれません。
■再就職可能な社会へ
前述の「理想のライフコース」を見ると、「一度離職しても再就職できる社会」であればよりよい、ということになります。これは、欧米のように各自のスキルが明確な社会なら実現可能ですが、日本の企業では配置転換が多いこともあって、スキルの蓄積がなされにくいのです。ですから、いざ転職というときに「履歴書に書けるようなスキルがない」と悩む人も少なくありません。
採用でも、欧米では初めから特定の職種を募集するのに対し、日本ではまっさらな新卒を一から訓練し、さまざまな職種を経験させていくのが主流になっています。これでは、専門的なスキルはなかなか身につきません。
自分のスキルがわからなければ、それを生かして再就職しようという発想も出にくくなるもの。職場において一定のスキルを磨いていける社会なら、転職も再就職もぐんとしやすくなります。出産や育児でいったん家庭に入っても、ひと段落したらまた働き始めることが可能です。
今後の日本には「働く女性」が欠かせません。それは国の経済だけでなく、家計においても同じです。そのためには、夫だけの力で年収800万円を目指す働き方より、夫婦それぞれの年収400万であっても、互いに仕事と家庭を両立しながら働ける環境づくりを目指す必要があるでしょう。
猛烈に働く夫と専業主婦の妻、共働きのDINKS、仕事を続けるために未婚を選択する──。どんな生き方を選ぶかはもちろん個人の自由ですが、どんなライフコースでもあまり悩むことなく選べるようになったほうがいいと思います。それが“誰もが働き続けられる社会”の理想のあり方ではないでしょうか。
----------
筒井 淳也(つつい・じゅんや)
立命館大学教授
1970年福岡県生まれ。93年一橋大学社会学部卒業、99年同大学大学院社会学研究科博士後期課程単位取得満期退学。主な研究分野は家族社会学、ワーク・ライフ・バランス、計量社会学など。著書に『結婚と家族のこれから 共働き社会の限界』(光文社新書)『仕事と家族 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか』(中公新書)などがある。
----------
立命館大学教授 筒井 淳也 構成=辻村 洋子 写真=iStock.com
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200122-00032375-president-bus_all&p=2
===========================================================================
なぜスウェーデンでは専業主婦=失業者なのか
「もっと家族と過ごしたい。もっと心に余裕ある生活がしたい」。そんなパートナーの強い希望で、スウェーデンへ家族3人で移住したのはエッセイ『スウェーデンの保育園に待機児童はいない』の著者・久山葉子さん。日本で共働きをしていたころは「仕事も育児も中途半端」という思いから自己嫌悪に陥る毎日をおくっていたという彼女が、「親になっても、自分のやりたい仕事を週に四十時間やる権利がある」と断言できるように変わった、共働き子育て家族に優しいスウェーデンでの暮らしとは? 移住してすぐの頃から仕事が軌道にのるまでの様子を一部抜粋し、スウェーデンの“共働き文化”の一端に触れます。
※本稿は著者・久山葉子『スウェーデンの保育園に待機児童はいない 移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし』(東京創元社)の一部を再編集したものです。
スウェーデンに移住…“専業主婦”という概念が存在しない
カルチャーショックと育児ノイローゼとホームシックに交互に見舞われ続けた移住当初の三ヶ月。真冬で暗いせいもあり、気分はどん底まで落ち込んだ。それにさらに拍車をかけたのが、「スウェーデンで仕事が見つかるのだろうか」という不安だった。
そもそも“共働きに優しい社会だから”という理由で生活の拠点をスウェーデンに移したのだ。確かに夫は毎日五時ぴったりに会社を出て、その十五分後には家に帰ってきている。東京にいたころとは比べ物にならないほど家族で過ごす時間が増えたし、余裕も生まれた。本当にありがたいことだ。しかしわたしの仕事が見つからなければ、肝心の“共働き”にはならない。
日本にいれば、「引っ越したばかりだし、子供も小さいし、しばらくは専業主婦でもいいか」と思えたかもしれない。しかしここは昼間子供を遊ばせる場所が少なすぎるし、昼間に集えるような専業主婦の友達もいない。わたしがこの街の出身だったとしても友達はみんな昼間働いているだろう。
それに加えて、なんだか肩身が狭いのだ。そもそも専業主婦という概念からして存在せず、仕事をしていない人は性別や子供の有無に関係なく、“失業者”という肩書きになってしまう。税金を払ってなんぼのこの社会では、税金を払わずに社会保障制度を利用しているというだけで申し訳ない気持ちになるのだ
専業主婦イコール失業者という肩書きに
最初にそのことを思い知らされたのは、保育園に申し込むための用紙だった。両親の職業を書く欄があった。書き方の詳細がよくわからず、わたしは市役所に電話して教えてもらった。担当者は不慣れなわたしに親切に教えてくれた。
「お子さんのパパのほうは“株式会社○○の正社員”と書けばいいですよ。そしてあなたは失業者だから……」
“専業主婦”と書くという選択肢はなかった。世間から見れば、わたしは失業者以外の何者でもないのだ。社会のお荷物ということか。やるせなさが胸にあふれた。
それとときを同じくして、夫の職場に寄ったときのことだ。男ばかりの夫のオフィスには、紅一点の総務担当の女性がいた。
彼女がわたしの顔を見るなり、「どう? 仕事見つかった?」と訊いたのだ。「……見つかってません」と答えなければいけなかったときの屈辱感。またしても自分が失業者であることを実感させられた。しかし、二歳にもならない子供を抱えて異国に越してきてまだ二週間の女性に、「仕事見つかった?」って訊くのって、あまりに酷なのではとも思う。いや、そう思うのは日本人だからか。この国ではどんなに小さい子供がいようとも、女性も働いていて当然なのだから。
「失業中の人こそ就職活動が大切」だから保育園に預けられる社会
保育園の申し込みは、移住してすぐにやった。夫の上司に「申し込んでから入れるまでたいてい三ヶ月かかるから、一日でも早く申し込んだほうがいい」とアドバイスされたからだ。本来は個人識別番号がないと申し込めないが、移住直後で取得中だからわかり次第連絡しますと注釈をつけて申し込んだ。
スウェーデンでは申し込みから四ヶ月以内に保育園に入れることが保証されている。つまり自治体には四ヶ月以内にその子のために保育園を確保する義務があるのだ。つまり待機児童は存在しない。自治体は子供の出生人数を把握し、必要な場合は新しい保育園を建てる。特にスンツヴァル市は人口が増加傾向にあるから、常にどこかで保育園の建設計画が進んでいる。日本でも、小学校・中学校については「空きがないから入れません」なんてことはありえない。スウェーデンではそれが保育園から保証されているのだ。
わたしの場合、仕事も決まっていないのに保育園に申し込んでいいのかと不安だったが、それは杞憂に終わった。ありがたいことに、失業中でも週に十五時間まで保育園に通わせることができる。むしろ失業中の人こそ、就職活動の時間を確保するのが大切だという考え方なのだ。確かに小さい子供が常にそばにいる毎日は慌ただしく、わたしも気ばかり焦りながら、就職活動はちっとも進んでいなかった。
一月半ばに保育園に申し込んで、二月頭にはもう保育園決定の通知が届いた。ちょうど四月にオープンする新しい保育園があり、そこに入れることになったのだ
「夫が働いている」の説得力はゼロ
保育園が決定すると本格的に仕事を探しはじめた。どの会社も律儀に返事はくれたものの、「今は日本市場には力を入れてないから」という返事ばかりだった。
久山葉子『スウェーデンの保育園に待機児童はいない 移住して分かった子育てに優しい社会の暮らし』(東京創元社)
この街の企業に採用されるという幻想を捨てたとき、残された選択肢は自分で起業することくらいだった。確かに、スウェーデンに暮らしている日本人の先輩方で、フリーランスの通訳やコーディネーターとして活躍されている方は何人か知っており、わたしもそういう働き方をしてみたいという憧れはあった。
そう思いはじめたころ、東京の元職場の紹介で、日本の展示会に出展するスウェーデンの団体からパンフレットの翻訳を依頼された。
報酬の支払いにさいして、スウェーデンのクライアントから確認があった。
「あなたが個人なら源泉徴収をするし、会社なら源泉徴収はせずにあなたの会社番号を税務署に連絡するから教えて」
こういう小さな仕事はときどき舞いこむのかもしれない。それならここで一気に会社登録をしてしまおう。そう思いつき、すぐに会社登録を行った。日本で言うところの、個人事業主というやつだ。
会社登録自体はオンラインでできるのだが、税務関係の登録用紙の書き方がよくわからなかったので、税務署に出向いて教えてもらった。そのとき、税務署の人にとても驚かれた。
「今無職ということですが、失業手当ももらってないんですよね? どうやって生活しているの?」
「いや、夫が働いていて、わたしは家に二歳児もいますし……」
日本だとそれはごく普通の回答だと思う。でもこちらの税務署のお姉さんは、それではまったく納得がいかないようだった。夫が働いている、という答えにはなんの説得力もないみたいだ。やはりこちらでは男女関係なく経済的に自立しているのが当たり前なのだなとつくづく思わされた。
仕方なく「日本で働いていたころの貯金を切り崩してもいます」と説明すると、やっと納得してもらうことができた。そして、こう言われた。
「じゃあこの申請用紙の余白にそう書いておいてください。じゃないとみんなが『この人、どうやって生きてるんだろう』って不思議に思うから」
さっさと仕事を軌道に乗せて一人前に稼がないと、この社会では理解不能な存在になってしまうということか――。無事に会社登録はすんだものの、そんなプレッシャーがのしかかってきた。
十五時間保育で作業時間を確保
求職中――つまり失業者でも週に十五時間保育園に預けられるというのは、本当にありがたい。日本でも就職活動中に保育園に申し込む権利はあるが、待機児童の多い中、なかなか入れてもらえないのが現状だろう。就職活動中から預けられるというのは、非常によいシステムだと思う。
いざ仕事が決まったときに、同時に子供が保育園にフルタイムで入園するとなると、親子ともにかなりの負担になるが、就職活動中から預けていれば、慣れ親しんだ保育園に通う時間が長くなるだけですむのだ。
学校庁のホームページにはこのように規定されている。
失業中および育児休業中の親を持つ子供も、一歳になった時点で、一日最低三時間もしくは週に十五時間通う権利がある。
この十五時間保育のおかげで、わたしはやっとやりたかった作業に手をつけることができた。フリーランスとして仕事を受けるための個人事業主登録や、そのための税金の手続きなどだ。
娘のいない静かな自宅でパソコンを開く。窓辺に並んだ植木鉢は、春の日差しをいっぱいに受けている。スポティファイ(スウェーデン発祥のデジタル音楽配信サービス)で昔好きだったスウェーデンのアーティストを探しては、それをBGMに作業を進めた。わたしの生活にも、ようやく落ち着きが訪れようとしていた。
写真=iStock.com
久山 葉子(くやま・ようこ)
翻訳家
1975年生まれ。神戸女学院大学文学部卒。交換留学生としてスウェーデンで学ぶ。大学卒業後は北欧専門の旅行会社やスウェーデンの貿易振興団体に勤務。2010年に夫と娘の家族3人でスウェーデンへ移住。現在はレイフ・GW・ペーション『許されざる者』、ダヴィド・ラーゲルクランツ『ミレニアム5—復讐の炎を吐く女』(共訳)などのスウェーデン・ミステリ作品の翻訳のほか、日本メディアの現地取材のコーディネーター、高校の日本語教師などとして活躍中