地下鉄「無人運転」が、フランス人にできて日本人にできなかった理由
7/7(日) 8:00配信
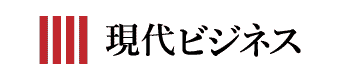

写真:現代ビジネス
先頭車両に乗ると、そこには…
フランスのパリで、運転士がいない無人運転の地下鉄に乗った。
電車が勢いよくホームに滑りこんで停車すると、電車のドアとホームドアが同時に静かに開く。列車の先頭部の車内に乗り込むと、そこには運転席がなく、前面窓に面した座席に乗客が座っている。
次世代新幹線「ALFA-X」が、高速運転を目標にしない理由
列車は、ドアが閉まると静かに走り出し、なめらかに加速・惰行・減速をして、次の駅に滑りこむ。最短運転間隔は85秒。初めて利用すると、ラッシュ時における運転頻度の高さと、駅での待ち時間の短さに驚かされる。
なぜ日本には、このような無人運転の地下鉄が存在しないのか。もちろん、無人運転の電車は、「ゆりかもめ」などの新交通システムで走っているが、地下鉄で走っていないのはなぜか。その理由を探ってみた。

パリ・メトロ14号線ホーム(筆者撮影)
なぜ「無人」が市民に理解されたか
本題に入る前に、まずパリの地下鉄で無人運転が行われるようになった経緯をたどってみよう。
現在パリでは、「メトロ」と呼ばれる地下鉄のうち、2路線(1号線と14号線)で無人運転の電車が走っている。最新の路線である14号線では1998年の開業時から、最古の路線である1号線(1900年開業)では2011年から、それぞれ無人運転を実施している。
これは、無人運転に多くのメリットがあるからだ。
無人運転のメリットと言うと、一般的には、運転士が乗務しないことによるコスト削減が注目されがちだが、それだけではない。運転士を確保する必要がないため列車の増発が容易になることや、高密度運転ができること、運転操作の無駄が少なく、最適な運転制御ができることなどの利点もある。
ただし、デメリットもある。
もし乗務員が車内にいれば、非常時に乗務員が乗客を避難誘導することができるが、完全な無人運転ではそれができないので、乗客の不安感が高まる可能性がある。ましてや暗いトンネルの中で電車が動かなくなるような事態を考えれば、なおさらだ。
そこで、パリの「メトロ」を運営するパリ市交通公団(RATP)は、14号線で初めて無人運転を実施するにあたり、一般市民に対して熱心に広報活動を行なった。
無人運転の技術はすでに確立されたものであり、同じフランス国内のリールやリヨンの地下鉄で導入実績があること。自動運転はヒューマンエラーを回避できるので、むしろ手動運転よりも安全性が高いこと。車内に非常用ボタンやインターホンを設け、非常時には指令室から避難誘導できるようにしたこと。
さらには、原則として駅間で電車を止めないこと。駅の照明を明るくしたり、電車の窓を大きくしたり、ホームドアをガラス張りにして、開放感や安心感を高めたこと――などなど。それらを広くアピールし、市民との議論を重ね、社会的コンセンサスを得たのだ。
14号線の開業当初は、運転士を廃止する代わりに半数の列車に巡回員を乗務させ、乗客の不安を和らげる工夫もした。完全な無人運転になってからは、フランスでたびたび起こる公共交通のストにも影響されずに電車が走り続ける地下鉄として注目され、パリ市民からの支持が高まった。
もちろん、日本でも可能だが…
こうした取り組みには、日本の地下鉄関係者も強い関心を持った。パリでの無人運転の成功を受けて、日本地下鉄協会は2001年に「次世代地下鉄システム研究委員会」を設置し、次世代の地下鉄はどうあるべきかを検討しはじめた。
また、専門家をフランスに派遣して、おもに無人(ドライバレス)運転の可能性について検討し、2002年に報告書をまとめた。日本地下鉄協会は、国内の地下鉄事業者などが加盟する一般社団法人だ。
ところが、この報告書が発表されてから17年経った現在も、日本の地下鉄では無人運転が実現していない。
たとえば福岡市営地下鉄七隈線は、技術的には無人運転を実施できる一歩手前に到達したにもかかわらず、今も乗務員を添乗させて非常時に備えている。
つまり、技術的には無人運転が可能でも、社会的に不安視する声が根強いために、実現できていないのだ。

パリ・メトロでは、他路線の無人運転化も検討されている(Photo by gettyimages)
日本人の「許容範囲」の狭さ
では、なぜパリでは無人運転が社会的コンセンサスを得ることができ、日本の大都市では得られていないのだろうか。
先ほどの報告書には、パリの「メトロ」で無人運転が実現した理由を「フランスの文化、フランス人のエスプリの所産といわざるを得ない」と記してある。つまり、フランスならではの環境があり、広報活動や議論を通して課題をクリアできたことが、社会的コンセンサスを得ることにつながり、実現に至ったのだ。
とはいえ、RATPと同様のやり方が日本でも通用するとは限らない。そもそも日本とフランスでは、社会や文化において根本的に異なる点が多々あるからだ。
筆者は先月、そのちがいを少しでも知ろうと、パリに1週間滞在してみた。もちろん、フランスのお国柄を知る期間としては短すぎるが、それでも日本では考えられないようなトラブルにたびたび遭遇し、社会や文化のちがいをまざまざと思い知らされた。
そもそも日本とくらべると、フランスでは物事が思い通りに進まないことが多い。日本からの長いフライトを終えてホテルについたら、テレビが映らないし、エアコンが動かない。地下鉄に乗ろうとしたら、自動券売機が壊れている。別の鉄道で移動しようとしたら、突然の運休でホームに至る階段が閉鎖されている。このようなことが日常茶飯事なのだ。
そこで筆者は、ある電機メーカーの幹部から聞いた話を思い出した。
「ヨーロッパの鉄道では、故障することを前提として機器を設計するという考え方がある。しかし、日本の鉄道では、この考え方がなじみにくい」
たしかにこれだけ故障に遭遇する機会があると、故障が起きても安全に機能するように機器を設計するのは自然な流れだ。一方、鉄道輸送の混乱を避けるあまり、ある程度の故障やトラブルすら許容しない日本の考え方は、フランスから見れば極端であり、奇異に映るだろう。
鉄道を社会全体で支える考え方へ
鉄道の安全に対する一般的な認識も、日本とフランスでは差があるようだ。
そもそも、鉄道の事故やトラブルを100%防ぐことは不可能である。それらが発生する確率は、安全対策を施すことにより小さくすることはできても、ゼロにすることはできない。
このことは、鉄道業界に従事する人など、知る人にとってはごく当たり前のことである。ヨーロッパでは鉄道に限らず、日本とくらべると物事がスムーズに進まないことが多いので、おそらくこの考え方が一般にも通じやすいのだろう。
ところが日本では、トラブルを前提とする思考は受け入れられにくい。ある鉄道事業者の幹部はこう言う。「日本では鉄道に対する期待が高く、鉄道が安全であることが当たり前であると考える人が多い」。
そのためか、鉄道でひとたび事故やトラブルが起こると、過剰とも思える反応やバッシングがあり、事業者の責任が強く問われる傾向があるし、かえって安全対策の議論も深まりにくい実情がある。
たとえば、この6月には、横浜の新交通システム「金沢シーサイドライン」で、無人運転の電車が逆走する事故が発生した。
事故によって負傷者が出たことは残念であるが、一方で、これだけを根拠に「無人運転は危険」と決めつけるのは早計だ。鉄道事業者やメーカーなどの責任を必要以上に問うことは、当事者を過度に萎縮させることにも繋がり、かえって新たなミスを招く恐れもある。
これからの日本には、地下鉄を含む鉄道の無人運転がますます必要となるはずだ。国の総人口だけでなく、生産年齢人口が急速に減少し、鉄道では利用者だけでなく、それを支える労働者も減ってゆく。
となれば、従来の運営方法で鉄道を維持することは難しくなるので、近年では複数の鉄道事業者が、自動運転や無人運転の導入に向けた取り組みを始めている。
こうした時代の変化に対応するには、われわれ鉄道利用者も発想の転換が必要だ。「お客様」として一方的にサービスを受けるという立場から脱却し、鉄道が取り巻く環境の変化を理解し、鉄道を社会全体で支えるという考え方で無人運転などの対応を少しずつ受け入れていく。そうした変化が、今後は日本でも求められるのではないだろうか。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190707-00065621-gendaibiz-bus_all&p=3
川辺 謙一
|


