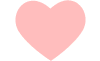神の鳩(3)
↑クリックしてね!
昼休みが終わって、国語の授業が始まったが、雪子は戻ってこなかった。
幸子は、雪子がひねくれて、わざと自分を不安にさせようとしているのだろうと、あまり気にしなかった。
それで担任の井上先生が、雪子がいないと大騒ぎし始めても、そしらぬ顔を決め込んでいた。
しかし放課後になっても雪子が戻らないと、遂に先生は雪子の家に連絡を入れた。
そして父親が学校へ駆けつけて来て、誘拐事件だと騒ぎまくった。
妻と死に別れ、男手一つで雪子を育てていた父親の心配ぶりは異常だった。
父親はすぐさま警察を呼び、やがてパトカ―が駆けつけてくると、学校は大パニックに陥ってしまった。
ここまで騒動に拍車がかかってしまうと、さすがの幸子も、取り返しのつかないことをしたと後悔したが、時すでに遅しだ。
幸子は恐ろしくなってしまい、とても真相を話す勇気など湧いてこなかった。
しかしこのままにしておくこともできない。
雪子は、本当に出口が分からなくなって屋根裏をさ迷っているのか、あるいは梁の上から転落して怪我を負い、助けを待っているのかもしれない。
幸子はこのことを連絡ノートに書いて、井上先生にこっそり伝えようと、決心した。
連絡ノートとは、口では伝えにくいことがあったら、ノートに書いて先生に伝えられるよう、先生が配慮して生徒一人一人に買い与えていたノートで、生徒達は他人には相談しにくい悩み事があったら、密かに書き記し、先生に渡して読んでもらっていた。
「先生、ごめんなさい。雪子ちゃんは屋根裏にいます。昼休みの時間、いつも一緒に理科室から二人で屋根裏に上がって、探検していたんです。でも私、いじわるして、雪子ちゃんを屋根裏に閉じ込めたまま、一人で下りてきたんです。どうか雪子ちゃんを助けてあげて下さい。お願いです」
幸子はそうノートにしたためると、先生に手渡そうとした。
しかし、職員室をのぞくと、県警から刑事がやって来ていて、険しい表情で先生に事情聴取している。
そんな緊迫した様子を垣間見ると、幸子は体がすくんでしまってノートを先生に渡せず、
結局その日は、机の引き出しにしまい、そのまま帰宅してしまった。
だが雪子は、その後いつまで経っても屋根裏から戻ってはこなかった。
警察は失踪と誘拐の両方の線で捜査を開始していた。
その頃になるともう、幸子はさすがに真相を明かす勇気などまったく失せ、ただひたすら、雪子が自力で戻ってきてくれることを祈るしかなかった。
そして運がいいと言うべきか、悪いと言うべきなのか、やがて理科室は床の腐食が激しくなってきていることを理由に使用中止となり、修理費用が捻出できないことからそのまま放置され、いつしか開かずの間と化してしまった。
こうして時は無情に過ぎていった。
幸子はついに卒業式を迎え、罪を自分の心の内に封印したまま、学校を去るしかなかった。
そしてその罪をいつか必ず償うつもりで、あの連絡ノートをタイムカプセルに入れて埋めることにしたのだ。
二十年も経って大人になれば、その時こそ、素直に先生に自分の罪を告げられるだろう。
そう自分に言い聞かせることで、幸子は罪悪感から、自分を解放しようしたのだ。
しかし結局、幸子はその呪縛から逃れることはできず、ずっと悩み続けることとなった。
やがて県警に設置された「雪子ちゃん失踪事件捜査本部」は解散し、風の噂では、この事件をきっかけに雪子の父と知り合った井上先生は、彼の後妻に納まったのだという。
それから二十五年―
橘第一小学校は市の方針で、廃校となることが決定し、校舎の解体工事が始まった。
そして工事中、作業員が瓦礫の中から、少女の白骨死体を発見した。
歯型を鑑定したところ、その白骨は二十五年前に失踪した雪子のものだと判明した。
こうして幸子の大罪は、ようやく白日の下にさらされようとしていたのである。
後はあの連絡ノートを先生に見せれば、全てが終わる。
刻一刻と、タイムカプセルが地表に現れる時が近づいていた。
土がひとかたまりずつ削り取られていくのを見ていると、幸子は胸がえぐられていくような気がして、苦しみのあまり気を失いそうになる。
幸子は思わず目を瞑ると、とっさに両手で耳をふさぎ、五感を完全に閉ざしていた。
「いえーい」
やがて歓声と拍手が沸き起こると、幸子は大きく息を吸い込み、再びゆっくりと目を開いた。
見ると、男連中の手によって、土まみれのビニールシートに覆われた、銀色のカプセルが、ゆっくりと穴から引き上げられていくところだった。
男達は慎重な手つきでカプセルを地面に置くと、まとわりついていたビニールシートを丁寧にはがした。
すると遂に、湿気ですっかり光沢をなくし、みすぼらしい姿に変り果ててしまった、灰色のタイムカプセルが、皆の前にさらされた。
「さあ、蓋を開けようよ」
皆の気持ちを代弁するかのように、悦子がせかして言った。
元学級委員だった糸井が、分かってるよと言いたげに軽く悦子を睨みつけると、ぎこちない手つきでカプセルの蓋を左へゆっくり回し、取り外した。
そして中から、ビニール袋に包まれて保管されていた、文集や手紙を一つずつ取り出すと、地面に並べていく。
幸子は恐る恐るその場へ近づくと、それらを一つ一つ目で確認しながら、あの連絡ノートを探し求めた。
すると突然、井上先生が近づいてきて、幸子の耳元で囁いた。
「藤井さん、何? 私に見せたいものがあるって」
相変わらずにこやかな表情だ。
だが幸子は先生の質問には答えず、そのまま無我夢中でノートを探し続けた。
そしてとうとう、一番隅っこに置いてあった、湿気でぼろぼろになった冊子が、そのノートであることに気づくと、震える手でそれを手に取った。
表紙を陽光にさらして、剥がれかけた文字を目で追うと、どうにか「薄井幸子」と読み取れた。間違いない。あの連絡ノートだ。幸子はページを開く前に、深呼吸して気持ちを落ち着かせた。
「これなの? 私に見せたい物って」
先生が、不思議そうな顔をしてノートを覗き込んだ。
幸子は覚悟を決め、大きく頷くと、ゆっくりとページをめくり始めた。
そして一番最後のページにたどり着くと、胸にそっと右手をのせ、緊張のあまり張り裂け
そうになる心臓を、ぎゅっと抑えた。
いよいよだ。
顔を近づけ、そのページに見入った。
おかしい。
思わず唖然とした。
消えている。
最後のページが、空白になっていたのだ。
なぜだ? 確かに、ここに書いたはずなのに……
幸子は他のページも捲り、丹念に調べたが、あの秘密をしたためたページは、どこにもなかった。
(つづく)