久しぶりに、白井先生の最新刊を読んでみました。
英語教師のための第二言語習得論入門/白井恭弘
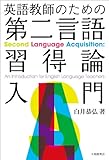
¥1,260
Amazon.co.jp
この本は英語教師の私にとって、非常にためになる、しかもワクワクする内容でした。
今までの私は、高校での英語教育のことばかりを考えていたのですが、この本を読み終えたことで、これからは、小学校英語から大学英語、さらに社会人の英語教育までを総合的に考えていきたいと思えるようになりました。
また、三日前にリモート受講した勝間塾月例会で、勝間さんとHALさんが言っておられた英語学習方法と共通する内容が、この本にかなり盛り込まれていたこともあり、一気に読み終えることができました。
この本は6章構成になっていますが、特に記憶に留めておきたい内容をまとめておきます。
第1章 第二言語習得論のエッセンス
この章では、SLA (Second Language Acquisition)の理論について、簡潔にまとめられています。ずいぶん前に大学院で学んだことを思い出すことができました。
特におもしろかったところは、外国語学習に成功する学習者の特徴が、
1. 若い
2. 母語が学習対象言語に似ている
3. 外国語学習適性が高い
4. 動機づけが強い
5. 学習法が効果的である
というところでした。これらの中で教師が変えることができるのは、4と5だけ。つまり、「教師としては、学習者の動機づけを高め、効果的な学習法をとれるように導いていくことに集中すればよい」のです。
また、3の適性に関しては、個別学習、例えばコンピュータを使って学習者の適性を測って、学習者独自の学習プログラムを作ることが可能になってきました。このような教え方を「適性処遇交互作用」といい、今後注目されることと思われます。
さらに、動機づけに関しては、「学習者の動機づけを高めると同時に、その高まった動機づけが、行動につながるようにしていくことがとても重要」です。
第2章 SLAからみた日本の英語教育
白井先生は、日本の英語教育では「大量のインプットと少量のアウトプット」の組み合わせが大切だと強調しています。具体的には、7:3の比率です。
ところで、日本の教育•学習の現状は、以下のとおりです。
1. 理論が自動かモデルに偏り、しかも自動化の訓練が不足
2. インプットの質•量ともに不十分
3. 意思伝達よりも正確さを重視
このような現状に対して、今後どうすればいいのでしょうか。
まず、外国語学習の目的は何か、を明確にすることが大切です。ここでの目標は、「使える英語」です。
具体的にどのようにすればいいのか。
①「多聴多読」が非常に有効です。
私は現在多読指導を行っていますが、最近ではFRLというシリーズを使っていることもあり、生徒たちが多読を楽しむようになってきました。
多聴については、まだ実践できていませんので、来年度から何らかの形で取り入れていくことにします。
②文法を最初から完璧に知識として理解して、それが終わってから、徐々に自動化するというモデルから脱却する。
文法指導の最初から、自然な言語習得の原則に沿って、言語をコミュニケーションの手段として習得できるよう指導を行わないと、ほとんどの学習者がひとこともしゃべれないまま終わってしまうことを、まずしっかり認識することが改革の第一歩です。
第3章 小学校英語教育のこれから
小学校では、ジェームズ•アッシャーのTotal Physical Response (TPR=全身反応教授法)と、パッツィ•ライトバウンらの自主的読書教育が望ましい方法だと、白井教授は述べています。
TPRに関しては、大学院で実際に指導法を少し学びましたが、中学校においても非常に効果的な指導法だと、私は思います。
小学校英語に携わるすべての人の必読書として、以下の本が紹介されています。
日本の小学校英語を考える―アジアの視点からの検証と提言/バトラー後藤 裕子

¥2,520
Amazon.co.jp
第4章 中学校英語教育のこれから
ここでのアプローチの仕方は、「コミュ二カティブ•アプローチを基本としつつ、学習者に正しさにも目を向けさせながら、fluency(流暢さ)とaccuracy(正確さ)のバランスをとっていく」ことです。
「初期の段階から身近な内容について、意味と形式の両方に注意を払って自然なコミュニケーションをしていけば、比較的短期間で、限られた単語を使って限られた内容について流暢なコミュニケーションができるようになるのです。」
これに関しては、田尻悟郎先生のウェブサイトが参考になります。
第5章 高校校英語教育のこれから
中学校では、昔に比べて、ずいぶん教授方法も改善されてきました。一方、高校においては、未だに文法訳読教授法が主流になっているといっても過言ではないと思われます。
高校教員の私が常日頃から心がけるべきことは、「まず、授業が成立するような面白い活動を多数ストックしておき、次に、どのようなタスクをすれば、より学習事項が定着していくか検証していくこと」です。
「その際、文法的正しさよりも、むしろ意思伝達ができているかという観点で全体的に評価すること」を忘れないようにしたいと思います。
そして今までは授業で文法を教える時間が非常に多かったのですが、これからは内容理解中心のCommunicative Readingに移行していくことが大切であることを、職場の同僚に理解していただき、そのような指導を実践していくことにします。
第6章 大学生、社会人のための英語教育
ここでの内容は、先日の月例会で聞いた内容と共通するところが多いです。
★インプットの材料を選ぶ時の条件
1. ある程度の理解度が保証できるもの
•「分野を絞ったインプット」(narrow listening/reading)が効果的です。
2. 感情に訴えるもの
•人の心を揺さぶるようなスピーチや、映画の一場面
私の場合は、TEDのトークが非常に自分に合っているみたいです。
3. 自分(学習者)にとって意味のあるもの
最後に、この本の最終ページには、推薦図書リストがありますので、このリストの中の本を丁寧に読んで、自分の指導技術を改善していくことにします。
英語教師のための第二言語習得論入門/白井恭弘
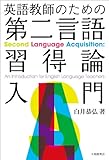
¥1,260
Amazon.co.jp
この本は英語教師の私にとって、非常にためになる、しかもワクワクする内容でした。
今までの私は、高校での英語教育のことばかりを考えていたのですが、この本を読み終えたことで、これからは、小学校英語から大学英語、さらに社会人の英語教育までを総合的に考えていきたいと思えるようになりました。
また、三日前にリモート受講した勝間塾月例会で、勝間さんとHALさんが言っておられた英語学習方法と共通する内容が、この本にかなり盛り込まれていたこともあり、一気に読み終えることができました。
この本は6章構成になっていますが、特に記憶に留めておきたい内容をまとめておきます。
第1章 第二言語習得論のエッセンス
この章では、SLA (Second Language Acquisition)の理論について、簡潔にまとめられています。ずいぶん前に大学院で学んだことを思い出すことができました。
特におもしろかったところは、外国語学習に成功する学習者の特徴が、
1. 若い
2. 母語が学習対象言語に似ている
3. 外国語学習適性が高い
4. 動機づけが強い
5. 学習法が効果的である
というところでした。これらの中で教師が変えることができるのは、4と5だけ。つまり、「教師としては、学習者の動機づけを高め、効果的な学習法をとれるように導いていくことに集中すればよい」のです。
また、3の適性に関しては、個別学習、例えばコンピュータを使って学習者の適性を測って、学習者独自の学習プログラムを作ることが可能になってきました。このような教え方を「適性処遇交互作用」といい、今後注目されることと思われます。
さらに、動機づけに関しては、「学習者の動機づけを高めると同時に、その高まった動機づけが、行動につながるようにしていくことがとても重要」です。
第2章 SLAからみた日本の英語教育
白井先生は、日本の英語教育では「大量のインプットと少量のアウトプット」の組み合わせが大切だと強調しています。具体的には、7:3の比率です。
ところで、日本の教育•学習の現状は、以下のとおりです。
1. 理論が自動かモデルに偏り、しかも自動化の訓練が不足
2. インプットの質•量ともに不十分
3. 意思伝達よりも正確さを重視
このような現状に対して、今後どうすればいいのでしょうか。
まず、外国語学習の目的は何か、を明確にすることが大切です。ここでの目標は、「使える英語」です。
具体的にどのようにすればいいのか。
①「多聴多読」が非常に有効です。
私は現在多読指導を行っていますが、最近ではFRLというシリーズを使っていることもあり、生徒たちが多読を楽しむようになってきました。
多聴については、まだ実践できていませんので、来年度から何らかの形で取り入れていくことにします。
②文法を最初から完璧に知識として理解して、それが終わってから、徐々に自動化するというモデルから脱却する。
文法指導の最初から、自然な言語習得の原則に沿って、言語をコミュニケーションの手段として習得できるよう指導を行わないと、ほとんどの学習者がひとこともしゃべれないまま終わってしまうことを、まずしっかり認識することが改革の第一歩です。
第3章 小学校英語教育のこれから
小学校では、ジェームズ•アッシャーのTotal Physical Response (TPR=全身反応教授法)と、パッツィ•ライトバウンらの自主的読書教育が望ましい方法だと、白井教授は述べています。
TPRに関しては、大学院で実際に指導法を少し学びましたが、中学校においても非常に効果的な指導法だと、私は思います。
小学校英語に携わるすべての人の必読書として、以下の本が紹介されています。
日本の小学校英語を考える―アジアの視点からの検証と提言/バトラー後藤 裕子

¥2,520
Amazon.co.jp
第4章 中学校英語教育のこれから
ここでのアプローチの仕方は、「コミュ二カティブ•アプローチを基本としつつ、学習者に正しさにも目を向けさせながら、fluency(流暢さ)とaccuracy(正確さ)のバランスをとっていく」ことです。
「初期の段階から身近な内容について、意味と形式の両方に注意を払って自然なコミュニケーションをしていけば、比較的短期間で、限られた単語を使って限られた内容について流暢なコミュニケーションができるようになるのです。」
これに関しては、田尻悟郎先生のウェブサイトが参考になります。
第5章 高校校英語教育のこれから
中学校では、昔に比べて、ずいぶん教授方法も改善されてきました。一方、高校においては、未だに文法訳読教授法が主流になっているといっても過言ではないと思われます。
高校教員の私が常日頃から心がけるべきことは、「まず、授業が成立するような面白い活動を多数ストックしておき、次に、どのようなタスクをすれば、より学習事項が定着していくか検証していくこと」です。
「その際、文法的正しさよりも、むしろ意思伝達ができているかという観点で全体的に評価すること」を忘れないようにしたいと思います。
そして今までは授業で文法を教える時間が非常に多かったのですが、これからは内容理解中心のCommunicative Readingに移行していくことが大切であることを、職場の同僚に理解していただき、そのような指導を実践していくことにします。
第6章 大学生、社会人のための英語教育
ここでの内容は、先日の月例会で聞いた内容と共通するところが多いです。
★インプットの材料を選ぶ時の条件
1. ある程度の理解度が保証できるもの
•「分野を絞ったインプット」(narrow listening/reading)が効果的です。
2. 感情に訴えるもの
•人の心を揺さぶるようなスピーチや、映画の一場面
私の場合は、TEDのトークが非常に自分に合っているみたいです。
3. 自分(学習者)にとって意味のあるもの
最後に、この本の最終ページには、推薦図書リストがありますので、このリストの中の本を丁寧に読んで、自分の指導技術を改善していくことにします。