今朝、暴風警報が発令中でしたので、今日は午前中で仕事を終え、すぐに自宅に戻りました 。
。
さて、それからしばらく経ち、久しぶりに齋藤先生の著書の最新刊を読んでみることにしました。
例えば、
・"I like play tennis."という文章は間違いです。likeとplayという動詞が2つ並んでいては「どうしようもない」ですね。(「どうしようもない」と「動詞ようもない」とを合わせたダジャレ)
 Intake Readingとは
Intake Readingとは
 Intake Readingの仕方
Intake Readingの仕方
 Intake Readingの効果
Intake Readingの効果
時間に少し余裕ができたので、二日前に届いた以下の本を、フォトリーしました。
生徒の間違いを減らす英語指導法―インテイク・リーディングのすすめ/齋藤 榮二
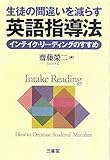
- ¥2,100
- Amazon.co.jp
- この本の筆者は、英語教育界では超有名な、齋藤榮二先生です。
- 私と齋藤先生の初めての出会いは、今から10年ほど前に、ある英語教育研究会で、ペア活動のペア同士になったことです。
当時、齋藤先生についてまったく知らず、この老年の方はいったい誰だろうかと心の中で思いながら、ペア活動をしていました。とてもやさしく、しかも紳士的な人だなあという印象を持ちました。
それから、数年経ち、齋藤先生のワークショップなどに数回参加する機会がありました。また、大学院でもたいへんお世話になりました。
さて、それからしばらく経ち、久しぶりに齋藤先生の著書の最新刊を読んでみることにしました。
この本は、齋藤先生独特の、質問者がいて、その質問に齋藤先生がお答えになるという問答形式で構成されています。
非常にわかりやすい言葉で、しかも齋藤先生の十八番のダジャレが要所要所に織り込まれていて、大笑いしながら一気に読み終えました。
例えば、
・"I like play tennis."という文章は間違いです。likeとplayという動詞が2つ並んでいては「どうしようもない」ですね。(「どうしようもない」と「動詞ようもない」とを合わせたダジャレ)
まるで、目の前で齋藤先生のお話を聞いているような気がしました 。
。
 。
。この本は、タイトルからもわかるように、
「Intake Reading(インテイク・リーディング)」
についての方法やその効果について述べられるています。
なお、Intake Readingという言葉は、齋藤先生が命名されました!
 Intake Readingとは
Intake Readingとは・ことばの習得過程は、 Input ⇒ Intake ⇒ Output という段階を踏みます。
・現在の日本の英語教育では、ほとんどInputにエネルギーを注ぎ、学習者がまだ準備ができていない状態でOutput活動を強いる傾向にあります。
つまり、Intake(「英語の文を脳に沈める作業)」がほとんどなされていないのです。
Intake Readingとは、学習者の脳に英語の文を沈めるための読みのことです。
 Intake Readingの仕方
Intake Readingの仕方1. 生徒をペアにして立たせる。
2. 片方の生徒はテキストを見ながら教科書の最初の文を、もう一方の生徒に言う。
3. 言われた生徒は、何もみないで、それを正しく復唱する。
簡単そうですが、実は冠詞a, theが抜けていたり、7語以上の単語が集まった文になると(7という数字は、人間の記憶において苦労なく覚えられるぎりぎりの数だそうです)、かなりしんどい作業です。
 Intake Readingの効果
Intake Readingの効果・読み手の責任が問われる
読み手が正しい英語を読まないと、相手も間違った英語を発することになります。
・Intake Readingは生徒の英語の力のバロメーターを示す
自分がよく知っている英語はすぐにIntake Readingできますが、まだ習得していない英語のIntake Readingは非常に難しいです。
・Intake Readingは生徒にとって楽しく、しかも力がつく
「楽しくやれた、だから成功した」などと考えてはだめだ。それではプロではない。
私は、日々の授業で「音読」を重視しています。
そして、数年前からIntake Readingを実践していますが、コーラス・リーディングの時にまったく声を出さない生徒たちが、Intake Readingの練習になると、いきいきと大きな声を出すのです 。
。
 。
。しかも、次の授業で行う小テストでも、多くの生徒が高得点を取っています 。
。
 。
。易しいタスクを与えるだけではなく、知的プレッシャーをかけることで、生徒が授業にいきいきと参加することがわかってきました。
そしてこの本の最後の章で、齋藤先生は、教師もIntake Readingで力を伸ばそうと提案されています。
最後に、齋藤先生の次のお言葉に、身の引き締まる思いがしました。
「英語そのものを勉強するということをやめた教師というのは、その先生から習っていても、なんとなくマンネリ教師を感じてしまう。教師としての魅力というか、やや大げさに言うとオーラを感じない。生徒というのは高校生くらいになってくると、そういうことにも敏感になってくる。」