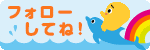にほんブログ村ランキング参加中![]()
下をポチっと押して貰えると
愛里跨はとっても元気になれるのよぉー(・ω・)![]()
↓↓↓↓↓↓
30、踏み入めなかった領域
恋も仕事も日常も、
安心を感じられるものは魅力的だった。
世間の当たり前が、見回すすべてがとても輝いて見えてた。
何せ、他の人と比べれば、
今までの私の日常は奇抜で常識外れで、自由を許されないもの。
でもこんな私がようやく、明るく穏やかな場所で、
親友や仲間達と恙無く過ごすようになった。
そしていつも私を優しく見つめ、
愛してると言ってくれる恋人の許で過ごせるようになった。
それなのに……
何故こんなにも悲しくて辛いの?
どうしてこんなにも涙が溢れて、自力で立っていられないの?
……あぁ。そうか。
束の間の幸せに目が眩んで忘れていた。
午前零時に魔法が解けるシンデレラみたいに元に戻るんだ。
哀れな自分を悟られないように、素敵な王子様の手を振り払って。
ここは踏み込むことなど許されない領域。
どんなに自由になっても、愛する人に愛されても、
私の両足首には岡留千重子の娘という分厚い二枚の鉄板がはめられ、
切りたくても切れない罪咎の鎖に繋がれている。
そして足枷の鍵は母、千重子が握ってる。
そう。私は、シンデレラにすらなれない。
生まれながらにして、自由に生きられない罪人(つみびと)……
柑太「おかえり、萄真。お疲れ」
萄真「お疲れ。
忙しい時に留守番頼んで悪かったな。
おまえも明日の準備で大変なのに」
柑太「大丈夫だよ。
待ってる間、ここで大まかな事はさせてもらったから」
萄真「そうか。それならいいんだが」
柑太「それに。
留守番だけじゃないだろ?
柚子葉さんの護衛でもある。
これは社長命令でもあるからな」
萄真「そうだった」
柑太「夏梅社長にも今回の件は連絡しておいた。
心配してたから後で報告しておくよ」
萄真「うん。頼む。
柚子葉、寝ちまったのか」
柑太「うん。勝手に毛布借りたぞ」
萄真「ああ。
彼女の修了試験も明日あるのか?」
柑太「いや。来週火曜日の検査結果が良くて、
職場に完全復帰してから受けさせるらしい。
明日は引っ越しもあるしな」
萄真「そっか」
柑太「もしかしたら坂野元や柚子葉さんの母親が、
会社に乗り込んでくる可能性も否定できないって。
あの事件で社長は第一発見者だったし、
路上に倒れてた柚子葉さんの姿が脳裏に焼き付いてるみたいで、
万全を期してやりたいんだろ」
萄真「そうか……そうだな。
そんな夏梅さんだから俺も安心していられる」
柑太「うん。僕もそう思うよ」
萄真さんはノートパソコンに向かう柑太さんと、
ソファで眠っている私を申し訳なさそうに見つめた。
そしてキッチンへ向かうと
冷蔵庫からオレンジジュース、食器棚からグラスを二つ取り出した。
その時、コンロの上にあるホーロー鍋に気がつく。
グラスとジュースをフロアキャビネットの上に置き、
蓋を開けて中身を確認した。

萄真「クリームシチューか」
柑太「あぁ、それな。
柚子葉さんが作ったんだ。
おまえが腹ペコで帰ってくるだろうからってね」
萄真「そっか」
柑太「柚子葉さんのお父さん直伝らしいよ」
柑太「へー」
ゆっくり蓋を閉じるとグラスにジュースを注ぎ、
リビングに戻って柑太さんにグラスを差し出した。
萄真「ほい。今夜は酒、出せないから」
柑太「サンキュー。
そのくらい分かってるよ。
萄真。すまないな」
萄真「何、謝ってんだ?」
柑太「おまえより先に柚子葉さんの手作りシチューを食べた」
萄真「なんだ。そのくらいで謝るなよ」
柑太「それと、柚子葉さんが料理してる初々しい姿も見せてもらった」
萄真「お、おい。いやらしい表現するな」
柑太「だって、萄真より先にってのは何となく申し訳ないだろ?
好きな女との初めてはすべて貴重だからさ」
萄真「べ、別にそのくらい気にしないよ、俺は。
ガキじゃないんだから」
柑太「いや。明らかに動揺してる」
萄真「おまえな」
柑太「シチュー、すごく美味かったよ」
萄真「ふっ。そっか。
俺も後で食べるよ」
柑太「うん。
それでどうだった?夏生さん宅は」
萄真「警察も相手が相手だから様子を窺ってたけど、
すぐの危険性はないだろうってことだった。
うちの会社は数年前に警察官立寄所の申請してるし、
事件のこともあるから自宅周辺のパトロールを強化してくれるそうだ。
今夜は澤田さんも泊まり込みで居てくれてる」
柑太「そっか。
だったら安心だな」
萄真「しかも幸いなことに、
来てくれた警察官の中に柚子葉を知ってる人が居て、
協力してくれるといってくれた」
柑太「へー。警察に知り合いがいるなんて意外だな」
萄真「その人曰く、警察官になってると柚子葉は知らないだろうって。
今回の被害届を見て彼も気がついたみたいだけど」
柑太「そうなんだ。
心強い味方が増えてよかったな」
萄真「ああ。
しっかし。兄貴夫婦の強さは俺の想像以上だった。
実蕗さんは柚子葉さんの母親に怯むことなく立ち向かうし、
兄貴は何を言われても動じることなく冷静に対応してた」
柑太「そっか」
萄真「帰り際、兄貴に迷惑かけてすまないって言ったら、
『おまえは父親に似て勇猛果敢で、私にとって頼もしい弟で片腕だけど、
人を救済するということは、諸刃の剣にもなると覚悟しろ』ってさ。
引き受けた時点で兄貴も実蕗さんも、
覚悟はできているから簡単に謝るなって反対に説教を食らったよ」
柑太「なんか、夏生さんらしいな」
萄真「あの二人はいい夫婦になったよ」
柑太「過去は完全に吹っ切れたみたいだな、萄真」
萄真「ああ。柚子葉に出会って完全に。
おまえは、吹っ切れたのか」
柑太「うーん。そうだな……」
柑太さんは泣き疲れて沈む寝顔を、
トロンとした目で愛おしそうに見つめる。
その潤む眼差しに萄真さんは微かにジェラシーを感じたけれど、
瞼をゆっくり閉じて隠し、彼の表情を確かめるように重ね見る。
柑太「完全じゃないけど、吹っ切らないと、だろ」
萄真「……」
柑太「でもさぁ。いくら部下だからと言っても、
これだけ毎日長時間顔を突き合わせてるとさ」
萄真「柑太」
柑太「笑ってるかと思ったら、急にぽたぽた涙を流してみたり、
普通に話してると思ったら、ぼんやり遠くを見つめていたり、
『おーい、戻ってこーい』って叫びたくなる。
彼女の無意識が僕の心をくすぐってくる」
萄真「おまえ。
(まだ、柚子葉さんを諦めきれないんだな)」
柑太「柚子葉さんと同等か、それ以上の女性に巡り合えれば、
スムーズにいくのかもな……
親友としての感情に戻すのには時間がいるかな。もう少し」
萄真「そう、か」
柑太「萄真」
萄真「ん?」
柑太「柚子葉さん、ボロボロだぞ。
もうメンタル限界だ、多分」
萄真「えっ」
柑太「まるでダウン寸前のボクサーみたいで。
クリンチ気味に僕にもたれて、
自分を保っていられないほど泣き崩れた」
萄真「……」
柑太「母親に見捨てられたってだけでも心には大きなダメージなのに。
今回の大怪我に加え、母親がみんなに迷惑を掛けて、
自分はどうやって償えばいいかって項垂れるんだぜ。
犯罪者の家族が抱えるスティグマみたいで、
その姿を見てるのが正直辛かったよ」
萄真「(柚子葉は俺達と出会う随分前からボロボロだった。
激しい神経の消耗、疲労感、虚無感、
この世に存在する罪悪感、すべての負の感情に苛まれてきた。
でも。こんなになっても彼女を奮い立たせていたのは、
父親の存在があったからだろうな、きっと)」
柑太「仕事柄、こういうのはたくさん見てきた。
適応障害に燃え尽き症候群、
僕の母親も一時期、空の巣症候群なんてものになったけど。
身近な人でここまで疲弊してる姿を見るのはこれで二度目だ。
久坊の闘病生活を見て以来だよ。
あの時は、何もしてやれなくて、
無力な自分を嫌というほど思い知らされた」
萄真「……そうか。
でも、今度は違う。だろ?」
柑太「そういう萄真もだろ」
萄真「俺達が彼女の傍に居てやらないといけないんだ。
俺とおまえで。
そして柚子葉を取り巻くみんなで」
柑太「そうだな。
いいのか、それで。
僕が彼女の傍にいても」
萄真「当たり前だろ。
俺達三人は親友。
それに、おまえが先に柚子葉に声を掛けたんだ」
柑太「そうだったな。
でもさぁ。
途中で僕の気持ちが変わって、
萄真から柚子葉さんを奪っちゃうかもしれないぞ」
萄真「そんなやつかよ」
柑太「かもしれない」
萄真「そんときは、力づくで柚子葉を奪い返す」
柑太「はぁ。腕力ではおまえに勝てないから」
萄真「ふっ。素直でよろしい」
二人は同時に横たわる私を優しく見つめる。
そんな温かい視線を向けられているとも知らず、
私は深海のように暗く全身が凍りつくほど冷たい水中に、
どんどん引っ張られて沈んでいく夢を見ていたのだった。

私を送って帰る途中の杏樹さん。
あと一ブロックで自宅のある中央区に差し掛かるところで、
バッグの中でバイブ音がする。
彼女はハザードを上げて車を路肩に寄せ、
スマートフォンを取ると着信を確認して受話ボタンを押す。
杏樹 「もしもし」
瀬戸口『もしもし、馬木。俺』
杏樹 「瀬戸口くん。
電話嫌いの貴方が電話なんて珍しい」
瀬戸口『そうでもないよ。
電話する人にもよる』
杏樹 「何それ」
瀬戸口『毎日会社で会えるから電話する必要がなかっただけだ。
それに電話より直接話したほうが誤解も少ないし、
何より的確に本心を伝えられるだろ』
杏樹 「それはそうだけど。
それで?何か用事?」
瀬戸口『俺はおまえの大事なものを預かっている!』
杏樹 「は?意味わかんないんだけど」
瀬戸口『今から西区まで来れるか?』
杏樹 「う、うん。
柚子葉さんの家からの帰りで中央区に入ったところだから、
十五分くらいでいけるけど」
瀬戸口『今、米山と一緒なんだ。
偶然ももち浜の海浜公園で会って』
杏樹 「えっ」
瀬戸口『俺が家まで送っても良かったんだけど
どうも何かあったらしくて、家にはまだ帰りたくないようだし。
それに追い打ちをかけて、
馬木と岡留から交互に着信が入ってるって米山がかなりビビってる。
それで俺が代わりに連絡したんだ』
杏樹 「そう。分かった。
それで、何処に行けばいいの?」
瀬戸口『西区豊浜のファミレス。
仕事帰りに馬木と一緒に行った』
杏樹 「OK。
今日は朝から動き回った上に、
食べたのコンビニのサンドイッチ一つだけだから腹ペコなのよ。
私を呼び出すからには、奢ってくれるわよね、瀬戸口くん」
瀬戸口『もちろん。
ステーキでもハンバーグでも、
馬木の好きなものをいくらでも食っていい。
なんなら俺を食っても構わないぞ』
杏樹 「あ。最後のは却下でお願いします」
瀬戸口『くそっ。流れでお願いっていうと思ったのに』
柚子葉「ったく。
図太い神経してるよね、瀬戸口くんは。
三日前にフラれた女に、よくもまぁそんな冗談が言えるわよ」
瀬戸口『俺をフッた張本人が、
しれっと触れられたくない俺の心に入ってくるな」
杏樹 「別に入ってないでしょ」
瀬戸口『もう諦めろってダメ押ししてるだろ」
杏樹 「そんなこと一言も言ってないでしょ?
まぁ、そういう意味合いがないわけじゃないけど」
瀬戸口『ほらみろ』
杏樹 「瀬戸口くんが増川トレーナーに勝つ自信があるなら、
リベンジ、ワンチャンあるかもよ」
瀬戸口『あんな優秀なイケメン男に俺が勝つなんて、
逆立ちしたって無理に決まってるだろ』
杏樹 「じゃあ、諦めて」
瀬戸口『そういうストレートな言葉グサグサくるんだよな。
増川教官か……あいつのこと、そんなに好きなのか。
やっぱり俺じゃ……駄目なのか』
杏樹 「そんなのあたりまえでしょ。
あの時話したじゃない。
私がリヴに入社した理由。
これだけは誰が何を言っても絶対に揺るがない」
瀬戸口『はぁ。同じ女に二度もフラれるとは。
俺は身体も態度もでかいけど、心臓はデリケートなんだ』
杏樹 「はいはい。
以後気をつけます。
ちゃんと行くから待ってて」
瀬戸口『おう。
まだ車多いから気をつけて来いよ』
杏樹 「うん。分かった」
電話を終えて深い溜息をつく。
本心を瀬戸口くんに悟られないように、
わざと明るく気さくに振舞った杏樹さん。
内心、不安で心細くて仕方がなかった。
心の整理に時間が欲しいと言った柑太さんが、
本当に自分に振り向いてくれるのか。
彼の恋人として一緒に過ごすことがこの先できるのか。
たくさんの車がヘッドライトをつけて川のように流れる中、
襲い掛かる不安を振り捨てる。
彼女は慣れたハンドルさばきで発進させ、
国体道路に出た車は二人が待つ西区へ向かったのだ。

小さくカチャカチャと食器が触れ合う音が遠くに聞こえて、
私は目を覚まし焦ったように飛び起きる。
知らないうちに身体に毛布が掛けられていて、
キッチンを見るとカウンターに向かう萄真さんがいた。
リビングに柑太さんの姿は既になく、
ローチェストの上のデジタル時計を確認すると
時刻は午後十時四十分。
私は泣き疲れて一時間以上も眠っていたんだ。
頭を抱えていると片づけを終えた萄真さんが、
キッチンから出てくる。
萄真 「目が覚めた?」
柚子葉「萄真。おかえりなさい。
(何たる失態。
柑太さんに悪いことをしたな)」
萄真 「ただいま、柚子葉。
疲れてたのかな、よく眠ってたね」
柚子葉「ご、ごめんなさい。
いつの間にか眠ってしまって。
帰ってるなら起こしてくれたらよかったのに」
萄真 「気持ちよさそうに眠っていたから。
それに寝顔も見たかった」
柚子葉「ね、寝顔を見るなんて、悪趣味だな」
萄真 「そうかな」
柚子葉「柑太さんは帰っちゃったの?」
萄真 「うん。帰ったよ。
明日は修了試験だし、
いつもより一時間早く出社だって」
柚子葉「そうなんだ。
お礼も言えなかったな」
萄真 「明日言えばいいさ。
仕事が終わったらここへ来るから」
柚子葉「うん」
萄真 「お風呂、お湯はってるから入っておいで。
目が覚めるよ」
柚子葉「う、うん。ありがとう」
萄真 「着替えは持ってる?」
柚子葉「柑太さんから言われたから一応持ってきた」
萄真 「そっか。
タオルは脱衣室のチェストの中にある。
浴室にあるもの、自由に使っていいから」
柚子葉「うん……」
萄真 「バスルーム、教えようか?」
柚子葉「……」
シャワーを浴びた後なのか、
彼の匂いと上品で爽やかな香りが混ざり合い優しく香ってくる。
本能的に彼が好きなんだと感じさせてくれる匂い。
そして何より安心感を与えてくれるこの匂い。
まつげを少し伏せて考え込んでいると、
萄真さんは横に座って、寝ぐせのついた私の髪を優しく撫でた。
柚子葉「(早く、萄真に謝らないと。
知らなかったとはいえ、
母が多くの人に多大な迷惑をかけて、警察沙汰にまで……
萄真やお兄さん家族に、
嫌な思いをさせてしまったことを、謝らないと)」
萄真 「柚子葉?」
柚子葉「……」

拳を胸に当てて話し始めようとした時……
萄真さんは優しく頬に触れ、私の唇にキスをした。
それは深く痛々しい傷口に接吻するような、
驚くほど柔らかく温かい感触。
私の心を読んで「分かってる」と諭すような慈愛のキス。
それが鈍感な私にも瞬時に伝わって、
嬉しくて嬉しくて、乾いたはずの涙がまた溢れだす。
柚子葉「萄真。ごめんなさい。
母が、大変なことをして、本当に……ごめんなさい。
お兄さんや、実蕗さんにも、申し訳ないことを」
萄真 「柚子葉の気持ちは分かってる。
気にするなといっても、君は気にするだろうけど」
柚子葉「萄真」
萄真 「俺も兄貴夫婦も、柑太も周りのみんなも、
何があっても柚子葉の味方だから安心して」
柚子葉「萄真は……こんな私でいいの?」
萄真 「どうしてそんなこと言うの」
柚子葉「私の母は、貴方の大切なお兄さんやその家族を、
平気で脅してお金を奪うような人。
そして私は、その人に育てられた娘。
ずっと、その柵は変わらない……」
萄真 「生い立ちは君が選んだんじゃない」
柚子葉「柑太さんから聞いた。
坂野元という人は凶悪で、前科があって警察も追ってる人だって」
萄真 「そうだよ」
柚子葉「時間が経てば、私のアパートへ来たみたいに、
お兄さんの会社や萄真の工房、ここにだって来るかもしれない。
貴方が築き大切にしてきた生活や、
狩野さん夫婦や従業員さん達も、危険に晒してしまうかもしれない」
萄真 「そういうことは、俺が考えることだよ」
柚子葉「でも。もしそうなっても、私を愛せる?
何もなかったように、一緒に生活できる?
足枷をはめられた罪深い私を、変わらずに愛せる?」
萄真 「俺は、変わらず愛せるよ。
足枷があるなら外して楽にしてあげるから、
そんなこと心配するなよ」
柚子葉「母親から死んでくれと懇願されるような女でも?」
萄真 「柚子葉」
柚子葉「普通はみんな、そんな人だと思わなかったと幻滅して、
蔑み愛想を尽かして私の前から去っていく。
それは罪深いから。
私なんて、居ないほうがいいのかもしれない。
事故に遭った日、あのまま、白うさぎのように、
逝ってしまったほうが、よかったのかも」
萄真 「どうして……
どうして君は感情を押さえつけて、
自分で自分を殺してしまうんだ。
負の感情はすんなり受け入れちまうくせに、
正の感情はまったく他人事なんだよ。
それじゃあ、喜びや楽しみや幸せは感じられないだろ」
柚子葉「……」
萄真 「そういうなら、逆だったらどうだ。
俺がそうだったら、柚子葉は俺を愛せないのか?
居ないほうがいいと思うのか」
柚子葉「それは、違う」
萄真 「君が思う普通がどんなものなのか俺は知らないし、
俺はそんな、人を蔑むような人間にはならない。なりたくもない」
柚子葉「と、萄真」
萄真 「君の母親が罪を犯したからと言って、
何故君が罪人になるんだ。
どうして自ら罪人になる必要があるんだ。
そんな人だったら俺はきっと君を愛していない」
柚子葉「……」
萄真 「君は罪深いと言うけど、俺にだって抱える罪はある。
人間は生まれながらに罪を背負ってるという。
この世の中、悪に手を染める人だけじゃなく、
善きサマリア人だってたくさんいる。
俺は後者だし、そうありたいと常に思ってる。
だからと言って俺は、
善きサマリア人として君の傍に居るんじゃない」
柚子葉「わ、私……」
萄真 「どうして、自分を大切にして生かそうとしないんだ。
どうして、一緒に生きようと差し出された手を、
握ろうともしないで自分から振り払うんだ」
柚子葉「そ、それは」
萄真 「どうすれば、この想いが君に伝わる。
俺は……君を愛しているから、傍に居るのに……」
柚子葉「萄真。私は……」
萄真 「柚子葉のことなら俺は、
良い事も悪い事も何でも受け止めて離さない。
だから……これ以上、自分を責めないでくれ。
俺や兄貴やみんなに申し訳ないなんて思わないでくれ。
償うとか謝るとか、考えないでくれ。
自分で自分を殺して、
逝ってしまうほうがいいなんて、もう言わないでくれ。
頼むから、もうこれ以上……あの時のように、壊れちまうから」
柚子葉「萄……真。
(今。あの時って、言ったよね)」
萄真 「俺は。柚子葉だから、
純粋無垢な君だから愛してる。
ありのままを愛してるんだっ。
それ以上の理由なんて……俺達にはいらないだろ」
萄真さんは震える両手で私を力強く抱きしめて、
激しい自責の感情に堪えかねて泣いた。
時々、呻きに似た涙声が漏れる。
封印していた感情が暴走し、
噴き出しそうになるのを必死で抑えてる。
今にも壊れてしまいそうだったのは私ではなく、
萄真さんだったのかもしれない。
ずっと踏み入ることのできなかった彼の心の領域に、
ほんの少し触れただけなのに、
この心臓はナイフで抉られるような辛さを痛感した。
柚子葉「萄真、ありがとう。こんなにも愛してくれて」
萄真 「柚子葉」
柚子葉「私。もう『逝く』なんて、言わないから。
『私でいいの?』なんて、思わないようにするから。
むちゃくちゃ頼りない私だけど、
差し伸べられた大きな手をしっかり握って、
私も貴方の全てを受け止めて決して離さないから。
だからもう、泣かないで」
萄真 「柚子葉。
やっと、伝わった……
俺と出会ってくれて、
愛してくれてありがとう」
冷静になった萄真さんは私の涙を指で拭い、
照れくさそうに頬を赤らめて微笑んだ。
そんなはにかむような笑顔に私はまた救われたのだ。

(続く)
この物語はフィクションです。
![]()
↑↑↑↑↑↑
皆様にここをポチッとクリックしてもらうだけで、
愛里跨はもっと執筆活動に活力を貰えて頑張れます![]()
ポチッ!と、宜しくお願いしますね(*^▽^*)