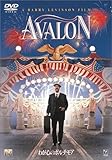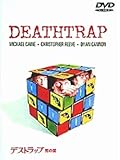シネリーブルで観賞。
あそこは入場までロビーで待たされる。そのロビーをふと見ると、みんな文庫なり単行本なりを取り出して読んでいる。携帯の普及以来、電車ではもう読書している人をさっぱり見かけなくなった。しかしここではほとんどの人が本を読んでいる。こういう景色、ひさしぶりに見たような気がする。モバゲータウンもソーシャルアプリも偽善的な絵文字もない空間。どことも「つながって」いない空間。ずっとここに居たいと思いながら、ボクはiPhoneのi文庫で読書していた。自分でもよくわからない立場にいるような気がした。
元刑事裁判官の主人公ベンハミンは25年前の未解決殺人事件を「庭いじりよりましだから」という理由で小説にしようとし、かつての上司でいまは判事補になっている美しいイレーネに会いにいく。
25年前の事件は、新婚の銀行員モラレスの若い妻リリアナが暴行を受け殺された殺人事件だった。刑事裁判官として現場に駆けつけたベンハミンは、殺されたリリアナの遺体に強烈なショックを受ける。
ほどなく現場近くで工事をしていた作業員が容疑者として逮捕される。しかしそれは拷問による自白を強要したえん罪であった。
捜査をつつけるベンハミンは、モラレスの古いアルバムの中に、異常な目つきでリリアナをみつめる男の写真を発見する。
アル中の同僚パブロとともに、イレーネの古い知人ゴメスの実家に侵入し、母親宛の手紙の束を持ち帰る。
しかしその手紙には住所も具体的な手がかりもなく、そのうえ家宅侵入がばれて捜査は打ち切りになってしまう。
1年後、偶然駅で銀行員モラレスと会ったベンハミンは、彼があのあとずっと駅でゴメスを探し続けていることをしり、捜査再会をイレーネに掛け合う。
しかしゴメスの足取りがつかめず、迷宮入りかと思われていたとき、パブロがあの手紙にかかれた暗号のような文章がすべてサッカーに由来することを突き止め、とうとうサッカースタジアムでゴメスを逮捕する。
しかしその後、服役中にはずのゴメスが大統領のSPとしてテレビに映っているとことをベンハミンはモラレスからの電話で知る。
軍事政権であった当時のアルゼンチンでは、このような超法規的処置がしょっちゅう行われていたそうだ。
ベンハミンとイレーネは、今やゴメスに命を狙われる立場にたってしまう・・・。
骨太でかつ南米流のロマンチックな映画である。ロマンチックするぎると感じるところもあったかもしれない。
しかしベンハミンとイレーネのプラトニックな愛の描き方や、ミステリーとしてのストーリーテリング、そのどちらもおろそかにせず両立できているのは、簡単そうでいて難しいことだと思う。
イレーネ役のソレダ・ビジャメル、知らなかったがすごい役者だ。再捜査願いを出すベンハミンの言葉を、てっきり愛の告白かなにかと勘違いしたイレーネが、そうではないと知って失望する場面のあの表情はさすが職業俳優といいたくなる。
ハリウッドで活躍しているらしいファン・ホセ・カンパネラ監督の力量もそうとうなものだと思った。
上司の愚痴をいいながら殺害現場に入っていくベンハミンが、リリアナの死体を見て激しいショックを受けるシーンは、決まりすぎじゃないかとおもうほど彼の思惑通りに観客もショックを受けたはずだ。
サッカースタジアムの俯瞰から、カメラが一挙に観客席に立つベンハミンまで滑走してくるように移動するシーンには腰が抜けそうだった。この手の技術も金もいる効果は、てっきりアメリカ映画でしか見れないものとばかり思っていた。昨日今日はじめた映画人ができるわざではない。こんな本当のプロにしかできない「技」を見ると、さっき払った1800円もおしくはないと思えるのであった。